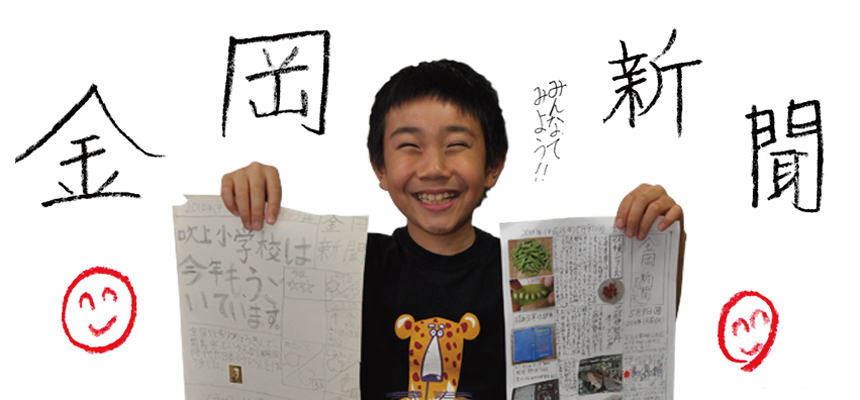点と点のものづくりが結束する美しいかたち。
那須は、かつて温泉や別荘・ペンションブームで賑わった時代もあり、
観光のまちというイメージが強い。
しかし最近では移住者も多く、特に静かな環境で
じっくりと活動をしたいという若い世代が移り住んでいる。
那須は、外から入ってくるひとが多く、“よそ者”を受け入れる土壌があるのだ。
そんななかで、自分たちのものづくりに没頭し、
それを生業としている5人がいる。
スノーボード用のビーニーをオーダーメイドで製作している
「レイドクロージング」の会田喜文さん、
ヨーロッパから買いつけてきた古着などを
リメイクして販売している「ターボ」の伊藤貴之さん、
手づくりで革靴をつくっている「山十」の大森克明さん、
染め物や織物を手がける「ブリランテ」の遠藤聖香さん、
苔盆栽などを製作・販売している「苔屋」の荒井正樹さん。
この地に移住してきてからつながりを持った同世代の5人だ。
扱っているジャンルは違えど、
どこも自宅兼アトリエ(工房)兼ショップというコンパクトな店構え。
「ものをつくるにはとてもいい環境。
雑念がないから余計な影響を受けにくい」と伊藤さん。
「住んでいるひとは、割と個人主義というか、群れないひとが多い。
ひとに変に合わせることなく、それぞれが独立した考えで動いています」
と遠藤さんもものづくりにおいての環境の良さを語る。
彼らはそれぞれ独立して活動しているが、
時に“個”が結束を持つことがある。
レイドクロージングの会田さんとターボの伊藤さんは、
5年ほど前、同時期に那須にショップをオープンさせた。
ショップのプロモーションをしたかったが、
地方紙などに広告を載せてもイメージと合わないし、
通常の観光客をメインのターゲットにしていたわけでもないので、
その効果は微妙。お互いに同じようなことを考えていた両者は、
「それなら自分たちでつくってしまおう」と、
フリーペーパー『New function of Artistic Store for U』の製作を思い立ち、
前出の3組を誘った。
フリーペーパーと言っても、それぞれの店舗の写真が象徴的に掲載され、
あまり説明的ではない。表紙も大胆なピンク。
それでも、置いてもらえる場所も多いし、すぐに捌けてしまうという。
次号は掲載してほしいという申し出も多数。
那須には彼ら以外にも、個人や夫婦で営んでいるような小さなお店が多く、
しかも扱っているものやつくっているもののクオリティも高い。
このフリーペーパーの“若い感覚”を理解してくれるひとが
地元にも多いようだ。
「那須には二面性があると思うんですよ。
街道沿いに大きな看板を出す、という観光的な表のイメージ。
ほとんどのひとはそれが那須だと思っています。でも観光だけではなく、
もっと生活に根ざした裏の那須もあるんです」(会田さん)
そんな奥深い那須のカルチャーへの突破口となる
この『New function of Artistic Store for U』。
これを片手にぐるっと“ウラナス”巡りしてみるのもいい。
例えばレイドにビーニーをつくりに来るひとたちは、
あまり表の大きな観光スポットには行かないだろう。
だからといって、
レイドのためだけに遠くから那須を訪れるのではもったいないし、
迎える側としても、もっと那須の新しい魅力に気がついてほしい。
そんなとき、このピンクの冊子。
山十やターボ、ブリランテ、苔屋などに行って、
“那須、面白いじゃん”と思ってもらえばしめたもの、という算段だ。

みんなで集まっては冊子を綴じ、酒を飲み、また綴じ、また飲み……。
実はまだゼロ号の『New function of Artistic Store for U』。
果たして次号は? 「もうちょっと掲載店舗数を増やしたいですね」と、
会田さんのやる気のある返答。
しかし「この感じはキープしたいので、無理しない範囲で」と
ガツガツしない独自のスタンスを貫く。
伊藤さんも「かっこいいというのは、
ひとそれぞれ基準や捉え方が違います。
だから自分たちなりの見せ方を少しずつでもやっていきたい」と、
あくまで周囲に迎合せず、個の立ち位置を忘れない。
このスタイルが那須で受け入れられれば、那須へ来る客層の幅も広がるし、
那須で活動しているひとにとっても
これまでになかった刺激になるだろう。
それが那須の活性化につながるかもしれない。
外から押し付けられるのではなく、
ボトムアップでそれが起これば、すごく強度がありそうだ。
「個人の“点々”が特色あるまちだと思います。
アートイベントとかも多いし、面白いことが起こりそうなポテンシャルはあるはずです」
と遠藤さんは言う。
それは、今は閑散としているペンションが握っているのかもしれない。
会田さんも言う。
「これまでのやり方は、箱ものをドンですよね。
でもこのフリーペーパーが発展するようなかたちで、
個人商店がたくさん集まったほうが絶対に盛り上がると思います」
東京都内、特に東東京では、
古い空きビルや廃校などをアーティスト・イン・レジデンスにしたり、
クリエイターの集まる物件にしている場所が増えた。
「那須のペンションも、もう空き物件だらけなんです。
そこにショップやものづくりのひとたちに入ってもらえるようにしたい」
という伊藤さん始め
『New function of Artistic Store for U』クルーは意欲的だ。
今日も誰かの家で、
ぽちぽちホッチキス留めしながら酒宴していることだろう。

山十の靴。牛革と天然ゴムとコルクなど、天然素材を使いオーダーメイドで仕上げる。手縫いのため、少しよれた風合いも味のひとつ。

ひとつずつオーダーメイドされているレイドクロージングのビーニー。あごにストラップが付いていて、バックカントリーなどに行くスノーボーダーに重宝されている。ショップにはランプもあるので、スケーターもぜひ。

古着のTシャツにステンシルや染めなどでカスタムしているターボのアイテム。他にも古着をリメイクしたり、コサージュも手染めで製作している。

ブリランテのバッグとストール。アルミニウムを、那須から得たインスピレーションで柔らかくアレンジ。草木染めなど、森のなかのアトリエで四季を意識した染め物や織物を製作。
Shop Information
Brillante
染織アトリエショップ ブリランテ
住所 栃木県那須郡那須町高久乙593-245
TEL 0287-74-5158
営業時間 11:00〜17:00
定休日 月・火曜日
http://www.kiyokaendo.com/
LADE clothing
レイドクロージング
住所 栃木県那須郡那須町大字高久甲5728-7
TEL 0287-74-5102
営業時間 土曜10:00〜20:00 日曜10:00〜18:00
定休日 平日
http://ladestore.com/
TURBO
ターボ
住所 栃木県那須郡那須町湯本206
TEL 0287-76-3152
営業時間 12:00〜19:00
定休日 水曜
http://turbo15.com/
山十
住所 栃木県那須郡那須町高久丙899
http://yamajyu.org/
苔屋
住所 栃木県那須郡那須町高久丙1148-559
http://www.kokeya.jp/