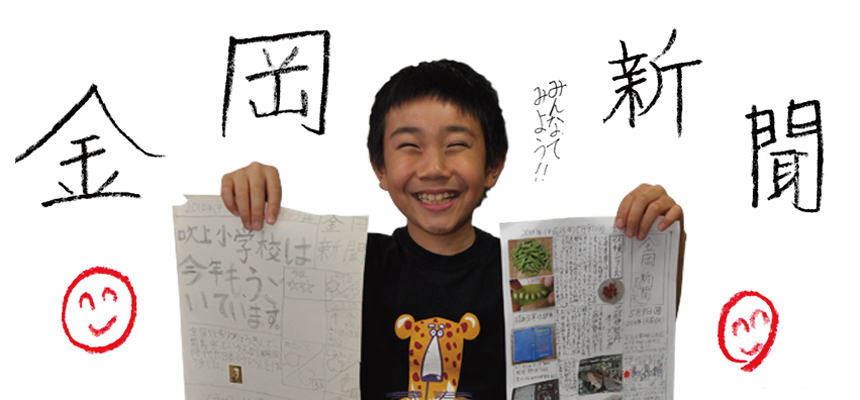火山大国・日本の地熱の有効活用。
地熱発電は、地球内部のマグマのエネルギーを活用し、
地上に噴き出た高温の蒸気あるいは熱水により発電を行う自然エネルギーの一種です。
火山大国である日本には、豊富な地熱資源があり、
その資源量はアメリカやインドネシアに次ぐ世界第三位と言われています。
実際に日本国内には多くの温泉があり、熱利用が盛んです。
地熱発電については、1966年に国内初の地熱発電所が運転を開始してから、
これまで導入された地熱発電所の設備容量は約55万kWに留まっています。
これは、2010年末の段階でアメリカの310万kW、フィリピンの190万kW、
インドネシアの120万kW、メキシコの100万kW、イタリアの90万kW、
ニュージーランドの80万kW、アイスランドの60万kWに次ぐ
世界第8位の規模になります。
その一方で、海外の地熱発電の設備の多くには日本の技術や製品が生かされています。
現在、世界の24か国で地熱発電所が稼働しており、
全世界で約1100万kWの発電設備が稼働しています。
ひとり当たりの発電容量ではアイスランドが世界のトップで、
アイスランド国内の発電量の約26%を占めるまでになっています(日本は0.3%程度です)。
日本では、1970年代のオイルショック後に地熱開発の機運が高まり、
民間主導で地熱発電設備が導入されました。
その後、1990年からは国の主導するさまざまな政策で発電設備の導入が進みましたが、
1999年の八丈島への導入を最後に新たな地熱発電の設備の導入が進まず、
「失われた10年」と呼ばれるような状況となっています。
これまで、大部分の地熱発電は、
エネルギー政策の中で特に支援が必要な「新エネルギー」として位置づけられておらず、
その普及を支援するRPS法の対象にもなっていませんでした。
最近、新しい固定価格買取制度や自然公園などでの規制の緩和などにより、
地熱発電の普及に向けた政策の見直しが始まっています。
日本国内で大きな地熱の資源ポテンシャルがあることから、
国内産業育成や温泉と共存したかたちでの地域の活性化などの観点から注目されています。
高温の蒸気ではなく、熱水を用いる地熱発電を、温泉熱発電あるいはバイナリー発電と呼びます。
比較的小型で、発電出力の規模も数10kW程度からあり、
高温の源泉を持つ温泉がある地域で、その導入が検討されています。
発電した電気やお湯を有効活用できればと、
地熱発電と温泉が共存できる新しい仕組みとしても注目されています。
日本国内で地熱発電が多い都道府県として、
九州地方の大分県や鹿児島県、東北地方の秋田県や岩手県などがあります。
大分県では、家庭やオフィスで使う電気のうち、
20%程が地熱発電による電気でまかなわれている計算になります。
市町村の中には、大分県の九重町や福島県の柳津町のように、
地熱発電によって発電された電気の量で、
計算上その地域の全ての電力をまかなえるような地域もあります。

民間ホテルの地熱発電所(提供:九重観光ホテル)