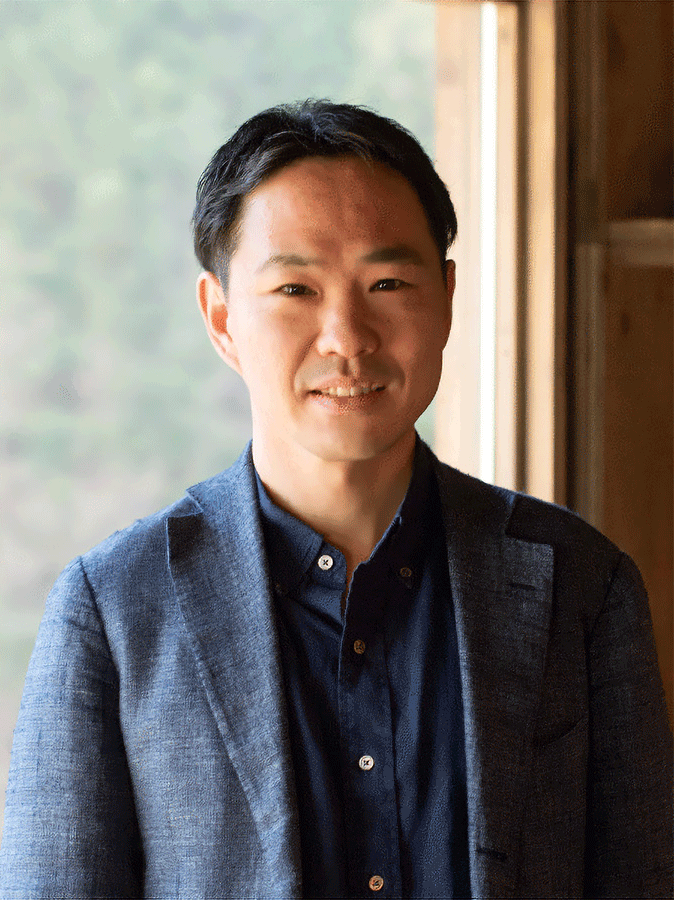伝統技術と 斬新なデザインが融合した、 陶器とは思えない薄さと軽さの器。 KIKOF前編

琵琶湖周辺の伝統技術を活かして。
滋賀県は、長い間、
京都の文化をバックヤードとして支えたものづくりが行われてきた歴史的背景もあり、
たくさんの工芸が伝えられてきた。
その伝統技術が活かされたテーブルウェアが、
直線的なデザインが特徴の「KIKOF(キコフ)」。
全体のクリエイティブディレクションを
グラフィックデザイン会社「キギ」が担当している。
KIKOFは、「Mother Lake Products Project」の一環として取り組まれている。
これは、琵琶湖のほとりで長年培われてきた伝統工芸の技術を活かして、
現代的なライフスタイルに合ったプロダクト製作を目指していくプロジェクトだ。
その中心人物が立命館大学の佐藤典司先生。
『「デザイン」に向かって時代は流れるー感性社会を制するパワーとは何か』を
上梓するなど、専門はデザインマネジメントだ。
パッケージや広告、空間など、デザインで差別化し、価値付けすれば、
売れ方や経営が変わる。デザインで、ビジネスや地域は動く。それを考える学問だ。

立命館大学の佐藤典司先生。DML(Design Management Lab)の代表も務める。
ことの始まりは、2004年のある“県ブランドランキング”の調査で、
滋賀県が最下位になってしまったこと。
「その事態をなんとかしたいと、県からの依頼がありました。
そのときはロゴを変えたりするという提案で終わっていて、大きな動きにはなりませんでした。
その後2010年に、滋賀県の商業振興課から
伝統技術を使って地域振興をやりたいという相談を受けたんです」と、
佐藤先生はきっかけを振り返ってくれた。
そこでやる気のある若手の職人を集めるべく、現場を見て回った。
協力してもらえることになったのが、長浜の浜ちりめん(シルクライフジャパン)、
彦根の漆(井上仏壇)、能登川の近江上布(北川織物工場[ファブリカ村])、
近江八幡の木珠(カワサキ)、信楽の信楽焼(丸滋製陶)の5つ。
それぞれが持っている技術を活かしながら、新しいデザインでプロダクト開発し、
現代のライフスタイルに合うような商品を発売した。
これがMother Lake Products Projectである。
商品はそれなりには受け入れられたが、滋賀県以外に発信するとなると、
「いささかインパクトが足りない」と佐藤先生は感じていた。
「いいデザインにはなっていたけど、伝統工芸の世界からは出ていないと思いました。
滋賀ではいいけど、たとえば東京の青山に並べたときに、他を圧倒できるのかと。
それにはあと2ジャンプくらい必要だと感じました」
そんな思いもあり、以前から知り合いであったキギにデザイナーとして参加を依頼した。
実はMother Lake Products Projectを始めるときに、
佐藤先生は、キギのふたりがかつて手がけていた「D-BROS」のプロダクトを
思い描いており、内部でもイメージとして共有していた。
「僕の頭のなかには、遊びがあって少しファンタジーなキギ的な世界観で、
最初からブレはなかったというわけです」
こうしてKIKOFが誕生する。デザインはもちろん、
コンセプトワークもキギのふたり、植原亮輔さんと渡邉良重さん。
「琵琶湖は日本の大きな器であるというテーマを立てて、
“器湖=キコ”というワードが思い浮かびました。
そこにFreeやFutureなどの頭文字Fを加えて、KIKOFにしました」
と植原さんは名前の由来を教えてくれた。

最初に考えつき、コンセプトのもとになったのが、このピッチャー。詳細は後編で。
第一弾としてリリースされたのが、「丸滋製陶」とつくった信楽焼の器。
しかしパッと見て、信楽焼と思う人はいないのではないか。
色はパステルでかわいいし、妙にカクカクしている斬新なデザイン。
なによりも薄い。陶器の常識を覆す薄さだ。
プラスチック製といっても信じてしまうくらい。
この強い個性も、佐藤先生の狙い通り。
「伝統技術というと、お勉強になりがちなんです。
漆は何回塗ったのかとか、土が何かとか。
それ自体悪いことではありませんが、そのマーケットはそれほど大きくない。
まずはデザインなど感覚的に気に入って、
“あとからよく見たら信楽焼だった”というくらいでいいと思います」
つくり手とデザイナー、フィフティ・フィフティの関係性。
全国的な例に漏れず、滋賀の伝統工芸もまた、衰退方向にあるといっていい。
「思った以上に、職人の世界はつくることに集中しています。
世の中のニーズに合わせたものづくりや流通、広告などのノウハウが少ないんです」と
佐藤先生は課題を指摘する。
職人はものづくりの技術には長けているが、宣伝やデザインなどは得意ではない。
そしてもうひとつ大きな理由がある。
「ひとの手でつくる部分が大きいので、必然的に人件費が高くなります。
だから伝統工芸は高い。
ただし高い商品を安くして売るのは、衰退の速度を速めるようなものです。
ですから、高くても買ってもらえるような商品にするしかありません。
それにはひとつはプロモーション。もうひとつがデザイン。
だからキギのような現代的な動きを知っていて、
高いデザイン性を持ったひとたちと一緒にできればと思いました」と佐藤先生は語る。

素焼き後のスプーン。
キギには、技術者的デザイナーというよりも、
クリエイティブディレクター的な役割が求められた。
キギという“メーカー”からの発注ではなく、“外部デザイナー”としての登用でもない。
ともにブランドを立ち上げる“パートナー”でなくてはならない。
「きれいなプロダクトをつくって、パッケージして
“ハイ、終わり”ということもできました。
しかし、これはプロダクト製作の仕事という側面以上に、
伝統技術を受け継いでいくという佐藤先生や職人のみなさんの思いから
外れてはいけません」と植原さん。
だから、それぞれに仕事の役割こそ分けられているが、
ブランド内での立ち位置はフィフティ・フィフティだ。
そこに第3者が介在していない。
「自分たちがちょっと多く働くぐらいの気持ちがお互いにあれば、
フィフティ・フィフティを保てると思います」

遠くからでもパッと見ですぐにKIKOFとわかるオリジナリティ。
“外部デザイナー”の指示通りにつくって、たとえ売れたとしても、
それでは現地に何も残らない。
ただ言いなりにつくって、周りを見ていないようでは、かつての構造と変わっていない。
「ブランドの考え方を売るという方向に社会の関心が移ってきていますから、
KIKOFのケースがうまくいってほしい」と植原さん。
渡邉さんも続ける。
「私たちに今できることは、このKIKOFをまずは地に足つけて、
ちょっとでも広めていくこと。良い例になるように」
伝統技術、現代的かつ斬新なデザイン、地域との密接な連携。
近江商人に倣っていうなれば“三方良し”なブランドに将来がありそうだ。
後編:[ff_titlelink_by_slug slug='tpc-thi-tsukuru-040' append=' はこちら']
Information
KIKOF
editor profile
photographer
http://fresco-style.com/blog/