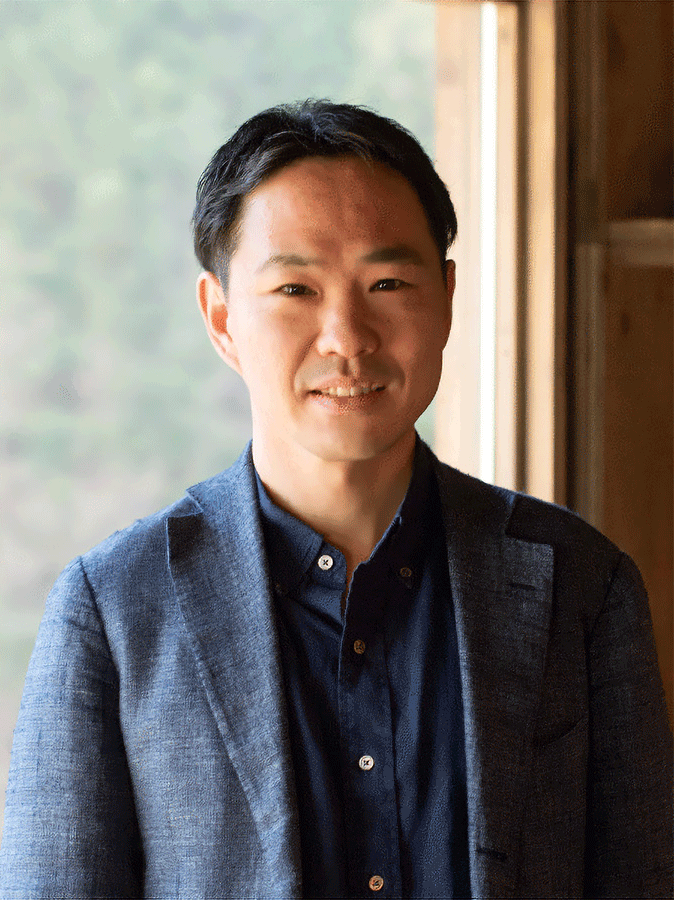津軽の海に厄災を流す。 初夏の渚に広がる祈りのとき 〈大間越春日祭〉

初夏の西津軽で行われる海と人の物語
東北の祭礼への旅。
それは東北が好きになり、岩手へ移住した僕にとっては必然の旅だった。
この土地で生きてきた人々が何に祈り、何を願うのか。
祭礼を訪れることで、
自分がこれから暮らしていこうとする東北という風土の理解を
深められるのではないか。
そんな思い携えて、東北各地に伝わる祭礼を訪ねる旅を始めた。
最初に目指したのが、西津軽の海岸線のはじまりとなる半漁半農の集落だった。

西津軽の海へ
青森と秋田の県境に近づくと、日本海はがらりと様相を変える。西津軽の海には断崖がそそり立ち、北へと向かう道は、海と陸の境目を伝うように進んで行く。いまとなっては、何度この先へと向かったかわからない道ではあるが、祭礼の撮影を始めたばかりの10年ほど前の僕にとっては、西津軽への入り口に立つと異世界に踏み入れるような気持ちになったものだった。
深浦町の大間越。西津軽の地での僕の向かう先は半漁半農の小さな集落だ。この集落の名を口ずさむたびに僕は、美しい西津軽の海を思い起こすことができる。
大間越に魅了されたきっかけは7年ほど前に訪れた大間越春日祭だった。まだ、祭礼への旅を始めたばかりの頃だったが、それ以前に東北の歴史街道を旅していた経験から津軽西海岸を南北に走る〈津軽西街道〉周辺の美しさは熟知していた。あの美しい海岸線の集落で行われる祭礼はきっと素晴らしいものだろうと、大間越に向かったのだった。
僕が暮らす岩手の雫石から大間越へは片道で4時間ほど。岩手から奥羽山脈を越えて秋田に出ると、日本海沿岸を北上した。

祭礼当日は、穏やかな晴天に恵まれた。海岸線に家が立ち並ぶ大間越には、穏やかな初夏の気配に包まれていた。僕は清々しい海風の心地よさを感じながら、祭り衆が集う青年会館へと向かった。
木造の古い分校のような佇まいをした青年会館の中では、浴衣姿の祭り衆が準備を進めていた。大人の男たちは白の浴衣を着て、子どもたちは赤い浴衣を着ていた。聞くところによると、浴衣を着ている者たちが〈太刀振り〉と呼ばれる踊り手たちで、色紙で美しく飾った〈太刀棒〉と呼ばれる棒を手に踊りながら集落をめぐるということだった。そして、その太刀振りの後方を守りながら進むのが、〈春日丸〉と呼ばれる弁財船を模した木造船だと聞かされた。

青年会館の中に鎮座している春日丸を見せてもらうと、まずその立派さに驚いた。全長5尺6寸(約1.7メートル)。帆柱には、大きな帆が上がり、細部についてもかつての西津軽の海を行き来していた北前船の弁財船を模して精巧につくられている。さらには、ひとりひとり顔が異なる7人の船乗りが乗るという凝りようだ。制作期間は約1か月。最終的には海に流すため毎年新たに制作するのだという。
祭りは、この春日丸へと灯明とお神酒をあげ、皆で拝礼をしてから始まる。
行列の先導となるのは、〈先振り〉と呼ばれる者で、太刀振りは先振りの合図で、太刀棒で地面を鳴らし、踊りを繰り返しながら進んでいく。


この太刀振りの踊りが実にユニークだ。先振りが色紙を重ねてつくった御弊を振り上げて、「アーラ、エンヤラ、エンヤラ、エンヤラホーイ」との掛け声を上げると、太刀振りは「エンヤラ、エンヤラ、エンヤラホーイ」と返す。すると、先振りが再び大声で「ア、シッチョイシッチョイ、シッチョイナ」と繰り返しながら進み、ある瞬間に「ア、シッチョイナ」と掛け声を発すると、太刀振りたちは、二人一組となり、飛びながら相手と体を入れ替え、「エイヤ」と叫び、太刀棒同士を力一杯に打ち付け合うのだ。腕ほどの太さの太刀棒がバーンと打ち付け合う踊りはなかなかの迫力。ときには力が入りすぎ、太刀棒が折れてしまうこともあるそうだ。
一方の春日丸は土地の古老たちを中心とした担ぎ手たちによって、神輿さながらに担がれ、太刀振りの後方から集落を進んでいく。土地の人によると、太刀振りによって集落から祓われた厄災を春日丸が集めてまわるのだという。
先振りが合図し、太刀振りが太刀棒を振って跳ね、太刀棒をぶつけ合う。この一連の所作を延々と続けながら進む行列の息抜きとなるのが〈舟宿〉でのひとときだ。集落内それぞれの班で持ち回りとなっている舟宿は行列への労いの場。激しい踊りで疲労した太刀振りや、重い春日丸を担ぎ続ける担ぎ手へ、酒やごちそうが振る舞われる。ここでの大間越の人たちの姿はいつ見ても幸福そうだ。ごちそうを配る女性たちも酒を酌み交わす男たちも、お菓子を頬張る子どもたちも、誰もが笑顔に包まれている。祭礼だけが持つ幸福なひととき。そう呼ぶことができる時間がそこにあると感じる。
[ff_assignvar name="nexttext" value="沖へ流されていったあとに"]
[ff_file_include_from_theme filepath="/include-unit/unit-layout-magazine-child-pagenation.php"]

船を見送る掛け声のなかに
あるものとは
僕が初めて大間越春日祭りを訪れたその日の行列もあらん限りの掛け声で太刀棒を振り上げ、跳ね、春日丸とともに集落を進んだ。
出発したのは午後1時。
海岸沿いに細長く伸びる集落の端から端まで周り終えた頃には、夕方が間近に迫る時間帯になっていた。その頃になるとさすがに疲労の色を隠せない春日祭り一行だったが、何とか元気な声を絞り出し、傾きかけた太陽の下で暖かな色で光り始めた海を目指した。
大間越の小さな海岸。そこが、この行列の終着地だった。


波が静かに寄せる砂浜で春日丸が下された。と同時に先振りの威勢のいい掛け声がかかる。太刀振りたちがすぐさま反応し、春日丸の周囲を、太刀棒を振り上げ掛け声を合わせながらぐるぐると3度回った。そして、一日中握り続けた太刀棒を勢いよく、光る波の向こうへ、「そうれ」と放った。
波に漂う太刀棒を見届けると、若い衆ふたりが春日丸を担ぎ、波の中へと入っていった。春日丸を押しながら、沖へ沖へと泳いでいく若者ふたり。浜に残る人たちは、まだ冷たい海を行くふたりに向かって声援を送った。
そこに現れたのが二艘の漁船だった。漁船は、漂う春日丸に近づくと甲板へと引き上げた。漁船に乗せられた春日丸は、強い潮流の流れる沖へと運ばれ、そこで再度流されるのだという。
「春日丸は、厄災を遠くに運び去る役目だから、再び岸に寄ってこないよう、遠くへ流れる潮に乗せるんだ」と古老が、僕には聞き取ることが少し難しい土地の言葉で教えてくれた。
春日丸を無事に引き上げた漁船は浜の前で再び大きく円を描き始めた。
青い海に夕方の陽光が差し込み、海は妖しく光り始めている。その海に円を描いていく航跡。円環へと至る船の道を見ていると、この土地にとってこの海がどれほど大切なものであったかを理解できるような気がした。僕の目に映ったのは海と人が紡ぎ出す物語のような時間だった。
「おーい、おーい、おーい」
漁船が金色に光る沖の波間に向かって進み出ようとしたとき、野太い声で叫ぶ男性がいた。

その人は、太刀振りを演じていたひとりで、部外者である僕にも幾度となく笑顔で語りかけてくれた50歳前後の男性だった。
その人はいわゆる祭礼の中心人物という感じではなかったが、太刀棒のぶつけ合いや踊りの一生懸命さはまさに迫真といった感じで、行列のなかで気になっていた存在のひとりだった。その人がひたすら漁船に向かって大きな声で
「おーい、おーい、おーい」と繰り返し叫んでいた。
僕は「おーい」の続きを待った。
「頑張ってこいよー」
と船に乗る人たちを応援するのか、
「ちゃんと流れていけよー」
と春日丸の背中を押すのか、あるいは何かの願いを託す言葉なのか、
「おーい」の先を待った。
しかし、その人は、先に続く言葉を放つことなく、ただ、ひたすらに
「おーい、おーい」と大きな声で叫び、輝く波間に手を振り続けた。
春日丸が去っていこうとする浜では、一日の疲れが出たのか座り込む人もいれば、波打ち際で遊ぶ子どもたちもいれば、愛犬とともに海をぼんやりと眺める人など、それぞれが春日祭の最後のひとときを過ごしていた。
「おーい、おーい」は、そのなかで繰り返し続けられたが、誰もが気にとめることないのか、それぞれが海と向き合っていた。

僕は「おーい」の先が出てこないことを知ると、
「おーい」の奥にあるものを想像しようとした。
声の抑揚は平坦で、際立った感情は込められていないようだった。
しかし、その人の祭り化粧が施された横顔は真剣そのもので、
どこか切実な思いを感じさせる声でもあった。
もしかして、死別した両親を思ってのことだろうか。
あるいは死別したのは、妻や子どもだったりするのだろうか。
いいや、そんな深刻なことではなく、今年が自分にとってよい年であるようにと、単純に願掛けをしているのだろうかなどと、僕は勝手にさまざまな想像を巡らせた。
しかし、当然のことながら「おーい」の意味を推し量ることはできないまま時が過ぎ、「おーい」は終わってしまった。


こうして僕にとっての初めての大間越春日祭が終わった。人気がなくなった浜には、水平線に近づいた太陽から鮮やかな朱に染まった光が届けられていた。
大間越での穏やかな一日を反芻しながら、僕はいつの日か「おーい」の意味を知ることができるのだろうかと考えていた。
学生時代までを関西で過ごし、就職で上京。その数年後に縁あって岩手に移住した僕が東北の祭礼を見てみようと思ったのは、自分が暮らしていこうとする土地を知りたいという素朴な欲求からだった。その先にあったものが祭礼だった。
東北の自然や歴史、生活、文化など、いわゆる風土と呼ばれるものが、きっと祭礼のなかに詰まっているだろう。それを知ることは、この先、東北で暮らしていくことをきっと豊かにしてくれる。そう思って始めたことだった。
大間越での一日を終えた僕には、祭礼を通じて「知るべきこと」が、あの人が叫んでいた「おーい」の奥にあることと、なぜか無関係ではないような気がした。
あの「おーい」のなかには間違いなく、この大間越という土地で生きてきた人生が詰まっている。そして、それはきっと、今の時代、この東北という土地で生きることが何であるかを教えてくれることにもつながっていくだろうと想像した。少し飛躍しすぎている想像にも思えたが、決して間違いではないという不思議な確信もあった。
その日、僕は小さな灯台下の草原で車を停めて、車中泊することにした。暗闇に包まれて、波の音だけが聞こえる海を車窓から眺めながら、東北各地に伝わる祭礼に足を運び、それぞれの土地で叫ばれる「おーい、おーい」を聞いてみようと思った。そして、「おーい」の奥にある意味を推し量りたいと思った。
祭礼への旅は始まったばかりだった。
profile
著書/『いわて旅街道』『とうほく旅街道』『手のひらの仕事』(岩手日報社)、『かなしみはちからに』(朝日新聞出版)ほか。
個展/『Country Songs 彼の生活』『明日をつくる人』『あたらしい糸に』(Nikonサロン)ほか。