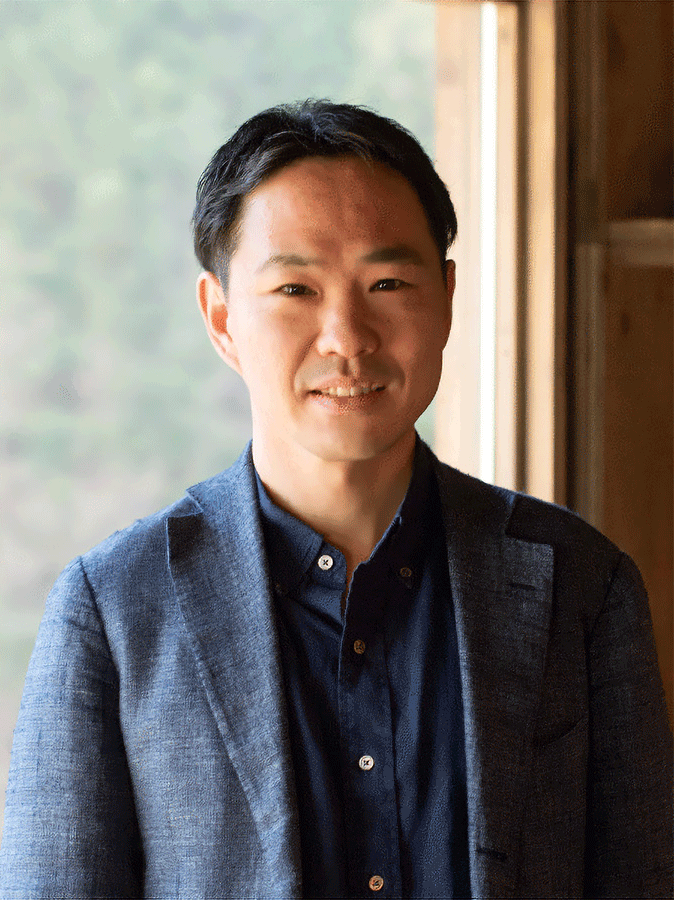〈高橋水産〉 真鶴の魚で究極の干物を 目指す求道者

神奈川の南西部、真鶴は魚のまち。
戦後は「ブリバブル」と呼ばれるほど、ブリで財を成した。
その後も豊富な魚を干物にして、観光バスが来たり、
多くの観光客が干物を買っていった。
その頃はたくさんの干物屋さんが軒を連ねていたが、
現在、真鶴で自家製造販売している干物屋さんは、
青貫水産、高橋水産、魚伝の3軒を残すのみ。
どこも小規模ながら毎日丁寧に魚を開き、干している。
今回は〈高橋水産〉のお話。
真鶴の伝統と革新をこめた干物づくり
真鶴の干物屋さんのなかでも、ひときわ異彩を放つ店頭ディスプレイ。
「毎日修業」「一人製造」「独学干物」といったスローガンが貼られている。
それだけでもすごく興味を惹かれてしまう。
店頭には七輪が置かれ、数種類の干物が試食できる。一杯やりたくなるくらいだ。
ここで試食してしまうと、買わずにはいられない。それくらい旨みが凝縮している。

試食コーナーは交流も楽しい。表面にプツプツと塩が浮いてきたら食べ頃。
高橋水産の現店主は辰己敏之さん。もともとは辰己さんの祖父が、
湯河原から真鶴へ干物屋を移転してきて始めたお店だ。
「干物が身近にある環境で育ったので、
子どもの頃から干物が大好きでした。食べ放題でしたからね。
昔から真鶴の人は魚の味に厳しいのでおいしい魚が食べられました。
だから真鶴の子どもは魚に対して舌が肥えてしまうんですよ」
当時、祖父のお店は調子がよく、現店舗以外にも
観光バスが何台も着くような大型店舗も構え、干物も大量生産していた。
辰己少年はそうしたお店に顔を出しながら、干物を食べ、
結果的に現在につながる“味覚を鍛える”日々となった。

店内には干物がたくさん干されている。
本人いわく「夢も何もなく」高校を卒業して、
お金がないので、祖父の干物屋をなんとなく手伝いながら、過ごしていた。
ところが時代の流れは避けられない。
10数年前に業務を縮小、大型店舗も閉め、現店舗のみとなった。
祖父も引退し、従業員もわずか数名に。
「見よう見まねで僕も干物をつくってみたけど、なかなかうまくいきませんでした。
でもだんだんと慣れてきたので、祖母にも引退してもらって、
ひとりでやることになりました」
ここから辰己さんの「干物求道者」たる道が始まる。
「夢も何もなかった高校生」なんて言いながら、
凝り性な側面がむくむく湧き上がってくる。
「じいさんから伝わってきたマニュアル通りにやっても、
子どもの頃食べていた味と違うんです。魚はとれる場所や時期、
サイズもバラバラ。だからマニュアルが通じないこともある。
すごくしょっぱくなったり、味がしなかったり。
じいさんがつくっていた塩度の少ない味つけを再現したかったんです。
ある程度納得できる味になるのに何年もかかりましたね」

高橋水産の辰己敏之さん。干物愛にあふれている。
地魚干物の種類は一番!
高橋水産の干物の特徴として、種類が多いことが挙げられる。
祖父の代から扱っていた一般的な干物は、だいたい6種類から多くて8種類。
そこに辰巳さんは真鶴の地魚を加えていった。
「市場に行ってセリに参加するようになりました。
最初はまったくやり方がわかりませんでしたが、
地元の先輩たちに教えてもらいながら少しずつ買えるようになってきました。
毎日市場に通っている干物屋は、うちだけです。干物は安く販売するので、
欲しい魚でも旅館や料理屋には価格勝負で勝てない厳しさもあります。
でも、毎日通っていればいい出会いもあったりしますからね」

ただし地魚を干物にするのは難しいらしい。
いろいろな地魚を入手しながら、コツコツと実験していく。
これだけの種類の干物を扱っているのは高橋水産だけだ。
「冷凍などで大量に仕入れる魚に対して、地魚は新鮮すぎてピンピンしています。
開きにくいし、味も染みにくい。魚自体は何でもござれですけど、
真鶴近海でとれるものでも、まだ扱ったことのない魚もあります。
でもメアジを干物にして販売しているのはうちくらいだと思いますね」

店頭のディスプレイ。「やさしいひもの」など気になるフレーズが並ぶ。
365日、干物づくり
「朝は市場に行って、午前中に仕込んで、午後は売店。
夜は近所の酒場に繰り出して、先輩がいたら最近の魚の状態の話。
ひとりだったら干物の製造方法について考えたりしています。
休みなく、そんな繰り返しの365日です」
頭の中は常に干物でいっぱい。まさに求道者。
店頭に貼られているスローガンを体言しているようだ。

「いろいろな魚の身の味を、引き立たせられるようになってきました。
まだ“極めた魚”というのはありません。でもアジはかなり理想に近づいていますね。
やはり1年通して一番数多く開いているので、
塩加減や干し加減を常に調整できるんです。だからどの魚でも、
ちょっとずつでも毎日コツコツとやっていれば、まだ伸び率があるのかなと」

愚問だし、答えも何となく想像できたが、あえて聞いてみた。
「干物のゴールはあるんですか?」と。
「ないと思っています。いま、水も塩も特別なものは使っていません。
数年前、知り合いにすごく高くていい塩をもらったんです。
どの魚に使ってやろうかと見計らっているうちに、結局まだ使ってない(笑)。
たまに塩にこだわってみたいなと思うこともあるけれど、
逆にいま使っている水と塩でどこまでいけるか」
想像の通りの答えで、やはりストイック。
「とにかく毎日修業。干物づくりに関しては、アドバイスはもらったとしても、
ほぼ独学。最終的に完成させるときには、やはり自分でやるしかないので」
干物が有名な真鶴で、独学で干物をつくるのは異色だ。
とはいえ、奇をてらったものをつくっているわけでもなく、とてもおいしい干物である。
いつか辰己さんの「完成した」干物を食べてみたい。

お店は真鶴港のすぐ目の前。この先の海が地魚の漁場だ。
information
高橋水産