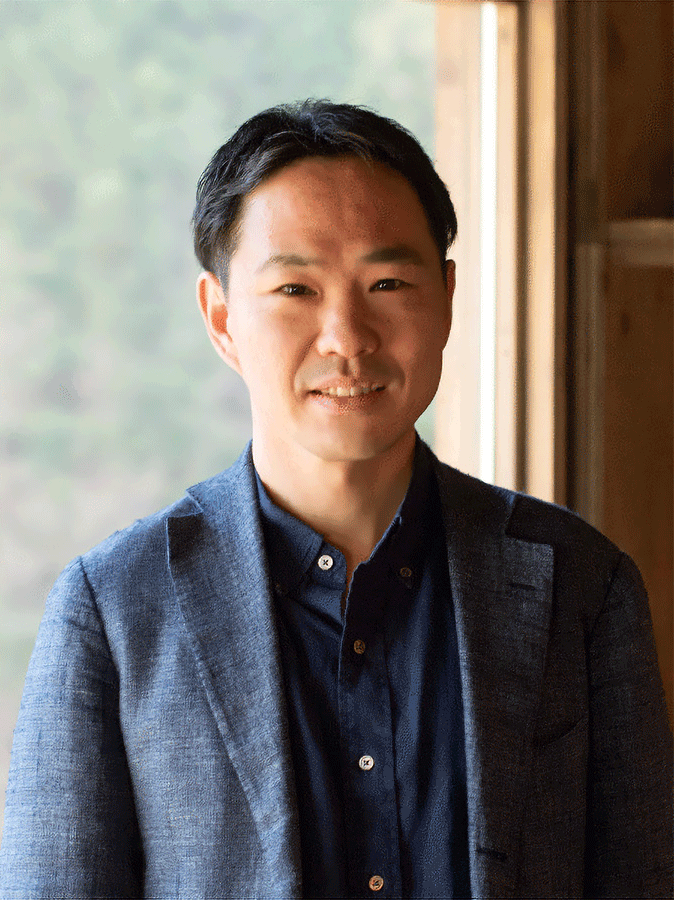〈うさと〉の服展示販売会に、
地域の作家による『みる・とーぶ展』。
岩見沢の山あいで何が起こっている?

森のなかに立つ、山荘で開催された〈うさと〉の服 展示会
6月末からの1週間、わたしのまわりではイベントが目白押しだった。
わたしと地元の仲間で続けている地域PRプロジェクト〈みる・とーぶ〉のイベントと、
上美流渡(かみみると)にある〈美流渡の森の山荘〉で行われたイベントがあり、
さまざまな人の交流が生まれていった。
まずひとつ目は、美流渡の森の山荘で6月28日から4日間開催された
「うさとの服 展示販売会」。
〈うさと〉とは、タイ在住の服飾デザイナー、さとううさぶろうさんデザインによる、
手紡ぎ、天然染め、手織りの布でつくられた服のこと。
着ごこちのよい服のファンは全国におり、うさとのコーディネーターを務める人々が
各地で展示会を企画、販売する活動を行っている。

美流渡の森の山荘に飾られた〈うさと〉の服。布の素材は、コットン、ヘンプ、シルクの3種類。布はタイの農村に住む女性たちを中心に織られている。(写真提供:やまだひろこ)
美流渡の展示会は、神奈川県在住のやまだひろこさんがコーディネーターとなった。
会場となった山荘のオーナーである中川文江さんと以前から交友があり、
月1回、神奈川から美流渡へやってきて太極拳の講座を開いている師範でもある。
今年は昨年に続き2回目。服の販売だけでなく、
東京から江戸小紋の型彫り職人も訪れ、作品展と体験ワークショップも開催。
また、この地域から〈コーローカフェ〉や、
アフリカ太鼓の奏者でマクラメアクセサリーの販売も行っている
〈らんだ屋〉も出店した。
このほか会期中の29日には、秩父在住のカゴ作家の長谷川美和子さんによる
クルミの皮を使った花カゴづくりのワークショップもあって、
昨年にも増してにぎわいを見せていた。

やまだひろこさん(左)と〈美流渡の森の山荘〉のオーナー、中川文江さん(右)。中川さんは地域で人気の森のパン屋〈ミルトコッペ〉の女将でもある。

花カゴづくりのワークショップ。クルミの皮を編んでつくった。
会場となった美流渡地区は、人口わずか400人ほどの集落。
岩見沢の駅から車で30分と決してアクセスのよい場所ではないが、
この展示会の吸引力には目を見張るものがあり、
4日間の開催で200人を超える来場者があったという。
「自然とともに暮らしているからこそ、
うさとの服の魅力が伝わるのかもしれません」(やまださん)


美流渡の森の山荘では、7月7日に「美流渡の森 2019夏 サロンコンサート」も行われた。ピアノ、バイオリン、声楽など音楽家が集まり、アットホームなコンサートが開催された。
森の恵みを持って札幌へ。『みる・とーぶ展』開催
もうひとつのイベントは、わたしたちが企画した『みる・とーぶ展』。
年に1回開催し、今年で3年目になるイベントで、札幌市資料館のギャラリーで、
地域の工芸家やクリエイターの作品を展示販売するものだ。
7月5日から3日間の開催となり、なかなか美流渡まで足を延ばせないが、
以前から興味を持ってくれた人など、多数の来場者があった。

札幌の大通りにある札幌市資料館が会場。東京や札幌など各地からクリエイターが集まり、毎年開催している『北にあつまる手しごと展』に、みる・とーぶメンバーも参加した。

岩見沢の山あいの地域は、陶芸家や木工作家などクリエイティブな仕事をする人たちが多い。そうした人々の作品を一堂に集めた。
このイベントのことは、連載でも毎回リポートしているが、
今回のトピックスとしては、新しい仲間が加わったことだ。
うさとの展示会にも出店したらんだ屋と、この夏、美流渡に移住しようとしている、
陶芸家のこむろしずかさんが作品を並べてくれた。

〈みる・とーぶ〉の展示に参加してくれた、陶芸家のこむろしずかさん(左)とアフリカ太鼓の奏者でありアクセサリーもつくっている〈らんだ屋〉の岡林利樹さん(右)。
ここ数年で、岩見沢の山あいには、個性的な移住者たちが増えていっている。
ミュージシャンであったり、陶芸家であったり、農家であったりと、
職種はさまざまだが、共通点も少なくない。
例えば、どこかの企業に就職しようという考えを持っている人はほとんどいないし、
家に多少の不備があったり、買い物に不便があったりしても、
自分でなんとかしようとするサバイバル能力に長けた人が多いところも特徴だ。

しずくや鳥、木々などをモチーフに、物語を感じさせる陶器をつくるこむろさんの作品。

昨年、岩見沢の山あいの万字地区に移住した岡林さんがつくるマクラメアクセサリー。
そして、移住者が増えるとともに、うさとの展示会を企画したやまださんのように、
住民とのつながりから道外の人たちが、
この地区を何度も訪ねてくれるという現象が起こり、
新しいイベントが生まれるきっかけにもつながっている。

『北にあつまる手しごと展』に参加した東京や淡路島、札幌のクリエイターのみなさん。3年前に札幌市資料館での展示に参加しないかと声をかけてくれたのは、東京で活動を続けるデザイナーの岩切エミさん(左から2番目)。
そしてイベントが生まれる背景には、実際に地域に住んだり、
何度も訪ねたりするなかから「こんなものがあったらいいな」とか
「こんなものが必要なんじゃないか」という考えがあるように思う。
そして、アイデアが浮かんだら、それを実現するのは、
もしかしたら東京などの大都市よりも、スムーズなんじゃないかと思えてくる。
開催場所を探したり、参加者を募ったりするとき、
いつも地域の仲間が協力してくれるし、
会場費もそれほどかからないケースも多いからだ。

『みる・とーぶ展』で飾られた上美流渡にある花のアトリエ〈Kangaroo Factory〉のリース。地域で採れた松ぼっくりやブドウの枝などが使われている。
こうした仲間の協力がある環境にいるからか、アイデアが広がっていって、
わたしは徐々に規模の大きなプロジェクトに取り組もうとしているところだ。
今年の3月で美流渡の小中学校が閉校になったわけだが、この話が決まって以来、
ずっと校舎をどのように活用していくのかがとても気がかりだった。
この小学校に息子が2年間通ったこともあり、
このまま廃墟のようになっていってしまったら、
やるせないという気持ちをずっと持っていた。
ただ、大規模な建物をどうしていったらいいのかについては、
正直思いが及ばない状況が続いていた。
そんななかで、以前から美流渡地区に注目し、学生たちのフィールドワークを行っていた
北海道教育大学岩見沢校のビジネス専攻の先生たちが、
岩見沢の山あいでアートプロジェクトを行おうとする計画を立ており、
この事業にわたしもゲストとして参加させていただくことになった。
ビジネス専攻の先生と何度か話し合いを重ねるなかで、
美流渡の小中学校の校舎を教育大学のラボスペースのように
活用できないだろうかというプランが持ち上がっていった。

フィールドワークに来た教育大学の生徒と訪ねた閉校になった小学校。
この計画については、連載でまたリポートをしていきたいと思うが、
ここ数年で移住者が増加し、イベントなど話題に事欠かなくなったことで、
いま岩見沢の山あいの地域での動きは、
着実に大きな広がりを見せていっているように思う。
個人個人がつくり出した動きは、あくまで小さな点だけれど、
それがつながって線になって、やがて大きなうねりになれば、
校舎という大きな施設だって、地域の力で活用できる道筋が
見つかることもあるかもしれない。

美流渡の隣の地区にある旧万字線の朝日駅舎が、地域の移住者の発案によって復活。ボランティアによるリノベーションが行われ、6月22日にはお披露目会があった。こんなふうに、各地でさまざまなプロジェクトが行われている。(写真提供:平野義文)
こうした希望をわたしが持てるのは、いま山あいで起こっている動きが、
企画する人たちが心から楽しんでやっていると感じられるからだ。
過疎化対策といった地域を背負うような気負いはなく、行政主導型でもなく、
「みんなでワイワイ楽しもうよ」というラフな姿勢があるからこそ、
地域外の人たちからも興味を持ってもらえるんじゃないだろうかという気がしている。
校舎の活用は、大がかりな取り組みと言えるが、
いままでのように軽やかな気持ちで、楽しみながら関わっていきたい。
information
森の学校ミルトをつくろう
開催日時:2019年7月13日(土)前編/7月20日(土)後編 13:00~14:30(各日とも)
会場:JR岩見沢駅舎内センターホール 有明交流プラザ(岩見沢市有明町南1番地1)2階 i-BOX前
定員:市民・学生30人
美流渡小中学校の利用についての市民と北海道教育大学の学生たちの話し合いの場。7月27日(土)には中学校の体育館を使ったイベントも実施予定。
https://www.hokkyodai.ac.jp/images/info_topics/00008500/00008579//20190625110803.pdf
writer profile

http://michikuru.com/