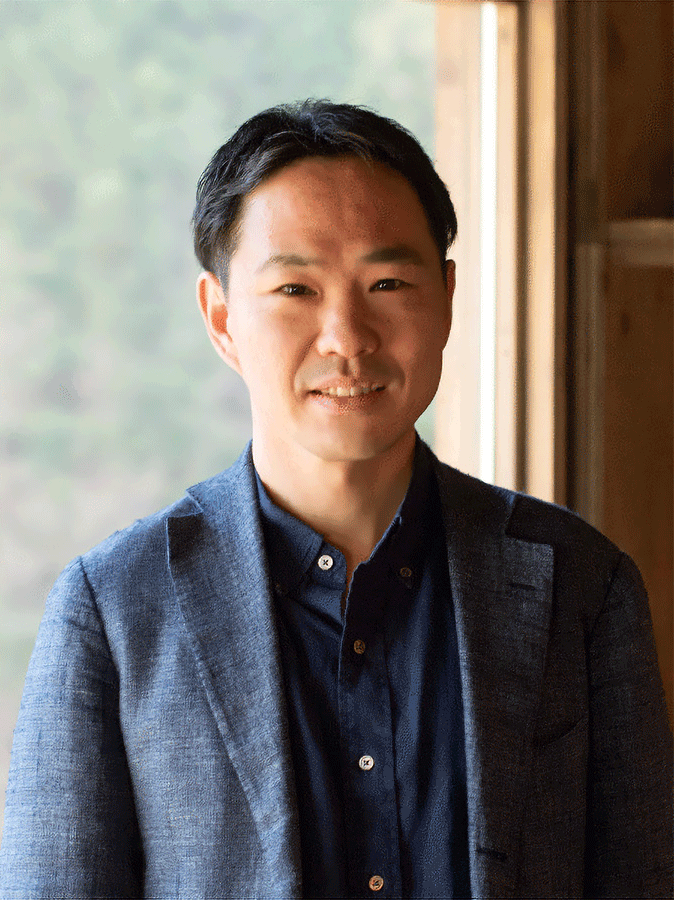自給的な暮らしを求め万字へ。
アフリカ太鼓とともに旅を続けた夫妻

大雪の中で始まった、アフリカ太鼓のワークショップ
岩見沢の山間の地域に引っ越して1年が過ぎるなかで、
わたしは個性的な移住者のみなさんと出会うことができた。
これまで、〈ミルトコッペ〉というパン屋を始めた移住の大先輩や、
森をたったひとりで開墾して暮らす青年などを連載で紹介してきたが、
さらなる“強者”とでも言いたくなるような夫妻のことを、今回は書いてみたい。

万字地区の岡林夫妻が住む家。母屋の隣にあるのが廃材を利用して建てた小屋。
その夫妻とは、昨年春より山間の万字(まんじ)地区に移り住んだ
岡林利樹さん、藍さんだ。秋に一度訪ねたふたりの住まいは、
わたしの住む美流渡(みると)から車で15分ほど山に入った場所にある。
敷地を見回して驚いたのは、移住してわずか数か月で、
廃材を利用した小屋を点々と建てていたことだ。
しかも、太陽光パネルで電力の一部を自給し、
また自分で火を起こして煮炊きをしているとのこと。
訪ねたときも小屋をつくっている最中で、近くで湧き出ている冷泉をくみ、
沸かして入るための風呂場になるのだという。

岡林利樹さん。「雪が降る前に風呂場になる小屋をつくらなくちゃ」と笑顔。

万字の町内会が大切に守っている冷泉「ポンネ湯」。硫黄の香りのする冷泉は、ポリタンクを持っていけば誰でもくめる。
興味がわいたのは、その暮らしぶりだけではない。
冬になるとふたりは〈アフリカ太鼓 in 美流渡〉と題し、
近くの会館で太鼓のワークショップを週1回のペースで始めた。
初回をのぞいてみると、その腕前にまたまた驚かされた。
藍さんは「ドゥンドゥン」というベースを担う太鼓をたたき、
そのリズムに合わせて利樹さんが「ジャンベ」という太鼓を軽快に打ちならす。
子どもも参加できると聞いていたのだが、だからといってゆるさはなく、
「いずれはバンドを組んで地域のイベントに参加したい」と
真剣に参加者と向き合っていた。

藍さんはドゥンドゥンを担当。利樹さんと息の合った演奏をしている。

ワークショップの様子。近所の子どもも参加。札幌からライブ仲間が訪ねてきたこともあったという。
いったい岡林夫妻とは何者なのか?
万字地区に移住するまでの道のりを、わたしはじっくり聞いてみたくなった。
夫の利樹さんは岩見沢市出身。
札幌の大学に進学した頃、旅に目覚め、
日本全国はもとより、東南アジア、インド、ネパールなどをまわり、
そうしたなかでアフリカの太鼓に出会った。
もともと太鼓は好きだったが、特にジャンベは心に迫るものを感じ、
以来、太鼓をキャリーに載せてさらなる旅へと向かっていった。
旅の途中で出会った仲間とセッションをしたり、ライブをしたり。
太鼓は独学だったが、場所の雰囲気に合わせて、
さまざまなリズムを奏でることができたという。
「ストリートで発表をしながら旅の資金が稼げるようになりました。
そうしたら旅が全然終らなくなって(笑)」

カリブ海沿いのキャンプ場で仲良くなった現地ミュージシャンと、夜のライブへ向けてリハーサルをしている様子。
旅は7、8年続き20代後半となっていた頃、東京へと赴き、
いくつかのバンドでパーカッショニストとして活動していた時期もあった。
この頃、妻となる藍さんとも友人を通じて知り合った。
藍さんもまた旅人だった。
石川県出身で大阪の大学に進学し、バックパックを背負って旅に出た。
中国、タイ、カンボジア、ベトナム、ラオスなど各地をめぐり、
卒業後は一時就職したものの、やはり旅に出たいという気持ちが強く、
今度は日本をまわることにしたという。
「旅をしながらその場でお金を稼いで、また旅をする
というスタイルをやってみたいと思っていました」
そんなことを考えていたなかで利樹さんに出会い、ともに旅をするようになった。

アフリカへ行くための、長い長い道のり
この頃、利樹さんは、太鼓の演奏に行き詰まりを感じていたという。
「独学のみの限界でした。アフリカの伝統音楽を勉強したい。
日本にだってアフリカ人がやっている太鼓教室はあるけれど、
アフリカに行ったほうが早いと思ったんですね」
アフリカに行く資金が手元あったわけではなかったという。
利樹さんは日本で働くのではなく、格安航空券でバリ島へ向かい、
ここからストリートで資金をためながら、アフリカを目指す旅を始めた。
藍さんも同行し、最初は利樹さんの演奏を脇で見ているだけだったが、
笛を吹いたり、凝った折り紙をつくって売ったりするようになった。
バリ島からは陸路と海路で、
ジャワ島、スマトラ島、シンガポール、クアラルンプールへと渡っていった。
ここまではそれほど資金をためられたわけではなかったが、
次にインドを訪れたことで、新しい展開が開けたという。
「ストリートで太鼓をたたきながら、足元にはアクセサリーを置いておこうと思って、
ラジャスターンにターコイズなどの石を仕入れに行きました」(利樹さん)
ラジャスターンは石材や宝石、貴金属が豊富に売られている砂漠の都市。
ここでたくさんの石を買い、ヒマラヤ付近にこもってアクセサリーを制作。
半年滞在をし、旅で仲良くなった知人を頼ってフィンランドへと向かった。

ヘルシンキでマクラメ編みでつくった石のアクセサリーを売る藍さん。
季節は夏。フィンランドは深夜0時になっても明るく
「体がおかしくなるくらい」ストリートで太鼓をたたき、アクセサリーを売った。
「今日泊まれる宿を探しています」というプレートを立ておくと、
必ず誰かが泊めてくれた。
その後、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フランス、スペインをめぐり
目標となる資金を稼ぎ出し、ついにヨーロッパとアフリカ大陸を隔てる
ジブラルタル海峡を越えてモロッコへ。
モーリタニアを経由してセネガルへ行き着き、ここで太鼓を学ぶことにした。
日本を出発してから1年が過ぎていた。

地球儀で場所をたどりながら夫妻に話を聞いた。バリ島からアフリカまでの長い道のりがリアルに伝わる。
「セネガルには太鼓を学べる教室はたくさんありました。
僕たちは海辺の森のコテージのようなところに住んでいました。
電気、ガス、水道もなく、夜はキャンドル、炭火で煮炊きをし、
井戸で水を汲んでいました」(利樹さん)
アフリカでは働かず、太鼓のレッスンに集中。
午前と午後にそれぞれ2〜3時間のレッスンがあり、利樹さんの手は豆だらけ。
「なかなかスパルタな先生(笑)」だったそうで、徹底的に基礎を仕込まれた。
太鼓を学ぶつもりのなかった藍さんも、やがてレッスンに参加し、
次第に魅力に引き込まれていったそう。
「レベルのケタが違うと思いました。アフリカは階級制度が残っていて、
音楽家の家であればずっと音楽を仕事にしています。
小さい頃から太鼓しかたたいていないわけで、当然スペシャリスト。
一生やってもこの人たちのようにはなれないけれど、
僕には僕にしかできないことがある。
やれることをやるしかないと思いました」(利樹さん)

セネガルではふたりの先生から指導を受けた。写真はひとり目の先生で21歳と若かった。
7か月間、太鼓を学び、資金が底をつきかけたこともあり、再びフィンランドへ。
仕入れた石が残り少なくなると、今度はメキシコへと赴いて石を購入。
さらにメキシコは装飾的に糸を編み込むマクラメが盛んな土地だったこともあり、
アクセサリー制作の技術に磨きをかけた。
「これからの人生において、マクラメのテクニックを上げれば、
役に立つのではないかと思いました」(藍さん)
その後、中南米を経由し、フィンランドで資金をためて、2度目のアフリカへ。
今度はブルキナファソに8か月滞在して太鼓を学んだという。

ブリキナファソ滞在中には地元の結婚式で演奏する機会もあった。
日本へ戻り、劇的に変化した暮らし
旅する4年を経て、やがてふたりは拠点を持った暮らしを
してみたいと考えるようになったという。
旅のあいだに祖父母が亡くなるという大きな出来事もあった。
また、友人ができたとしても旅の途中では気軽に会うことも難しくなる。
各地でバンド活動をしている人々の姿を見て、うらやましく感じることもあったそうだ。
「海外のどこかに移住したいと考え、理想の土地を探したりもしていましたが、
結局、身内もいるし昔の仲間もいるし、
日本に帰ろうということになりました」(利樹さん)
まっすぐアフリカから日本に帰るのではなく、フィンランドとタイを経由し帰国。
その後は札幌でライブ活動やアクセサリー販売を続けていった。

ふたりの暮らしが劇的に変化することになったのは、入籍をすることになってからだ。
利樹さんはそのとき35歳。結婚するのであれば、実家が営む建設会社に入り
定職についてほしいという父の希望もあり、岩見沢に戻って働き始めた。
「朝から晩まで本当に忙しく働いていましたが、それまで就職したことがなかったし、
やっぱり僕の人生はこれじゃないと思いました」(利樹さん)
そんななかで、利樹さんはあるとき万字の小さな別荘を訪ねる機会があった。
会社の取引先だった家主は、この家を手放したいと語ったそうで、
自然豊かな万字で暮らしたいという想いが芽生えていった。

岡林夫妻が住む家。冬には家がすっかり雪に埋もれてしまう。
月日を共にしたことで、「会社を辞めて、万字に住みたい」という
夫妻の想いを父親も受け入れてくれたという。
父のもとで働いた3年間は利樹さんにとって辛い時期だったが、
それでも「親子として必要な時間だった」と振り返る。
万字の人口は100人弱。岡林さんの家の近くには人家もなく、
自然のど真ん中にある3000坪の土地で、いま北海道犬と鶏とともに暮らしている。
「もう、最高ですね!」
ふたりは口を揃えて、そう語ってくれた。
旅をするなかで見えてきたいまの目標は、便利さを追求する消費社会に加担せず、
環境に負荷をかけない自給的な世界に身を置くことだそう。
利樹さんは建設会社で学んだ知識を生かして小屋を建て、
藍さんは漬物や味噌など保存食を仕込んでいる。
いずれも旅のなかではできなかったことだそうで
「ここにずっといると思っているからこそ、張り合いも出て楽しくなってきた」
のだという。
今後は、地域の古家を改修してゲストハウスを運営したり、
地元のイベントなどでアクセサリーの販売もしていきたいそうだ。

ワークショップでは、小さな子どもも、リズムに合わせて手を動かす。
ふたりの姿を見ていると、ひとつの職業にしがみついている自分の価値観は、
まだまだ堅く不自由なものに思えてくる。
学校でそれなりに勉強はしてきたけれど、
旅のなかで培った“生きる力”にはとうてい及ばない。
人里離れていても自活できる、揺るがない力をふたりは持っているのだと思った。

アフリカ太鼓のワークショップで、みんなで練習しているのは
「バラクランジャン」という曲。子宝を授かりたいという女性が、
鳥であるバラクランジャンへ祈りの歌を捧げるというものだ。
この曲を歌い、ドゥンドゥンをたたく藍さんのお腹の中には、
いま新しい命が宿っているという。
ふたりにとって、ここは長い旅の終着点であり、
いままさに新しい旅の始まりとも言えるのではないだろうか。
そう思いながらふたりの演奏を聞いていると、
太鼓の音色が何かよりいっそう心弾むものに感じられた。

「どんなにたくさんのおくりものもこどもひとりにはかなわないよ」。「バラクランジャン」の歌は日本語にも訳されている。
writer profile

http://michikuru.com/