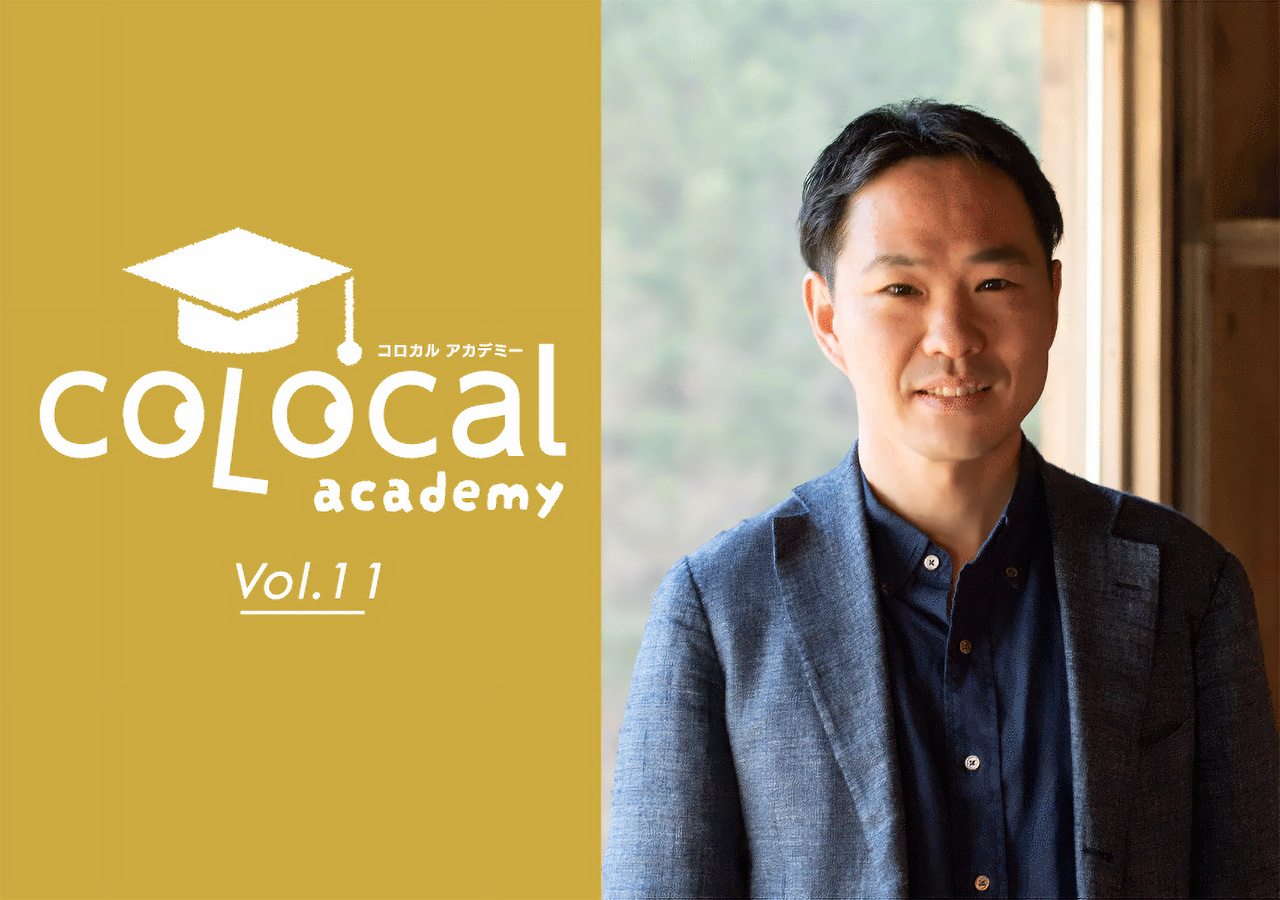コロナ禍であっても、
穏やかに未来をつくる
美流渡の移住者たちの暮らしぶり

コツコツ積み重ねてきたものが、いま花開いて
私の住む人口400人の集落・美流渡(みると)地区は、
コロナ禍であってもなくても、いつもと変わらぬ時を刻んでいるように思える。
北国が遅い春を迎えると田植えシーズンとなり、
農家のみなさんは忙しそうに車を走らせている。
朝、散歩しているご近所さんもいるし、のどかな山あいの風景はあいかわらず美しい。
では、私と同じようにこの地に移住した仲間たちは、
コロナ禍をどう過ごしていたのだろう?
緊急事態宣言中は、訪ねるのをちょっと遠慮していたが、
6月下旬、少しずつ人の行き来が増えつつある時期に、
みなさんのもとを巡ってみることにした。
向かった先は、美流渡から車で5分ほど山あいに入った上美流渡地区。
このエリアでは、この春から新しい動きが起こっている。
そのひとつは森のパン屋〈ミルトコッペ〉。
薪窯で焼き上げた香ばしいコッペパンは、お昼には売り切れてしまう人気のお店。
パン屋を営む中川さん夫妻が、札幌から移住したのは22年前。
以来、集会所として使っていた古家でパン屋を開いてきたが、
主人の中川達也さんが10年前からコツコツつくり続けてきた工房がようやく完成し、
新店舗にて6月3日からオープンとなった。
冬期は休業で、普段なら4月中旬に営業を始めていたが、コロナ禍だったことに加え、
新しい窯でいつもの味を再現するための十分な研究の時間を取りたいと、
いつもより2か月遅れのスタートとなった。

〈ミルトコッペ〉の新店舗。屋根は業者さんに依頼。できる部分は達也さんが少しずつつくっていった。札幌軟石を手で積み上げていったそうで、苦労がしのばれる。

店内は温かな雰囲気。窓の奥には手製のパン焼き窯が見える。
ミルトコッペから歩いて300メートルほど行くと、中川夫妻が住む〈森の山荘〉がある。
山荘では、妻の中川文江さんが出迎えてくれた。
文江さんはパン屋の女将であり、リンパ液の流れを活性化する施術
「リンパドレナージュ」のセラピストとしても活動している。
普段であれば、ひと月のうち10日ほど東京で施術をし、
いつも予約でいっぱいなのだが、外出自粛要請を受けてからは
東京との行き来をストップさせていた。
思いがけず時間ができたことで、文江さんは新しいことをふたつ始めたという。
ひとつは野菜づくり。根っこつきのネギを友人からもらい、
土に植えたら育つかなと思ったのがきっかけという。
クワで固い土を掘り起こし、ブロッコリーやレタスなど
さまざまな野菜を配置した小さな畑が誕生した。
「このあたりは鹿がくるから、木の枝を畑の周りに差してみたの」とうれしそう。
柵の形はハート型。なんとも文江さんらしい畑だなあと思った。

いろんな種類の野菜が並ぶ、ハート型の畑。
そしてもうひとつは薪割り。
昨年、薪ストーブを山荘に設置し、薪となる木材を
友人たちと手分けして、山から運んでいた文江さん。
還暦のお祝いにご主人に斧を買ってもらったそうで、
コロナ禍ではせっせと薪割りに励んだという(!)。
薪割りは全身運動。私などは、斧を持つだけでフラフラしてしまうのに、
文江さんのわき出るようなパワーに圧倒された。

斧を持ってマスク姿で微笑む文江さん。会うと必ず元気がもらえる。
続いて山荘のお隣で、花のアトリエ〈Kangaroo Factory〉を営む
大和田さん夫妻のもとも訪ねてみた。
大和田さんたちは、自分たちの手で育てた花でアレンジメントをつくりたいと
神奈川から移住し、2016年に花のアトリエをオープンさせた。
家の周りの土地は、セイタカアワダチソウなど外来種が生えていた荒れ地。
ここを少しずつ整備して花畑に変えていった。

〈Kangaroo Factory〉のガーデン。歩いて巡ることのできる散策道がある。
訪ねたちょうどそのときにつくっていたフラワーアレンジメントは、
すべてガーデンで育てたものだという。
ふたりは、ここにアトリエを開いた頃から、
すべて土地のものでアレンジをつくりたいという夢があった。
けれど、荒れ地をすぐに花畑に変えることは難しく、
札幌の市場で仕入れた花もアレンジに取り入れながら試行錯誤を続けていた。
毎年、花は少しずつ増えていき、ついに今年、
育てたものだけでアレンジができるほど豊かに咲くようになったのだ(!)。

数種類のミントが使われていてさわやかな香り。やさしい色合いのアレンジ。
アレンジやリースづくりなどのワークショップを各地で開催してきたおふたりだが、
今年はイベント自粛で時間ができたそうで
「庭づくりに専念できました」と夫の誠さんは語る。
そして、今年のチャレンジは、ガーデンにウッドデッキをつくること。
「このあたりには座って休めるところがないので、
いらした方がお弁当を広げたりできるスペースになればと思って」と妻の由起子さん。
ガーデンにはさまざまな種類のミントもあって、
ゆくゆくはミントティーも振る舞えたらと笑顔で話してくれた。

Kangaroo Factoryの大和田由起子さん、誠さん。ノブドウの根が張って花が育たない場所にウッドデッキをつくろうとしているそう。

シラカバをホダ木にして、キノコの栽培も始めたそう!
移住者が、少しずつ地域の風景を変えていく
続いて訪ねたのが、木工作家・五十嵐茂さんのアトリエ。
15年ほど前にここに移住し、〈遊木童〉という名前で、
さまざまな種類の木を組み合わせた木工作品をつくっている。

木のおもちゃ。色合いの異なる木を組み合わせて表情を出している。
アトリエに入ると、木の小さなパーツがたくさん積まれていた。
「コロナで僕の仕事がなくなっているんじゃないかと、
まわりが心配してくれて、たくさん注文が入っちゃって」
木工作品を販売するイベントの多くは中止になっていたが、
友人らからの仕事でてんてこ舞いの様子(もしかしたら普段より忙しい!?)。
五十嵐さんは、木工をしつつ、舞踏や小説、音楽など、
さまざまな表現も模索していて、個性的な人々との交友関係がある。
こうした友人について、いつも楽しそうに話してくれていて、
その眼差しには温かさがあふれていると私は感じる。
そんな五十嵐さんだからこそ、この危機的状況に仕事が集まってくるのだと思った。
「声かけてもらえると、うれしくて仕事断れない……」と言いながら、
黙々と手を動かしていた。

工房での五十嵐茂さん。木のパーツをたくさん制作中。
Kangaroo Factoryの大和田さんや遊木童の五十嵐さんは、
この春から近隣にある〈栗沢工芸館〉でも活動を始めている。
上美流渡は、1980年代に陶芸家の故・塚本竜玄さんが窯を開いたことがきっかけで、
工芸家やアーティストが多く住むエリアとなっていった。
こうした人たちと市民とをつなぐ場をつくろうと市の施設として工芸館が生まれ、
主に陶芸家によってこれまで運営が行われていた。
今年、美流渡の移住者・ホジャティさん夫妻が中心となって声をかけ、
この施設に関わる作家が増え、陶芸に加え、ガラスや木工、
フラワーアレンジメントのワークショップがスタートすることとなったのだ。

緊急事態宣言中は閉館していたが、現在は開館。ホジャティさん、大和田さん、五十嵐さんとともに、陶芸家のきくち好恵さん、こむろしずかさんが講師となって、土日を中心にワークショップが行われている。

ホジャティ文さんはガラス作家としても活動中。夫のスティーブンさんとともに、普段は観光客向けのアクティビティを行う〈メープルアクティビティセンター〉やイングリッシュキャンプを行っている。
さらに、この連載でも古家改修の様子を紹介してきた〈マルマド舎〉が、
5月からゲストハウスとしてオープンしたのだった。
地域おこし推進員(協力隊)としてこの地域に入ったふたりが、
その任期を終えてもずっと改修をし続け、ついに2年の歳月をかけて、
ようやくここまでたどり着いた。
コロナ禍とぶつかったこともあり静かな滑り出しとなったが、ここは森の中。
静寂さも魅力のひとつとなっているので、隠れ家的なゲストハウスとしては、
それほどの影響もないのではないかと思う。

築70年以上の建物。2階に丸い窓があったことから〈マルマド舎〉と名前がついた。(写真提供:マルマド舎)
コロナ禍であっても、家づくりや改修などを自分たちの手でやってきたみなさんは、
暮らしにかかる費用がもともと少ないため、
それほど大きな影響を受けているようには見えなかった。
むしろ、じっくりと自分のやりたいことに専念でき、
誰もが清々しい表情を浮かべていたことに、私も勇気づけられた。
こうして記事にしてみると、地域がダイナミックに変化しているように感じられるが、
住んでいる者からすると、その歩みはとても穏やかなもののように思う。
Kangaroo Factoryが、荒れ地を毎年少しずつ花の咲くガーデンに変えていったように、
自然のサイクルに逆らわず、そして自分たちのできることを
一歩ずつ積み重ねてきた結果がここにはある。

writer profile

http://michikuru.com/