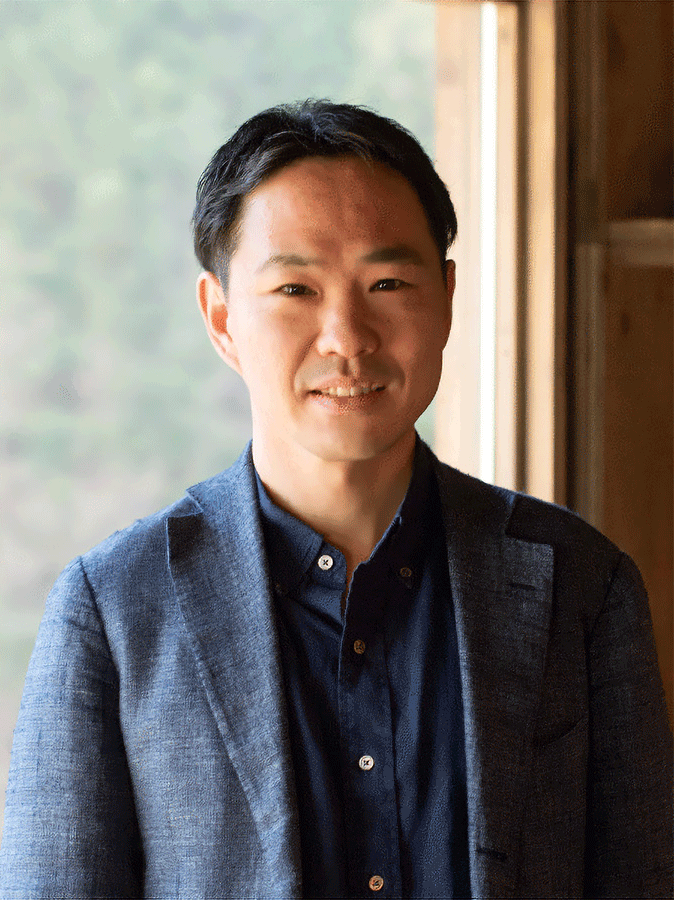地域でのインタビューは
“仲良し”の秘訣…!?
奥底にある本当の声を聞きたくて

苦手だった文章を書くことと向き合った連載
コロカルのこの連載は、スタートから6年が過ぎた。
日頃から出版に関わり、ライターとしても活動をしている自分にとっては、
文章を書くことの鍛錬の場でもある。
連載が始まったのは長年勤めていた出版社を辞めて独立したばかりの頃。
最初は自分の暮らしや地域の人々について
どのように書いたらいいのかわからず困惑していた。
出版社で働いていた頃は、編集部や会社といった
組織の考えにそった匿名性の高い内容の文章を書くことが多かったため、
まったく異なる領域に踏み込んだ感覚があった。
もともと美術系の高校・大学に進学し、絵ばかり描いていて、
文章を書く経験は少なかったし、本を読むのも苦手だったこともあり、
書くことにコンプレックスがつきまとっていた。

2年前に自宅とは別に仕事場を設けた。取材で出かける以外はひとり部屋にこもって編集や執筆を続ける。
最初のうちは連載記事に1週間を費やしたこともあった。
取材で収録したインタビューの音声起こしを始めれば、
途中で眠くなってしまって、なかなか前に進められず3日間をかけてしまったり。
つい長く話を聞いてしまって、とにかくそれを端から端まですべて文字に起こしていた。
こうしてできた大量の音声起こしの原稿を解読するのに、またも時間を費やし、
さらにはその中から骨子を見つけ出すのに2、3日使ってしまい……。
仕上がった原稿の多くは長文。
コロカルの担当編集さんに「また、大作ですね」と言われることもしばしばだった。
要点をシンプルに伝えられない自分に、もどかしさが募った。

連載でもっとも執筆に時間がかかったのは、南インドの出版社〈タラブックス〉の編集者が来日したときのシンポジウムをまとめた記事。タラブックスみたいな本づくりをしたいと思っていたので、思い入れがありすぎて長文になってしまった。
そんな状況が変わってきたのは、連載を初めて3年が経過した頃。
その頃、私は、道南せたなでオーガニックな農法で家畜や野菜を育てる
〈やまの会〉のメンバーに取材をした本をつくろうとしていた。
このとき私は、1回の取材でわかったような気持ちにならず、
何度も取材をして話を聞いてみようと思った。

私が続けている出版活動〈森の出版社ミチクル〉で刊行した『やまの会が語った死ぬと生きる』。出版までに約2年かかった。(撮影:佐々木育弥)
代表の富樫一仁さんに2度目の取材をしたとき、
私は「生まれてから現在までのことを話してください」とお願いした。
富樫さんは、ゆっくりと丁寧に人生について語ってくれた。
生まれたときから重度のアレルギーがあり、毎週のように病院で注射を打っていたこと。
ミュージシャンになることを目指していたが、
20代でアレルギーの薬が効かなくなってしまい症状が悪化。
デビューを諦め、食生活から変えていこうと、
農薬を使わない野菜を育てるようになったこと。
せたなへと移り住み、音楽仲間ができ、やまの会のメンバーと出会って、
新たな世界が開かれていったこと。

富樫さんへの取材。次女が2歳になるまでは取材に同行させていた。(撮影:佐々木育弥)
インタビューは3時間以上に及んだ。
富樫さんの壮絶な人生に触れ、私は大きく心を動かされたが、
同時に何か「軸のようなもの」が見えてこないと思った。
そう感じていることを富樫さんに投げかけてみると、
家族しか知らないという5年前の出来事について話してくれた。
「実は一気に20キロやせて、半年間寝込んでいました。
まるで末期癌の患者のような状態で、いま思い出してもゾッとしますね」
体の毒素を一気に放出するようなこの経験を経たあとに、
ついに「健康」を手に入れたのだという。
この話が終わった途端、富樫さんの顔がパッと明るくなった。
「50年間の目標は自分が健康になることでした。
それが叶ったいま、目標がなくなって、
軸が見えなくなってしまったのかもしれませんね。
話をしていて、自分のような悩みを抱えている人たちに手を差し伸べること、
そして人を育てる方向に向かえばいいんだということを再認識できました」
そして、じっと下を見つめながら、
「これに気づくために來嶋さんが来てくれたんですね」と話してくれた。

『やまの会と語った死ぬと生きる』は、イラストも文字もすべて手書き。パソコンで文字を打つよりも、自由な気持ちで取り組めたらと試行錯誤した。(撮影:佐々木育弥)
大きなものを受け取ったと感じた。そして、私はこのとき気がついた。
インタビューとは、相手も自覚していなかった心の声を
一緒に探り当てる作業なんじゃないかということだった。
新しい発見が沸き起こる瞬間を体験すること。
文章表現がうまいとか下手ということよりも、ここが大切なのだと思った。
相手の根幹にある心の衝動を探ろうとして
それ以来、私は取材の姿勢が変わった。
インタビューをするときは、相手の根幹にある心の衝動、
何かをどうしてもやりたいという気持ち(これを軸というのかもしれない)が
どこにあるのかを探るようになった。
時間がたっぷりあるときは、生い立ちをただただ話してもらうようにしているが、
1、2時間で切り上げなければならないときは、
幼少時代のことや転機となった体験などを聞くなかで、それを見つけようとしている。

冬は雪に覆われる仕事場。降りしきる雪を見ながら原稿を書く。
自分の場合もそうなのだが、これまでの人生を誰かに話すとき、
相手に伝わりやすいように、物語をつくっているようなところがあると思う。
例えば私は「絵が好きだったから美術大学に行った」と相手には説明するけれど、
本当のところは「子どもの頃から見たものをそっくりに描ける資質があって、
描くとみんなが褒めてくれて、体操も勉強も友だちとのコミュニケーションも
イマイチ苦手だったので、自分がかろうじて存在を発揮できる絵にしがみついていて、
周りに美術系の学校を目指すだろうと思われていたので、その期待に沿って進学した」
というほうが近い。
しかし、取材に来た初対面の人に、こんな「面倒な話」をしても仕方がないと、
知らず知らずのうちにブレーキをかけてしまっている。
こういう状態は、誰しもあるんじゃないかと思う。
このブレーキを取り払って、私は話を聞きたいと思っている。
だから相手が本心から出ていない言葉を使っているのかもしれないなと思ったら、
そのことについて、いろいろな角度から質問をしてみるようにしている。
そして自分の中で「こうかもしれない」という確信が持てるまで会話を続けていく。
話を重ねていくうちに、富樫さんとの体験のように、
ずっとモヤのかかっていた風景がパッと明るくなるような感覚に出合うことがある。

ただ、こうした風景が明るくなるような瞬間は、すべての取材で起こるわけではない。
ほとんどの場合は、「なんとなくわかったかな?」という心許ない感覚のままだ。
そんなときは、わかった時点のキワのギリギリまで詰め寄って原稿をいったん書く。
いい文章を書こうという気持ちよりも、淡々と事実を重ねていって、
ほんの少し最後に「こうなんじゃないか?」という
自分なりの解釈にグッと踏み込んで、そこで原稿を閉じている。
自分としては物足りなさも残るのだが、そんなときは
「再び取材をさせてもらおう、きっと次回にわかることがあるんだ」
と思うことにしている。

三笠市にアトリエを持つアーティスト・上遠野敏さんとは、私がコロカルと並行して連載をしている『The JR Hokkaido』という車内誌での取材がきっかけで、行き来が始まり、その後コロカルでも取材。今後は、美流渡(みると)で一緒にプロジェクトを行う計画があるので、また取材をさせていただきたいと思っている。
幸いなことに、コロカルの連載で取材するのはご近所さんが多い。
取材以外でも会う機会はあるので、そんななかで
少しずつ心のブレーキがほぐれていくこともある。
自分も何度も同じ人について書いていくことで、
だんだんと核心に近づいていっているように感じるときもある。

三笠市の山あいにあった〈湯の元温泉旅館〉を継業し、同時に障がい者福祉施設も運営する杉浦一生さん。杉浦さんも以前に別媒体で取材したのだが、一度だけでは捉えきれないことあり、コロカルでも取材した(それでもまだ、捉えきれていないと思っているのだけれど……)。
そして何よりうれしいのは、取材したご近所さんと、
以前よりも“仲良し”になれたような気持ちがすること。
さらに記事を読んでくれた人が、取材した人のことを、
これまで以上に身近な存在として感じてくれたりすることだ。
日常的には初対面の人とうまく会話を弾ませることができない性格なので、
取材という設定に助けられて、いろいろな人と出会うことができている。
連載では、道内で自分なりの道を模索する人々についてインタビューしてきたが、
まだまだ紹介しきれていないと感じる。
じっくりと時間をかけながら、出会いを深め、これからも原稿を書いていきたい。
writer profile

http://michikuru.com/