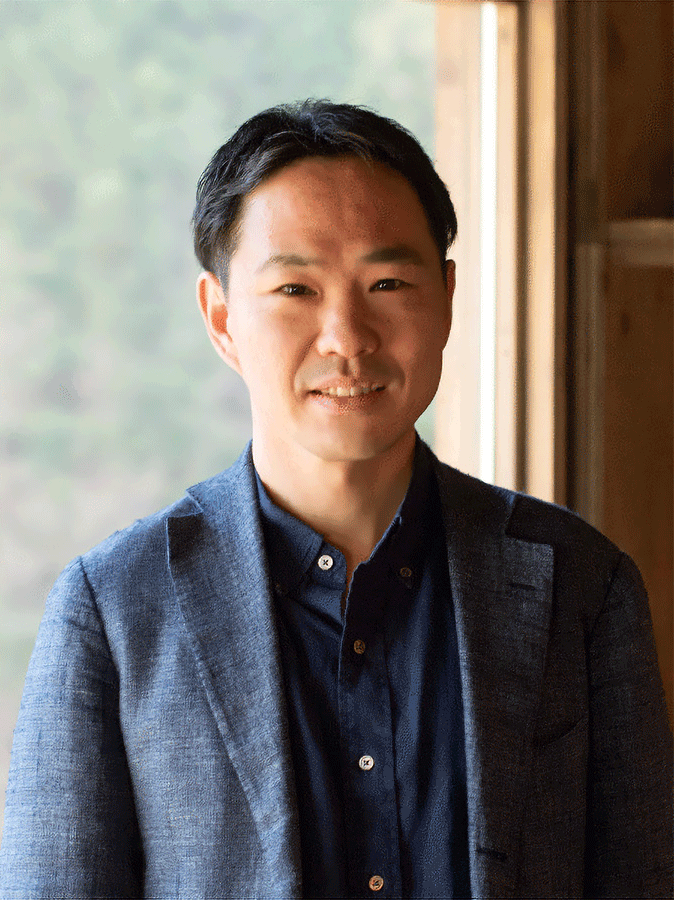1枚の古写真を手がかりに
明治初期の建物を復元。
函館市〈港の庵〉

富樫雅行建築設計事務所 vol.2
北海道函館市で設計事務所を営みながら、施工や不動産賃貸、店舗経営など、
幅広い手法で地域に関わる、〈富樫雅行建築設計事務所〉富樫雅行さんの連載です。
今回のテーマは、解体の危機にあった明治の米穀海産物委託問屋〈旧松橋商店〉。
1枚の古写真を手がかりに市民有志の手でリノベーションして復元し、
この場所を基点にスペインのバスク地方に伝わる美食倶楽部
「ソシエダ」が函館に誕生したお話をお届けします。
魅力を秘めた古い建物を救いたい
前回の〈常盤坂の家〉のリノベを2年半もかけてコツコツやっていると、
いろいろな人が訪ねてきてくれました。
そのなかのひとりが西部地区で生まれ育ち、お土産屋さんを営みながら、
函館の外国人居留地を研究する清水憲朔(しみず けんさく)さん。
「常盤坂を下ってすぐのご近所に、もうすぐ壊されてしまいそうな建物があり、
一度見てほしい」と相談を受け、2013年の夏、見に行くことになりました。

新島襄の石碑と緑の島を結ぶ新島橋。木立の上から見えているのは、2018年に函館出身のGLAYが5万人を動員した野外ライブのセット。
その建物は、函館港に突き出た「緑の島」への入口前にありました。
「緑の島」の橋の横には同志社の創立者である新島襄(にいじま じょう)が
ここからアメリカに密出国した記念碑があります。
周りはヨットハーバーになっていて、地元の釣り人がいたり、
花火大会があったり、屋外イベントなどにも親しまれるエリアです。
最近まで倉庫と事務所として使われていたそうで、どこにでもあるような外観の建物。
研究熱心な清水さんも元は何の建物だったかわからなかったようで、
「ひとまず解体は待ってほしい」と東京にいる所有者から借り受け、
私のところに建物の調査依頼がきたという流れでした。
中に入ると、幅約9メートルの空間を支える大きな梁に圧倒されました。
彫刻が施された階段を上がると、立派な床の間のある広間があります。
1階の奥には蔵前戸があり、ここが店蔵だったことがわかりました。

1階の奥に抜けると大きく重厚な観音扉の蔵前戸がある。この横だけ1枚積みのレンガが現れていた。
玄関を見返すと、ドリス式の鋳鉄の柱が大きな梁を支えていました。
この店蔵を抜けると通り土間が続き、木造2階建ての家屋と、
さらに奥には土蔵が残っていました。
私もこの建物が何だったのか、ますます知りたくなりました。
明治時代の1枚の写真を手がかりに
現場調査後のある日、この建物が米穀海産物の委託問屋
〈松橋商店〉であったことが判明しました。
清水さんが図書館から明治45年の電話帳を見つけ、地番から割り出したのです。
私も調査に着手し、函館市のデジタル資料館にある数万点の資料から、
当時は建物前の通りが「仲浜通り」と呼ばれていたことがわかり、
絵葉書や古写真などからさらなる手がかりを探していきます。
そして、ある1枚の古写真に辿り着きました。

「函館仲浜町通り(西部の景)」というタイトルの明治時代の古写真。出典:函館市中央図書館デジタル資料館所蔵(資料番号PC001269)

古写真と同じアングルで見た2013年の様子。左側の白い壁が松橋商店。右側が函館港。
写真を見ると、左から2番目に写る建物のシルエットがこの建物に近似していて、
当時の松橋商店の姿だと確信しました。
翌日、清水さんに写真を見てもらい、古地図の状況とこの写真とを照らし合わせます。
すると、右手前に見えるのは函館の外国人居留地で、その板塀の向こうには海があり、
ここから物資を荷揚げしていたことがうかがえました。
外観になにか痕跡はないかと、玄関の鋳鉄の柱の外側にある不自然な天井を
一部剥がしてみると、なんと当時のものと思われる3連の漆喰のレリーフが現れました。
以前ここで働いていた人にも話を聞いてみると、1993年の南西沖地震で大きく崩れた際、
今のかたちに改装されたのではないかという話でした。

天井の中に隠れていたアールヌーボー調の漆喰鏝絵のレリーフ。※漆喰鏝(こて)絵とは、日本で発展した漆喰を用いてつくられるレリーフのこと。左官職人がこてで仕上げていくことから名がついた。
この建物の歴史を多くの人に知ってもらい、後世に残したい。
そんな思いが芽生え始めました。
そこで1枚の写真と実測調査から復元予想図を起こしたうえで、
建物を活用してくれる人を募ることに。
ところが、貴重な建物だとはわかっても復元には費用がかかるものであり、
現状の姿から活用イメージを持ってもらうのは困難でした。
そこで、西部地区で元々清水さんと交流があったスペイン料理店
〈ラ・コンチャ〉を営む深谷宏治シェフにこの建物について話したところ、
地域のためになるならと協力してくれることになり、まずは外観を復元することに。
所有者の了解も得て、2014年盆明けに復元工事に着手しました。
現代の工法に置き換えた復元

復元の立面図。赤いラインだけが既存で残る部分で、そのほかはすべて残っていなかった。
主に正面の店蔵部分の外観の復元と、内部を飲食店や物販店など
幅広い用途に活用しやすいよう、水道などのインフラを整備することを
最初の目標にしました。
外観の復元には函館市の景観形成住宅等建築奨励金制度を使い、
総工事費1980万円の改修費のうち200万円を補助していただけることになりました。
復元にあたって、準防火地域内なので外壁等に防火構造が求められ、
開口部も一部防火戸などが求められます。
さらに本式の復元には相当なコストがかかるため、
今回の工事では、現代の工法でメンテナンス性も考慮し、
屋根も本物の瓦ではなく軽量な鋼板瓦を採用したり、
外壁も本漆喰ではなく、乾式の下地にスタッコフレックス
(vol.1〈常盤坂の家〉のお風呂でも試した伸び縮みする特殊な塗料)を採用したり、
当時の姿を模した復元風の方針で進めました。
今後の活用を見据えた用途変更の手続きも必要で、
自動火災報知器の設置なども行いました。
建物は基礎から耐震補強しながら、当時の柱の痕跡から屋根の高さを割り出すなど、
独立したての自分には難易度が高い作業が続きます。
〈常盤坂の家〉などほかの工事と同時進行で、ハードな仕事となりました。
工事も終盤に差しかかったころ、工務店の中川健さんが屋根裏で
貴重なものを発見しました。
梁にかかっていた長い1枚の板に、
この建物を建てた建主と大工さんの名前が記してあったのです。
この発見は建物の歴史を裏づけ、建物の価値を大きく飛躍させました。

棟札には、「明治35年7月に函館鍛冶町の大工棟梁山本により建築され 、 普請係(建築係)に越中国東岩瀬1の住人 鈴木義明」と記されていた 。

リノベ後の店蔵の内部。写真右側が正面入り口で、中央奥にあるのがキッチン。キッチン側の壁では土蔵の骨組みを見せ、漆喰も補修した。オープンキッチンの厨房を想定し、入って右の床を1段下げて給排水を整備した。
復元の完成とソシエダの始まり
工事が終わり、この場所は〈港の庵(みなとのいおり)〉と名付けられました。
2014年11月には内覧会を実施。
多くの新聞やメディアに取り上げられるなど反響があり、
この建物の活用者募集も続けたのですが、何件かはお話があったものの、
なかなかご縁に結びつきませんでした。
そこで、清水さん、深谷さんに加え、パン屋〈ヒュッテ〉を営む木村幹雄さん、
ワインショップ〈丸又・和田商店〉の和田一明さん、
オフィス〈オリゾンテ〉の田村昌弘さんと末席に私が発起人になり、
次の世代の誰かがここで何かを始めたいと思うそのときまで、
まずは自分たちが楽しみながら時をつなごうと、
ソシエダ〈臥牡牛快食倶楽部〉を立ち上げることにしました。
ソシエダとは、会員制の美食倶楽部のこと。
深谷さんがスペインのバスク地方サンセバスチャンでの料理修行の際に見てきたもので、
古い建物を生かし、男たちが好きに料理をつくり、政治や宗教や肩書を捨て、
誰もが平等に食を楽しむ場です。
本場スペインでは女人禁制であり、限られた会員だけが利用できるそうですが、
函館では男性の本会員に加え、賛助会員として女性も入会できるようにして、
約30人が集まりました。本会員からの入会金10万円と月1万の会費で建物の維持費や
家賃などを賄い、入会金を元手にプロ仕様のキッチン設備を導入し始めました。

2015年4月、初めて開催したソシエダの様子。会員の紹介であれば一般の人も有料で利用できる。
基本的にこの場所は〈臥牡牛快食倶楽部〉の定期食事会で使用しており、
一般公開はされていませんが、ソシエダが始動してから、
さまざまなイベントとの連携がありました。
まずは、函館西部地区の店を訪ね歩く「バル街」というイベント。
2004年から深谷さんの呼びかけで始まったもので、のちに全国に波及しました。
2015年からこの場所はバル街でもひとつの拠点となりました。
もうひとつが「世界料理学会 in HAKODATE」。
国内外から多くの料理人が集まり、その哲学や手法、
その背景にある風土などを語り披露し合う学会です。
その二次会ではここが会場になり、和洋中の垣根を越えて
ひとつの場をつくることができました。

2019年に開催された、「第32回 秋のバル街」のポスター。その年バル街の取り組みが「第41回 サントリー地域文化賞」を受賞。バル街は春と秋の年2回開催されてきたが、2020年からはコロナの影響で開催されていない。

2015年の料理学会の前日に行われた「バル街」の様子。同年には「第20回 函館市都市景観賞」も受賞。
「おいしい料理をつくれば、人が集まり、まちが変わる」と深谷さんは言います。
食を通してまち並みを守ろうという大人たちの活動、
ひいては自分たちが一番楽しむという自然体の姿に感銘を受けました。
この活動に大きな影響を受けて、そののちに店舗設計をする際は、
バル街にプレオープンを合わせたりと、まちとのいろんなコラボが生まれていきます
(そのお話はvol.4でお伝えします)。

2015年「世界料理学会 in HAKODATE」の二次会の様子。国を問わず和洋中の料理人が肩を並べる活気あるキッチンは、なかなか見ることができない貴重な風景だった。
次回のテーマは外人住宅。
〈港の庵〉の内覧会で出会った映画監督が、
外国人住宅に惚れ込み菜園つきのカフェへとリノベするお話です。
information
港の庵(旧松橋商店)
住所:北海道函館市大町8-26
profile