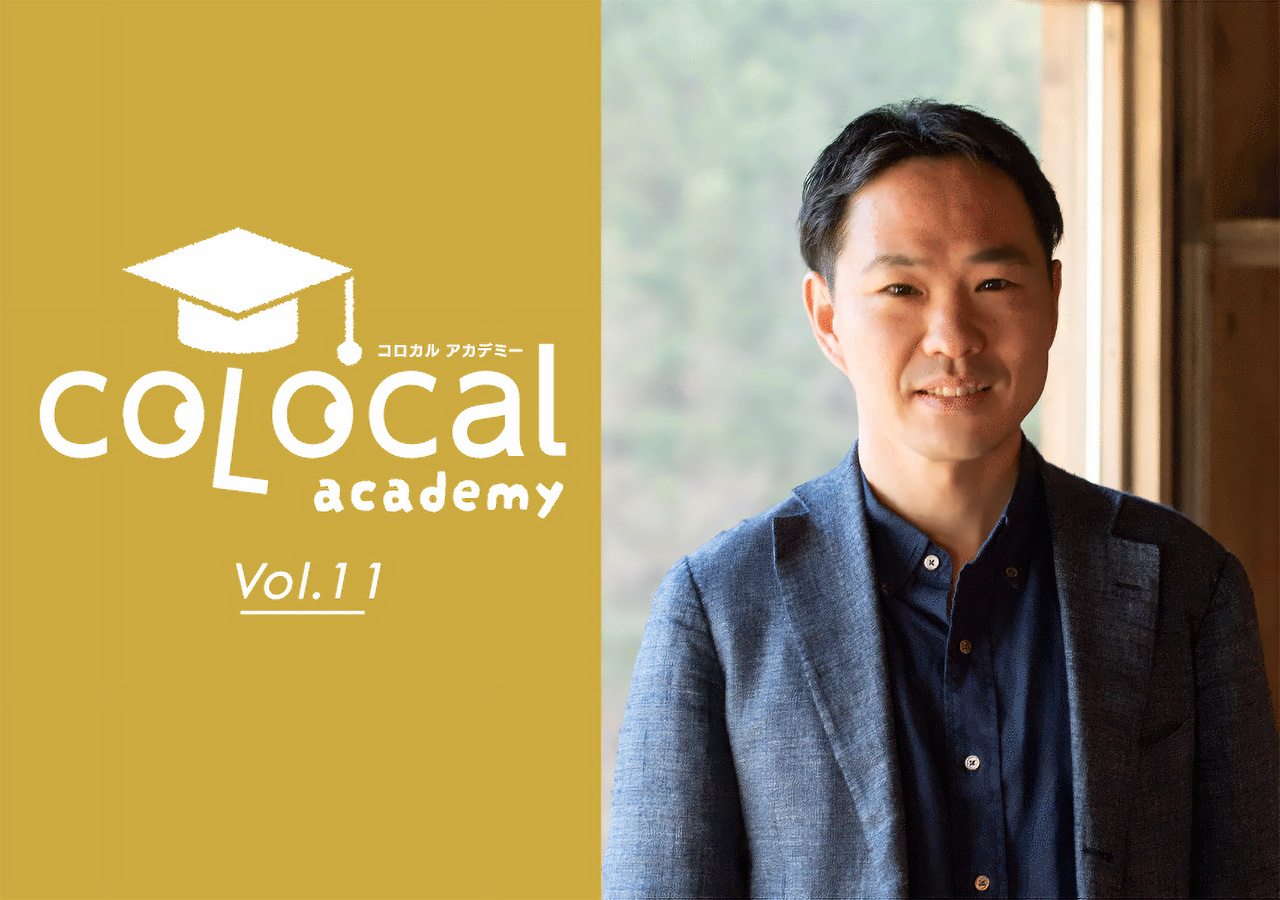〈良品計画〉が取り組む廃校舎活用から
美流渡(みると)のまちづくりを考える

“土着化”をキーワードにした地域とのつながりづくり
昨年、地元岩見沢市の小中学校が閉校して以来、
校舎をどのように活用していったらいいのかについて日々想いをめぐらせている。
これまでさまざまな活動をしてきたが、
昨年末からは、校舎のような規模の大きな施設を運営するためには、
どんなスキルが必要なのかを考える連続セミナーを企画している。
このセミナーは、前半はゲストスピーカーの話から運営方法のヒントを探り、
後半は参加者みんなで校舎活用のアイデアを話し合うというもの。
「森の学校ミルトをつくろう みんなでまちと校舎のことを話してみませんか?」
と題し、第1回目は〈さっぽろ天神山アートスタジオ〉という、
札幌市の旧宿泊施設を活用してアーティスト・イン・レジデンスの拠点を運営する
ディレクターの小田井真美さんをゲストスピーカーとしてお招きした。
年が明けた1月18日には、第2回目を企画。
ゲストスピーカーは、株式会社〈良品計画〉で地域推進を担当する
鈴木恵一さんにお願いした。
良品計画は、〈無印良品〉の商品開発や店舗展開とともに、
近年では地域のサポートも行うなど、活動領域を拡大させている。
千葉県の廃校舎活用も行っていることから、
今回、そうした取り組みについて話をしてもらおうと考えていた。

鈴木恵一さん。1982年西友に入社し、88年に無印良品に出向(のち転籍)してから、主に販売畑を中心に約30年活躍。現在は、北海道地域推進担当となり、地域連携や地域再生のサポートに取り組む。
鈴木さんとの出会いは、一昨年にコロカルで、北海道胆振東部地震から
3か月が経った厚真町の取材をしたことがきっかけだ。
取材したのは「厚真町の今を知る見学会」。
その参加者のひとりとして鈴木さんの姿もあり、この会の帰り道で
お話ししたことがきっかけで、その後札幌で何度かお目にかかる機会があった。
ここ数年、わたしが暮らす美流渡(みると)に
移住者が増えていることに鈴木さんは注目してくれていて、
それならばゲストスピーカーとしておいでいただけたらとお誘いしたのだった。

話し合いに集まったのは約20名。地元住民に加え、市内にある北海道教育大学の学生も参加した。(撮影:吉川幸佑)
鈴木さんのお話は多岐にわたっており、校舎活用はもちろん、
まちの未来を考えるうえで多くの示唆に富んでいた。
まず、良品計画の活動として紹介してくれたのは、千葉県鴨川市での取り組みだ。
地元で活動するNPOとともに棚田の再生をしたり、
地元の生産者の団体が運営していた直売所などからなる総合交流ターミナルを
〈里のMUJI みんなみの里〉としてリニューアルするといった活動が紹介された。
「いま良品計画では“土着化”をキーワードとしています。
鴨川は首都圏から近く里山と里海があります。
未来に残すべき場所として棚田の再生をお手伝いし、
そこから派生して味噌をつくったり、お酒をつくったりもしています」

高齢化にともない維持管理が困難になった棚田を、都市に住む人たちとともに保全する活動をNPO法人〈うず〉と共同で実施。田植え・田の草取り・稲刈りなどの農業体験イベントを実施。(写真提供:株式会社良品計画)
旧校庭にいくつもの小屋を建てる取り組み
学校活用の事例としてあげてくれたのは、
千葉県南房総にある〈シラハマ校舎〉での取り組みだ。
〈ウッド〉という会社が、廃校舎を改修し、
シェアオフィス、ゲストルーム、レストランのある複合施設として
2016年から運営している。
この廃校の校庭には〈無印良品の小屋〉が立ち並んでいる。
ウッドが旧校庭部分を菜園つき小屋の用地として区画・貸し出しし、
良品計画は施工費込みで小屋を販売している。

〈無印良品の小屋〉。水回りなどの設備はない6畳ほどの小さな空間。「気に入った場所でくらす」という夢がかたちになるように、家や別荘ほど大げさではない小屋を提案。小屋の価格は税込300万円からという(オプションや小屋の用地賃貸料は別途。施工は地元の工務店が実施)。(写真提供:株式会社良品計画)
「校舎のある場所は海から近く、春から夏にかけては
サーフィンを楽しむ方がたくさんいます。
また週末に家庭菜園を楽しむ方などもいて、小屋を休憩場所として使っています。
廃校舎が母屋となっていて、調理スペースや食堂、シャワーもあって自由に使えます。
共用できるところは共用して、プライベートスペースは最小限にするという考えは、
活用のヒントになると思います」
同じ千葉県にある大多喜町旧老川小学校の活用も良品計画で手がけており、
地域の課題解決のためのスペースとして活用しようと、
2017年からコワーキングスペースを開設。
このほか食に特化した活動にも力を入れ、
小商いを応援する〈菓子シェア工房老川〉も運営しているという。

2013年に廃校となった大多喜町旧老川小学校。特徴のあるデザインが印象的な建物。(写真提供:株式会社良品計画)

旧老川小学校のコワーキングスペース。一時利用会員は1日500円で使うことができる。(写真提供:株式会社良品計画)
お話を聞いているうちに旧校舎活用の可能性が
どんどん膨らんでくるような気持ちになった。
しかし、同時に千葉県の事例を北海道にそのまま持ち込むことは
難しいという指摘もあった。約半年、雪に閉ざされる北海道では、
冬場の利用をどのように考えるかが重要になってくるという。
無印良品の小屋を北海道でも建てたいという要望もあるが、
断熱や水回り設備をどうするかなどクリアしなければならない課題も多く、
いまのところ実現にはいたっていないそうだ。

美流渡は雪深い地域。今年は積雪が少ないものの除雪がされていないと校舎近くまで行くためには、カンジキやスノーシューが必要になる。
「道内で『道の駅を手伝ってもらえませんか?』と
良品計画へお声がけをいただくことがありますが、
冬のしつらえをどうするかが非常に大事になってきます。
冬場は地元の農産物もありませんし、お客さんもあまり来ませんが、
人を雇う以上は冬季だけ店を閉めるわけにはいきません」
そこで鈴木さんは、冬場活用のヒントになりそうな、
良品計画以外の全国の校舎活用の取り組みについても教えてくれた。
そのひとつは、岡山県西粟倉にある廃校舎が本拠地となっている
〈エーゼロ〉という会社の事例。
ローカルベンチャー支援や建築・不動産関係など事業内容は多彩で、
旧体育館を利用してうなぎの養殖も行われている。
「このように校舎活用のリーダーシップをとってくれる企業があるなかで、
地域の人たちも校舎を利用できる環境にするというのは、
ひとつの方法かなと思っています」
そのほか、冬場も上手に活用している事例として、
美瑛の廃校を利用した〈美瑛料理塾〉についても紹介してくれた。
寄宿制の料理塾があり、レストランと宿泊スペースも併設されており、
夏場は塾生が厨房やホール、ホテルで実技を行い、
観光客が減る冬場に座学を行っているのだという。
また山形県高畠町では、廃校舎を屋内遊戯場〈もっくる〉として
地元材をふんだんに使い改修。人気のスペースとして定着し、
2019年夏にオープンし、わずか1か月で来場者が1万人以上となったという。
このように観光客だけに頼らない、地元の人たちにも愛される施設となれば、
冬場でも有効利用できるのではないかと鈴木さんは教えてくれた。

校舎活用の事例を豊富な写真とともに紹介してくれた。
風と土がうまく融合すると、新しい“風土”になる
わずか1時間ほどのお話であったが、全国でも道内でも、
校舎活用のさまざまな取り組みが行われており、
地域に新しい賑わいをもたらしていることが知ることができて、
わたしは勇気がわいてくるような想いがした。
そしてまとめとした、地域の特色をいかにつくるかという話は心に響いた。
「僕はよく“風の人”“土の人”という言葉を使います。
もとからその土地に住んでいらっしゃるのが“土の人”。
学校の先生や地域おこし協力隊、そして我々のように
住んでいないけれどもお手伝いをしている人を“風の人”と呼んでいます。
土だけで行動を起こすのはなかなか厳しい。風だけでも何もできない。
けれど風と土がうまく融合すると、僕は新しい“風土”が生まれると思っています」
北海道でも続々と移住者がやって来る地域がある。
例えば下川町や東川町など。鈴木さんは、こうした地域の特徴として
「もともとの“土の人”たちが、新しく来た人を受け入れる力があり、
移住した“風の人”たちも溶け込もうとする力を持っていて、
やがて“土の人”と交わってまちができている」と考えていた。
こうした溶け込む力は、美流渡にもあるのではないか。
鈴木さんは、このエリアは元炭鉱街ではあるものの
“炭鉱特有の地域性”が、それほど色濃くないのではないかと感じたという。
これまで夕張など元炭鉱街の課題解決に取り組む活動も行ってきた鈴木さんによると、
石炭がエネルギーの中心的役割を担っていた頃、
炭鉱で働く人の暮らしを大企業や国が手厚くサポートしていた歴史があり、
自分たちが自分たちの手であらゆることを行わなければならないという意識が
根づいてこなかったのではないか、そんなふうに感じることがあるのだという。
「僕は美流渡には、受け入れる力と溶け込む力があるように感じています。
美流渡の移住者は、夢があってここに来ていると思いました。
10年かけて家を建てている人もいれば、手作業でリノベーションをやっている人もいて、
それが着々とかたちになっていく。こうした活動をともに行い、
見守ってくれる土壌がここにはあるのかなと思います。
ですから、これを生かしていくのが、今後のやり方なんじゃないでしょうか?」

美流渡では自分の手で古家をリノベーションする移住者が多い。2年ほどかけてコツコツと改修を進める〈マルマド舎〉は、春からゲストハウスとしてオープンする予定だ。
会の後半では、前回、参加者で話し合った校舎活用のアイデアについて、
さらなる検討を行った。
アーティスト・イン・レジデンスとしての活用や
オーディオ・レコードのコレクションの展示施設にする案などがあったことを
鈴木さんにお話しすると、こうした施設運用をするためにも、校舎で1年を通じて
収入が見込める事業を行うことが欠かせないとアドバイスをしてくれた。

校舎活用のアイデアを黒板に掲示しながら意見交換を行った。(撮影:吉川幸佑)
鈴木さんの言うとおり、さまざまな校舎活用のアイデアは出ているが、
年間数百万規模の収益がなければ、長期的に運用していくのは難しいだろう。
また、それを運用していくための組織づくりも必要になってくる。
今回の話し合いで、重点的に考えていかなければならないポイントが、
くっきりと浮かび上がってきたように感じられた。
そして何より、さまざまな地域とまちの未来について見つめてきた鈴木さんが、
美流渡に可能性を感じてくれていることが本当にうれしかった。
しかも、〈札幌パルコ〉にある無印良品の店舗が
3月にリニューアルオープンするにあたって、
毎月「つながる市」というマルシェを開催していくそうで、
美流渡とその周辺地区でクリエイティブな活動を行うメンバーにも
参加の要請をしてくださったのだ。

美流渡に昨年移住した陶芸家のこむろしずかさんの作品。このほかアクセサリーやフラワーアレンジメントをつくる移住者がおり、地域のメンバーで札幌パルコの無印良品「つながる市」に参加することになった。
「僕は美流渡との関わりは、今日からがスタートだと思っています。
まずは札幌パルコのつながる市で、
情報発信のお手伝いをさせていただきたいと思います。
そして、お互いにこれから行き来しましょう。
また、雪が溶けたら、僕も美流渡にお邪魔したいと思います」
春風が吹く季節になったら、またやってきてくれるという、
鈴木さんは美流渡にとって“風の人”。
鈴木さんが美流渡に注目してくれること自体が、
自分たちの地域に魅力があると再認識できる、とても大切な機会となった。
そして、春までに校舎活用についてビジネスというアプローチから考えを深めて、
鈴木さんともまた意見交換をさせてもらえたらと思っている。

次回の校舎活用の話し合いは3月28日。施設運営に欠かせないビジネス感覚を養うために、税理士で北海道教育大学ではシミュレーションゲームを取り入れ、ビジネススキルを養う講義も実施する前島治基さんがゲストとなる。
writer profile

http://michikuru.com/