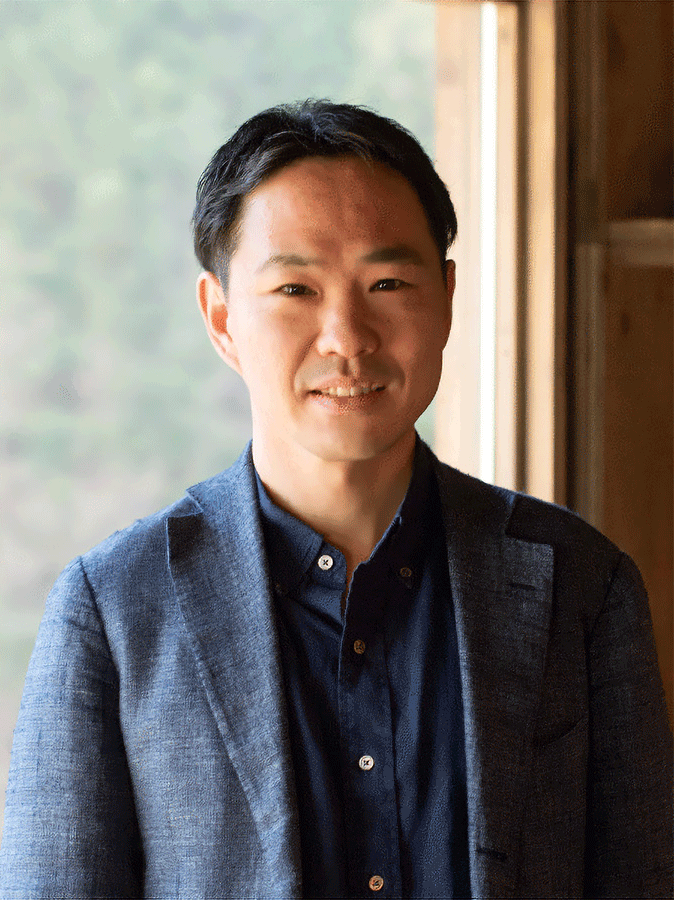いつもの卒業式が
できなかったみなさんへ。
MAYA MAXXの小さな絵本を届けたい

突然の休校、落ち着かない毎日
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
北海道では全国より早く学校や幼稚園がお休みになった。
3年生の長男と幼稚園に通う長女が突然家にいることとなり、
保育所では子どもの受け入れはしていたものの、
大事をとって次女もお休みさせることにした。
考えてみれば、休日でも習い事などがあり、子どもが出かけていることも多く、
家族全員が家で長時間過ごすという状態は案外少なかった。
私は編集の仕事の締め切りが迫っていたので、
基本的には夫が子どもたちをみてくれたのだが、
仕事にあてられる時間は思うようにとれなくなった。

家の前の雪山で遊ぶ子どもたち。休校になったけれど、一歩外に出れば、どこでも駆け回れるのはありがたい。
少ない時間のなかでなんとか仕事をこなさなければと気は焦るが、
まるではかどらなかった。
世界各地に感染が広がり、マスクやトイレットペーパーが品薄になり、
イベントなどの多くは中止や延期。
さらには北海道に2月28日からの3週間、道知事によって「緊急事態宣言」が出され、
とくに29日からの土日は外出を控えるよう呼びかけられた。
次々と変化する状況のなかで、
出口の見えないトンネルの中にいるような感覚がわき上がった。
これは、東日本大震災が起こった直後の感覚ととてもよく似ていた。
あのとき私は、心がザラザラとして胸が詰まるような無力感に襲われた。
揺れ、津波、そして原発事故。多くの人が亡くなり、生活に困る人が出るなかで、
自分は何もできず、ただただニュースを見るばかりだった。
無力ではあったが、震災から2か月ほどして落ち着きを取り戻し、
「できることを、できるかぎりやろう」と、小さな本をつくったことも思い出した。
この本は、当時、福島第一原発の事故がなかなか収束せず
放射能汚染に関する情報が入り交じるなかで、
自分なりにわかりやすく絵と文とでそれを解説したものだ。
タイトルは『放射能と向き合う本』。小さな冊子で150円で配布。
SNSに情報をアップしたところ、多くの反響があり、
1000冊ほどがみなさんの手に渡っていった。
あのとき「自分ができることは本づくりしかない。
それを生かすことが、難しい局面に向き合う一歩なのでは?」
と強く実感したことを覚えている。

2011年5月『放射能と向き合う本』という小さな冊子をつくり、その後『3つのお願い』という絵本も出した。
緊急事態宣言が出た翌日に始まった本づくり
北海道で緊急事態宣言が出された翌日、とても心が揺れていた。
重苦しい空気が渦巻いていたが、そのなかで、
何かに駆られるように本をつくらなければと思った。
真っ先に思いついたのは、突然休校になり、
区切りも何もないまま春休みに入ってしまう子どもたちもいることだった。
卒業式がなくなってしまったり、いつもどおりできなくなってしまったことを、
子どもたちはどう思っているのだろう?
そもそも、卒業する「式」という行為のなかで、
心に温かく染み入るようなできごとというのは、なんなのだろうと考え始めた。

なぜ、こんなことを疑問に思ったのかというと、
私自身、子どもの頃、卒業式の意味がいまひとつわかっていなかったからだ。
卒業は節目であるけれど、友だちとはまた会って遊べばいいわけだし、
授業もたいしておもしろいと感じたこともなく、式で泣く人が不思議でならなかった。
けれどなぜ泣くのかの理由が、あるときハッとわかったことがある。
人口400人ほどの美流渡(みると)地区に移住して、
小さな小学校のたったひとりの卒業式に参加したときのことだった。
6年生の少年は、大粒の涙を流し続けていた。
その姿を見ていて、いま彼の頭の中に、この6年間が走馬灯のように蘇っていて、
そのひとつひとつに精一杯取り組んだ自分というものを感じ、
涙があふれているんじゃないかと思ったのだ。

たったひとりの卒業式。それを見送る生徒たちは教室のあちこちをメッセージで飾った。
こんな体験から考えたのは、式が大切なのではなく、
自分の人生を振り返り、そこから未来に気持ちを向ける
きっかけがつくれたらいいんじゃないかということだった。
きっかけなら本でもできるかもしれない。
今回、私にはとても心強い存在がいた。
この連載でまた書くことになると思うが、20年来の友人で、
美流渡にも何度か訪ねてくれたことのある画家・MAYA MAXXさんと、
いま新しいプロジェクトを計画しており、毎日のように連絡を取り合っているなかで、
「卒業おめでとう」で始まる絵本をつくってくれないかと相談してみた。

画家のMAYA MAXXさん。
先に書いたような、卒業式に対する考えをMAYAさんにお知らせしたところ、
なんと30分も経たないうちに、絵本の言葉を送ってくれたのだった。
それを読んで、本当にすばらしいと思った。
そしてMAYAさんの「みんなよくやったね!」という言葉にとても共感した。
卒業のときにこんなふうに声をかけてもらえたら、
次なる一歩を踏み出せるエネルギーがわいてくるんじゃないかと思った。

MAYAさんは数々の絵本を刊行している。写真は愛くるしい表情の『ぱんだちゃん』と『らっこちゃん』。
そして、もうひとつMAYAさんは私に教えてくれた。
「友だちとみんなで泣いたり歌ったり
別れを惜しんだりしたかったと残念な子も
卒業式がなくなってほっとしている子も
いい思い出がたくさんあった子も
いい思い出なんかひとつもなかった子も……」
誰にでもフラットな眼差しを注ぐ、MAYAさんならではの言葉。
卒業式がいつもどおり行えないことを、
みんな残念に思っているんじゃないかという一方的な感覚でいたけれども、
確かにホッとしている子もいるだろうし、
学校に行かないという選択をしている子もいることに
意識が及んでいなかったことに気づかされた。
そして、言葉とともに、制作中だった青い馬の絵の画像を送ってくれたので、
さっそく言葉に合う絵を選び、レイアウトをして、
その日のうちに絵本ができあがった(すごいスピード!)。
翌日、私は新しいFacebookのページをつくった。
Luceとはイタリア語で光。
MAYAさんが考えてくれた、新しいプロジェクトの名前だ。
そのプロジェクトとは、MAYAさんの制作の本拠地となるアトリエを、
私が住む美流渡地区に設け、地域のみなさんの協力のもと、
大きなスケールの作品を制作していこうという取り組みだ。
詳細は、もう少し時間をかけて発表していくつもりだが、
この時期に届けたい絵本が生まれたので、とにかくその公開を優先することにした。


サイトには自由にダウンロードをしてもらえるよう、面つけした絵本のPDFもアップした。
絵本をアップして早々、さまざまな反響が寄せられた。
卒業式は開かれるもののいつもどおりには行えなくなったという先生が、
生徒にこれを渡したいと言ってくれた。
MAYAさんの温かな気持ちが伝わってきてうれしかったというコメントもあった。

MAYAさんは、現在、東京にアトリエを持っているが、もっと大きな絵をどんどん描いていきたいと、美流渡地区に拠点を持つことを決めた。
今回、新型コロナウイルスの感染拡大によって、
当たり前だと思っていたことに目を向けるよい機会になったと思う。
そして、私の「卒業式とはなんだろう」という素朴な疑問から、
何十倍何千倍も跳躍して、すてきな絵本を生み出してくれたMAYAさんに
心から感謝したいと思った。
自分ひとりだったら躊躇してしまうアクションも、
MAYAさんと並走することで大きく可能性が広がっていく。
これから始まるLuceプロジェクトに注目してもらえるとうれしいです。

writer profile

http://michikuru.com/