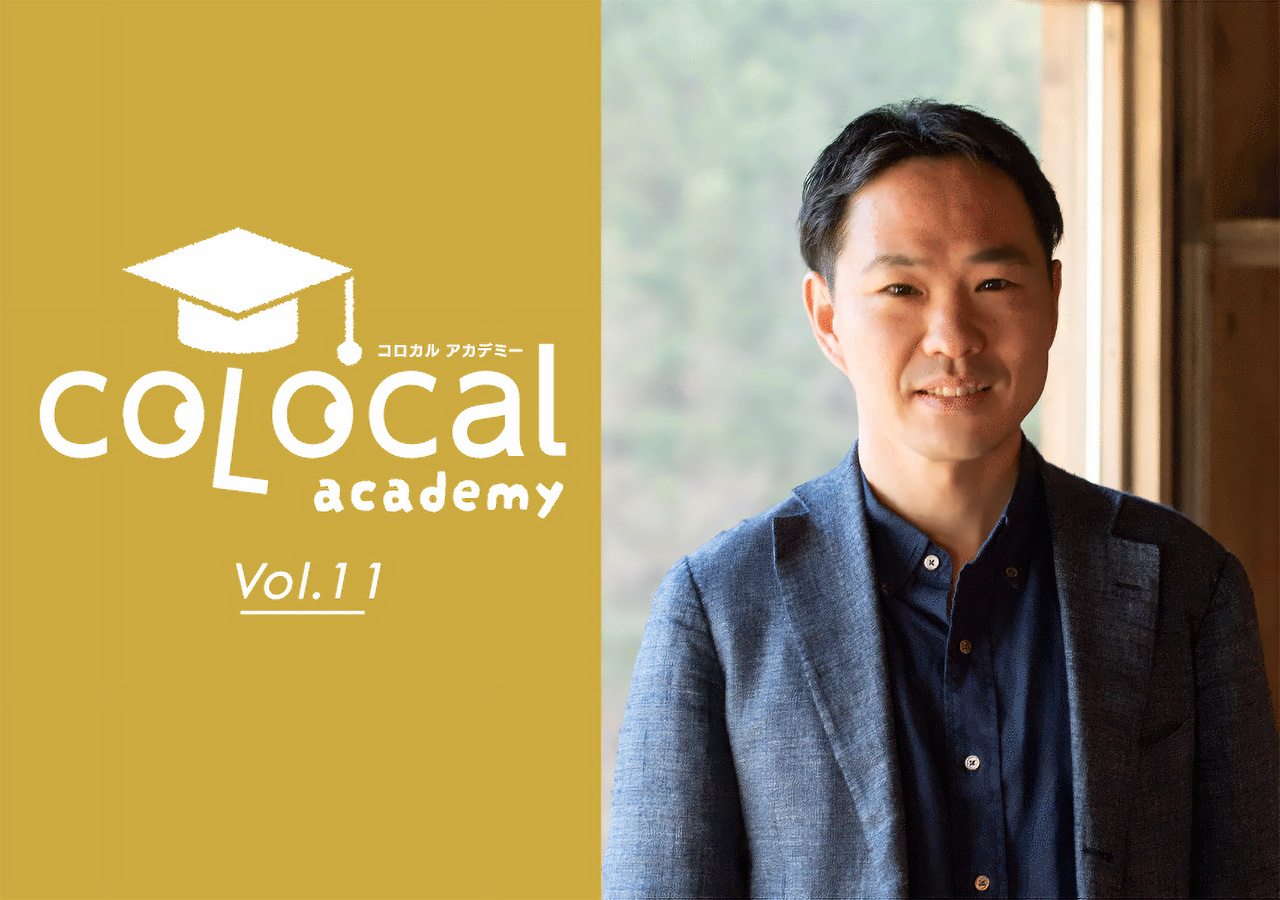閉校した美流渡の小中学校を活用して
〈森の学校 ミルト〉をつくりたい!

北海道教育大学岩見沢校との協働で生まれた、新しいプロジェクト
今年の春、わたしが住む美流渡(みると)地区にあった小中学校が閉校となった。
閉校前の生徒の数は、小中合わせてわずか18名。
学校をなんとか存続させたいという地域の想いもあったのだが、
今後は入学者がいない年もあると予想されることもあり、閉校が決まったのだった。

小学校の全校生徒は7名だったが、教室には元気いっぱいの声が響き渡っていた。(撮影:佐々木育弥)
昨年より閉校に関するPTAの話し合いが何度も行われた。
わたしの息子が小学校に通っていたため、
この話し合いに参加していたのだが、そのたびに
「当たり前にあった学校が地域から姿を消すこととはいったいどんなことなのだろう?」
「校舎は今後どのようになっていくのだろう?」と疑問がわいた。
そこで、学校の施設を管理する教育委員会の職員や校長先生に、
今後の校舎利用の方針について尋ねてみたりもしたが、
検討中ということで展望は開けていない状態だった。

小学校の閉校式の様子。開校から115年ということで、115個の風船を飛ばして学校とのお別れをした。(撮影:佐々木育弥)
そんななか、地域のPRなどで日頃から活動をともにしている仲間と、
機会があるごとに、学校利用について語り合ってきたが、
なかなかアイデアを実行に移すことができないでいた。
細々と続けている地域PRの活動ですら本業との両立が難しくて手薄になっており、
学校の活用プランまで手が回らないというのが現状で、
気がつけば春になり、閉校を迎えることになってしまった。
校舎1階の窓には板が取りつけられ、雑草もどんどん大きく育ち
閑散とした風景が広がるようになった。
そして、市街地の学校へと通うことになった生徒の家族数名が、
この地域を離れていくこととなった。

閉校後の小学校の校舎。玄関や1階の窓には板が貼られ、ひっそりと静まり返っている。
わたしは校舎の脇を通り過ぎるたびに、
見て見ぬ振りをしていてはいけないのではないかという思いが募っていった。
また、息子に荒んでいく学校を見せたくないという気持ちもあった。
こうした悶々とした気持ちを抱えていたときに、
北海道教育大学岩見沢校の教授・宇田川耕一先生から、
計画中のプロジェクトへ協力してほしいという依頼があった。
そのプロジェクトとは「万字線プロジェクト」という名称の教育プログラム。
万字線とは、岩見沢の山あいがかつて炭鉱街として栄えた時代に、
主に石炭輸送のためにつくられた鉄道路線のことで、
わたしが住む美流渡地区をはじめ各地に駅があった(1985年に全線廃止)。
教育大では、現在過疎化が進んでいるこの地域で、学生がリサーチを行い、
必要とされる拠点づくりなどの企画やイベントを実施し、
そのプロモーションも行うという一連の体験を通して、
実践的な課題解決に取り組める人材を育てるプログラムを行おうと考えていた。

宇田川先生は、芸術・スポーツビジネス専攻の教授。毎年1年生を美流渡に引率し、フィールドワークも行っている。こうしたつながりから「万字線プロジェクト」が生まれていった。
宇田川先生の話を聞いていくなかで、わたしはハッとひらめいたことがあった。
「万字線プロジェクト」のひとつの目玉として、
炭鉱街として栄えた時代に多くの生徒でにぎわっていた美流渡の小中学校を、
学生の手によって復活させるというプログラムにしてはどうかと提案した。
北海道教育大学岩見沢校は、市内では唯一の大学で、
芸術、スポーツ、それをつなぐビジネスという専攻が集まっているという特徴を持つ。
美流渡をはじめとする岩見沢の山あいには、
工芸家やアーティスト、ミュージシャンなども住んでおり、
移住者によってスポーツのアクティビティも増えていることから、
この大学の専攻との親和性も高いとわたしは思っていた。
宇田川先生は「それはおもしろいですね」と目を輝かせてくれ、
わたしが学校復活のアイデアの大枠を書くことになった。

プロジェクトの最初に書いたプラン。
名づけたタイトルは「森の学校 ミルトをつくろう」。
学生たちが炭鉱街としてにぎわった歴史を探り、
こうしたなかからイベントや施設利用の企画を生み出し、
活動全体を外に向かって発信していく、
リサーチ・アクション・プレゼンテーションを行う
ラボスペースのようになればと考えた。
そして、わたしの構想をもとに、宇田川先生が
7月の毎週土曜日に3回連続でセミナーを行うことを計画してくれた。

セミナーで話をする宇田川耕一先生(中央)。
学生と市民が考える、〈森の学校 ミルト〉の未来像
3回のセミナーのうち2回は、市民と学生とが集まって、
森の学校 ミルトの未来について考えるというもので、
7月13日、20日に岩見沢駅の有明交流センターで実施した。
13日には「もし1日、イベントで体育館が使えるとしたら何をしますか?」
がテーマとなった。

2回のセミナーが行われたのは岩見沢駅にある有明交流センターというオープンスペース。グループに分かれて、小中学校の活用方法が話し合われた。
参加したのは約20名。それぞれ5チームに分かれてアイデアを出し合った。
わたしが座ったテーブルでは、美流渡にあるお寺「安国寺」の
岡田博孝住職も話し合いに参加してくれていた。
安国寺は小中学校の向かいに建つお寺。学校とともに歩んできた歴史を振り返り、
閉校後はお寺が子どもたちの集う場になったらと
“寺子屋”をやってみたいという話をしてくれた。

岡田博孝住職の話からグループトークで上がったのは「教育大分校 寺子屋」というプラン。模造紙にプレゼンシートをつくり、学生が中心となって発表を行った。
このほか美流渡には最近移住者によってカフェやカレー屋さんなどもでき、
隣の地区である毛陽には果樹園なども多く「食」に魅力があること。
また音楽やスポーツのワークショップなどの「体験」も行われていることから、
こうしたさまざまな才能を体育館に集めて
「ミニミルト」をつくってはどうかなどのアイデアが出た。

小中学校は隣り合って建っており、こちらが中学校。2010年度に大規模な改修が行われ、設備が行き届いている。(撮影:tacaё)
20日には「森の学校 ミルトの3年後の未来予想図」というテーマで
話し合いが行われた。
「展示、キャンプ、宿泊、交流スペース、保育園も! 教育大学のサテライトに!!」
というアイデアや、
「ミルトはアートのまち。体育館が美術館に。
アーティストインレジデンスが恒例行事になっている」という
芸術とスポーツに特化した大学ならではのアイデアもあった。

アート専攻の学生も参加して、プレゼンシートを制作。模造紙に楽しげな絵をたくさん描いたグループも。

〈森の学校 ミルト〉の3年後の未来予想図とは? キャンプや美術館として活用するアイデアなど、ワクワクするようなプランばかり。
なかでもわたしが注目したのは「毎月第3水曜日はみるとの日」というプラン。
月1回、美術、音楽、飲食、スポーツ、雪があればかまくらなど、
さまざまな体験をやってはどうかというものだ。
いま美流渡地区では週2回ほどアフリカ太鼓の奏者である岡林利樹さんが
太鼓教室を行っているし、美流渡の森の山荘では月1回太極拳の講座も行われている。
こうしたアクティビティを同じ日に開催するようにしたり、
マルシェを開いたりすれば、地域外の人たちがきっと来やすくなる。
特に大きな準備をせずとも、すぐに始められるこのプランは
ぜひとも試してみたいと思った。
閉校した校舎に戻った子どもたちの笑顔
翌週の27日には、閉校になった中学校の体育館を使った
教育大生によるイベントが開催された。

閉校になった小学校に通っていた子どもたちも集まった。「理科」コーナーで片栗粉のスライムづくりを体験中。(撮影:tacaё)
2日間のセミナーと並行して、学生たちはこの日のために企画を検討してくれており、
元学校ということで「図工」「理科」「体育」をテーマにし、
プリザーブドフラワーなどを瓶につめてオイルで満たす「ハーバリウム」づくりや、
片栗粉、重曹などを使った「バスボム(入浴剤)」づくり、
子ども向けの水鉄砲による的あてゲームなどが行われた。
美流渡の町内会も協力して地元住民への参加も呼びかけたこともあり、
62名もの人たちが中学校を訪れてくれた。

金魚すくいのアミをダンボールでつくったキャラクターに取りつけて、水鉄砲で的あてゲーム。(撮影:tacaё)

ハーバリウムづくりは一番人気。ドライフラワーやビーズなどを思い思いに入れたら、最後に専用のオイルで満たして完成。1年ほどもつという。
この日、体育館の壁には、2回行われたセミナーで挙がったプランも掲示されており、
長年地元に住む人が、それをじっと見つめながら
「こんなふうに学校が使われたらいいよね」としみじみと語ってくれた。
また、閉校してひっそりとしていた学校に
「子どもたちの歓声が響いてすごくうれしくなった」と語ってくれた人もいた。
また、来場者も学校の未来についてのコメントを書く場を設けてみたのだが、
そのどれもが希望にあふれるものだった。

来場者にも書いてもらった森の学校 ミルトの未来像。アートスポットとしての活用意見が複数挙がっていた。(撮影:tacaё)

予想以上に子どもたちが集まり、水鉄砲のゲームは外へと移動。思いっきり遊び回った。
何より町内の人たちがずっとその場に残ってくれて、
地域の今後のことを夢中で語り合っていた姿に、こちらも胸が熱くなる思いがした。
たった3日のイベントではあったが、校舎の活用について、
みんなで考える本当によい機会になったと思う。
これまで地域では、学校の運動会に住民みんなが関わって
アットホームな場をつくり出していたり、さまざまな恒例行事があったが、
閉校によってそのいくつかは姿を消してしまった。
学校があってもなくても日常は変わらずに過ぎていくが、
地域をつなぐ核であった場所がないということは、
なにかぽっかりと穴があいてしまったような気がしてならない。
生徒数の減少によって学校が存続できないという事実は受けとめつつも、
それであれば、いまの地域にフィットしたサイズの、
新しい拠点として生まれ変わっていけばいいのではないか?
3回のセミナーを終えて、わたしはまたひとつプランを書いてみたくなった。
例えば、美流渡の中学校をまずは生かすと考えるならば、
1階はシェアオフィスとして美流渡に住んで仕事をしやすい環境をつくる場に、
2階と体育館はさまざまなワークショップができる体験施設として、
3階は近年増えている移住希望者が活用できる“おためし移住”施設として
活用していくのはどうだろうか?
いま、移住者が徐々に増え、さまざまなアクティビティが生まれているこの地域で
起こっている動きを積み上げていけば、こんなかたちが自然ではないだろうか?

3回のセミナーを通じて新たに考えてみたプラン。あらためて中学校の図面を見直してみると、市街地の学校よりもずっとコンパクトな施設であることに気づいた。
「森の学校 ミルトをつくろう」は、まだ始まったばかり。
今後も学校施設の活用について、さまざまな意見を出し合って、
その輪を大きく広げていきたい。
writer profile

http://michikuru.com/