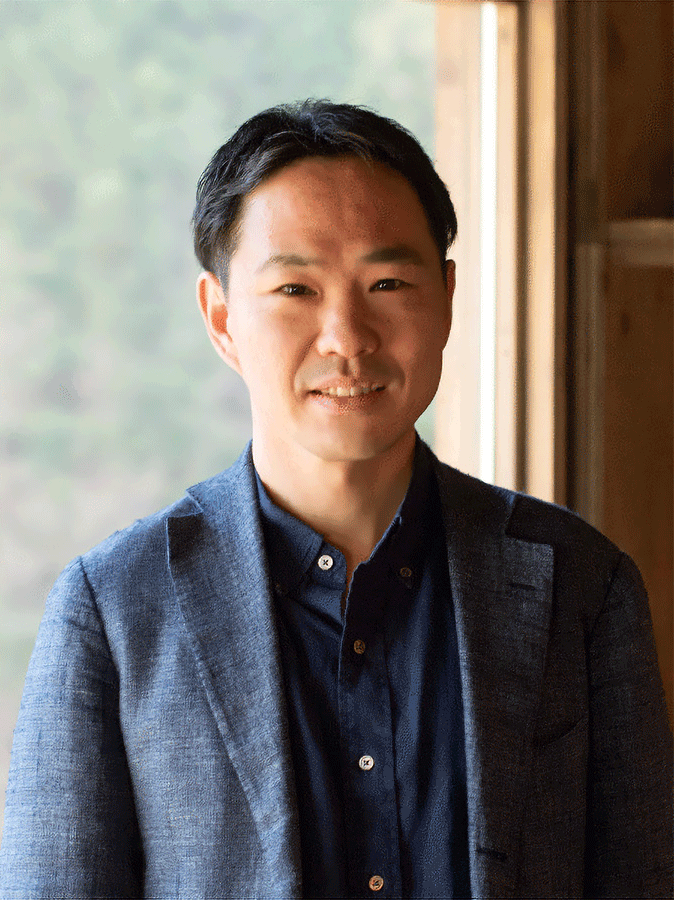キャンピングカーは“住まい”となるか?
太陽光発電、リフォーム、収納。
工夫に満ちた暮らしを追う

美流渡の展覧会にケビンとキャサリンがやってきた!!
北海道岩見沢市で開催した、地域のつくり手の作品を発表する『みる・とーぶ展』と
美流渡(みると)在住の画家・MAYA MAXXさんによる
『みんなとMAYA MAXX展』が、10月1日に幕を閉じた。
舞台となったのは4年前に閉校した旧美流渡中学校。
私が代表を務める地域PR団体が毎年企画していて、今回で6回目。
この秋の開催は、12日間で参加メンバーは20組以上となった。
人口わずか300人ほどの美流渡地区に道内外から多数の来場者が訪れた。

会場となった旧美流渡中学校の入り口にはMAYA MAXXさんによる赤いクマのAmiちゃんが置かれている。展覧会前にケビンさんとキャサリンさんがキレイに洗ってくれた。
展示だけでなくワークショップやライブなどがにぎやかに行われるなかで、
新しい試みとなったトークイベントについて、今回は紹介してみたい。
企画をしてくれたのは、キャンピングカーでソフトクリームを販売しながら
日本各地をめぐっているケビンさん(本名は中谷兼敏さん)。
これまで3つの小屋をつくってきた経験をもとに
「タイニーハウスと太陽光発電 ケビンの体験トーク」を、会期中の9月23日に開催した。

ケビンさんの体験トーク。YouTubeの「おっ!チャンネル」にたびたび登場しており、チャンネル視聴者もトークに駆けつけた。
このトークの内容を紹介する前に、ケビンさんとの出会いについて紹介しておきたい。
2019年に美流渡とその周辺を紹介するツアーが行われ、
そこにケビンさんが参加してくれたことで、私は知り合った。
ケビンさんは新婚旅行中。妻のキャサリンさん(本名は中谷清美さん)と
キャンピングカーで北海道をめぐっていて、
いつかソフトクリームを販売したいと話していた。
その2年後に再会。ふたりはこのとき〈カフェ・アルコバレーノ〉という名で
ソフトクリームの移動販売を始めていて、美流渡でも営業をしてくれた。
北海道にいるのは夏の間だけ。現在は、寒くなると三重で営業し、
その後、宮崎で数か月を過ごし、また北海道にやってくるという暮らしを続けている。

旧美流渡中学校でみる・とーぶ展を開催するようになって、毎年、カフェを開いてくれるようになった。
素人でも建てられる! と実感した、第1の小屋づくり
トークでは、専門的な技術を持っていなかったケビンさんが
小屋を建てることで気づいた、さまざまな体験が語られた。
現在の移動できる小屋(キャンピングカー)に住む以前、
長野と三重に小屋を建てたことがあるという。
小屋に憧れを持ったのは、子ども時代。
木を集めて簡単な小屋をつくってみたり、好きな小屋のイメージ図を描いたりしていたそうだ。
若かりし頃、旅をするようになり、ロッキー山脈の麓にあるユースホステルを訪ねた。
宿泊できる小屋が点々とあり、センターハウスにはキッチンや冷蔵庫があって、
そこをみんなで使っていたという。
見上げれば満天の星。
こんな小屋で暮らすことができたら幸せなんじゃないかという思いが湧いたと語る。

長野で小屋を制作中のケビンさん。
そんな夢が具体化したのは28歳のとき。
名古屋で暮らしていたケビンさんは、小屋を建てる土地を探していたという。
なかなかいい場所に巡り会えずにいたが、ちょうど友人が長野の土地を手に入れ、
そこで一緒に小屋を建てることにした。
休日に長野へ通い小屋づくりに励んだ。
当時は、ログハウスに注目が集まりブームとなっていた時代で、
ログハウススクールが各地で開かれていた。
講習に通うと時間もお金もかかると考えたケビンさんは、
スクールを見学させてもらって、そこでログハウスの構造をしっかりと目に焼きつけ、
見よう見まねでつくっていったという。

ログハウスを仲間たちと一緒につくった。
「大失敗したのは、4×8メートルの広さにしたことです。
市販の木材は3.6 メートルが基準になっているものが多くて、
途中でつなぐことになるなど面倒な作業が増えました。
また、道より上に小屋をつくることにしたので、材を運ぶのがとにかく大変でした。
道より下につくったほうがいいと、あとから気づきました」
こうした体験から効率のいい木材の取り方など、
ある程度の知識が必要であることを痛感したという。
また、思った以上に時間がかかることもわかったそうだ。
想定の10倍。80%完成するまでに3年を要した。

傾斜地に立てたので土台をつくるのも大変な作業だったという。
では、こうした小屋は一体いくらでできるのだろうか?
材料費は、地元の杉丸太を使うなどして90万円ほど。
そのほかキッチンなどの設備は無償で手に入れたものも。
「材料を買うのは最終手段。念じていると材料を拾ったり、もらったりできるし、
工夫してつくったりもできるとわかってきました」

小屋の内部。シンクや換気扇は人からもらったそう。
仮に人件費を考えるならば、3人が40週働き、それが3年続いたとして360人工。
1人工を2万円とするならば720万円(!)
ケビンさんによると、プロに施工を頼む場合、
おそらく100〜200人工となり300万円くらいなのではないかという。
さまざまな課題を乗り越え完成したとき、
「素人の技術でも小屋は建てられる」と実感したとケビンさん。
その後も補修や改装などを行いつつ、20数年ほどこの小屋に通っていたそうだ。

母屋ができ、時間的な余裕ができてから風呂場をつくった。
第2の小屋は極小空間。暮らしてわかった優先順位
第2の小屋をつくり始めたのは56歳のとき。
三重県に移り住み、フリーランスで木材商を営んでいたときのこと。
あるとき知人の山の一角に小屋を建て、そこに住もうと考えたという。
このとき建てたのは2×4メートルという4畳一間の小屋。
仲間が10数名集まって、ワークショップのようににぎやかに作業が行われ、
わずか2週間で完成させた。

第2の小屋。沢があって陸の孤島のような場所に、みんなで橋をかけてから、小屋づくりを行った。
この小屋の材料費は20万円くらい。
材料費のうち3割強は、断熱材に使用したウールの価格。
本来は、材木代だけで20万円くらいするが、
たまたま廃業した大工さんの持っていた木材を利用できることになり3万円で済んだ。

この頃から、もらった太陽光パネルで発電を始めた。

暖房設備は湯たんぽ。手製のロケットストーブでお湯をわかした。
4畳一間という極小の空間に住むことになり、暮らしに何が必要なのか、
その優先順位を考えることになった。
第1に「寝られるところ」、
第2に「収納するところ」、
第3に「食べるところ」。
この3つをまず確保したうえで、時間的、空間的に余裕があれば
「楽しむところ」をつくったらいいのではないかという。

ベッドと小さな机、棚が設置されている。
この小屋に住んだのは3年。
その後、ケビンさんはキャサリンさんと出会い、結婚することとなった。
現在の小屋は手狭なため、新しい小屋を建てて暮らそうと考えた。
長野の山に土地の候補も見つかった。
そのため、いままで住んでいた小屋は長野に住む友だちに譲ることを決め、
また愛知に所有していた家も売りに出し、買い手がついたという。

小屋はクレーンで吊り上げ長野まで運んだ。移動費は15万円ほど。
第3の小屋は移動可能。キャンピングカーで暮らし、5年が経過
「候補の土地はあと一歩で購入というところまでいったんだけど、うまくいかなくて。
そんなときに、キャンピングカーで生活したら、おもしろいんじゃないかって思ったんだよね」

購入したキャンピングカー。
2019年に200万円でキャンピングカーを購入。
しかし、購入後とんでもないことに気がついたという。
内装はキレイにリフォームされていると思ったが、
壁を少しはがしてみると、内部の木材がすべて腐っていた。
そのため全面改修することとした。

内装は割合キレイだと思っていたが……。

内部の木材は腐っていた。

そのため内装のすべてを外して一からやり直すことに。
「愛知の家も、住んでいた小屋もなくなって、むしろよかった。
退路が絶たれていて、背水の陣。もう改修するしかなかった」
今まで住んでいた小屋は、友人に譲渡するためトラックで三重から長野に運んであった。
友人に頼み、この小屋に1か月間仮住まいさせてもらい、急ピッチで改装を進めた。

三重にあった小屋が長野に到着。
その後は、旅をしながら改装を続け、3年で8割が完成。
水道工事は、札幌のホームセンターの駐車場を借りて行ったこともあるという
(材料がすぐに手に入るので、とても助かったそう!)。
キャンピングカー暮らしは5年目となったが、いまだに改装は続いている。

キャンピングカーの全長は6メートル。
運転席が1.5メートルで、住居部が1.9×4.5メートル。
これがふたりで暮らせる最小面積だと思うと、ケビンさん。
暮らしのなかで大切なのは収納だそうで、椅子やベッドの下に
ものが入るように工夫している。

引き出しはそれぞれ高さを変えている。移動中に食器が割れないように布で包む。

天地の幅がある引き出しには、ボールやザルなどを収納。

調味料入れの引き出しは、板だと厚みが出てしまうのであえてダンボールで制作。汚れることも考慮に入れ、作り替えられるようにしてある。ボトルはすべて四角。円だとデッドスペースができてしまうから。
冷蔵庫やクーラーが常時稼働! 太陽光発電で電力はまかなえるの?
太陽光発電は三重に建てた小屋のときからチャレンジを始め、
キャンピングカーの屋根には、4枚のパネルが取りつけられている。
私は電気についてはまったく知識がないが、ケビンさんの説明はとてもわかりやすかった。

天井に取りつけられた太陽光パネル。
一般的に太陽光は1平米あたり1000W発電できるが、
そのうち電力に変換できるのは20%程度の200W。
ケビンさんの取りつけたソーラーパネルは7平米で、
通常の性能だと1240W発電できる。
実際に発電できる電力量は1日あたり、晴天の場合、
春夏秋が6000Whほどで冬が3000Whほど。
冷蔵庫(300L)やクーラーを動かしつつ、
余剰が出ればバッテリーに充電するようになっている。

太陽光発電の充電状況がわかるモニター。
ケビンさんによると太陽光発電だけで、すべての電力をまかないきれないときもあるという。
そのため別の方法も併用していて、車のエンジンをかけたときと
外部に電源をつないだときに充電ができるシステムも用意してある。
これら電気関係でかかった費用は65万円ほどだったそうだ。
「夜中に冷蔵庫が止まってしまうなんてこともあるけれど、
そうしたらエンジンをかけて充電するという対応もできます」

ソフトクリームの機械の配線。

外側にも収納が! 工具類をたくさん収納。
太陽光発電についてのトークのあとは質問タイム。
「暮らしのなかで困ることは?」との問いかけに「ゴミの処理」とケビンさん。
まずは量り売りなどゴミの出ない買い方をし、スーパーで買った食材はその場で処理し、
発泡トレイを資源回収ボックスに捨てたりもするという。
また、全国に友人がいて、訪問したときにゴミの処理をお願いしたり、
ゴミの回収業者に直接持ち込むこともあったりと、その場、その場で工夫をしている。

水をタンクに溜めるときに使うアタッチメント。これだけあれば、どんな蛇口の形状でもほぼ対応できるそう。
「旅の途中で、キャンピングカーを停める場所をどうやって見つけるのか?」
という質問もあった。
移動中はキャンプ場などを利用し、
それ以外の場合は友人の敷地に停めさせてもらうことも多いそうだ。
トークのあとはキャンピングカーの見学会が行われ、
ケビンさんが苦心してつくった水道の配管や発電の様子などを見せてもらった。

ソフトクリームにもこだわっている。北海道の西興部村(にしおこっぺむら)で草だけを食べて育った牛のミルクを使用。口の中でさっと溶け、さわやかな風味が広がる。
今回のトークで、キャンピングカーで暮らすということは、
私たちが「当たり前」だと思っていることの外側にいるということで、
日々、工夫や試行錯誤の連続なのだということがわかった。
どんな課題があっても、ケビンさんとキャサリンさんは、いつでも着実に情報を集め、
それを精査し、クリアしていくということを繰り返している。
そして何よりこうした暮らしを続けていける最大のわけは、ふたりが、
その場のムードをパッと明るくする魅力を持っていて、
相手を想う気持ちにあふれているからなのではないかと思う。

みる・とーぶ展に参加していた焼き菓子屋〈グランマヨシエ〉のシフォンケーキをソフトクリームに合わせて。「来年はメニューとして出そう!」とケビンさん。こんなふうにいつも、一緒に並ぶ店舗を応援するようなメニューを考えてくれる。
「みっちゃん、おはよう! コーヒー飲みにおいで」
みる・とーぶ展、みんなとMAYA MAXX展の期間中、
朝、必ずケビンさんとキャサリンさんは私にそう声をかけ、キャンピングカーに招いてくれた。
おいしいコーヒーと、とっておきのおやつと、ふたりの楽しい旅の話と。
この朝の一杯のおかげで、12日間乗り切れたといってもいいくらい、
大切なひとときだった。
こんなふうに各地でふたりは幸せを届けている。

朝の日課。ケビンさんが、自身で焙煎したコーヒーを淹れてくれる。
10月1日17時。
会期が終了してすぐに、ケビンさんとキャサリンさんは美流渡を出発し、
中継地点のひとつである札幌へ向かった。
溌剌とにぎやかだった思い出と、人生の指針となるようなタネのようなものを残して、また旅へ。
その姿は、まるで映画『男はつらいよ』の寅さんのようであり、
小説『ムーミン』シリーズのスナフキンのようでもあった。
ケビンさん、キャサリンさん、ありがとう! また来年!!

writer profile

https://www.instagram.com/michikokurushima/