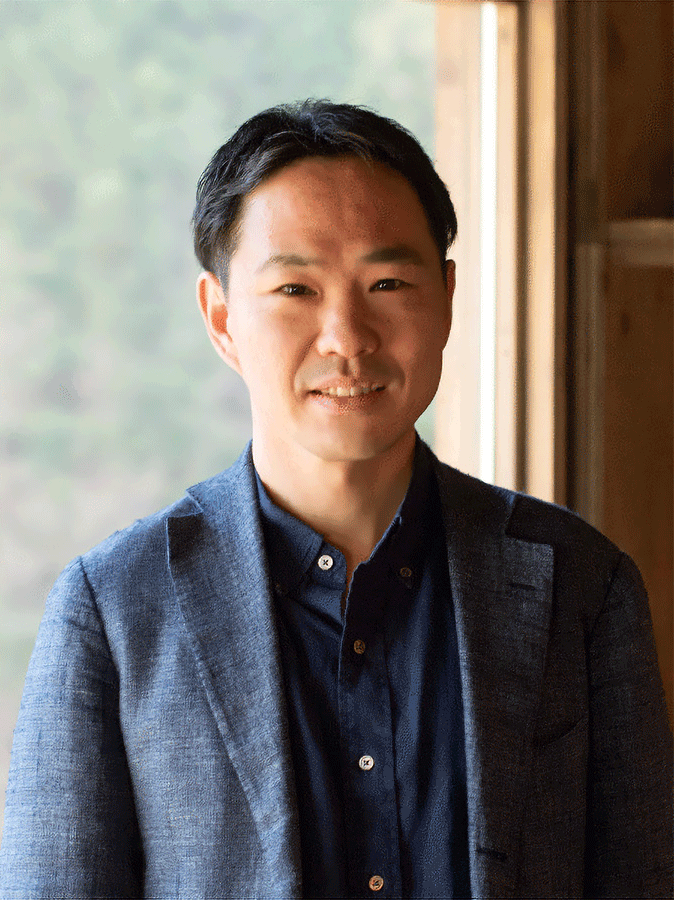言葉と向き合うアニメーション作家、
折笠良さんはなぜ、1年をかけて
ひとつの詩を読んだのか?

なぜ文字や言葉を主題とした映像をつくるのか?
〈札幌文化芸術交流センターSCARTS(スカーツ)〉で
『ことばのいばしょ』展が始まった。
「言葉」というものを表現の重要な要素とする作家が集うこの展覧会では、
小森はるかさんと瀬尾夏美さんによる映像作品の展示と人々との対話の場とがつくられ、
折笠良さんによるアニメーション作品と、その関連作品の展示が行われた。
さらに「言葉と版画、本の森」と題したコーナーでは、
札幌にゆかりのある4人の作家の詩歌からインスピレーションを受け、
版画家が作品を制作。詩歌とともに展示するという試みも実施された。
オープニングとなった8月22日には、折笠良さんのアーティストトークが行われた。
私はこの展覧会の図録制作に関わっていたことからトークに参加したのだが、
その仕事を超えて折笠さんの言葉に強く惹きつけられた。
折笠さんは、これまで詩や文学作品を主題として、
言葉に質感や動きを与えるアニメーションを制作してきた。
展覧会では、その中のふたつの映像を上映。
ひとつは石原吉郎の詩『水準原点』の文字が、
一文字一文字、波のようにうねる粘土の中から現れ出すというもの。
もうひとつは、ミュージシャンの環ROYさんの楽曲
『ことの次第』のミュージックビデオであり、歌詞が音楽に合わせて現れ、
反転したり形が変化していくというものだ。

折笠良『水準原点』(2015年)。粘土を少しずつ手で掻いていきながらコマ撮りをし、アニメーションをつくりあげた。

折笠良『ことの次第』(2017年)。環ROYさんのラップミュージックに合わせて、文字がダンスをしているかのように自在に動く。
トークでは、北海道を拠点に活動する映像作家、大島慶太郎さんと
環さんが聞き手となって、折笠さんにさまざまな質問を投げかけた。
最初に大島さんが質問したのは
「なぜ文字や言葉が映像のモチーフとなっているのか?」だ。
「一番よく聞かれる質問ですが、ただすごく難しくて。
映像作品における言葉はちょっと異物だと思われているという前提があって、
逆に一般的な映像のイメージとはなんだろうと考えます、と
斜めから答えることがあります。
正面から答えると、言葉の物質性を探求するとか、
言葉というものが個人的なものと社会的なものの境目にあって、
書き手にとってはそれがつながるかというカケみたいなものだから、
その呼びかけに自分は応えたいと話すのですが、必ず語り落とすものがある。
答えたあとに、やっぱりうまくいかなかった、何も言うんじゃなかったと思うんです」

トークの様子。左から大島慶太郎さん、折笠良さん、環ROYさん。(撮影:リョウイチ・カワジリ 写真提供:札幌文化芸術交流センター SCARTS)
語り落とすものがある。
この言葉に私は大きく頷いた。
このような連載の文章を書くときにも、
すべてを伝え切れないもどかしさをいつも感じていたからだ。
また伝え切れない部分があるために、
私は同じテーマについて何度も書くことがあるのだが、
そのとき「斜めから」や「正面から」捉える感覚があって、
折笠さんが語りの角度を意識している点にも共感を持った。
ひとりの人を理解しようと思ったら、
同じ時間ずっといなきゃわからないかもしれない
そして、トークを進めるなかで、ハッとした言葉があった。
なぜ石原吉郎の詩をアニメーションにしたのかが語られたときだ。
石原吉郎は1915年生まれの詩人。
終戦時から8年間シベリアに抑留された経験があり、
その後に詩を発表し始め、1977年に亡くなっている。
「日本の詩の中で唯一の人という感じがする」という折笠さんによれば、
大きな災害や社会の変革時に石原への関心が高まり、
ちょうど生誕100年という再評価の機運があるなかで、
アニメーション作品『水準原点』もつくられたという。

会場に展示された石原吉郎の詩『水準原点』が収録された同名の詩集。水準原点とは水準を測量する基準点のことで、国会前の庭園に設置されている。
会場には、折笠さんがかいた『水準原点』のスケッチも展示されていた。
その中には、ひとつの文字を何コマで表すのかを示したものがある。
例えば最初の言葉である「み」は1から21までの数字が割り振られ、
21コマで少しずつ文字がかかれていることが示されている。
つまり21回粘土を少しずつ移動させて動きをつくり出していったのだ。
1秒間にアニメーションは24コマの絵が必要になるため
「み」は21/24秒で約0.9秒の映像になる。
このような途方もない作業が1年という歳月のなかで行われた。

文字をかく速度が記された『水準原点』のスケッチ。
環さんが「作業は楽しかったんですか?」と尋ねると、
「楽しいとも思わないですけど、苦ではないです。
石原吉郎は、8年間のシベリア抑留があって、僕は1年ですからね。
すごく思うのは、時間という要素は誰かを理解するときに必要。
本当にひとりの人を理解しようと思ったら、
同じ時間ずっといなきゃわからないことも多い気がして」と折笠さんは答えた。
ひとりの人を理解しようと思ったら、同じ時間ずっといなきゃわからない。
この言葉を聞いたことによって、私は折笠さんについてもっと知りたいと思い、
トークのあとに、ほとんど衝動的に追加取材を申し込んだ。
いつも誰かに取材をして、その後に記事を書くとき、
私は可能な限り取材対象者について考える時間を持ちたいと思っている。
ただ、締め切りにいつも追い立てられていて
1本の執筆にかけられる時間は、それほど多くはない。
人生そのものを捉えるには圧倒的に時間が足りず、
やり切れていない思いが募っていたため、折笠さんのように1年を費やし、
ある人物に深く切り込むということはいったいなんなのか、
それを行ったときにどんな世界が見えるのかを知りたいと思った。
さらには、ある人物について理解しようとしたときに、
なぜアニメーションという手法を選択したのかにも興味を持った。

『ことばのいばしょ』展示風景。中央に置かれたのは『ことの次第』の原画。無数の原画が棺のような箱に納められた。
ひとつの詩を1年かけてゆっくりかく
突然の依頼にもかかわらず、折笠さんは翌日、時間をとってくれた。
単独インタビューでは、『水準原点』や『ことの次第』とともに、
2016年に制作した『Notre chambre(われわれの部屋)』という
フランスの思想家ロラン・バルトが、アメリカの画家サイ・トゥオンブリについて書いた
テキストをアニメーションにした作品や、
現在制作中の、フランスの詩人であり画家のアンリ・ミショーを主題にした
アニメーションについても話をうかがった。

茨城県で制作を続ける折笠さん。トークを終えた翌日、フライト前の時間にインタビューに応えてくれた。
折笠さんは、作品の主題にした作家について話しているとき、
作家の言葉を多数引用する。それが何年頃の文献であるのか、
その言葉が語られた時代的背景も語りながら、常に思索をめぐらしているようだった。
ときには折笠さんの言葉と作家の言葉とが混じり合い、
どちらの発言なのか境目が曖昧になっていく瞬間があった。
そんななかで折笠さんは、作家への「批評」を、
論文とは別のかたちでやっているのではないか? という考えが浮かんでいった。
「それはうれしい言葉ですね。
『水準原点』は、石原吉郎論としてつくっているところがあります。
テキストはいかに読んでもいいとも言えますが、
石原吉郎のシベリア体験をどう扱うかは、直線ではつなげないけれど、
離してはいけないものだと思います。
テキストを分析しようと思って、考えれば考えるほど、
テキストそのものを反復するしかなくなる。そのものをかくしかない。
『水準原点』のことをわかりやすく語るときに、
ひとつの詩を1年かけてゆっくりかいた記録ですと言うことがあります。
きっとリニアモーターカーに乗ったら、風景はさーっと線のように見えてしまう。
僕の場合は、ほふく前進なのか虫みたいなものかわからないですが、
読みの速度が大事な気がしています」

会場に映し出された『水準原点』。
石原吉郎の詩を1年間かけて読む、あるいはかく。
確かに、膨大な制作時間を要するアニメーションという手段は、
極端に読む速度を遅くする有効な手段と言えるのかもしれない。
圧倒的な時間をかけていくなかで、
折笠さんは石原吉郎について、どんな気づきがあったのだろうか?
「石原吉郎の詩って難しくて、日本語なのに何を言っているのかわからない。
単語に特別な負荷がかかっていて、詩集を真っ直ぐではなく
角度を斜めにして見てみたいと思ったのが制作の始まりです。
映像ができたあたりからは、たぶんシベリア抑留ということから
石原吉郎を解放させてあげたいとどこかで思っている気がします。
つくり手に能力があるとしたら、対話が成立しない人との対話を成立させる力がある。
昨日のように環ROYさんがいて、石原の話をするというのは
すごく幸せなことなんじゃないかと思います。
石原は亡くなって、環さんとは会うことができなかったけれど、
実際に会っていたら結構話が合う気がします。
それで何が起こるのか、どういう会話がされるのか聞きたいというか」

死者の声を聞くというのはオカルト的なもののように感じられるかもしれないが、
先ほどの批評という視点にもつながっているように感じられた。
ある論を書くにあたって、批評家は徹底的に作家を調べあげる。
そして何を考えていたのかを探求するなかで、たとえ亡くなっている人物であっても、
その人物がその場に存在しているかのように語ることがあるのではないか。
言葉に関わる限り、新しく生き直すことができる
このような、時空を超えた対話の場をつくるというのは、
折笠さんの作品を理解する重要なキーと言えるように思う。
「自分の中で大きな概念としてあるのは、ロラン・バルトが1976~77年に行った
コレージュ・ド・フランスという学校での講義
『いかにしてともに生きるか』なんですね。
この講義の冒頭に『イディオリトミー(固有のリズム)』について語っています。
これはバラバラであるものが、それぞれの輪郭を保ちながら
一緒に過ごす、共生できるというビジョンです。
話の始まりにロラン・バルトは、
ニーチェ(ドイツの哲学者)、マルクス(ドイツの思想家)、
フロイト(オーストリアの精神科医)、マラルメ(フランスの詩人)は、
年齢差もあるし、住んでいたところも違うけれど、一時期パリのカフェで集まって
話すことも可能だったのではないかという妄想するんです。
僕がこの妄想から思ったのは、4人のうち誰かが亡くなっていたとしても、
もしかしたら何か別の方法で出会うことができるんじゃないかということでした」

折笠良『Notre chambre(われわれの部屋)』(2016年)。
固有のリズムを保ちながら共存するという概念は、
折笠さんの作品『Notre chambre(われわれの部屋)』にも表れているという。
アニメーションでは、サイ・トゥオンブリの絵について
ロラン・バルトが書いた文章が朗読され、朗読に合わせて筆記体の文字が画面に浮かび、
次第にそれが変化してサイ・トゥオンブリの絵のタッチのようになったり、
線が具体的な形を表したかと思えばランダムに画面の彼方に消えていく。

折笠良『Notre chambre(われわれの部屋)』(2016年)。
「ロラン・バルトの文章は、客観的なものを装いつつも、
だんだんとサイ・トゥオンブリ自体にメタモルフォーゼしていきます。
僕は、ロラン・バルトの筆跡を真似しようとしたのではく、
自分の筆跡でフランス語をかき、あるときはロラン・バルトが文字を書き、
あるときはサイ・トゥオンブリが絵を描いているという、
呼吸するように線を動かしたかった。
バルトという層とトゥオンブリという層があったら、
その層の間なのか上か下かはわからないですけれど僕の層もあって、
アニメーションは3人の空間にしたいと思いました」
そして折笠さんは
「バルトとトゥオンブリのいる部屋に、居候する作品」
とつけ加えた。この感覚は石原吉郎についても、
現在取り組んでいるアンリ・ミショーについても共通しているのだという。
「毎回、主題によってアニメーションの技法を変えているのですが、
なぜそんなことができるのかといえば、これは勘なんですけど、
言葉というものによって連続性が保たれているからだと思うんです。
言葉に関わる限り、新しく生き直すことができる気がするんです」

主題に合わせて制作する技法からつくっていきたいという折笠さん。『ことの次第』は、原画は手描きだがデジタル加工に取り組んだ。
新しく生き直すことができる。
これは、主題とした作家の人生を「追体験」することとは違うと折笠さんはいう。
追体験とは、過去に確定した事実があって、それを体験するものであるが、
折笠さんが作品をつくるときには、過去に生きていた人々と同じ部屋に暮らし、
そこでは新しい出来事が起こっているような気さえするのだという。
折笠さんと2時間話していくなかで、ある人物について理解をするという観点から、
私の記事を書くという行為と折笠さんの制作を重ねてみたが、
まったく次元が異なることに気がついた。
取材者の過去の話をたどって、その足跡を原稿として書いていただけでは、
それは折笠さんのいう「追体験」の範疇を出ることはない。
では、折笠さんは何をしようとしているのか。
どこに向かっているのだろうか。
私の拙い言葉では手に余るけれど、あえて言葉にしてみると、
ひとりの人間がそこに生まれて、生き生きと動いていると
確かに感じられる強烈なビジョンをつくり出すことなのではないかと思った。
「過去すら変えられるかもしれない」
折笠さんは、声のトーンを強めてそう話してくれた。
「表現」というものの限りない可能性が感じられるひと言だった。
information
ことばのいばしょ
会期:2020年8月22日(土)~ 9月22日(火・祝)
会場:札幌文化芸術交流センターSCARTS(札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ1・2F)
TEL:011-271-1955
開館時間:11:00~19:00
休館日:9月9日(水)
writer profile

http://michikuru.com/