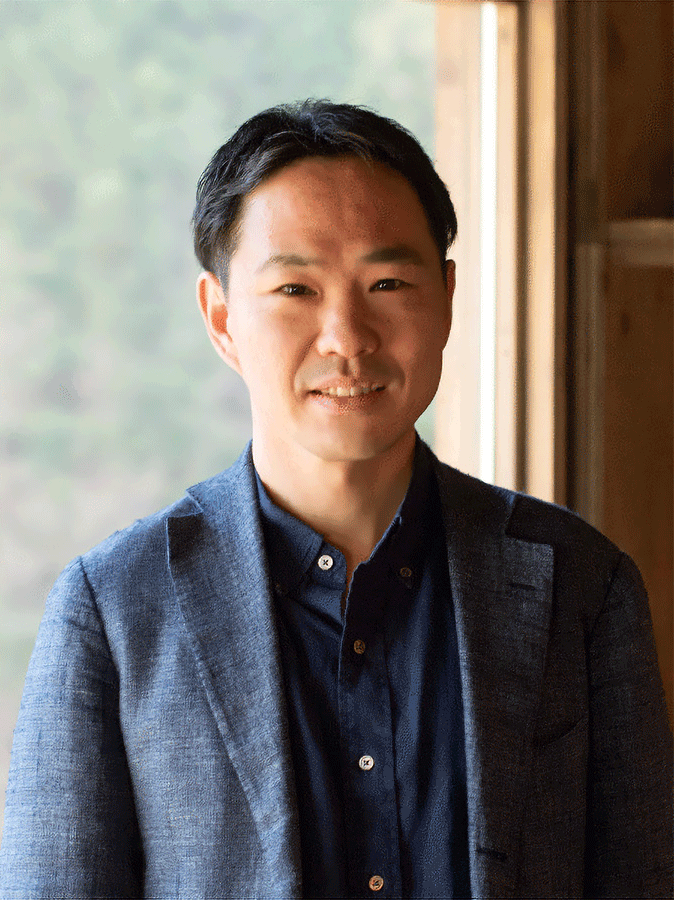金沢21世紀美術館「島袋道浩:能登」 くちこづくり

能登の珍味をつくり、味わう。
金沢21世紀美術館が毎年行っているプログラム
「金沢若者夢チャレンジ・アートプログラム」。
アーティストとプログラムメンバーが共同制作することにより、
若者たちの社会参加や文化活動を促すという1年間にわたるプログラムだ。
昨年度は、ベルリン在住のアーティスト島袋道浩さんとメンバーたちが、
能登でさまざまな活動を展開し、その成果を美術館でも展示。
以前「ローカルアートレポート #048」でも紹介した。
島袋さんが能登をテーマにしようと思ったのは
「くちこ」に興味を持ったからだったという。
くちこは能登の特産品で、なまこの卵巣を干した珍味。
プログラムが始まる前にリサーチをしていた島袋さんは、
くちこづくりの名人に出会い、すっかりその人に魅せられてしまった。
それが森川仁久郎さん。
2月と3月の限られた時期にくちこづくりをする以外は、
なぜか「鉄をつくる」という森川さんに、メンバーたちは鉄づくりを教わりに行き、
そのようすは展示でも紹介された。
そして3月の頭、今度は森川さんの本業、くちこづくりを習いに、
島袋さんとメンバーたちは能登の穴水を訪れた。
森川さんの作業場は、まちのはずれの、すぐ海に面したところにある。
鉄づくりで何度か森川さんのもとを訪れているので、
森川さんとは顔なじみのメンバーも。
作業場には、森川さん同様、くちこづくりの名人のお母さんたちが3人、
手際よく作業をしている。
なまこの腹を割き、取り出したものをきれいに分けていくのだ。
オレンジ色の細い糸のようなものがくちこ、
腸にあたる「このわた」と口のまわりの「くちわた」、
そして「えら」と部位によって選別する。
ちょっと見ただけではよくわからないが、
お母さんたちがさっさと分けていく様を、メンバーたちも興味深く見つめる。

なまこの腹を割いて内臓を取り出す。たまに何も入っていない「はずれ」もあるのだとか。

名人お母さんたちのそばでその手つきに見入ってしまう。

1匹のなまこから少ししかとれないくちこを選り分け、きれいに洗う。
こうして選り分けたくちこを、三角形のかたちにして干すのが森川さんの仕事。
森川さんは夜にその作業をするらしく、
残念ながらそのようすは見ることができなかったが、
前の晩につくったとおぼしききれいな三角形のくちこが干してあった。
これも熟練の技が必要だそうだ。
干したものが落下してしまうこともあり、
森川さんの言葉によれば「くちこづくりは重力との戦い」だそう。

森川さんが深夜までかかってきれいに干したくちこが並ぶ。孫がたくさん訪れたかのような雰囲気。

作業場の外にはなまこがたくさん入った生け簀が。なまこ製品の直売もしているので、商品を買うお客さんがたまに訪れる。
島袋さんは1年前のくちこづくりも体験していたので、メンバーたちよりちょっと先輩。
まずは島袋さんがやってみてから、メンバーたちも順になまこの腹を割いてみる。
日常生活のなかでは、なまこに触れることなどあまりないし、
ましてなまこの内臓となるとなかなかグロテスクなものだが、
これまでも鱈をさばくなどいろいろな体験をしてきたメンバーたちは、
度胸がついたのか、物怖じせずにチャレンジ。しだいに楽しんでいるようにも見えた。
そんなメンバーたちを森川さんも島袋さんもやさしく見守る。

最初はぎこちない手つきでも、みんな勘がよく上手にこなしていく。

部位の判別は難しく、お母さんに教わりながら。
メンバーが順になまこの割腹作業をしているあいだに、
牡蠣を焼いて食べようということに。
森川さんが、みんなのために牡蠣を用意してくれていたのだ。
と、何を思ったか、森川さんは海辺のほうに降りていく。
そしてなんと朽ちかけの大鍋を拾ってきて「これで焼こう」と森川さん。
まさか海から鍋が出てくるとは思わず、その場は驚きと笑いに包まれた。
その鍋を使い、みんなで焼いて食べた牡蠣がおいしかったのは言うまでもない。

放置してあったのを思い出したのか、森川さんが海から鍋を引き上げてきたのには、みんなびっくり。

一度に焼ききれないほどたくさんの牡蠣。
牡蠣を焼く一方、おにぎりを握ってお昼の準備。
森川さんの奥さんが、なまこのえらの部分を入れたすまし汁をつくってくれた。
えらや生のこのわたも、地元の人の口にしか入らない珍味中の珍味。
このわたは、口に含むとウニのような磯の香りがふわっと広がり、
イカの塩辛のような食感。みんな口々に「おいしい」と顔がほころぶ。
これまでも島袋さんとメンバーたちは、出かけた先々で
能登産の七輪を使って魚や干物を焼いて食べ、能登の食を味わってきた。
おにぎりと一緒に珍味を味わったこのひとときも、
その場にいた全員にとって忘れられないものになったに違いない。
昼過ぎになり、島袋さんとメンバーたちは何度も森川さんにお礼を言って、
名残惜しそうにその場をあとにした。

作業をしながらこのわたを食べさせてもらう。

塩むすびにこのわたを乗せて食べ、えらが入った汁をいただく。
これからが、本当の始まり。
金沢在住のメンバーの広田祥子さんは
「いままでは観光地としての能登しか知らなかったけれど、
くちこづくりや干し柿づくりをする人に会えたり、
自分では行かないような場所に行くことができて楽しかった。
能登のものを買うことはあっても実際につくっているところは
見たことがなかったので新鮮でした」と、1年間のプロジェクトを振り返る。
富山に住む勝島則子さんは、プロジェクトに参加する以前から能登に興味を持って
たびたび訪れていたが、こんなに能登に通った年はなかったという。
「くちこづくりもそうですが、あんなふうに森川さんが鍋を引き上げてきて
牡蠣を焼いて食べるなんて、思いもよらない展開だし、ふだんは体験できないこと。
その場所のものを食べるということがその土地を知ることになるし、
その味の記憶がそこに行った記憶になるんだと思います」

ふっくらした牡蠣。能登でのいろいろな体験がからだに染みていく。
プロジェクトは終わったけれど、島袋さんには、
これから何かが始まるという予感がある。
「みんな、なかなか経験できないことをしてきたと思う。
そういうことがこれからのみんなの生活のなかにどう生きるか。
鱈をさばいたりなまこをさばいたり、そういうことを
経験しているのとしていないのでは、大きな違いがあるんじゃないかな」
何か作品をつくって見せるよりも、こういう場所を見せるほうが大きな経験になる。
そう考える島袋さんならではのプロジェクトになった。
そしてもうひとつ、島袋さんが感じたのは「間に合った」ということ。
「みんなの手つきを見ていると、おぼつかないけれど様になっていたというか。
こういうことをして生きてきた人たちの末裔なんだなあと思いました。
現代の人たちがどこかに置いてきてしまったものを、いまならまだ拾いに戻れる。
みんなの姿を見ていて、そんなことを実感しました」
1年間、能登で活動を展開してきて、
ようやく旅をするためのガイドブックができたという島袋さん。
「またお祭りも見に来たいと思うし、自分たちがよりよく旅するための
友だちができたような、道しるべができたような感じ。
これからもっといろいろなことができると思うし、
展覧会が終わって、何かが始まる気がします」
美術館の中で行われるワークショップとはまた違う、
能登という土地でのさまざまな体験は、島袋さんにとっても、
メンバーたちにとっても、大きな収穫になったはずだ。