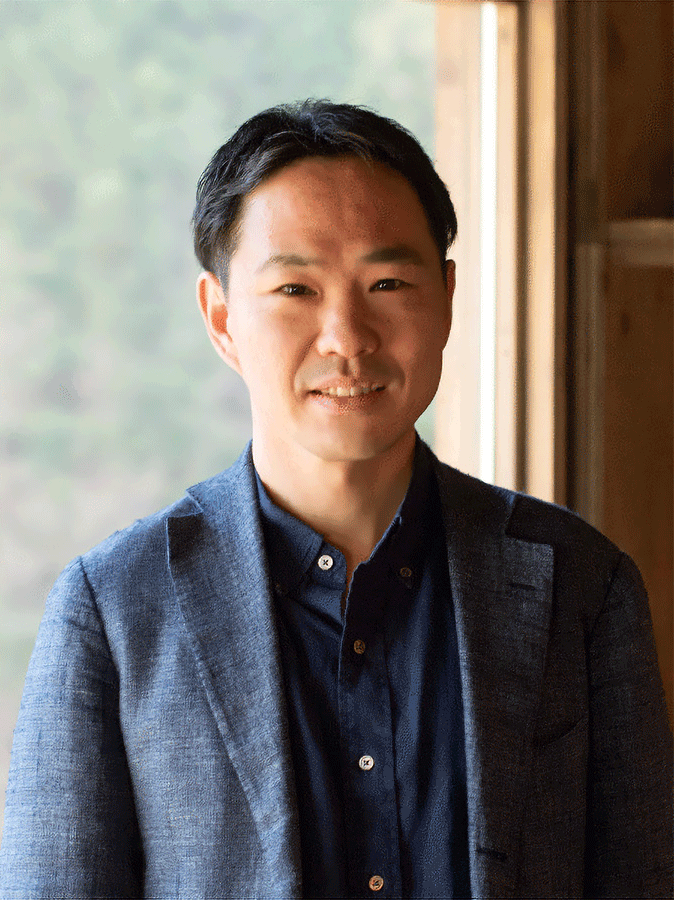梅仕事、まだ間に合う? シロップ、コンポート、ジャム…… 今年からはじめる簡単梅レシピ

もう6月ですね。あっという間に今年も半分が経とうとしています。
この時期になると、コロカルでも人気となるのが「梅仕事」の記事。
興味はあるけど、まだチャレンジしたことがないという方のために、
いまからでも間に合う、梅仕事の人気記事をご紹介します。
[hidefeed]
[/hidefeed]
まずは、梅仕事の基本。旬や種類について
「梅仕事」とは、旬を迎える梅をつかった、自家製の保存食づくりのこと。
実が硬くフレッシュな青梅は、早くて5月下旬から6月上旬までが旬で、
爽やかな味わいの梅酒や梅シロップなどに使われます。
完熟梅は6月下旬ごろまで市場に出まわり、梅酒や梅シロップはもちろん、
豊かな香りが楽しめる梅ジャムや梅干しにするのもオススメです。
コロカル編集部には各地へ移住した連載陣たちから、梅仕事の様子が届きます。
小豆島〈HOMEMAKERS〉の三村ひかりさんの連載『小豆島日記』もそのひとつ。

ザルいっぱいの青梅たち。この後、傷の有無やサイズ別に選別します。
「実を採るっていうのはほんとに幸せで没頭する作業」と綴っている三村さん。
ご家族や友だち同士でワイワイと収穫。その後、選別作業をして、
丁寧に洗って、拭いて、乾かして、ヘタをとってと、梅の仕込みへ。
梅シロップや、梅のコンポート、梅ジャムなどになるそうです。
その様子は、連載『小豆島日記』vol.178の記事をご参照ください。
「〈HOMEMAKERS〉の梅仕事、梅コンポートと梅干しづくり」
小豆島〈HOMEMAKERS〉カフェの梅のコンポートのつくり方
梅仕事は、梅酒や梅干しだけじゃありません。
三村さんが教えてくれた「梅のコンポート」のレシピをご紹介します。

【梅のコンポートのつくり方】
① 収穫後、新聞紙に包んで追熟させておく
② ヘタを取り、きれいに洗う
③ 梅と砂糖、白ワインを鍋にいれる
④ 80度程度を保ちながら弱火でことこと煮詰める
⑤ 冷ましてから、ガラス瓶などに詰めて冷蔵庫で保管。
以上! と、とっても簡単です。
煮汁は梅シロップとしても使えて、炭酸で割れば梅ソーダにも。
これなら、初心者でもすぐにはじめられそうですね。
傷んだ梅も余さず使いきる、梅の状態別活用術
不作の年は「多少傷がある梅でも大事に使いたい」とレシピを教えてくれたのは、
福岡県糸島で自給自足生活をする〈いとしまシェアハウス〉の畠山千春さん。
コロカルの連載『糸島での自給自足の日々を綴った ―田舎暮らし参考書―』にて
梅の状態にあわせた5つのレシピを紹介した記事がヒットしました。

左上が(1)、右上が(2)、左下が(3)、右下が(4)の梅。
(1)ピカピカときれいで、粒の大きい梅
(2)小さく傷がついている梅
(3)収穫の際に割れてしまった梅
(4)熟して黄色くなった梅
畠山さん曰く、(1)の「きれいで粒の大きい青梅」は追熟して梅干しに、
(2)の「小さくて傷がついている梅」は、梅シロップにするのがよいそうです。
(4)の「ちょっと傷んだ、熟して黄色くなった梅」は、
くつくつと煮込んで、コンポートにしてしまうのがオススメとのこと。

畠山さん流の梅干しは、重石を使わない「てきとう」レシピなのだとか。詳細は連載記事へ。
梅干し、梅シロップ、梅のコンポートのレシピ、以下の大ヒット記事をご参考ください。
「レシピ、教えます! 傷んだ梅も余さず使いきる、私の“簡単”梅仕事」
ここでは、(3)「収穫の際に割れてしまった梅」の活用術を抜粋してご紹介します。
畠山さん流・梅肉エキスのつくり方
前述(3)の「収穫の際に割れてしまった梅」は、梅肉エキスにするのがベスト。
しかし、青梅でないと栄養が少ないので、熟しているものは避けたほうがよいとのこと。
1キロの青梅から20~50グラムほどしかつくれないので、大量の梅を用意します。
【梅肉エキスのつくり方】
① ジッパー付き保存袋に入れて梅を棒で打ち、果肉と種を分離させる
② 果肉をフードプロセッサーで砕く
③ 果肉をサラシで濾して、梅のエキスと果肉を分ける
④ 濾した梅のエキスを煮詰めて、黒くなるまで水分を飛ばす

つくる過程で梅を割るので、割れていても問題なし。
エキスを絞りおわった梅の果肉は、お砂糖とレモン汁を混ぜてジャムに。
貴重な梅を、畠山さんは、余すところなく使います。
最後の手段・梅ジャムのつくり方
「我が家では、最終的に残った梅たちは梅ジャムに変身していきます」
というコメントとともに教えていただいた畠山さん流最後のレシピは、梅ジャム。
先に紹介した梅肉エキスづくりで残った果肉を、梅ジャムにしたように、
前述(1)~(4)のどれにもあてはまらなかった梅たちは、
最後の手段として、「梅ジャム」にしてしまうのがよいとのこと。

傷んだ梅も、余すことなく使い切るのが畠山さん流。
【梅ジャムのつくり方】
① 傷んだ部分を切り取り、あく抜きのために茹でこぼす
(青梅なら2〜3回、完熟梅は1〜2回繰り返し)
② 種を除き、果肉をお砂糖で煮る(お砂糖の量はお好みで)
状態別・梅仕事レシピは、収穫と選別から行う、
ローカル移住者ならではの視点かもしれませんね。
梅干しの最適な塩分濃度は?
続いても「コロカル」で人気の移住者連載から、梅干しづくりをご紹介します。

見ているだけでよだれがでてきそうな津留崎家・自家製梅干し。
伊豆下田に移住した津留崎家『暮らしを考える旅 わが家の移住について』では、
塩分濃度を変えてつくってみた記事が人気になりました。
ここでは、梅仕事上級者・津留崎家のノウハウを記事から一部、ご紹介します。

「わが家が仕込むのはもっぱら梅干し」という津留崎家。10年以上梅干しづくりを続けている上級者です。
梅干しづくりのレシピは、さまざまありますが、
「梅の重さに対して、18%の塩で仕込む方法」をよく見かけます。
そこで、津留崎家は、10%、16%、18%の3段階で仕込んだ梅干しをつくり試食。
すると意外にも、ほとんど違いを感じなかったのだそうです。
しかし、塩分濃度が低いと、カビや雑菌の繁殖リスクが増えるのでケアが重要。
結果、安心して漬け込めるだけの塩分濃度にしているそうです。
素材ついては、一般的には完熟梅を使う梅干しですが、
伊豆下田の直売所に出まわるのは、青梅がほとんどなのだそうで、
傷まないように湿度に気をつけながら追熟していました。
そのうち、青梅で梅干しづくりをしてみるという実験を検討中とのこと。
伊豆下田で試行錯誤する津留崎家梅仕事の様子は、以下の記事からご覧ください。
「10%? 16%? 18%? 塩分濃度を変えて梅干しをつけてみた」
米麹で発酵させた「梅麹シロップ」に挑戦

「みんなの発酵BLEND」サイトでも、6月は梅仕事が人気。コツや注意点など詳細は、該当記事へ。
梅シロップのつくり方はよく目にしますが、
「発酵」の力でさらにおいしくなる「梅麹シロップ」のつくり方もご紹介します。
日本の発酵文化を紹介する『みんなの発酵BLEND』は、
100年以上歴史ある発酵飲料「カルピスⓇ」(アサヒ飲料)が運営する発酵ポータルサイト。
コンテンツ制作やサイト運用は、「コロカル」編集部が担当しています。
こちらのサイトでも、6月になると人気が出るのが、
連載「おうちで発酵体験レシピ」の「米麹で発酵させた梅麹シロップ」の記事。
麹と梅に含まれた酵素が、砂糖を栄養として発酵。
その過程で、砂糖はブドウ糖に変わり、
私たちの体を動かすエネルギー源になるのだそうです。

青梅と砂糖は交互に入れ、最後に砂糖でフタをする。表面を砂糖で覆うことで、浸透圧が高まり、微生物汚染の抑制になるのだとか。
【梅麹シロップのつくり方】
① 青梅をよく洗い、水気をしっかり拭き取る
② 青梅のヘタを竹串などで取る
③ 1キロの青梅の半数分は、種を挟んで3つに切る、または半分に割る
④ 事前に煮沸したガラス瓶などの容器に、砂糖と青梅を交互に入れる。
(砂糖は、青梅1キロに対して1.1キロ)
⑤ 米麹(100グラム)を入れて、砂糖で表面をフタするように覆う
⑥ 容器にガーゼでフタをして、口を輪ゴム留める
⑦ 直射日光を避け、翌日から毎日1~2回ほど、底からしっかりかき混ぜる
※発酵でガスが発生するため、フタで密閉すると開ける際、吹き出す恐れがあります
⑧ 7日間毎日混ぜて、水分が多くなり、梅の実が浮いてきたら完成
⑨ ザルで濾して、保存容器に移し替えて、冷蔵庫で保管
※完成後も発酵しているため、保存の際もフタで密閉しないでください。
通常の梅シロップよりも、手間ひまかけた分、発酵のパワーを感じられるはず。
梅仕事経験者、次のステップとしてもいいですね。
今年も梅仕事の時期が過ぎてしまいそうですが、思い立ったが吉日。
まだ、チャレンジしたことがない方は、ぜひ、梅仕事デビューしてみては?
日本のローカルをテーマにしたWebマガジン「コロカル」では、
梅仕事のようなローカルの生活では日常的な知恵やレシピを、
移住者たちの四季折々の連載記事を通してご紹介しています。
夏は、ビールにあう「パドロン」やメロンみたいな「マクワウリ」などの野菜話、
秋には、熟れすぎた柿や、新米時期に残る古米の活用術などの記事もあります。
日々の生活も季節を感じながら、楽しめるといいですね。