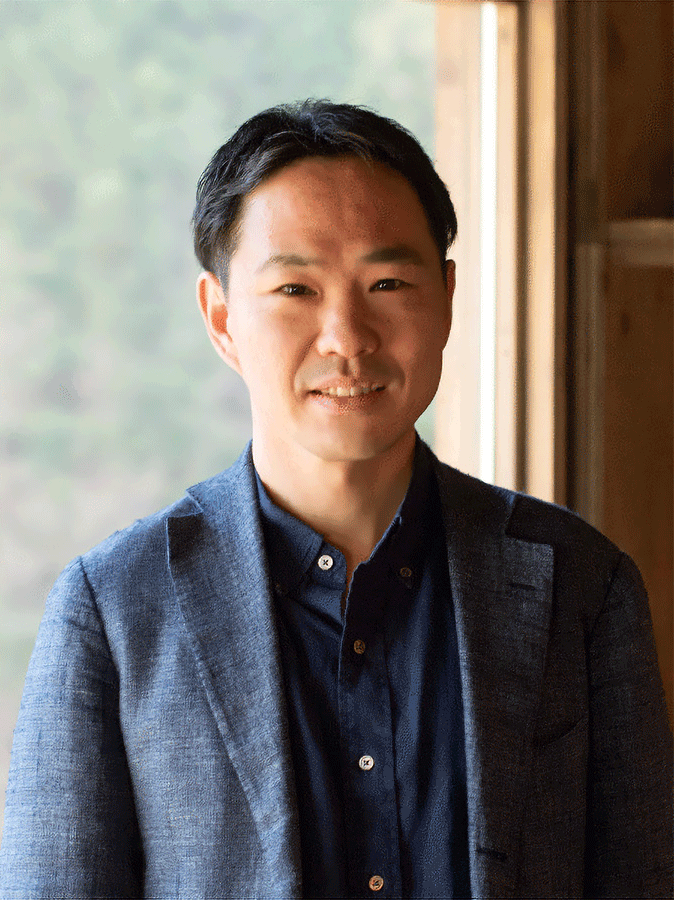写真家・高橋ヨーコ
東京→カリフォルニア・ベイエリア
→横須賀
形もルールも違う「移住」という双六

「東京は引きこもるには最高なんです」
「カメラマンとして独立したころは都会が好きでした。
人がたくさんいて、ひっきりなしに動いているまちの感じが。
誰もいないところでのんびりと、という気持ちはなかったですね。
いまは都会がそこまで好きかはわかりませんけど」
写真家の高橋ヨーコさんが
10年間続いたカリフォルニアのベイエリアでの生活にひと区切りつけ、
神奈川県横須賀市秋谷の家に拠点を移したのは
2020年、パンデミックの最中だった。
渡米までは東京に暮らしていた高橋さん。
旅をベースにさまざまな撮影を続ける高橋さんにとって、
ローカルシフトは必然のことかと思いきや、
東京での生活にさしたる不満はなかったようだ。
「独立した頃は東京で引きこもっているか、
海の向こうで写真を撮っているという2択の生活でした。
幸い外から見ると身軽に見えるのか、いろいろな撮影が舞い込んできました。
景気もよかったですし、いい時代でしたね。
そもそも自分は京都で育って、最初は市内にいました。
のちに田舎に引っ越して、それが嫌だった記憶があります。
引きこもるには東京は最高なんです(笑)。
人が多いので、そんなに寂しくもないですし、仕事もあります。
むしろ地方で引きこもるのは辛いと思いますよ。
とことん孤独になりますから。
当時、住んでいたのは目黒でした。
低層のささやかな集合住宅で、高級という感じではなかったですが、
場所も家も環境も最高でした。
さりげない中庭にふわっと光が灯っていて、
夜に帰ると、なんか気分が上がるんですよ。
『外国みたいで、いいところだな』と帰るたびに思っていました。
ほんとうに満足で、東京にいてこれ以上のところはもうないだろうなと。
仕事も順調でしたし、双六のゴールのように“あがり”かなと」

横須賀の家は、塗装をし直すなどの手は加えたもののほぼオリジナル。
そんな不満のない環境のなか、高橋さんは海外への移住を決意する。
目的地として選んだのはカリフォルニア、サンフランシスコに近いバークレー。
せっかくあがりまで進めたコマをまた振り出しに戻した。
「振り出しといっても、変なところに止まって戻されたのではなくて、
また新しい双六が始まった気分でした。
いつか海外に住んでみたいという小さな夢はあったんです。
大きな夢はある程度、東京で叶えたというか、やりたいことはやってきたので、
今度はちょっとささやかな願望に手をつけたいと」
仕事関連ではある程度の感触を得た高橋さんを駆り立てたのは、
海外移住という、以前から抱いていた夢。
きっかけは海外との仕事で意思の疎通が難しいことがよくあり、
もう少しスムースに進められないかという悩みだった。
「それには海外に住むのが一番かなと思ったんです。
だとするとアメリカかなと。
LAは仕事でよく行っていましたが、広すぎるし、クルマもすぐに必要。
サンフランスコも候補に上がりましたが、最初は嫌でした。
なんかおばさんの観光地みたいな印象があったんです。
そうしたら長尾(智子・料理研究家)さんが
『バークレーはどう?』って薦めてくれたのです。
バークレーってどこですか? から始まって、いろいろと調べていたら、
大学があったり、ヒッピーカルチャーがいまだ息づいていたりと、魅力的でした。
で、『バークレーにします』ってことになったわけです(笑)」

グラフィックデザイナーの黒田益朗さんとつくった庭。春に向けて手入れする。
バークレーならではローカルコミュニティ
最初に住んだまち、バークレーは、
「ベイエリア」と呼ばれるサンフランシスコ湾に隣接するエリアの、東側に位置する。
カリフォルニア大学バークレー校のお膝元で、
カウンターカルチャーが息づくリベラルな土地柄だ。
学生、大学関係者、ミュージシャン、アーティスト、文筆家、活動家などが集い、
アリス・ウォータースらによるオーガニックな食文化が華やかな土地でもある。
高橋さんにとってはうってつけのエリアだった。
「バークレーは学生街。自分も京都で京大に近いところに育ってきたので、
そんなアカデミックな感じに惹かれました。
実は私、中学生のときに父親に連れて行かれたLAで
すっかりキャンパス文化にかぶれたんですよ。
バックパックに短パン、スニーカーで自転車に乗って大学に通っている。
『あんな格好で学校に行っているのか!』と
すごいカルチャーショック受けたのを覚えています。
大学に行ったら、絶対にあれをやるって、心に決めて帰って来たんですが、
日本の大学は山の上にあって、自転車は絶対に無理で、バイクでした(笑)。
なのでバークレーに来て、やったことといえば短パンにバックパックを背負って、
UCバークレー校を自転車でぐるぐる回ること。
ローカルシフトというより、カルチャーギャップを埋める行動ですね(笑)」

もともと別荘として建てられた築40年の家。持ち主が変わっても大事に住み継がれた。
高橋さんが移り住むことになる2010年のベイエリアは
サードウェイブ・コーヒー・ブームや
〈シェ・パニース〉などを系譜としたナチュラル志向の料理人が次々と現れ、
ローカルコミュニティ、地産地消、
サステナブルと新しいムーブメントが蠢き始めていた。
「新しいライフスタイルに接するにはいいタイミングでした。
食にしろ、プロダクトにしろ
ローカルを大切にするなどコミュニティの意識の高さにすごく感銘を受けましたね。
シェ・パニースでいえば、野菜、肉、卵などの食材はもちろん、
パンや器にいたるまで、すべてがローカル、本当に素晴らしいことです。
そして農業がとてもクールな分野でしたね。
みんな大学で農業を勉強して、フィードバックさせる。
日本とはちょっとカルチャーが違いました」

高橋さんがライフワークとする東欧、とくに旧ソ連の国々を切り取った作品。
高橋さんもそのコミュニティに入りたいという気持ちが
無意識のうちに芽生えたという。
コミュニティとの関係を閉ざしていた東京では考えられないことでもあった。
「バークレーに移って、いろいろなことが楽になったんです。
日本にいたとき
『私はもしかしたら、ちょっと変わっているかも』と思っていたことが、
アメリカに来たら普通のことでした。
いろいろなチョイスができる。
人間関係も感情も食べ物も。いい意味で適当。
そういう風に接していたら、とても気が楽になりました。
自分はアメリカにいて、言葉の問題もあるし、3歳児くらいの気持ちでいよう。
子どもなんだから、じっとしていてもしょうがないし、
せっかく来たんだから解放されてみようと。
バークレーのコミュニティは私みたいな人間にはすごく向いていましたね」
引きこもりがちだった東京の生活から、
ベイエリア・コミュニティ独特のつかず離れず、ほどよい人間関係は、
高橋さんを解き放したように外に向けた。

家の中からでもわかる1日の移り変わり。ひだまりが心地いい。
こうして、高橋さんのバークレー〜サンフランシスコと、
ベイエリアでの生活は10年続く。
仕事は日本よりはスローだったものの、ほどよい加減で、むしろ適量だった。
アメリカ横断のロードトリップからマサチューセッツに半年ほど。
冬が来る前にまたベイエリアに戻って、今度はサンフランシスコにも住む。
そして砂漠でのソロキャンプなど。
本人いわく「孤独の調整」、セルフメイドの旅を続ける。
ベイエリア盤の双六もあがりに向けて順調だった。
10年を節目にそろそろ帰国をとうっすら考え始めていた頃、
きっかけにもなる、ある事件にサンフランシスコで遭遇する。
「隣の家で火事があったんです。
仕事から帰ったら、すっかり焼けていて、私の部屋のドアは壊され、
『Do Not Enter』のテープが貼られていました。
『ネガもデータも全部ダメだ』と最初は人生が終わったくらいのショックでしたが、
幸い風向きが反対だったようで、私の家の被害は少なかったんです。
ネガもデータも無事でした。
ただ水浸しで、電気もガスも水道も全部止まっていました。
消防隊はYMCAに泊まれって言ってくれましたけど、
どうにも家から離れたくなくて、
『中でキャンプするから大丈夫です』とドアもないその家で
しばらくキャンプをして過ごしました。
そのときにふと、今回は被害者だけど、
万が一、自分が火事を起こしたらどうなるんだろうと。
10年アメリカにいたといっても、ここは訴訟の国ですし、
法律やシステムもわからないことが多すぎる。
病気にしたってそうですよね。
そろそろ人生のことをちゃんと考えたほうがいいんじゃないかと、
お告げのようなものを感じて、海外での生活がしんどくなってきたんです」

特に冬の光はたまらなく、ダイニングのこのスペースで1日が過ぎる。
不動産サイトが導いた3番目の双六
そんなとき、趣味ともいえる不動産サイトのチェックで、
コンクリートの箱にガラス箱を埋め込んだようなチャーミングな家を見つけた。
神奈川県横須賀市秋谷にある、
建築家の宮脇檀が設計した〈森ボックス〉という名のこの家だった。
「この家を見つけちゃったのが帰国の最大の理由ですね。
不動産を見るのが趣味なので、10年ぐらいずっと見ていましたが、
『これだ!』ってピンと来たのはこの家が初めて。
これもお告げですかね。タイミングもバッチリでした」

高橋さん曰く「サウンド&ヴィジョンコーナー」。デビッド・ボウイとともにするリスニングスペース。
相模湾を望む高台に建つ家は、
まるで世界的建築家のル・コルビュジエの代表作である
「カップ・マルタンの休憩小屋」のよう。
とてもコージーなスペースだった。
瞬く間に帰国の手続きを済ませ、
3つめの双六はパンデミックの最中、2020年、秋谷にてスタートした。
「帰るなら東京かなとは思っていたんですが、
ベイエリアの生活から考えると、本当に暮らせるのかなと疑問がありました。
もはや家の中から緑が見えないのは絶対無理と意識も変わっていましたし。
駒沢あたりまで行けばなんとかなるかなとか、
海外に出やすいから、いっそ成田がいいかも(笑)と考えたりもしました。
結果、ここは最高でした。
時間の変化が、家に中にいてわかります。まるで外にいるみたいです。
特に冬の光の動きは素晴らしく、
ステイホームのときも、日差しや景色が助けてくれました」
食文化やコミュニティの点も心配するほどではなかったようだ。
「もう山盛りのおいしい野菜は食べれないなと、
ベイエリアから帰るときに思っていたんですが、
野菜もお魚もおいしくて助かります。
なんたって調理をしない私にとって素材が大事ですから。
コミュニティも近すぎず、遠すぎずで、みんなフレンドリーです。
田舎の都会というか、あいさつはするけど、詮索はしないという風に」

久留和漁港は徒歩圏内。晴れた日は堤防の正面に富士山も見える。
もともと通勤圏であるエリアに加えて、
この一帯は、別荘と居住の割合がほぼ半々で都会的だ。
クリエイターや仕事関連の知り合いも多く、それも人間関係を円滑にする。
「一時、仕事用にと東京に事務所を借りていましたが、
いまは葉山の〈サンシャイン+クラウド〉(クルマで5分ほど)に
作業場を間借りしています。
山の上にひとりで住んでいると、人と接する機会があるのは大事です。
部屋に入ればひとりですから、これもまた『孤独の調整』ですね。
こういう“虫のいい”環境を獲得するのはとっても難しく、
本当についていると思います。
ローカルの生活はロケーションと憧れだけでは長続きしませんから」

〈サンシャイン+クラウド〉内に間借りした仕事場。
写真家としての高橋さんは、ゆくゆくは「撮る」から、
撮った作品を「編む」へとシフトしていきたいと考えている。
そうなれば、外へ出る必要も最低限となり、
居心地のいいスペースと環境さえあればすべてが整う。
そういう意味では、ここ秋谷の生活はうってつけだ。
東京、ベイエリア、秋谷とタイプもルールも違う双六を進めてきた高橋さんに
双六の行方を聞いたところ。
「うーむ……。もう1拠点かなと思ってはいるんです。でも考え中です。
東京ならまだしも、ひとりでしか暮らせないようなこんな家で、
ここにいる理由はなんだろうと自問します。
かといって東京に戻る意味も考えます。
東京に行くとまた引きこもっちゃいそうですし。
京都はありかな? 京都にいればたくさん人が来ますし。
孤独は嫌いじゃないですが、そろそろ積極的に解消していく年齢なんで(笑)。
ましてや外国人の友達が増えたいま、京都にいるメリットはあります。
ここであがるのか、それとも?
どうしたって楽しい双六になりそうです」

仕事場への移動はバークレーから持ち帰った愛車、フォード〈ブロンコ〉。
Creator Profile

YOKO TAKAHASHI
高橋ヨーコ
たかはし・よーこ●1970年京都府京都市生まれ。大学卒業後、フォトグラファーを始めて以来、第一線で活躍するかたわら、旧ソ連を中心とした東ヨーロッパでの撮影を精力的に行う。2010年サンフランシスコより帰国。サンフランシスコの10年をまとめた『SAN FRANCISCO DREAM』など、著作は多数。
writer profile
『BRUTUS』『Casa BRUTUS』など雑誌を中心に活動。5年前にまわりにそそのかされて真空管アンプを手に入れて以来、レコードの熱が再燃。リマスターブームにも踊らされ、音楽マーケットではいいカモといえる。