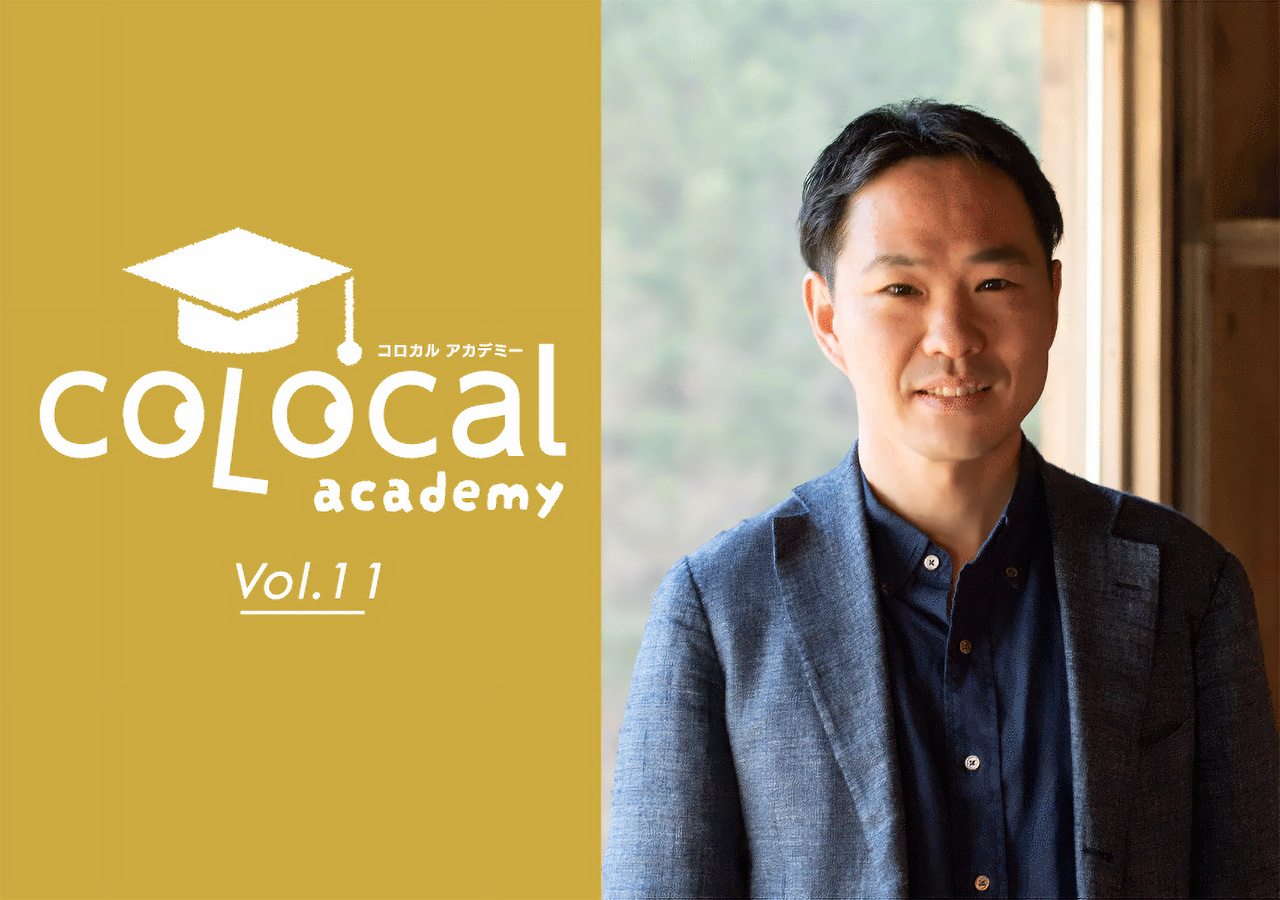絵描きとして地域とつながる。
鎌倉生まれ鎌倉育ちの
横山寛多さんが描く、このまち本来の姿

鎌倉から考えるローカルの未来
長い歴史と独自の文化を持ち、豊かな自然にも恵まれた日本を代表する観光地・鎌倉。
年間2000万人を超える観光客から、鎌倉生まれ鎌倉育ちの地元民、
そして、この土地や人の魅力に惹かれ、移り住んできた人たちが
交差するこのまちにじっくり目を向けてみると、
ほかのどこにもないユニークなコミュニティや暮らしのカタチが見えてくる。
東京と鎌倉を行き来しながら働き、暮らす人、
移動販売からスタートし、自らのお店を構えるに至った飲食店のオーナー、
都市生活から田舎暮らしへの中継地点として、この地に居を移す人etc……。
その暮らし方、働き方は千差万別でも、彼らに共通するのは、
いまある暮らしや仕事をより豊かなものにするために、
あるいは、持続可能なライフスタイルやコミュニティを実現するために、
自分たちなりの模索を続ける、貪欲でありマイペースな姿勢だ。
そんな鎌倉の人たちのしなやかなライフスタイル、ワークスタイルにフォーカスし、
これからの地域との関わり方を考えるためのヒントを探していく。

横山寛多さんが自宅兼仕事場を構えている海辺のまち・材木座。隣町の大町で長年過ごした後、現在は海から徒歩数分の場所にある古民家で暮らしている。
絵描きの家系に生まれ育ったクリエイター
四季折々の自然に囲まれ、歴史的遺産も豊富な鎌倉は、
古くは鎌倉文士の時代から、多くの表現者たちが創作活動の拠点としてきたまちだ。
そんな鎌倉で「絵描き」の家系に生まれ育ち、
現在もこのまちを拠点に活動を続けているのが、横山寛多さんだ。
風刺漫画で一世を風靡した横山泰三さんを祖父に、
『フクちゃん』で知られる横山隆一さんを大伯父に持つ横山寛多さんは、
幼い頃から自然と絵を描き始め、
鎌倉の豊かな自然や風土のなかで若き日を過ごしてきた。
20代後半よりイラストレーターとして本格的に活動を始めてからは、
さまざまな媒体のイラストを手がける傍ら、
〈邦栄堂製麺〉〈朝食屋コバカバ〉〈かかん〉など、
本連載でも紹介してきた地域を代表する店舗のロゴや看板、
パッケージなどのヴィジュアルを制作してきた。
さらに、地域の子どもたちに向けたお絵描き教室などを積極的に行い、
コロナ禍にはテイクアウト可能な飲食店マップを有志でまとめるなど、
絵描きとして、一住民として、このまちと関わり続けている。

日本有数の観光地としてだけではなく、近年は居住地としての人気もますます高まり、
横山さんが生まれ育った鎌倉のまちを取り巻く状況は年々変わりつつある。
さらに、昨今のコロナ禍の影響によってこのまちはいま、大きな岐路に立たされている。
こうした状況のなかでも自然体を貫き、日々の創作や生活を淡々と続ける横山さんは、
鎌倉というまちの本来の姿や、持続可能な未来のあり方というものを、
僕らに伝えてくれているように思える。
鎌倉のまちと関わり続け、地域の表情をかたちづくってきた
クリエイターの素顔に迫るべく、
横山さんの自宅兼仕事場である材木座の古民家を訪ねた。

特殊な環境下で育った幼少期
日蓮ゆかりの寺が点在する鎌倉・大町エリアで、
何度か引っ越しをしながら少年時代を過ごした横山さん。
漫画家の祖父・横山泰三さん、写真家の伯父・横山泰介さんらも
近所に暮らす環境のなかで、幼少期から自然と絵を描くようになったという。
「子どもの頃から虫の絵などをよく描いていたので、
いまとあまり変わっていないかもしれません(笑)。
9歳くらいの頃には、当時よく遊んでくれていた大人がおもしろがって、
雑誌のエッセイの挿絵を僕と弟に描かせるようになったんです。
毎回良いほうが採用されていたのですが、
このときに初めて絵を描くのは大変だなと感じた記憶がありますね」

子どもの頃から虫が大好きだったという横山さん。仕事場にはさまざまな昆虫の標本や図鑑などが置かれている。
その大人とは、アートディレクターとして名を馳せ、
後に鎌倉・由比ヶ浜にバー〈THE BANK〉をオープンさせた、
いまは亡き渡邊かをるさん。
幼少期の横山さんが、鎌倉のクリエイターコミュニティの大人たちに囲まれた
特殊な環境で育ってきたことが伺い知れるエピソードだ。
絵描きとしての英才教育を受けてきたかのように見える横山さんだが、
絵との向き合い方は時とともに少しずつ変わっていった。
「18歳の頃からはずっと祖父の家で暮らしていたのですが、
家族に会社勤めの人がいなかったこともあり、
自分も自然と絵に関わる仕事をしようと考えるようになり、
美大を目指すことにしました。
ただ、予備校に通ってデッサンなどの勉強をしていくなかで、
絵を描くことが徐々に楽しくなくなっていったんです」

葛藤とともに過ごした20代
やがて美大の油絵科に進学した横山さんだったが、
その頃には子どもの頃のような絵に対するピュアな感情は持てなくなっていたという。
「ファインアートの世界に進んだこともあり、
美術史などの知識を身につけなくてはいけないという考えがありました。
一方で、本当はもう少し気軽なところで絵を描きたいという思いもあって、
相反する気持ちが共存していましたね」
卒業後の横山さんは、美大予備校の講師など複数の仕事を掛け持ちするようになったが、
自ら絵を描く機会はほとんどなかったと当時を振り返る。
「絵を描くことをしばらくやめていたら、
自然と創作意欲が湧いてくるだろうと思っていたのですが、
そんなことはありませんでした(笑)。
子どもの頃、じいさんが楽しそうに絵を描いているのを見て
自分も絵を始めたわけですが、いざ大人になってみると、
自分にはそこまでの創作意欲はないのではないかと。
でも当時は、表立ってそれを言ってしまうのが怖かったですね」

横山さんの作業スペースは家族の食卓。昼間は連絡などで仕事が中断してしまうため、家族が寝静まった深夜に集中して描くことが多いという。
そんな複雑な思いを抱えながら20代を過ごしてきた横山さんだったが、
あるとき、掛け持ちしていた3つの仕事のうちのふたつが
同時になくなってしまったことがターニングポイントになった。
「そのときに知人の編集者に相談し、イラストの仕事をもらったんです。
この頃から、子ども向けのお絵描き教室も始めるようになりました。
手に職ではないですが、多少なりとも絵を描く技術はあったし、
これを生かして一生続けられる仕事がしたいという思いを持っていました」

なるべく小さなサイズで描きたいという横山さんは、ポストカード大のケント紙に原画を描くことが多いという。
好きなものを描ける喜び
絵を自らの生業にすることを決意した横山さんはやがて、
本連載でも紹介した〈ルートカルチャー〉主宰のイベントで、
同じく鎌倉に暮らす養老孟司さんと仕事をともにする機会を得る。
「最初に連絡をいただいたときは、養老先生とご一緒できることがうれし過ぎて、
平静を保つのが大変でした(笑)。
その後スタッフたちと山に下見に行ったのですが、
子どもの頃に夢中になった虫取りの楽しさをあらためて体感し、
昆虫熱に火がついたんです」

2016年に開催された「海のアカデミア 養老孟司先生と海の近くで昆虫採集をしよう! 鎌倉の海・夏の昆虫大調査」。子どもたちが山で採集した昆虫を、メインイベント「海のカーニバル」のフラッグにスケッチした。(写真提供:横山寛多)

最近では仕事で虫の絵を描く機会も多い横山さん。「虫のカッコよさを再確認しながら、自分のものにするような感覚」で描いているそうだ。
養老さんを講師に山で昆虫を観察し、
捕まえた虫を子どもたちがスケッチするというこのプログラムは、
「好きなものを描く」という、忘れかけていた
絵に対する根源的な欲求が刺激されるきっかけになったようだ。
「子どもの頃って自分が好きなものや欲しいものを描きますよね。
大人になった自分は、美術の歴史や文脈を踏まえて
描かなくてはいけないという思いを持つようになっていましたが、
もっと子どものような感覚で向き合ってもいいんだと。
かなり遠回りしましたが、それからはだいぶ楽になりましたね」
そこからまもなく、雑誌『ブルータス』の「ZEN」特集号の表紙に
横山さんのイラストが使われることになる。
これを機にイラストの仕事も軌道に乗り、
現在は複数の雑誌の連載ページで挿絵などを手がけるまでになっている。

『ブルータス』の表紙を飾ったことによってイラストの依頼が急増。投げかけられたお題を、大喜利のように打ち返していくイラストの仕事は性に合っているそうだ。
まちに寄り添う、無理をしない絵
横山さんは、イラストレーターとして名が広まる以前より
仕事を依頼されていたという邦栄堂製麺、
全国にファンを持つ麻婆豆腐屋かかんをはじめ、
本連載で紹介してきた鎌倉の飲食店のロゴや看板などの
ヴィジュアル制作も手がけてきた。
雑誌など印刷物のイラストが、
不特定多数の人たちに広く流通するものであることに対して、
店舗のロゴや看板などは地域に残り続け、
まちの表情をかたちづくっていくものだと言える。
「毎回お店の個性や立地、店主の物語などを汲み取りつつ、
その場所に自然になじむものを描いているつもりです。
自分が描いたものが少しでもお店が続いていくための
手助けになればと考えているのですが、
お店が長く続くというのはつまり、地域の人たちに愛されるということ。
そのためには、無理をしないということが何よりも大切だと思っています」

本連載でも取材した〈邦栄堂製麺〉の店主・関 康さんは横山さんの中学時代の先輩にあたる。近年は横山さんのイラストとともに雑誌などに紹介される機会も多く、市外・県外のファンも増えている。(写真提供:横山寛多)
決して声高に何かを主張するわけではないが、
そのお店やオーナーの個性が的確に表現され、
鎌倉のまち並みに溶け込むかのように静かに佇む横山さんの絵。
そこには、横山さんが見てきたこのまちの素顔や、
地域に根ざし活動を続ける人たちのスタンスが重ね合わされているように思える。
「鎌倉は観光客や移住者が年々増えていますが、長く暮らしていて感じるのは、
そんなに盛り上がらなくてもいいんじゃないかということ(笑)。
幕府がなくなってから長らく田舎の漁師町だったこのまちには
いまも保守的な人が少なくないし、
僕自身、ちょうどいい温度のところで、なるべく静かに、
淡々とやるべきことをしていたいという思いがあります。
僕が関わってきたお店のオーナーたちもブレない信念を持ち、
決して無理をせず、自然体であり続けている人たち。
その姿勢に共感しますし、それこそがこのまちらしいあり方なのかなと」

同じく本連載で紹介した本格麻婆豆腐専門店〈かかん〉の新業態〈みやげ屋かかん〉や、〈朝食屋コバカバ〉のロゴも横山さんが手がけたものだ。(写真提供:横山寛多)
「持てるもの」を通じて地域とつながる
鎌倉は長年、狭い市街地に多くの観光客が集中するオーバーツーリズムの問題を抱え、
昨今のコロナ禍においては、都心から移住を希望する人たちも急増している。
こうした状況が、このまちに「平熱」を保たせることを難しくしていることは事実だが、
横山さんは自らの絵やその活動を通じて、持続可能なこのまち本来のあり方を、
内外に伝えてくれているのかもしれない。
「コロナの影響で海の家がなくなった昨年の夏、
鎌倉の海にはいないと思っていたスナガニを見つけたんです。
人間のせいで見えていなかったものがコロナによって見えてきたし、
会社に通勤しなければいけないということが
幻想だったと気づいた人もたくさんいたはずです。これまでの無理や嘘が顕になり、
本当のことが見えてきているときなのだと感じています」

横山さんが手がけた鎌倉市のコロナ禍における注意喚起ポスター。「いざ、鎌倉 その前に……」というコピーは、横山さんが打ち合わせ中に何気なく口にしたひと言なのだという。
このコロナ禍に横山さんは、鎌倉市による感染防止ポスターなどを手がけるとともに、
テイクアウト可能な飲食店マップの制作なども自ら行った。
また、さまざまな事情から自宅で暮らせない子どもたちが集まる児童ホームで
数年前からお絵描き教室を開催するなど、絵描きとして、
ひとりの住民として、生まれ育ってきたこのまちに関わり続けている。
「お世話になってきた地元に対して何かできることはないかということは、
常に考えていますね。昨今のコロナ禍もそうですが、
何かつらい状況があるときに、自分が持てるものを使って、
『良かったな』『楽しかったな』と
少しでも感じてもらえるようなことをしたいと思うんです。
そういう活動を続けていると、必ずいいつながりが生まれる。
お絵描き教室などを通じて保護者の方たちともたくさん知り合うので、
このまちで何も悪いことができなくなっていくんですけどね(笑)」
生まれ育った鎌倉のまちと「絵」を通じて関わり続けてきた横山さんは、
これからも自然体の姿勢を崩さず、自らの技術と地元への愛を持って、
このまちとの心地良い関係を描いていくのだろう。

写真提供:横山寛多
writer profile
photographer profile
http://d.hatena.ne.jp/rufuto2007/