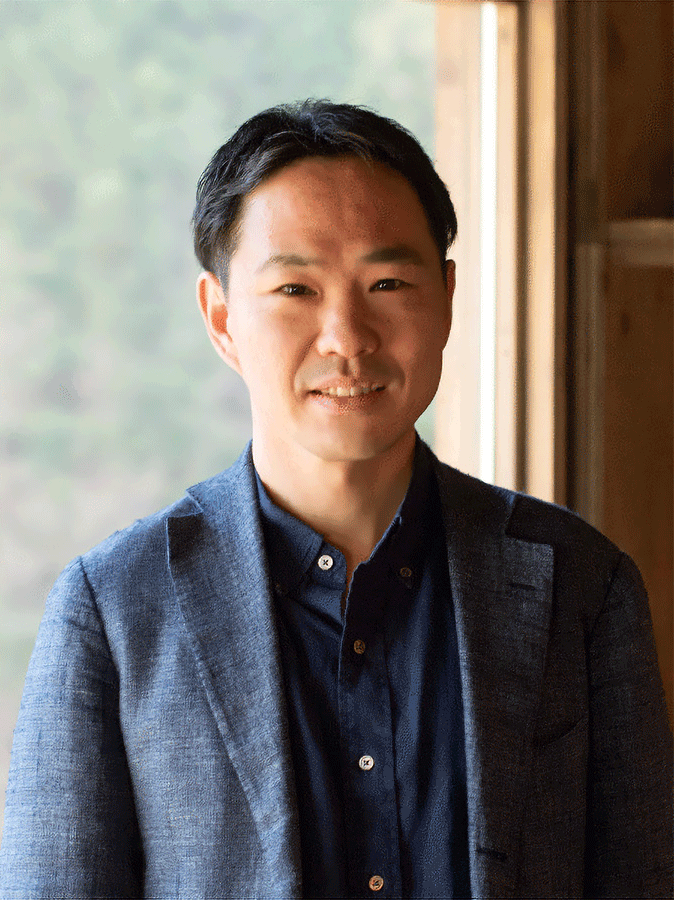伝統技術が実現させた、 日本ならではのアートがここに。 『REVALUE NIPPON PROJECT展 中田英寿が出会った日本工芸』

元サッカー日本代表の中田英寿さんが、
現役引退後、「ReVALUE NIPPON」というプロジェクトを
展開しているのをご存じでしょうか。
これは中田さんが日本各地を旅して、
伝統的な工芸、文化、技術の価値や可能性を再発見し、
その魅力をより多くの人に知ってもらうきっかけをつくることで、
日本の伝統文化の継承・発展を促すことを目的としています。
このプロジェクトで生まれてきた作品が結集する展覧会
『REVALUE NIPPON PROJECT展 中田英寿が出会った日本工芸』が、
パナソニック 汐留ミュージアムで実現しました。
2010年から「陶磁器」「和紙」「竹」「型紙」「漆」と、
毎年ひとつの素材をテーマにして作品を制作・発表してきたのですが、
ユニークな作品の生まれる大きな要因となっているのが、その進め方。
作家とデザイナーのコラボレーションは今でこそ珍しくありませんが、
ここでは「アドバイザリーボード」「工芸家」「コラボレーター」の3者がチームを結成。
さまざまな分野の専門家である「アドバイザリーボード」が
直接的なつくり手となる「工芸家」と、
アーティストやデザイナーなどの「コラボレーター」を選び、
自由な発想とスタイルで制作していきます。

「存在感のある土鍋を」というコンセプトのもと、中田英寿さん(アドバイザリーボード)、現代美術家の奈良美智さん(コラボレーター)、陶芸家の植葉香澄さん(工芸家)のチームで制作された《UFO鍋》(手前)。どっしりしているのに、そのままくるくると宙に浮いてしまいそうなたたずまいは、まさにインパクト大!
照明を落とした展覧会場に足を踏み入れると、浮かび上がる作品の数々。
素材別に展示されているものの、ひと目でその素材とはわからない作品も多く、
伝統工芸技術の奥深さを感じさせます。
どこか遠い存在だった工芸が、大胆かつポップに装いを変えることで、
ぐんと親しみやすくなるのも不思議です。

染色道具である型紙そのものを型枠に貼りつけた、照明器具《silver balloon》。伊勢型紙で知られる、三重県鈴鹿市で活躍する兼子吉生さん(工芸家)は、扇や花の形につくられた彫刻刀を用いて型紙を彫る彫刻師。東京都現代美術館チーフキュレーターである長谷川祐子さん(アドバイザリーボード)と建築家の妹島和世さん(コラボレーター)が兼子さんの型紙を選び、妹島さんが直径100センチの照明器具を設計。型紙からこぼれる淡い光が幻想的。

クリエイティブディレクターの服部滋樹さん(アドバイザリーボード)が「空間の境界線」をつくる表現者という共通点を見出し、選出した彫刻家の名和晃平さん(コラボレーター)と、竹工芸家の森上仁さん(工芸家)による《Trans-Ren》。黒い物体が彫刻、編み目のあるものが竹なのだが、彫刻と竹が融合して、不思議な一体感を醸している。
展覧会を開催するにあたり、3人の工芸家にお話をお聞きすることができたので、
それぞれの作品とともに、貴重な制作エピソードをお届けします。
一子相伝の工芸技術から生まれた、繊細で美しい竹の文字

《Takefino》 谷村丹後(工芸家)×田川欣哉(コラボレーター)×佐藤可士和(アドバイザリーボード)(写真:たかはしじゅんいち)
「Love」、「Peace」、そして中央の文章。これらはすべて竹でできています。
中央の文章は竹という言葉を使わずに竹を表現した詩になっています。
クリエイティブディレクターの佐藤可士和さん(アドバイザリーボード)、
デザインエンジニアの田川欣哉さん(コラボレーター)、
谷村丹後さん(工芸家)のチームで制作された《TakeFino》。
谷村さんの家系は奈良県生駒市高山町で500年にわたって、
お茶をたてるときに使う茶筅(ちゃせん)をつくってきました。

《Takefino》を制作した茶筅師の谷村丹後さん。一家代々継いできたこの名前は、現在で20代目!

谷村さんが制作した茶筅。先端部分は、薄く削ることによって物理的に曲げている。茶筅黒竹色糸(ピンク)5400円。(パナソニック 汐留ミュージアムのミュージアムショップにて限定販売)
「竹で文字を表すというコンセプトだったのですが、
切った竹を曲げて表現しようとしたら折れてしまったりなど、
この形に行き着くまで紆余曲折がありました。
本業の忙しい年末年始に制作期間が重なってしまったため、
当事者のひとりでありながら無理じゃないかと正直思いかけていたのですが、
縦方向に竹を差したら行けるんちゃうかと気づいたのです」
作品の詩の部分は、鏡面板に田川さんのデザインしたフォントで溝をつくり、
そこに茶筅の穂先の部分を差し込んでつくっています。
使用した竹は、茶筅で計算すると300本分くらい。
谷村さんはとにかく竹を削り続けて東京へ送り、
田川さんたちが差し込むという遠隔の流れ作業が行われました。

(写真:西部 裕介)
一方、LoveとPeaceで使われているのは、茶筅の穂先を削るときに生まれる削り屑。
「普段はどんどん捨てている部分なのですが、上から見るとふわふわしていて驚きました」
谷村さんが上京して、できあがった作品を初めて目にしたときは、
「きれいということより先に、細かい竹を差し込んだ苦労がしのばれました(笑)」
とのこと。
茶筅は伝統工芸でありながら、茶道には必需品かつ消耗品なので、
少々特殊な位置づけだと谷村さんは言います。
日本で伝統的に茶筅をつくっているのも、谷村さんが生まれ育った集落のみで、
その技は一子相伝とされてきました。
「僕自身は普段やっていることをやっただけともいえるのですが、
こういったかたちで自分のつくったものに
違う価値を持たせてもらったことがうれしかったですし、
何よりモチベーションが上がりました。
最近もSNSを見た外国の方が、わざわざ田舎道を歩いて訪ねてきてくれたりして、
昔だったら考えられないような動きが生まれています。
これからもこういう機会があったらぜひやりたいですが、
その前にたまっている注文を仕上げないと(笑)」
手づくりの高い技術が成せる、新たなおもしろさ

《 Life size polar beer in papier mache》 橋本彰一(工芸家)×片山正通(コラボレーター)×NIGO(R)(アドバイザリーボード)(写真:たかはしじゅんいち)
四つ足でどっしり立つ、体長200センチを超える迫力満点のシロクマ。
クリエイティブディレクターのNIGO(R)さん(アドバイザリーボード)、
〈ワンダーウォール〉の片山正通さん(コラボレーター)、
そして張り子職人の橋本彰一さん(工芸家)の手による
《Life size polar beer in papier mache》は、和紙でつくられています。
片山さんの事務所にある実物大のシロクマのオブジェがモデルなのですが、
橋本さんが普段つくっている張り子は、わずか10センチ程度。

自らの作品の前に立つ、橋本彰一さん。作品がいかに大きいか、わかるはず。子どもが乗っても壊れないくらいの強度なのだとか。

橋本さんが普段手がけている作品。左から三春張り子6480円、白虎の張り子7560円(ともに税込)。
しかしサイズは大した問題ではなかったようです。
「2倍、3倍の大きさでもつくりますよ、と言っていたくらいなんです。
だけど現状より大きかったら展示が難しかったかもしれないので、
これでよかったと思っています(笑)」
サイズよりも苦労したのはむしろ、毛並みの質感。

リアルに表現できる和紙を日本中で探して、
結果的に橋本さんが暮らす福島県内の和紙に辿り着きました。
「これを制作したのは、東日本大震災の起こった年なのですが、
福島の和紙を使えたのは私としてもとてもうれしかったです。
和紙の塊をちぎると毛並みっぽく見えるのですが、
何度も試行錯誤しながらひとつひとつ貼り付けていきました」
張り子の場合は通常、木の型を使いますが、
大きさを考慮して加工しやすいスタイロフォームを使用。

木造建築などの断熱材に使われる、板状のスタイロフォームを重ね合わせて型を作成。
地元で、張り子をつくっている工房は「デコ屋敷」と呼ばれています。
「デコ屋敷のデコは方言で張り子を意味して、
郡山には私の家を含めて4軒の工房があります。
でも張り子の型を制作できる職人は私だけ。
周りからは変わったことばかりしているように見られているかもしれませんが、
自分がイメージしたものを型からつくることができるのは、強みだと思っています」

スタイロフォームをカッターで削って、整形していく過程。シロクマのリアルな形が徐々に浮き上がってくる。

型の上から和紙を貼っていく。

和紙を乾燥させている様子。最終的に30枚ほど重ね貼りをする。

仰向けにしたシロクマのお腹の部分を切って、型を抜いた状態。同じ型を使ってもう1体制作されたのだが、1体目は中が空洞で、2体目は型が埋め込まれている。
橋本さんは大学で家具のデザインを学び、
卒業後、家業を継ぐまでは高校の美術教師をしていました。
「これを言うと笑われるのですが、張り子そのものより、
張り子を乗せる台をつくっているほうが楽しいんです」と冗談っぽく言うものの、
あらゆる意味で規格外のこういった作品をつくることができるのは、
豊富な知識と技術があるからこそ。
「張り子という技法は、ひと手間加えるとなんでもつくれてしまうのではという可能性を、
以前から感じていました。そんな折に、このプロジェクトをテレビのニュースで知って、
これに関われたらおもしろいことができるかもしれないと思っていたのです。
まさか本当に声をかけてもらえるなんて」
デコ屋敷大黒屋の21代当主である橋本さんは、
先代から受け継いだ機械生産による一部の商品も、
すべて手づくりに変えようとしています。
「時代と逆行しているかもしれませんが、手づくりの技術があるからこそ、
いろんなものをつくることができると思っています。
そういう意味でもこれを制作した2011年は、伝統は守るのではなく、
つくっていくものだという方向性が明確になった年ですね」

「自由」が示してくれる漆表現の新たな広がり

《コロロデスク 彦十蒔絵 鳥獣花木図屏風蒔絵》 若宮隆志(工芸家)×鈴野浩一・禿真哉(コラボレーター)×柴田文江(アドバイザリーボード)(写真:阪野貴也)
《コロロデスク 彦十蒔絵 鳥獣花木図屏風蒔絵》は、
コロロデスクという箱型デスクに、
かの有名な伊藤若冲の《鳥獣花木図屏風》を漆で再現したもの。
プロダクトデザイナーの柴田文江さん(アドバイザリーボード)、
トラフ建築設計事務所の鈴野浩一さんと禿真哉さん(コラボレーター)、
塗師屋の若宮隆志さん(工芸家)のチームによる作品です。
若宮さんは、分業制で漆作品を手がける輪島塗の職人集団〈彦十蒔絵〉の主宰者。
トラフ建築設計事務所が化粧板メーカー〈伊千呂〉の依頼で制作した家具
「コロロデスク」には、かねてから注目をしていたそう。
「これ自体は小さな机ですが、使い方次第で大きなお部屋になる、
自分の空間をつくるための道具というコンセプトがとてもおもしろいと思っていました」

塗師屋の若宮隆志さん。「漆はある種贅沢品ですが、今回のプロジェクトは馴染みのない方にも楽しんでいただくチャンスだと思いました」

若宮さんが手がける漆椀(本朱 ケヤキ)19440円。
さらに偶然が重なり、若宮さんが取り組んでいたテーマのひとつが若冲でした。
「若冲のコレクターであるジョー・プライスさんとも知り合いなのですが、
以前から若冲を入り口に漆をPRさせてもらっているんです。
若冲の絵のおもしろさは、デフォルメにあると思っています。
本物とは違うけど、それを感じさせない迫力がある。
蒔絵も実物をデザインにいったん起こして、それをデフォルメして描きます。
現在は、蒔絵師が自分でもとの絵を描いて、それを蒔絵にしていますが、
伝統的には絵師と蒔絵師に仕事が分かれていました。
ですから、若冲の絵を我々が蒔絵にするのは、むしろ伝統に沿っているのです」
パッと目を引く象の白は漆で出せない色らしく、意外な素材で表現していました。
「100個以上のうずらの卵の殻を使っています。
割る前にお酢につけるとやわらかくなって、黒や茶色の模様が白くきれいになるんです。
それを伸ばし、乾かして貼り付けています」
箱の中に精緻な絵を施すのは、やはり並大抵の苦労ではなかったよう。
「蒔絵は通常、平らな板に描くものですし、細かいということもあり、
目と板の距離を30センチくらいしか離しません。
しかも漆は縦の一方向にしか筆を動かせないので、くるくる回しながら描くのですが、
これは箱型なので箱の中を覗き込むような無理な体勢で、
自分が回りながら描かなければいけない。それがかなりきつかったですね」

(写真:たかはしじゅんいち)
若冲の動物たちについ目が行きがちですが、外側の塗りは1年の歳月を要した労作。
「上塗りには岩手の浄法寺漆を、下地には輪島の漆を使っています。
実を言うと輪島で漆はほとんど採取できないのですが、
90歳の職人さんに1キロほど特別に取ってもらいました。
輪島産漆の漆芸品は、この世にそれほど存在しないと思いますよ」
プロジェクトを通して、若宮さんが感じたのは「自由」の意味。
「関わってくださった方々の考えを取り入れるのは、大変だからこそおもしろい。
形やデザインの制約は一見不自由に思えるのですが、
そのなかで技術を生かす方法を見出すことで逆に自由を感じることができました」

漆コーナーに並ぶ作品。梅の花をかたどった直径200センチを超える漆塗りの風呂(左)や、南国の花のように生命力あふれるオルゴール(中)、アクリルケースに収納された木皿(右)。
つくり手も作品を見る側も、Revalue(価値を再発見)できる今回の展覧会。
日本の工芸は完成しているどころか、
まだまだ成長途中なのかもしれないとわくわくできる、
これらの作品をぜひ間近で鑑賞してみてください。


この展覧会図録をコロカル編集部で制作。作品解説のほかに、中田英寿さんや、元文化庁長官で東京大学名誉教授の青柳正規さんのインタビューも収録。アートディレクターは日本デザインセンターの大黒大悟さん。本体価格:2130円(税別)(写真:岩﨑 慧)
information
REVALUE NIPPON PROJECT展 中田英寿が出会った日本工芸
会期:2016年4月9日(土)〜6月5日(日)
会場:パナソニック 汐留ミュージアム
(東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階)
開館時間:10時〜18時(入館は17時30分まで)
定休日:休館日:水曜日
入場料:一般1000円、65歳以上900円、大学生700円、中・高校生500円、
小学生以下無料、20名以上の団体は各100円割引
障がい者手帳を提示の方、および付添者1名まで無料で入館可能