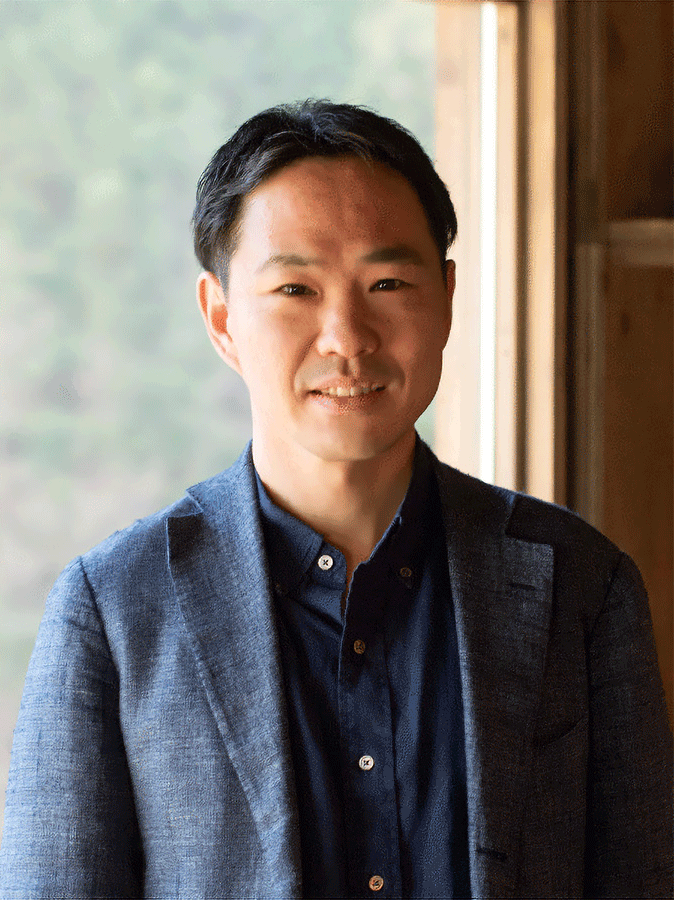【へラルボニー・松田崇弥・文登×
スノーピーク・山井梨沙】(後編)
自然とアートは似ているのか?

連載5回目となる今回は、
岩手と東京の二拠点で「異彩を、放て」というミッションのもと、
新たな文化をつくりだす福祉実験ユニット「ヘラルボニー」代表の
松田崇弥&松田文登さんにお話を伺った。
前編では、へラルボニーの活動内容の原点、
「障害者」や「障害」の現状やその言葉に対して思うことなどを語った。
今回は後編をお届けする。
(※前編「『違うからこそおもしろい』アートで『障害』の概念を変えていく」はこちら)

自然とアート
山井梨沙(以下、山井): もともと個人的にアートが好きで、
今は『さどの島銀河芸術祭』も仕事で関わらせてもらっていますが、
自然とアートってものすごく近い存在だと思うんです。
もちろん、どちらも価格というかたちでその価値が決められてしまう面もありますけど、
本来アートは生活の延長線上にあるもの。
それって自然のフィールドとすごく近いですよね。
スノーピークは自然と共に楽しむことをビジネスとして展開しています。
自然は誰のものでもないし、誰がどう楽しもうがその人次第。
だからこそ純粋な信頼関係ができる。
アートにもそんな部分があって、
作品を前にしたら社会的地位とか関係ないじゃないですか。
以前、スノーピークで社員とその家族でキャンプをする
「スノーピーク・ファミリー・ウェイ」というイベントを企画しました。
検品や製造の補助をする〈スノーピークウェル〉という子会社では、
障害のある方の就労支援をしているんですけど、
彼らにも一緒にキャンプを体験して欲しくて。
スノーピークウェルのスタッフのなかには
初めてキャンプをするという人もいたのですが、とても楽しんでくれました。
普段あまりコミュニケーションをとるきっかけがない人たちばかりだったので、
キャンプを通じてひとりの人間として関わることができて、
私もすごく楽しかったんです。
アートにもその感覚に通じる部分を感じていて、
作品を通してコミュニケーションをとるということは、
お互いにとても自然なことだと思うんです。

(写真提供:さどの島銀河芸術祭)
松田文登(以下、文登): 自然とアートが似ているって、おもしろいですね!
確かに、なんでだろう。
そんなに詳しいわけじゃないんですけど、
『どうぶつの森』というゲームのコンセプトも
「なんにもないけど、なんでもできる」って感じですよね、確か。
梨紗さんの「自然は誰のものでもない」という発言を聞いて、
何もないと思うか、それとも何でもできると思うかっていうその感じは、
確かにアートも同じだと思う。
価値づけというよりは、人それぞれ価値観が違うっていう意味で
共通点があるのかなと思いながら聞いていました。
松田崇弥(以下、崇弥): 私たちのパートナーである
知的障害のあるアーティストのなかには、
自分の作品をアートとすら思っていない人も多いと思います。
特に重度の人たちは。
点を打ち続けることが好きだとか、円を描き続けることが好きという方が多くて、
こちらでおこがましくもアートと定義させていただいているんです。
ただしその作品が売れないと、その好きな行為を辞めさせて、
コーヒーのパック詰めの作業を勧めることにもなりかねない。
私たちは、好きな行為を続けることを肯定していきたいと思っています。
文登: それが喜びにつながるのであればね。
崇弥: これは『let it be』という作品なんですけど、
作品が結構有名になったおかげで
オノヨーコさんが実際会いにいらっしゃることになったんですよ。
そのときに、作者の小林 覚さんは
オノヨーコさんと会ってもまったく喜ばなかったそうなんです。
『Let it be』という曲が好きなのであって、オノヨーコが好きなわけではないから。
もし私だったら、
無理矢理でも「来てくれてありがとうございました」と言ってしまうと思いますね。
当時、周りにいた人たちは滅茶苦茶焦ったらしいです(笑)。

(写真提供:HERALBONY)
アートが売れて高まるアーティストの自尊心
山井: でも、確実にアートがコミュニケーション手段になっていますね(笑)。
本人がアートと思っていないっていうのは、すごく興味深いです。
ヘラルボニーの活動を通じて絵が売れたりして、
実際にその対価としてお金を得たりするうちに、
なんとなく意識が変わっていくこととかもあるんですか?
文登: ありますね。例えば原画だったら40〜50%が作家さんへ還元する仕組みです。
ただ、仮に僕らの兄が絵を描けるとしたら、
価格が30万円だったとして兄に15万円入っても、
その価値を兄が理解するのは難しい。
チョコレートアイスを100円で買うのと、15万円の価値は、
彼のなかではあまり変わらないと思いますが、そのお金が入ることによって、
親御さんの考え方が変わったり、
福祉施設がアーティストという立ち位置で見るようになってきたりするんです。
親御さんが親戚に「うちの子の絵が、30万で売れたんだよ!」と
発信することによって、「俺、やたらと絵で褒められてるなぁ」っていうことを、
本人は二次的に理解していくこともある。
そういう意味で自尊心が高まっていくことは、確実にあると思いますね。
山井: 自尊心が高まることによって、横暴になる人もいたりしますか?
お金を稼ぐことによって、
何かマイナスの意味で変わってくることもあったりしますか?
文登: それはあまりないと思います。
自信がついて、施設を訪ねると「俺の絵を観ろ」と言ってくる人もいたり。
「すげぇだろ」みたいな。
そういう意味で自分の作品に自信を持つというのはありますけど、
横暴になるという印象はあまりないですね。
崇弥: ただ、あるアーティストの方からは、
僕が違う作家さんのアートマスクをつけて会ったときに、
「お前のマスクは格好悪い」って言われたりしたよね、結構。
文登: いたいた、ライバル心が出てました(笑)。

山井: 家族の方々や施設側だって、
実際のところお金を生んでいかないと養っていったり、
運営をしていくのは難しいと思う。
だからお金を稼げるようになる仕組みをつくられているのは、
本当にすごいことだと思います。
崇弥:: 自分の母も、家族から障害のある子を産んだことは隠さなければいけない、
地域にばれてはだめだよって言われたみたいで、
いまだにそう思っている人って結構いらっしゃるようなんです。
でもヘラルボニーが存在することによって、
落書きと思っていたものがアートとして評価されるようになることで、
本人や家族が外に出ていくきっかけになっています。
さらに親御さんをはじめ、おじいちゃんやおばあちゃんからも、
「うちの子を、初めて誇りに思った」という連絡をもらったりすることも多いんです。
山井: 本人にしても、自分が社会に認められたり、
みんなが自分の絵を求めてくれるってこと、
それ自体が幸せだったりするのかなとも思う。
売れるからうれしいんじゃなくて、ただ描きたい、表現したい、つくりたいというのは、
アートの原点というか、いちばんプリミティブなアートの姿なのかもしれませんね。
文登: 現代アートだと、歴史的にコンテキストが重要だと思うんですけど、
僕らがやっていることは、なかなかそのコンテキストには収まらないんですよね。
山井: アウトドア業界も、登山、キャンプ、スキー、釣りとか、
みんなすごくカテゴライズしようとするんですよ。
アートも結局現代美術や古典美術とか、
そう呼ぶのがいいのかわからないですけど「障害者アート」とか区別されがちで、
表現することでいったらみんな同じなのに。
そういう価値観が増えていくとおもしろいですよね。
文登: そう、好きが溢れているだけでいいんじゃないかと思うんです。
そう言ってもらえると、とてもうれしいです。

(写真提供:HERALBONY)
異彩を放ち、人間性を回復する
山井: ヘラルボニーさんが掲げている「異彩を、放て。」というミッションは、
どのようにしてその言葉ができたのですか?
文登: まずは、福祉業界の外に完全に振り切って共感を獲得したいと思っています。
私たちは知的障害がある人たちと一緒にクリエイトしていく集団なので、
(いわゆる福祉業界全般のみなさまと)手をつないで
「みんな一緒です!」と主張するのではなくて、
ある種の差別化する必要があったんです。
それで「異彩を、放て。」というミッションを掲げて、
さらに「普通じゃないということ、それは同時に可能性だと思う」という
一文も入れています。
「障害があるからこそできる」ということを
強烈に打ち出したいという気持ちがありました。
山井: スノーピークは「人間性の回復」というミッションを掲げていますが、
自然とアート、フィールドは違えど、
目指すとことろはそんなに変わらないんじゃないかとも思うんです。
凝り固まった価値観を見直そうよとか、違いを認めたうえで、
体験を通じて多様性について改めて考えるということを示唆しているように感じて。
それこそ『FIELDWORK―野生と共生』という本でも書いたのですが、
私自身、ほかの人たちと同じことができない。
学校も通えないとか、もちろん字の読み書きとか喋ることはできるけど、
やっぱりほかの人が普通にできることができなかったりして、
除外されたりしたこともあったんです。
もしかしたら、だからこそ服をつくることや
経営みたいなことが少しできるのかもしれないですけど。
だからといって、平等な社会になって欲しいとか、
誰もが認め合える世界になって欲しいとかいうことではなくて、
人それぞれが違うのって当たり前のことじゃないですか。
その違いを認めておもしろいと思えるようにありたいと思うんですけど、
やっぱり人間という生き物は、
自分と違うものに対して脅威に感じてしまうものだと思うんですよね。
多分、宗教とか国籍とか人種とか性別とか、全部そうだと思う。
経営を学んでないのに経営者になっていることに対しても、
ものすごく拒否反応とかあったりするし。
文登: どこからの拒否反応なんですか?
山井: 株式マーケットとか、いろいろと……。
文登: これだけ数字的に結果を出していれば、
何を言われようがという気もしますが……。

山井: そう願います(笑)。
私は、小さい頃から個性的なおじさんたち、
それこそ歯が全部抜け落ちていてどんな食生活を送っているのかわからないけれど、
ずっと会社に泊まり込んでものすごいプロダクトをつくる人とか、
社会性がまったくないんですけど魚を釣るのが異常に上手い人とかに
育てられたような部分があるんです。それこそキャンプ場で育ったような感じ。
自然のなかだから認め合えて、協力して、足りない部分を補い合うことが当たり前で。
そういう経験を通じて、アートと自然が似ていると思うようになったのかもしれない。
アートって何が正解とか不正解とか、ないじゃないですか。
本来は誰かの純粋な表現に触れて「すごい!」って純粋に言える世界なわけで。
自然も同じで、自然をフィールドにそんな感覚を体験してもらって、
常識とされていることや社会で良しとされているいろいろな価値観が本当にそうなのか、
ひとりの人間に戻って自然のなかで人と関わって何を思うのか、
スノーピークでは、そんなプロセスを「人間性の回復」と呼んでいるんです。
崇弥: 確かに、自然とアートって本来近しいものなのかもしれないですね。
その「個性的なおじさんたち」は、
社会で生きていくのはうまい人たちではないかもしれないけど、
猛烈な能力を持った人たちで、まさに異彩を放っていますよね(笑)。
文登: やっぱり今のこの社会だと、
対人感受性やコミュニケーション能力が重要だったりしますよね。
社会で生きるってことにあまり向かなかったとしても、
サバイブしていくうえである種の領域で爆発的能力を持つ人たちが
適材適所で活躍するのかもしれない。
僕たちの活動も、もしかしたら深いところで自然と紐づいているのかもしれないですね。

そもそも多様性なんて、ないのかもしれない
山井: 最近、多様性という言葉がひとり歩きしているように感じています。
例えばLGBTQという言葉がありますが、
逆に多様性をカテゴライズしてしまっているんじゃないかと思ったりしていて。
ヘラルボニーさんの活動を見ていると、
まさにそこに問いを投げかけているように感じるんです
文登: 多様性って何なのかを考えずに、
多様性って重要だよねということを
語り合う社会になっているのかもしれないと思います。
実際に僕らも「障害」については実体験としてわかるけれど、
LGBTQのことはあまりわからないから、
触れないほうがいいのかなと思ってしまう場面もあったりして。
誰しもが多様性についてオープンに話せるようになった反面、
自分の意見を持って話しづらい感じにもなっている側面も
あるんだろうなって感じますね。
山井: 養老孟司さんがおもしろいことを言っていました。
「そもそもみんな違うから、多様性なんてものはない。
落ち葉でも何でも、自然のなかにあるもので
ひとつとして同じ形のものはないんだよ」みたいなことで。
スノーピークの活動は、詰まるところそういうことに気づいてもらうことだと思うし、
ヘラルボニーさんの活動も、まさに同じなのではないかと思うんです。
文登: そう言っていただけると、とてもうれしいです。
崇弥: 今日はヘラルボニーのギャラリーで作品を見てもらいましたけど、
山井さんにはもっとたくさんの作家さんの作品を観ていただきたいので、
今度ぜひ福祉施設にもご案内したいです。
山井: 福祉施設って、アトリエが併設されている場所もあるんですか?
崇弥: 併設されている所も、結構多いですね。
花巻市にある〈るんびにい美術館〉とかは、
アトリエを見学できて、ギャラリーも併設していたり。
山井: ぜひ連れて行ってください。また岩手に来るの、楽しみにしています!

(写真提供:るんびにい美術館)
profile

Takaya Matsuda
松田崇弥
代表取締役社長。小山薫堂が率いる企画会社〈オレンジ・アンド・パートナーズ〉、プランナーを経て独立。4歳上の兄・翔太が小学校時代に記していた謎の言葉「ヘラルボニー」を社名に、双子の松田文登と共に〈ヘラルボニー〉を設立。異彩を、放て。をミッションに掲げる福祉実験ユニットを通じて、福祉領域のアップデートに挑む。ヘラルボニーのクリエイティブを統括。東京都在住。双子の弟。世界を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」受賞。
Web:へラルボニー
profile

Fumito Matsuda
松田文登
代表取締役副社長。ゼネコン会社で被災地の再建に従事、その後、双子の弟、松田崇弥と共に〈へラルボニー〉を設立。4歳上の兄・翔太が小学校時代に記していた謎の言葉「ヘラルボニー」を社名に、福祉領域のアップデートに挑む。ヘラルボニーの営業を統括。岩手在住。双子の兄。世界を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」受賞。
Web:へラルボニー
profile

LISA YAMAI
山井梨沙
株式会社スノーピーク代表取締役社長執行役員。1987年新潟県生まれ。祖父は同社創業者の山井幸雄、父は代表取締役会長の山井太。文化ファッション大学院大学で服作り、洋服文化を専攻し、ドメスティックブランドで約1年間勤務。2012年に採用試験を受けスノーピークに入社し、アパレル事業を立ち上げる。その後同事業本部長、企画開発本部長、代表取締役副社長を経て、2020年3月より現職。著書に、『FIELDWORK―野生と共生―』や『経営は、焚き火のように Snow Peak飛躍の源泉』がある。
Web:スノーピーク