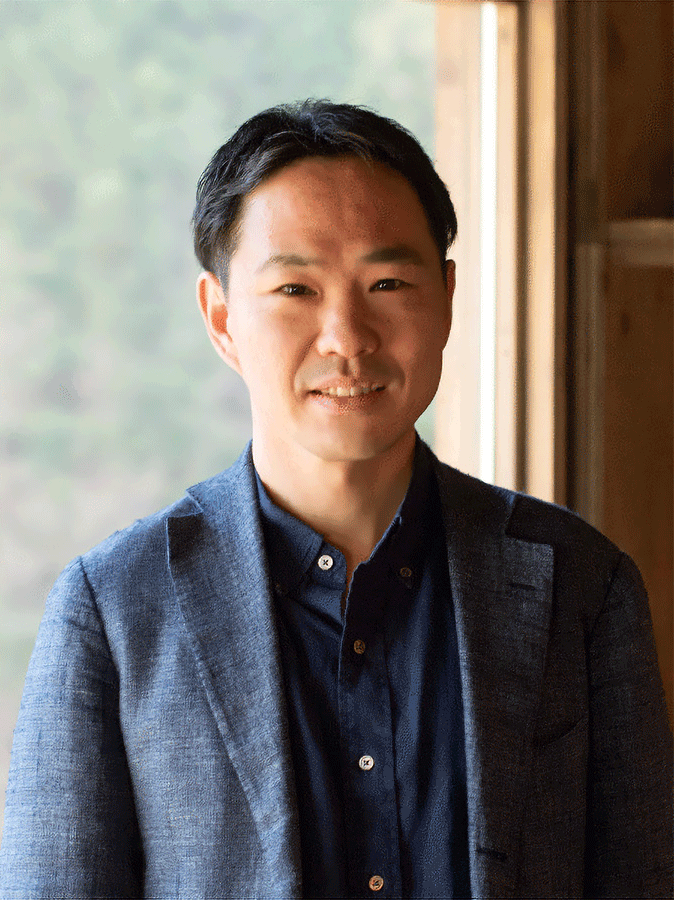高山の夜祭り〈本町四丁目夏酒場〉
シャッター商店街にグルーヴを。
人生にロックンロールを!

写真提供:hiroko.hashimoto
飛騨への移住は何が違う?
仕事、住居、暮らしを支える飛騨コミュニティ vol.2
世界中から集まる、多くの旅人の心を掴んで離さない飛騨。
観光地として有名な飛騨は、高山市・飛騨市・下呂市・白川村の
三市一村からなる広域エリアだ。
伝統に触れつつ、新しい生き方を実践できるこの地域には、
観光客だけでなく移住者が増えている。
地域で暮らすうえで、大きなポイントとなるのが、人とのつながり。
縁を感じられる地域には、移住者は自然と集まってくる。
コロカル×未来の地域編集部でお届けする、飛騨の魅力に迫る連載。
外の人々を迎え、つながりを強くする。そんな飛騨のコミュニティを訪ねていく。
レトロな商店街で人々を熱狂させる、夏の恒例イベント
歴史ある家屋が並ぶ「古いまち並み」や、
日本三大朝市のひとつ〈宮川朝市〉で有名な高山市。
まわりを山に囲まれた情緒深いまちの風景は、近年外国人旅行者にも人気が高い。

趣のある夕方のまち並み。日中は外国人旅行者も多数訪れる。
ちょうど、まちの中心を流れる宮川に沿って、レトロな雰囲気の本町商店街がある。
ここでは、毎年夏に多くの人々を熱狂させる
〈本町四丁目夏酒場〉(夏酒場)というお祭りが行われている。
このイベントを主催するのは、本町四丁目商店街振興組合のみなさん。
商店街の持続と発展を目的として、四丁目で商店を営む19名で構成されている。
40年以上前からある組合だが、近年は高齢化や後継者問題を抱える商店も多く、
昔と比べて活動規模は縮小している。
そんな商店街で毎年行われている夏酒場は、飛騨地域には珍しい屋外の大型イベントだ。
いまでは、夏の恒例イベントとして多くの人に知られるようになったが、
活動が始まった背景には、さまざまな人たちの思いが詰まっていた。
空き店舗をなんとかしたい! 靴屋の原田さんの思い
原田憲一さんは、本町四丁目にある〈靴のハラダ〉の息子として生まれ育った。
大学進学を機に上京し、東京の靴屋で修業時代を過ごした後、25年前に帰郷。
高山で自身の靴屋をオープンさせた。
もともと郊外に出店していたが、何度かの移転を経て、
現在は本町四丁目でブーツ専門店〈Knockin’ Boots〉を営んでいる。


Knockin’ Bootsはネット販売が中心。店舗では、原宿系のカラフルなブーツが目を引くこともあり、外国人旅行者がよく立ち寄るという。
「この場所で靴屋を始めたのは2012年。
ちょうど四丁目でも空き店舗が目立ってきた頃でしたね。
昔は、地元の人は商店街で買い物していましたが、やっぱりいまは、
郊外の大型店やショッピングモールなどに出てしまう人が多い。
何もせずに放っておいたら、衰退する一方です」
本町四丁目は、市街地のメインストリートから少し離れていることもあり、
人通りが多いとは言えない。
なかには、どうしても環境の変化に対応しきれない商店もある。
シャッターが下り、空き店舗が目立つようになってきた商店街は、
原田さんにとって、なんとかしたい課題だった。

夜の商店街は、人通りもまばら。閉店してしまっている店舗も多い。
「もともと、本町では毎年8月1、2日に〈納涼夜市〉というお祭りがありました。
一丁目から四丁目まで、それぞれの組合が管理していますが、この日は一致団結。
本町商店街がすべて歩行者天国になって、金魚すくいや動物のレースなど、
お祭りらしいことをやっていたんです。
組合としては、自分たちの父親世代が頑張っていた時期ですね」

以前は靴以外にも商品を販売していたが、現在はブーツが看板商品だ。
一丁目から三丁目までは、いまでも多くのお店が開店しているが、
空き店舗が増えてきた四丁目では、イベント運営が徐々に難しくなっていった。
原田さんがUターンしてお店を始めた頃は、
四丁目のみ納涼夜市のすべての運営を企画会社に委託していたという。
子どもの頃に体験したかつての賑わいと、
目の前にある空き店舗だらけの商店街とのギャップ。
何かできないかと思案していた原田さんに、ある店で転機が訪れた。
ロックンローラーが集う、名前のない酒場
高山には、名前のない居酒屋、通称「どや」がある。
「どや」は地元の人々が呼ぶ名前であって、店に屋号はない。
原田さんは、そこの常連客だ。数年ほどかけて、
オーナーには相談ごと、頼みごとができるまでになった。
この店をひとりで切り盛りしている、柳原洋介さん(通称ヨウさん)の生き方は
ロックンロールだ。
生まれは東京の神田で、10代後半は下北沢で過ごした。
21歳の頃には、1年半ほどヨーロッパやアフリカを旅し、
帰国後は、東京とアメリカで複数の飲食店を経営した。

お店の住所、電話番号は非公開となっている。偶然見つけることができたら、ぜひ立ち寄ってほしい。
個性的なバックグラウンドを持っているが、結婚を境に生活ががらりと変わる。
会社を離れて、奥さんの実家である高山に移住し、ひとりで店を始めたのだ。
誰も知らない場所で、飲食店のあり方を追求した結果、
名前がなく、メニューもなく、ひとりで店に立つというスタイルに至った。

見知らぬ土地で、お店をオープンさせたのが2001年。いまでは地元の常連客で賑わっている。
そんな個性的な店に、原田さんがお客さんとして来るようになったのは、15年ほど前。
「原田さんは、はじめのころは友人と来ていて、カウンターで少し話すくらいでした。
だんだん彼ひとりで飲みに来ることが増えていって。
そのうち、引越しの手伝いまで頼まれるようになりました」
ふたりのつき合いは長い。
原田さんが商店街でKnockin’ Bootsをオープンするときには、
ヨウさんが店舗の内外装施工を手伝った。
ギャラの代わりだったのか、原田さんは施工中の2か月は、
毎晩お店に顔を出したそうだ。
この地域では、お酒を酌み交わすことは、何よりも信頼関係の構築につながる。
カウンター越しに、つき合いは深まっていった。

「どや」にはメニューもない。できるものはできる、できないものはできない。出てくるものはヨウさんにお任せだ。
「どやでみんなと飲んでいるうちに、原田さんをはじめ、飲食店仲間とも
『四丁目の納涼夜市を、再び自分たちで運営しよう』という話が出たんです。
まちが楽しくなるのはうれしいことだし、協力してくれそうな馴染みの飲食店も多い。
成功してもしなくても、おもしろそうだから
すべての運営をやってみるかということになりました」

10年ほど前には、自腹でアーティストを招聘する〈高山ロックンロール作戦〉を立ち上げた。店でも定期的にライブを開催。
単純におもしろそうだから、と話す一方で、
商店街が盛り上がっていることを、広く伝えたい思いもあった。
周囲を巻き込むイベントを大人たちがつくり続けていれば、
閉まっている店舗のシャッターを誰かが開けてくれるかもしれない。
好奇心と期待を込めて、原田さんとヨウさんは
四丁目納涼夜市のリニューアルに向けて動き始めた。
商店街にグルーヴをつくる、自分たちでつくりあげた夜祭り
2013年の夏、かつての四丁目納涼夜市は、全面刷新して行われた。
本町一丁目から四丁目までの道路をすべて封鎖し、
飲食店は店を閉めて、商店街全体が酒場となった。

ライブパフォーマンスも圧巻! 2017年は、地元住民御用達、選りすぐりの飲食店12店舗が出店した。
リニューアルした当初は名前すらなかった夜市だが、
2015年からは正式に〈本町四丁目夏酒場〉と名づけられ、
いまでは2日間で1000人以上を集客する規模のイベントに成長した。
酒場の名の通り、「大人が楽しめる夜祭り」をコンセプトに、
飲食と音楽が混ざりあう賑やかなイベントだ。
出店している飲み屋の常連客から、祭りに引き寄せられる地元客、
たまたま商店街を通りかかった外国人観光客と、客層も幅広い。
みんな、気持ちのいい夏の夜を、音楽とともに楽しんでいる。

多くの参加者が集まり、大盛況のステージ。本町一丁目から四丁目まですべてを歩行者天国にしている。
「これからは、この地域に住む若い人たちが、
どんどん展開していってくれたらうれしいです。
夏酒場を継続させつつ、自分たちの手から離れていくのが理想ですね。
去年がこうだったから、という慣習にとらわれず、新しいことを積極的に試してほしい。
多様な人が関わり合っていくことが、夏酒場らしくていいんじゃないでしょうか」
そう話す原田さんは、組合の理事として夏酒場の取りまとめを行いつつ、
商店街の振興にも注力している。
これからは、空き店舗を期間限定のバーにしたり、
川床をつくって商店街イベントの幅を広げたいそうだ。
今後も、周囲を巻き込む原田さんの挑戦は尽きそうにない。
高山のセッション文化をつくってきた、もうひとりのキーマン
〈本町四丁目夏酒場〉では、路上セッションも魅力のひとつだ。
ライブやパフォーマーのステージだけではなく、
通りすがりの観光客が飛び入りで参加することもある。
ライブステージの監修を任されているのが、久田上総さんだ。
久田さんは、高山で生まれ、高校までを地元で過ごした。
当時から音楽少年で、ある一流のミュージシャンの
ライブドキュメンタリーを見たときに、ジャムセッションをしながら
すべての音づくりをしていく様に圧倒されたという。
いつか、そういった音楽を自分でもやりたいと思い、
アメリカへの音楽留学と自身の音楽活動をスタートさせた。
帰国後、しばらくは関西を拠点としていたが、
子育てをきっかけにして地元に戻ってきた。

高山に戻ってきてからは、実家の郷土料理店〈久田屋〉で働きつつ、音楽活動も並行して行っている。
「即興性のある音楽を、ずっとやりたいと思っていました。
地元に帰ってきたとき、それができる場はどこにもなかったので、
知り合いのバーで定期的にジャムセッションを行っていたんです。
最初の頃は、ジャムセッションをやったことのない人たちが集まってきたので、
うまくいかないことだらけ。
それでも音楽のある場をつくっていくことは、自分が大切にしていた思い。
継続していけばおもしろいことになるんじゃないかと思っていました」
2年ほどバーでのセッションを行ったことで、音楽関係のつながりは増えていった。
そこで、ヨウさん、原田さんと出会った。ロックな生き方をするふたりとは意気投合し、
すぐに夏酒場の運営に関わるようになった。

ニューヨークのイーストビレッジのような、セッションが日常にあるまちが理想だという。
高山でも音楽活動を行う傍ら、プロミュージシャンを招いたライブを定期的に開催し、
音を楽しむ場づくりも行ってきた。
夏酒場に関わるようになってからは、コンサートホールではなく、
まちの路上でセッションできてしまうことに可能性を感じたという。

地域内で音楽イベントができたことは、大きな自信になった。2018年には〈飛騨高山ジャズフェスティバル〉の開催も決定している。
真剣に場をつくる人がいれば、イベントはどんな場所であれ開催できてしまう。
音楽活動を通して、地域の人が求めている場をつくることが、
久田さんが思い描く未来だ。
今年で、5年目を終えた本町四丁目夏酒場。
運営に携わるメンバーは、今後はジャンルを横断し、
より混ざり合う空間をつくっていきたいと口を揃える。
地元のミュージシャンと観光客がジャムセッションをしたり、
商店街オーナーと新しい世代が運営に関わり合っていくことで、
予想もできない化学反応が起こるかもしれない。
そこには、地元住民も移住者も関係なく、同じ感性を持つ人々が集まってくる。
廃れていくだけの商店街ではなく、変わったことも受け入れられる場として、
感化された人には寄ってきてほしいという思いがある。
この数年で、四丁目商店街には、カフェが3軒、宿泊施設が1軒、
雑貨屋が1軒オープンし、少しずつ活気が戻ってきた。
本町四丁目夏酒場は、これからも多くの人を惹き寄せていくのだろう。
「未来の地域編集部」が発信する、
グッとくる飛騨