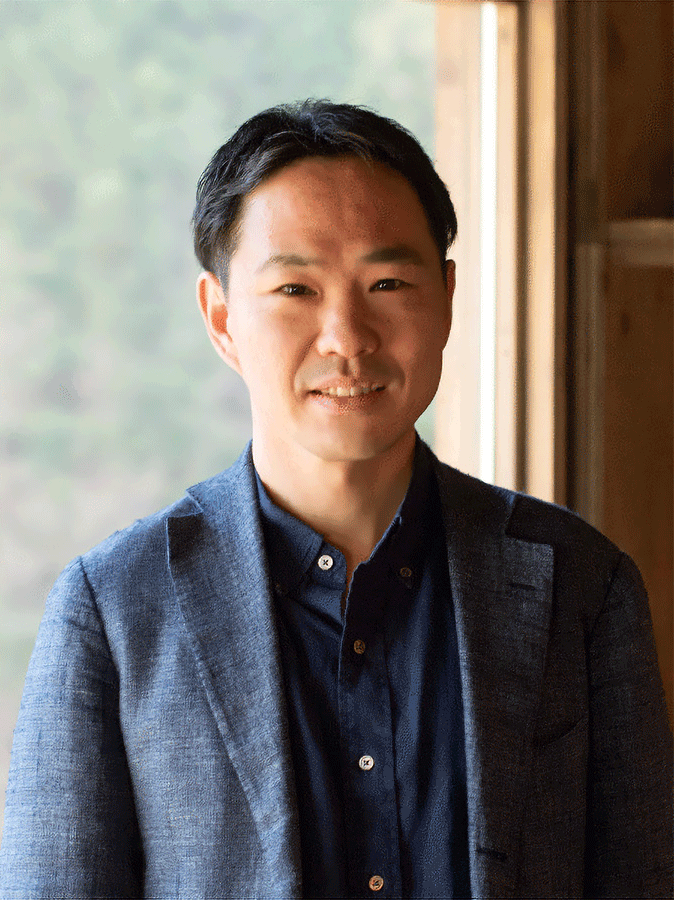美術家 深澤孝史さん 歴史や文化、 そして人々の思いを 地域に深くダイブしてアートにする

〈アートフロントギャラリー〉代表の北川フラムさんが推薦したのは、
〈大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ〉など、
日本のローカルを舞台に作品を発表する美術家・深澤孝史さんです。
推薦人

北川フラム
アートフロントギャラリー・
アートディレクター
Q. その方を知ったきっかけは?
東日本大震災で被災した東北の子どもたちを〈大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ〉で受け入れた際、実によく動き楽しくさせた。停電など、スクランブルがかかった際、アクシデンタルな事態に適格な人間として記憶に残った。
Q. 推薦の理由は?
以降、奥能登国際芸術祭、内房総アートフェスなどに参加してもらったが、そのひとつひとつで地域を読み込み、地域の人たちの中に入って優れた仕事をしてくれた。
特に〈大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2024〉では、2年間秋山郷に入り、7人のアーチストと共に、地域を浮かびあがらせる作品展示『アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-』を、2020年に廃校になった小学校で行った。これは地域住民、美術関係者、民俗学関係者だけでなく一般の観客にもその深さ、楽しさが伝わり、多くの人が自然と人間のかかわりの大切さを知ったと思う。
縁もゆかりもなかった札幌で、なぜ彼は制作を行うのか
11月下旬。
札幌市にある天神山緑地はうっすらと雪化粧をして、冬の訪れを告げた。
緑地の敷地内には、アーティストインレジデンスである
〈さっぽろ天神山アートスタジオ〉があり、
美術家の深澤孝史さんも、かつて制作活動を行うときに
スペースを借りていたことがあると話す。
「大きいものをつくるときに、広い場所が必要だったので。
いま、作業はほぼ札幌市内の自宅で行っています」

札幌市が運営する、〈さっぽろ天神山アートスタジオ〉。滞在だけでなく、市民の交流場所としても利用されている。

滞在中アーティストの作品などが展示されるスペースもある。
山梨県に生まれ、静岡県の大学に進学し、卒業後も浜松市に8年ほど居住していた深澤さん。
移住のきっかけは、〈札幌国際芸術祭2014〉に参加したときに出会った奥さまだ。
「僕の活動の場所が国内を転々とするので、
札幌出身在住の妻の拠点に合わせようという軽い気持ちで移り住みました。
実際、地方への移動は結構大変なのですが、気持ちのいいまちです」

札幌市内でありながら自然豊かで、空気が澄んでいる天神山緑地。
深澤さんがこれまで参加してきたグループ展やアートプロジェクトは、
活動年表にするだけでもずらりと長く、その場所も日本全国に広がっている。
それぞれの地域に根差し、土地の歴史を学び、人と交わりながら
“一緒に作品をつくっていく”のが深澤さんのやり方だ。
「教員免許を取って、大学卒業後に浜松の定時制高校で非常勤を務めながら、
〈NPO法人クリエイティブサポートレッツ(現在は認定NPO法人)〉に
関わるようになったのですが、
それが、いまの活動のベースになっているかもしれないです」
ただひとりのためのアートセンター
クリエイティブサポートレッツは、障害を持つ子どもたちの可能性や選択肢を広げ、
同時に障害者を受容する社会づくりを目指すNPO法人。
代表の久保田翠さんが、
重度の知的障害を持つ息子の壮(たけし)さんをきっかけに立ち上げたもので
深澤さんは、2008年ごろから運営に関わるようになった。
「最初はたまたま近くにいるから、ということでレッツに関わるようになり、
主に放課後や週末に講座の講師などをしていたのですが、
だんだんと渦に飲まれて、気づいたらいろいろと企画をするようになっていました」

美術を主体的にはじめたというより「自分がのびのび生きられる環境を整備していたら、今の状態になった」と話す。
そのなかのひとつが、たけしさんのためのアートセンター〈たけし文化センター〉だ。
紙を破るのが好きなたけしさんのために移動式の小屋を紙でつくり、
それを破ってもいいルールにしたり、砂利で遊んでいい場所をつくったり、
音楽家を呼んでワークショップをしたり。
やがてこれが契機となり、たけし文化センターは2018年に市街地に移転。
現在は障害を持つ人のみならず、市民が集う地域に開かれた文化センターとして、
さまざまな人たちがともに生きる社会をつくる一端を担っている。

「たけし文化センターBUNENDO」 2009 認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ
たけし文化センターは、久保田さんの熱意がまずあって、
それをどうしたいかという問いから、
久保田さんがやってきたことを深澤さんらスタッフが整理し、
それを実践に結びつけてみよう、という流れで生まれたものだった。
一個人の思いを増幅させて、みんなと広く共有していく企画や仕掛けをつくる。
深澤さんが、アートとこのような関わり方をするようになった理由はなんだろうか。
「小6のときに父が亡くなり、人間ってすぐ死ぬって、結構トラウマになったんです。
なんて言ったらいいのかな、
現代人って、生きている意味みたいなものがつかみにくいですよね。
誰かとつながって生きているわけでもなかったり、
住んでいる土地との結びつきも弱かったりして。
持続・継承的な生の仕組みを個人の自由と引き換えに手放していったのだということを、
徐々に感じるようになったんです。
同時にレッツで学んだのは、さまざまな条件の人たちが共にある場を考えるということ」
そこで「過去の継承や現在における共同体や他者との関わり方」ということを
考えているうちに、
他人がこれまで積み上げてきた思いや、土地の歴史などを
どう自分が引き継いでいくかということに、関心が向いていったのだという。

秋と冬の狭間にある札幌市の風景。
たけし文化センターを企画したときはまだ20代で、
当時はまだこのようなことを意識していなかったにもかかわらず、
個人の表現という枠組みではない芸術の実践を自然に行えたのは
「たぶんもともと、僕が持っていた表現における主体性の低さという特性なんだと思う」
と、話してくれた。
そしていまも、さまざまな地域と密に関わりながら、制作活動を続けている。
アートを通じて「自分が変わる」体験
なかでも深澤さんが長く参加しているのが、地域芸術祭のパイオニアである、
〈大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ〉(以下、大地の芸術祭)。
大地の芸術祭2012から関わりはじめた。
特に2回目となる大地の芸術祭2015には、十日町市の市街地プロジェクトを企画。
地域の家庭に宿泊し、生活調査をしてその成果を集めて博物館をつくるという
『越後妻有民俗泊物館』(略して民泊)を企画し、注目を集めた。

『越後妻有民俗泊物館』 (写真提供:深澤さん)

『越後妻有民俗泊物館』深澤孝史 (撮影:Ishizuka Gentaro)
「集落といってもひとりひとり生き方が違うので、
それぞれの話を聞いて資料を集めて、近現代の民俗博物館をつくろう、と。
それで一般の人が、調査員として各家庭に泊まれる仕組みをつくりました」
基本的には山村の近代化をテーマに、
開発でなかったことにされた縄文土器や発電所誘致、
あるいは冬でも出稼ぎせず外貨を稼ぐためにはじまった鯉の養殖などについて、
現地の人にヒアリングしながら、情報を拾い上げていった。
「結局観光しても、現地の人たちとの主体的なつながりって、
生まれにくいじゃないですか。
景色がきれいだったな、ごはんがおいしかったな、で終わってしまう。
それもいいけれど、自分の生き方が決定的に変わるという経験を目的にするのであれば、
現地の人との関係をつくったほうが早いと思ったんです」

大地の芸術祭で行ったプロジェクトは、ひとつの冊子として記録・出版されることも。
狩猟、信仰、山の技術を作家が表現
そして、2024年11月10日に終了した大地の芸術祭2024で、
深澤さんは7名のアーティストと
『アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-』というプロジェクトを実施した。
日本のなかでも秘境と呼ばれる秋山郷にある、
義務教育免除地の悲願の学校として生まれた大赤沢小学校は2021年に廃校になった。
それがアケヤマの舞台だ。

アケヤマ外観 (撮影:金本凛太朗)
江戸時代後期に、鈴木牧之という随筆家が秋山郷を旅して書いた紀行文
『秋山記行』にも記されているが、
秋山郷に住む人たちは、明治時代にようやく稲作ができるようになるまで
焼畑、狩猟、採集など、ほぼ自給自足の生活をして暮らしていた。
そして戦後、世の中が落ち着いた頃に、
民俗学の視点でもう一度秋山郷を再発見しようという機運が生まれてきたのだという。
今回深澤さんを「次をつくる」人であると推薦した、
大地の芸術祭総合ディレクターであり、
〈アートフロントギャラリー〉の北川フラムさんにとって、
秋山郷はいつかきちんと手をつけたい、重要な場所だった。
2021年に小学校が廃校になり、
芸術祭のメイン拠点のひとつにすることができるようになって
深澤さんに声がかかったという流れだ。
「リサーチのため、2021年にまずは僕がひとりで秋山郷に入りました。
米がつくれなかったこの場所で、狩猟採集のみで、人々がこれまでどう生きてきたのか。
いわば、極限までの知恵と技術が高まった場所ともいえます」

秋山郷とは、長野県との境界に位置する越後8集落と信州5集落の総称。 (写真提供:深澤さん)
ジャンルは大きく3つ。山の素材と技術、信仰、狩猟だ。
それらについて1年間リサーチし整理して、
深澤さんがそれぞれを井上唯さん、内田聖良さん、永沢碧衣さんという3人の作家に託した。
「その3名に加え、僕が関わる以前から会場で作品を展開していた
山本浩二さん、松尾高弘さんと、フラムさんの紹介で会場構成に入った、
〈一般社団法人コロガロウ〉佐藤研吾さんとも協働しました」と深澤さん。
「山の素材と技術」を依頼した井上唯さんは『ヤマノクチ』というプロジェクトを実施。
植物の繊維を使い、この地に伝わるアンギン編みという技術を実践したり、
栃の実のアク抜きして『コザワシ』をつくったりと、
秋山郷で古くから親しまれている山の自然素材を集め、
さまざまな技術を再生していった。

井上唯『ヤマノクチ』 (撮影: Kioku Keizo)(アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-)
また秋山郷は、その山深さや豪雪といった土地の特徴により
天然痘の魔除けの儀礼やススを使った結界づくりを行ったり、
雪が積もったときに葬式を開くのが困難で、集落の人が住職の代わりに祈祷したりと
近年まで独自の信仰が続いていた。
近代化で徐々に途絶えつつあるが、山の神の儀礼などは現在も続いている。
内田聖良さんには秋山の信仰の分野を依頼。
秋山の集落や各家に伝わってきた信仰を
作家が現代的な視点を取り入れつつ再演する作品を制作した。

内田聖良『カマガミサマたちのお茶会:信仰の家のおはなし』 (撮影: Kioku Keizo)(アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-)
狩猟の分野を担当した永沢碧衣さんは、秋山郷のマタギと対話しながら、
山から採集した素材や、狩猟で獲った猪や熊の血などから
絵の具を使って絵を描いていく『山の肚』を制作。
「永沢さんには、秋山郷のクマ猟にも同行してもらい、
そこでフィードバックしたことを元に洞窟壁画をつくってもらいました。
秋山郷は火山地帯で、
山深くの休憩地として人や動物に使われてきた洞窟(リュウ)がたくさんあり
マタギは洞窟に滞在しながら狩猟を行っていました」

永沢碧衣『山の肚』 (撮影:Kioku Keizo)(アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-)
また、深澤さんは『続秋山記行編纂室』を制作。
鈴木牧之が『秋山記行』で書いたことを、
この200年間、さまざまな専門家、地元の人、
移住者など秋山に関わる人たちが継承してきた。
その『秋山記行』の続編とみなして紹介していく展示である。
例えば、地元の猟師・山田正道さんは、
すでに途絶えたと思われていたさまざまな山の習俗や狩猟技法を人知れず続けている。
山田さんが特に注目するのは「ワダラ猟」と呼ばれるウサギ猟だ。
「ワダラ」と呼ばれる藁を円形に編んだものを投げ、
驚いて雪の中に隠れたウサギを捕まえる。
ほかにも100年前の発電所建設で多くの朝鮮人労働者が動員されていたのだが、
そこで亡くなった朝鮮人労働者からもらって
代々大切にしてきた庭石を個人的な慰霊碑として展示をするなど、
全館にまたがって展開した。

山田正道さんのワダラ猟。 (写真提供:深澤さん)
「おもしろいことに展示に訪れた人たちの多くが、
自分が住んでいる土地の見え方が変わったとおっしゃっていましたね。
でも、訪れた人たちは秋山郷ではなく、
自分のいま生きている場所と関わりながら生活していかなければなりません。
『自分の住むまちの持っている可能性は思ったより深いのではないか』
ということに気づいたという感想もいただきました」
先人の思いを絶やさないように
フラムさんは、深澤さんが担当したアケヤマのプロジェクトについて
「地域住民、美術関係者、民俗学関係者だけでなく、
一般の観客にもその深さ、楽しさが伝わり、
多くの人が自然と人間のかかわりの大切さを知った」と評した。
深澤さん自身ももちろん、モノの見え方や、関わり方が変わったと話す。
現在、子どもがほぼ存在しない秋山郷では、深澤さんたちのような人たちが外部から入り
学び、感じ、表現することでしか、土地の文化は継承されない。
「それは新たな養子制度のようなものかもしれないですね」と深澤さんは語る。
アケヤマのプロジェクトは、まだはじまったばかりだ。

やることを押しつけるのではなく、相手が何をやりたいか常に捉えて対応する。フラムさんにとって深澤さんは「アクシデンタルな事態に適格な人間」。
「フラムさんも先人の『地球をどうよくしていくか』といった意志を受け継いで、
この、大地の芸術祭という形に行き着いているのだと思います。
フラムさんの過去の活動をさかのぼると、そこにはたくさんの美術家や活動家たちがいる。
彼らの想いを継承していくなかで、フラムさんは自己表現の枠を超えた、
人間の文化活動の強みのようなものを、つくろうとしているのだと思います」
紐解いていくと、フラムさんの思いは、深澤さんの思いと通じているように思う。
そう伝えると、「そうかもしれないですね。まあ僕がしゃべっているから、
そういうことになっちゃうんでしょうけど」と言って、子どものように笑った。
これからも深澤さんは、長い歴史を、積み上げてきた文化を、
そして誰にも届かなかった声を丁寧に拾い上げて、
アートという息を吹き込み、未来へと受け継いでいく。
profile

TAKAFUMI FUKASAWA
深澤孝史
ふかさわ・たかふみ●美術家。1984年山梨県生まれ、北海道在住。共に在る場や継承にまつわるプロジェクトを各地で実施。2008年に鈴木一郎太とともにNPO法人クリエイティブサポートレッツにて「たけし文化センター」を企画。2011年より、自分のとくいなこと預けたり誰かのとくいを引き出したりできる『とくいの銀行」を取手、山口、札幌などで展開。越後妻有のさまざまな民家に民泊をすることで生活調査をしてその成果を集めて博物館をつくる『越後妻有民俗泊物館』(2015、大地の芸術祭)、常陸太田市にて恣意的に埋もれさせられていた佐竹氏の歴史を現代に結びつけ主体的な歴史選択の場をつくる『常陸佐竹市』(2016、茨城県北芸術祭)など。2024年には『アケヤマ ー秋山郷立大赤沢小学校ー』(越後妻有大地の芸術祭)を監修。