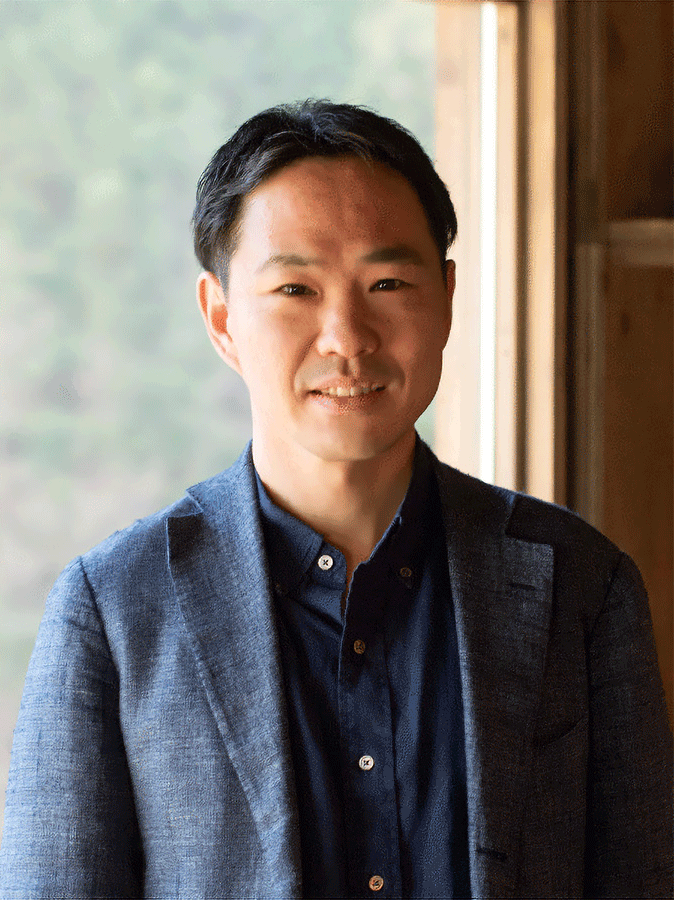たべよう たべよう めしあがれ
心と身体が喜ぶ食卓の物語

写真:うえすぎちえ
ひわさんと囲んだ食卓での出来事をスケッチブックに記して
私が美流渡(みると)地区を拠点に続けている出版活動〈森の出版社 ミチクル〉では、
昨年からローカルブックスという仕組みを立ち上げ、
本づくりに思いを寄せる仲間と知恵を出し合い、「編集・印刷・流通・販売」を
ともに協力しながら本を刊行する取り組みを行ってきた。
これまで島牧(しままき)、美流渡、美唄(びばい)といった
ローカルな地域に住む人たちの、本に残しておきたい大切なことを綴ってきた。

これまで刊行してきたローカルブックス。左から『さくらの咲くところ』(吉澤俊輔)、『移住は冒険だった』(MAYA MAXX)、『おらの古家』(渡辺正美)。
12月、4冊目となる新刊が登場。
新千歳空港にほど近い長沼町にある〈大きなかぶ農園〉の
およそ13年前の食卓が舞台となっている。
本づくりの始まりは2008年。
札幌で音楽教育の講師を務めていた、うえすぎちえさんが、
この農園で小さなピアノコンサートが開かれることを知り、訪ねたことから。
「D型倉庫に案内された私は、不思議の国の物語の中の扉を開いてワクワクと恐る恐るの気持ちに揺れながら足を踏み入れました。そこには台所に立って洗い物をしている魔女。私を見るなり、コンサートのために知り合いの農家さんからいただいたお花をたくさんの小瓶に飾ってほしいと仕事を与えてくれたのです」(本書より、ちえさんの序文)

『たべよう たべよう めしあがれ 大きなかぶ農園の食卓の記録』より
“魔女”と形容されたのは、永野ひわさん。
夫のさとしさんとともに、2001年から長沼で農園を営んでいる。
夫妻は作物を育て、各地の有機農産物や無添加の加工品などの販売を手がけている。
当時、母屋の改修が終わっていなかったふたりが住んでいたのは農業用D型倉庫。
住まいといっても床は土間。
靴を履き、近くの川から水をひき、薪ストーブひとつで暮らしていたという。
私自身も北海道に移住してしばらくして、八百屋さんを通じてひわさんと知り合った。
ひわさんは、敷地に生えているハーブを薬代わりに活用するなど、
昔ながらの知恵を生かした暮らしをしており、
その姿を“魔女”と言ったちえさんの言葉はピッタリだと思った。

以前住まいとなっていたD型倉庫は、現在、野菜の貯蔵場所となっている。極寒の北国で断熱が十分でない倉庫で暮らしていたとは本当に驚く。(写真:うえすぎちえ)
このコンサートのあと、ちえさんはたびたび農園を訪れるようになった。
いつしか、ひわさんがつくってくれた料理を写真に収めるようになり、
それをスケッチブックに貼って、
自分自身が忘れたくないと思った出来事を書き残していった。
3か月ほど書きためたスケッチブックを2009年のクリスマスに、
ひわさんへプレゼントした。
「その時々に食べたなんでもない昼ごはんや夕はんの写真が、素直な感想と共に綴られている。日々の食卓の風景を通して、大切なひとと共に食卓を囲む豊かさ、ひとと共に在る歓び、それを伝えずにはいられないという思いがあふれ出ている。この空間でこんなことを感じていたのね、と思わず目から涙もあふれ出ました」(本書より、ひわさんのあとがき)
翌年もちえさんはスケッチブックを制作。それらはひわさんの宝物となった。
そして13年の間、これを宝物として秘密にしておきたいという気持ちと
自分だけが独占してしまっていいのだろうか? という気持ちの間で揺れ動いていたという。
「世界中を巻き込んだコロナ旋風のさなか 2021 年、これからの暮らし方、人と人との関わり方などを考えていたとき、ふと、やはり、どうしても『すべてのひとにわたしの宝物を捧げたい』と、内なる声がはっきりと浮上してきたのを見過ごすことができなくなり、自費出版する決心をちえさんに告げました」(本書より、ひわさんのあとがき)
この提案に最初は戸惑いがあったちえさん。
しかし数週間後、私と仲間が企画し旧美流渡中学校で開催した
『みんなとMAYA MAXX展』『みる・とーぶ展』に足を運び、
〈森の出版社 ミチクル〉の存在を知った。
そして、ローカルなつながりで本がつくれるのであればやってみたいと思ったそうで、
スケッチブックを世に出すプロジェクトが始まった。

現在のひわさんの食卓。置かれているのは、まとめられた2冊のスケッチブック。(写真:うえすぎちえ)
個人的な記録は、本になるのか?
スケッチブックを初めて見せてもらったのは昨年の秋のこと。
あんかけ焼きそばや餃子、ドリアなど、おいしそうな食卓の写真が、
スケッチブックいっぱいに詰め込まれていた。
そして、その日に起こった出来事や食卓での会話などが記されていた。
ちえさんは自信がなさそうな様子で、
「ミチクルで出版に値する内容かどうか、意見を聞かせてもらえませんか?」と語った。
本を出したいという話のときに、こう質問されることは多く、いつも返答に詰まる。
出版の基準は、突き詰めれば突き詰めるほどわからなくなっていく。
自分がおもしろいかどうかで判断してしまっていいのか、
それほど自分の感覚というのは絶対なのだろうかと疑問がわいてくる。
仮に現状で引っかかりがなくとも、推敲を重ねていくうちに、
よいものが表れるかもしれないし、出版以前に
その可能性を摘み取っては、もったいないとも思う。
そもそもローカルブックスは、デザイン費と印刷費は著者が負担し、
私が担当する編集は、費用を支払ってもらう代わりに、
つくった本を200冊預かるということにしている。
なので、まずふたりが出したいという意思を尊重するのが、私の立場だと思うのだ。

ローカルブックスの仕組み。本制作に関わるコストをみんなの協力によってできるだけ抑え、販売もお互い助け合うことで、本を継続して刊行できるようになったらと考えた。
こうして本づくりがスタートすることとなり、スケッチブックのなかから、
本に掲載したいページをちえさんがピックアップし、それをまとめていくこととなった。
毎回、ローカルブックスのデザインを担当してくれている
〈ナカムラグラフ〉のアートディレクター・中村圭介さんに、
私は新しい本が動き出したことを伝え、スケッチブックのなかから
いくつかの画像を見本として送付した。
すると、中村さんからこんな返信があった。
「個人的な主観でお話をつくる場合は、その人の作家性が試されるなあとか、誰か見て楽しいのかなあとか。と、このあいだ自分でも本をつくってみて思いました。本は誰でもつくることができるので、ミチクルの本として編集者として、厳しい目で取り組む部分も必要かもですね」
中村さんのこのコメントはグサリと刺さった。
13年前に、ひわさんにプレゼントするためだけにつくられたスケッチブック。
それはふたりにとっては大切な事柄ではあるが、
それが不特定多数に向けて共感を生むものなのか?
編集者として30年ほど本をつくり続けてきたが、
わたしがこれまで手がけてきたのは、美術関連の実用書がメイン。
確固とした内容があって、それをいかにわかりやすく読者に伝えるのかというものが多く、
何気ない日常の出来事を綴ったような、ある意味とらえどころのないものを、
どのように編集していけばいいのか、その方法論は持ち合わせていなかった。

ひわさんがつくったコーンスープ。味つけは塩のみという超シンプルなレシピ。(写真:うえすぎちえ)
また、中村さんからもうひとつ指摘されたのは、
食事をつくったひわさん自身の文章ではなく、
そこに居合わせたちえさんが執筆をしているという点。
「どちらに温度感をおくのか、いいまわしが難しそうな本ですね」とも指摘があった。
ひとりで出版活動をしていると、どうしても自分に甘くなって、
適当なラインで終わらせてしまうところがある。
中村さんが、こうしてズバッと指摘してくれるおかげで、毎回、客観的な気持ちが生まれる。

マローの花。ひわさんはサラダとして食べたり、乾燥させてお茶にしたりしている。(写真:うえすぎちえ)
私は、ちえさんの文章を読みながら考えを巡らせていた。
そして、もっと深く自分が感じたことを突き詰めて書いてもらいたいと思った。
これは自分の経験から考えたことだ。
コロカルで、自分の身の回りの出来事をテーマに連載するという状況になって、
最初は戸惑ってばかりだった。
書いても書いてもしっくりこないなかで、やがて、事実を包み隠さず書くこと、
そして本当に思ったことを書くこと以外に道はないと思うようになった
(人におもしろいと思ってもらおうというよこしまな気持ちがあると、うまくいかない)。
「とにかく、当時思ったことをまずは洗いざらい書いてください。なぜ、ひわさんの食卓をスケッチブックに残したいと思ったのかを序文として書いてください」
そう、ちえさんにお願いした。
ちえさんは、ひわさんと食卓を囲み、細胞が喜びを感じるような料理を食べることで
自分が変わっていったという。
ならば、変わる前にはどんな問題を抱えていたのかを「洗いざらい」
表に出してほしいと思った。

数日前に友人を亡くし悲しみの底にあったちえさんは、農園を訪ねた。大根を干すさとしさんのお母さんと思いがけず「死」について話したという。(写真:うえすぎちえ)
「私」という言葉を消して
ちえさんは、ひわさんとの出会いについて、序文でこう書いた。
「ひわさんマジックにかかったごはんを食べながら、または温泉に入りながら、話すいつものおしゃべりは、少しずつ少しずつ私の心に染み入りました。いろいろな身の回りに起きる良い事や嫌な事を、あーでもない、こーでもないと、紐といていくと、だいたいにおいて辿り着くのは、『自分の心のままに動く事』。
そうすると、些細な出来事でイライラする時間が減り、いろいろな現象がスムーズな流れに乗って運ばれ嫌な思いをほぼしなくなったのです。私にとってはガーンと一撃された様な大きな出会いで転換点のひとつとなりました」(本書より、ちえさんの序文)

カボチャとゴボウの油炒め。ひわさんの料理は、いつも野菜が主役。(写真:うえすぎちえ)
ちえさんは、鍵盤演奏と歌を歌って体をととのえることを教える仕事を続けているが、
以前はレッスンが思うようにいかず、一時、職を離れて
イギリスで半年間暮らしたことがあったという。
また、腸閉塞を何度かわずらったこともあり、食の大切さに目を向けるようになり、
そうしたなかでひわさんとの出会いがあったそうだ。
自分の整理されない思いと向き合って、それを文章にするというのは、
ときに辛さを伴うものだと思う。
しかし、そうすることによって、本の核のようなものが見えてくるのではないかと思った。
けれど、まだ「本当にこれだ!」という確信は持てなかった。
そこで、若干言い訳のように感じる部分や、
テーマから逸れる部分に修正を加えてもらった。
また、文章に「私」という言葉が多かったので、できるだけカットしてもらった。
こうした作業のあとで、私はページを思い切って圧縮し、
読者にしっかりと内容が伝わるものだけを選んでまとめてみた。

編集途中のラフレイアウト。
それを、ちえさんに見せたところ……
「内容を削ったことで、本ができるというワクワク感がシューっとしぼんでしまったと感じました」
そんな返事を聞いて、いいものをつくりたいと進んできたつもりだったけれど、
もしかして、これは自分の価値観の押しつけになっていたのかもしれないと思った。
ちえさんに、文章から「私」を削ってほしいとお願いしたのに、
自分こそ「私」というものをなくす必要があったんじゃないかと感じた。
あらためてちえさんが入れたいという文章をすべて載せ、
巻末にひわさんが書いてくれた料理のレシピをまとめた。
これらの文章と写真を、中村さんに渡した。
ちえさん、ひわさん、中村さんが集まってのオンライン会議で、
「ちえさんの文章、とてもよかったですよ」と中村さんが語ってくれた。
その後、デザイン作業はスムーズに進み、先日印刷所へ入稿。
12月1日に発売できることとなった。
個人的に書いたものが、多くの読者の共感を呼ぶものにどうしたらなっていくのか。
自分でも答えの見えない課題を探る道のりに、ちえさんは辛抱強くつき合ってくれた。
こうやってデザインが上がり本として読んでいくと、飾らない気持ちが感じられ、
日々の暮らしのそこここに希望があると思えるものとなっていた。

巻末に掲載した、ひわさんによる料理レシピ。大勢人が集まったときは「野菜のあんかけ」。「どんなに人数が増えようが、水を足して無限に増やせるから」など、ユーモアたっぷりの文章に思わず笑顔に。
私が、この本で好きなのは、朝について書かれた一文だ。
「『朝』という漢字は『十月十日』。胎児はお母さんのおなかの中でこの長い時間を過ごしたあと、世の中に産まれてきて、新生児となる。だから、どんな人も『朝』が来れば、生まれかわるのだ、みたいな事が、本に書いてあった話をコクのあるアツアツ納豆オムレツをほおばりながら話した。すると、ひわさんが言った。『朝は毎朝、毎朝、違っていて、その日にやってくる朝は、今までの人生で初めて体験する日の始まりだよね』」(本書より、ちえさんの文章)
朝食を食べながらふたりが話した情景が目に浮かぶ。
まるで自分もその食卓を囲んでいるみたいだ。
読者のみなさんも、この食卓に招待されて、心が、身体が、リフレッシュされるような、
そんな気持ちを味わってもらえたらと思う。

『たべよう たべよう めしあがれ 大きなかぶ農園の食卓の記録』うえすぎちえ、永野ひわ。
注文は森の出版社 ミチクルのFacebookから。
writer profile

http://michikuru.com/