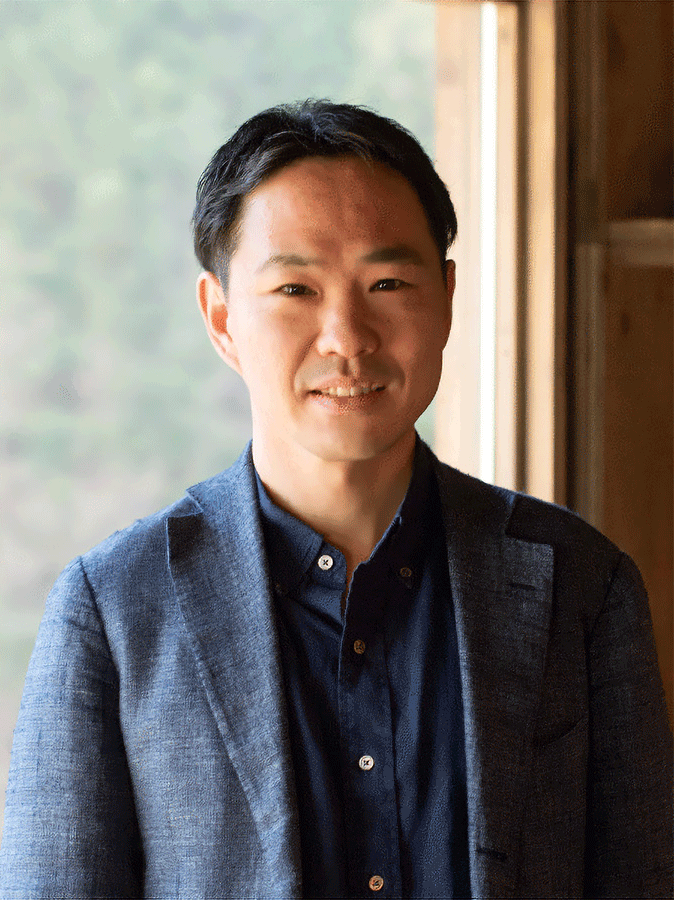軽やかな口当たりがおいしい! 兵庫県の進化する日本酒はいかが? 〈ひょうごフィールドパビリオン〉 Vol.3

歴史も風土も多様な五国は、まるで日本の縮図のよう。
兵庫県では県そのものを大きなパビリオンに見立て、
地域の人々が主体となって地元の魅力を発信する〈ひょうごフィールドパビリオン〉を展開。
県内各地でユニークなプログラムが用意されている。
兵庫県は日本一の酒どころと呼ばれている。
土地が生み出すお米と、その旨みを最大限に引き出す杜氏の伝統技術の賜物であるが、
さらに兵庫県の日本酒をめぐる文化にはSDGsも関係していた。
酒米の王様〈山田錦〉が生み出す日本酒
大吟醸の日本酒。フルーティでさわやかな酸味が特徴で、
お店によっては、より香りを楽しんでもらうために
ワイングラスで提供されることも珍しくない。
その原料となる酒米の多くに「山田錦」という品種が使用されているのはご存知だろうか。
山田錦の生産量全国1位は、兵庫県である。
山田錦がつくられる前から、兵庫県は日本酒の一大産地として名を馳せてきた。
〈大関〉〈白鶴〉〈菊正宗〉など、
全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアでも売られているような
メジャーなブランドも数多く出している。

兵庫県にある酒米研究交流館で閲覧できる資料。
最近では全国各地で日本酒がつくられ、小さな酒蔵も多い。
さまざまな流通環境の進化や技術革新の賜物であるが、
そもそも日本酒は、その土地の水や米、自然環境に味が左右される
テロワールの元祖のような存在(かつての日本の食文化のほとんどはそうだった)。
それぞれの食文化に適した場所がある。
つまり兵庫県は米づくり、とくに山田錦の生育環境として適していたのだ。
それに加え、江戸時代より酒造りが盛んだったことも兵庫県が
酒どころとして発展した重要な要素となっただろう。
山田錦が酒米としてすぐれている理由
〈酒米試験地(酒米研究交流館)〉は、全国でも唯一の酒米専門の試験研究機関。
兵庫県が生産量全国1位である酒米「山田錦」が
ここまで受け入れられるようになった理由には、着実な研究結果による裏付けがあった。
「この地域は何メートルも火山灰が積もっていて、非常に崩れやすくて柔らかい。
その分、根が深くまで入り込みやすく、水や養分を吸ってくることができるという
特徴があります。カルシウムやマグネシウムが多く、肥料の吸着能力も高い」と
教えてくれたのは、酒米試験地の主任研究員である松川慎平さん。

稲が土壌の中で広がる様子を示した展示。
この肥沃な土壌に合わせた酒米の栽培が行われてきたのかと思えば、そうでもないようだ。
「実は歴史的には仕方なしにつくってきたようなんです。
山田錦が生まれたのが昭和11年。
当時は大阪のお米のほうが酒づくりに向いているといわれていました。
その後、戦争の時代に突入。米の流通や移動に知事の許可が必要になるなど、
ハードルが高くなりました。
そこで兵庫の酒蔵さんは“仕方なし”に山田錦を使っていたようです」
はじめは酒米として使いにくかったようだが、
研究を進めていくといいお酒がつくれることがわかり、
昭和38年には作付面積が最大になった。
はじめは“仕方なし”だったかもしれないが、
灘を中心に酒づくりのプロフェッショナルが多くいた兵庫だからなし得たこと。
偶然のようでいて、必然だったのかもしれない。
山田錦の特徴のひとつに「削りやすさ」があると松川さんは言う。
お米を50%以下にまで削る(精米する)のが大吟醸の日本酒。
最近では精米歩合が30%や20%台なんて大吟醸酒も見かける。
「心白というお米の中心の白濁部分が小さいので、
たくさん削っても割れにくいという特徴があります。
だから流行りのフルーティな吟醸酒に適しているともいえます」

40%にまで削った山田錦。大吟醸などに使われる。
突出した特徴があるというより、バランスがよく使いやすいのが山田錦であるとも、
松川さんは続ける。
「扱いやすいというのも受け入れられている理由のひとつです。
思った通りのお酒ができるというのは、何回も酒蔵さんから聞いたことがありますね」

品種による背の高さの違いがわかりやすい。山田錦は右から8番目で長いほうに分類される。
最近の課題は暑さ対策。「冷害」への対策は過去の資料にもあったが、
「高温」対策はなかったという。
「肥料や田植えの時期などを調整して、
山田錦を高温でも適切に育てる試験なども進めています。
同時に『高温に強い山田錦』のような新しい品種の『育種』も行っていますが、
なかなか簡単ではありません」
山田錦を守りつつ、進化もさせていきたい。山田錦がすぐれた酒米であるからこそ、
そうしたニーズが高まっていくのだろう。

酒米試験地の主任研究員、松川慎平さん。
information

酒米試験地/酒米研究交流館(兵庫県立農林水産技術総合センター)
菊正宗の進化=フルーティな日本酒
〈菊正宗〉の〈キクマサギン〉は世界的なワインコンテスト「IWC」のSAKE部門にて
最もすぐれたコストパフォーマンスを発揮した酒に与えられる
「グレートバリュー・チャンピオン・サケ」を受賞するなど、
現代的に進化している日本酒だ。
まるで大吟醸を飲んでいるかのようなフレッシュな味わい。
それでいて大吟醸ではないのでお手頃価格。
洋食にも合わせやすく、現代の食スタイルに毎日合わせられるお酒である。

左から/しぼりたてギンネオカップ 180ml 239円、しぼりたてギンパック 900ml 875円、上撰720ml 927円、百黙 純米大吟醸 無濾過原酒 720ml 3372円(兵庫県限定販売)、純米樽酒 720ml 1104円、樽酒ネオカップ 180ml 261円(すべて参考小売価格)
これは1659年創業の酒蔵〈菊正宗〉が送り出した、進化した品。
吟醸酒ではない普通酒でありながら、酵母を独自開発してこの味を引き出したのだ。
「これまでの歴史で扱ってきた、たくさんの酵母。
当社の研究所でそれら酵母を研究しました。
そのなかでりんごやバナナなどフルーティな香りを出す酵母を培養して、
独自開発したものを使用しています」
と話す〈菊正宗酒造記念館〉館長の井内雅巳さん。
本来、吟醸酒はお米を多く削らないといけないので、その分、手間やコストがかかるが、
それを乗り越えることで価格を抑えることに成功したという。
こうした進化は、たくさんの酵母を扱ってきた長い歴史の上に成り立っているものだ。
菊正宗がある兵庫県の灘エリアは全国に誇る「銘醸地」。
今津郷、西宮郷、魚崎郷、御影郷、西郷の5つを合わせて「灘五郷」と呼ばれ、
25の酒蔵が集積している。地域として400年にもわたる日本酒づくりの歴史があり、
今なお日本一の清酒生産量を誇る。
日本人のライフスタイルや社会性が変容するなかで、長くトップリーダーであるには、
たゆまぬ努力があるはず。進化することと歴史を守ること。
どちらも必要な要素だろう。前述のキクマサギンが菊正宗の進化だとしたら、
守りの部分は「生酛造り」と「酒樽」だ。

菊正宗酒造記念館で展示されている生酛造りの様子。
菊正宗の伝統=生酛造りと酒樽
菊正宗では、伝統的な生酛造りを行っている。人力で蒸したお米と麹米をすり潰したり、
かき混ぜたりすることで、そのときに自然と入り込む乳酸の力を借りて
酵母を育てる手法だ。
「最初から乳酸を入れてしまえば、時間も手間も格段に少なくなります。
しかし生酛造りで強い酵母を育てたほうが最後まで発酵が進んで、
辛口で押しの強い味になります」
生酛造りを行っているのは、もう全国でも数が少ない。
もっと生産量が増えて、効率がいい手法もある。
やらないという選択肢を選ぶのは簡単だ。
しかし生酛造りを続けるのは伝統を絶やしたくないから。
進化とは伝統や歴史の上に成り立っていることは言うまでもない。

酒樽のタガを編む職人。
かつて輸送時にお酒を入れるものは木製の樽だった。
当然、手仕事でつくられていた。
しかし時代とともに、酒樽はほかのものに取って代わられ、その伝統は失われつつある。
そこで菊正宗では、廃業した酒樽製造会社の樽職人を社員として迎え入れ、
自社で酒樽づくりを続け、さらに社員にその技術を受け継いでいる。
〈樽酒マイスターファクトリー〉は、ミュージアムではなく、
実際にこの場に材料の吉野杉が置いてあり、職人が作業をしている工房である。
(※見学は要予約)
女性職人がタガを編む作業を見学していると、
数メートルもある細くて長い竹をまるでムチのようにしなやかに編んでいく。
しかし実際に触らせてもらうと、とてもかたくて驚いた。
確かに広い場所で全身を使っていて、まるで舞を踊っているようだった。
その後、師匠が樽を組んでいく。とにかくきつく、かたく、締め上げる。
釘も接着剤も使わないが、酒の一滴も漏らしてはならないのだ。

酒樽にタガをはめていく。
技術をただの表面的な伝統として受け継ぐのではなく、
きちんと機能として活用しているのがすばらしい。
酒樽で保管して吉野杉の香りが移ったものを、その名も〈樽酒〉として発売している。
樽酒が売れないと酒樽が必要なくなってしまう。
世の中の受け継がれなくなった伝統技術のほとんどは、ニーズが少なくなったから。
伝統技術の保護は、日本酒全体の底上げと表裏一体なのかもしれない。
information
菊正宗酒造記念館
清酒の原点「伊丹諸白」
大阪国際(伊丹)空港にほど近い、伊丹市にある〈白雪ブルワリービレッジ長寿蔵〉は、
小西酒造の築250年以上の酒蔵をリノベーションしたレストラン&展示施設。
1階は、酒蔵からまるでビアホールのように大胆に改装し、
日本酒はもちろんクラフトビールやベルギービールも楽しめるレストランに。
日本酒をより広い層にカジュアルに楽しんでほしい、そんな思いが込められている。
「かつてほど日本酒=和食という時代でもありませんので、和食もありますが、
さまざまなジャンルを取り扱っています。
みなさん多種多様なペアリングをしていますよね。このようにピザに合わせたり、
洋風のオードブルでペアリングしていたこともあります」
と、日本酒の多様化について話す店長の合志達矢さん。

「大吟醸ひやしぼり」でつくる清酒ハイボール(600円)と白雪 酒粕ピザ(1380円)。

生ハムのなめらかな舌触りと奈良漬の食感、コクがいいアクセントに。
白雪ブルワリービレッジ長寿蔵での、新しい試みでもある「清酒ハイボール」は、
すっきりとした味わいで、清酒の新しい境地を開いてくれそうだ。
そもそも清酒は伊丹が発祥の地といわれる。
それまでは白く濁った「濁り酒」が一般的で、
伊丹市鴻池の鴻池家が初めて「澄み酒」をつくり江戸に出荷したとされている。
こうじ米と掛米の両方に精白米をふんだんに使用した伊丹のお酒は
「伊丹諸白」と江戸で珍重され、西からの「下り酒」として人気を博した。
「くだる・くだらない」という言葉の語源ともいわれる。

伊丹市の指定文化財である〈鴻池稲荷祠碑〉。鴻池家発祥の地といわれている。
1550年創業の小西酒造でも、現代における清酒の新しいあり方を模索している。
ビアレストランの業態で提供することも、カクテルのようにして提供することも、
どちらも正しく現代の清酒の姿。
その奥には400年の歴史を感じることができるだろう。
進化をやめないことが伝統を守り伝えることにつながるのだ。

長寿蔵限定の微発泡日本酒〈超特撰純米吟醸淡にごり〉720ml 2200円
information
白雪ブルワリービレッジ長寿蔵
住所:兵庫県伊丹市中央3-4-15
TEL:072-773-1111(ブルワリーショップ 072-773-0524)
営業時間:11:30〜21:00(L.O.20:30)※ランチメニューの注文は14時迄(ブルワリーショップは10:00〜19:00)
定休日:火曜
Web:白雪ブルワリービレッジ長寿蔵
田んぼは多様性のあるビオトープであるし、里山保全にもつながる。
米どころが酒どころになるのは当たり前で、エネルギーのロスは少ない。
酒造りは土地、水、菌の力など自然由来のものばかりで、廃棄物も少ない。
つまり日本酒づくりは、稲作〜酒造りと、数百年の間、大きな変化がなく、
SDGsなんて言葉がない頃から持続可能なものだった。
伝統を受け継いでいくことがSDGsとして大きな意味を持つ現代において、
最も歴史のある兵庫県の酒造りに注目して、体感していきたい。
information

ひょうごフィールドパビリオンとは
兵庫県内のさまざまな「活動の現場(フィールド)」を、地域の方々が主体となって発信し、多くの人が来て、見て、学び、体験する取り組みです。
Web:ひょうごフィールドパビリオン
Instagram:@hyogo_field_pavilion
*価格はすべて税込です。