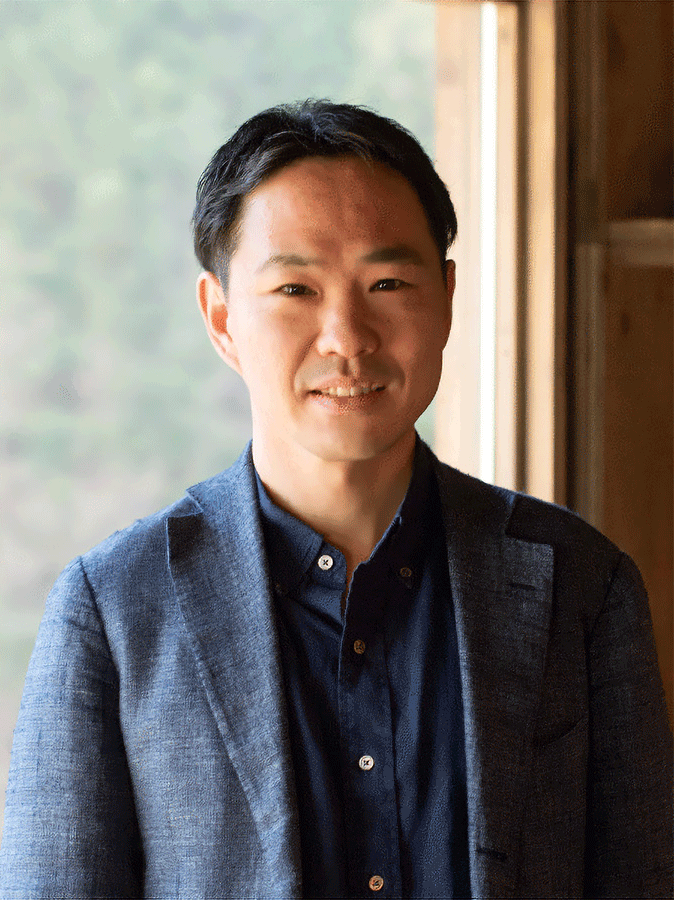島で考える、本と本屋のこと

夜の小豆島にて
小豆島を目指したのは4月上旬。
夜8時半、高松港から島行きの最終フェリーに飛び乗ると、風には冷たさが残る。
薄手のセーターに薄手のジャンパーの装いでは寒さを感じるほどだ。
夜9時半、フェリーが小豆島・土庄(とのしょう)港へ着く。
仕事帰りの勤め人、予備校帰りと覚しき学生たちの列に混じり、僕も島へと降り立った。
小豆島に来たのは、前回紹介した夏葉社・島田さんが主宰する
「町には本屋さんが必要です会議」(通称:町本会)を取材するためだ。
町本会はそれまで、東京のブックカフェを会場に、
本屋のあり方を参加者と一緒に考えるトークイベントを3度開いていたが、
存続の厳しさを指摘されているのはむしろ地方の町の本屋だ。
島田さんもそのことを気にかけていて、4回目にして地方での開催となった。
僕が本屋を開こうとしている勝山(岡山県真庭市)も、いわば本屋の空白地帯。
勝山で店を立ち上げるヒントを求めて、小豆島を訪ねたというわけだ。
島田さんとは、島で落ち合うことになっていた。
すでに島にいる島田さんに連絡すると、「すぐ迎えに行きます」とのこと。
待つことしばし、てっきり島田さんが迎えに来てくれるのかと思いきや、
クルマで僕をピックアップしてくれたのは、
今回の町本会で島田さんと対談するサウダージ・ブックスの淺野卓夫(あさのたかお)さん、
僕がかねてからお会いしたいと思っていたその人だった。
僕が淺野さんのことを知ったのは、2年ほど前のことだ。
お世話になっているミシマ社という出版社のウェブマガジン「ミシマガジン」で、
インタビュー記事を読んだのがきっかけだ。
(思えば、島田さんとのご縁も、「ミシマガジン」での取材だった)
記事で読む淺野さんの経歴は、僕には眩しすぎた。
学生時代に文化人類学を学び、
大学院生のときには、レヴィ=ストロースに憧れてブラジルへ留学する。
レヴィ=ストロースは、ブラジルでのフィールドワークを土台に、
構造人類学という分野を切り開いた20世紀の知の巨人。
『悲しき熱帯』(中公クラシックス)、『野生の思考』(みすず書房)などの著作がある。
怠惰な学生だった僕には、とても手が出せる人ではなかった。
淺野さんは、小学生のころから民俗学者・宮本常一の熱烈なファンでもあった。
きっかけは、祖父から手渡された宮本常一の代表作『忘れられた日本人』(岩波文庫)。
この、辺境の地に生きる老人たちの生きざまを記録した聞き書き集は、
少年だった淺野さんの心をとらえ、
忘れられた庶民の生き方にこそ、生きる喜びや知恵があると感じるようになる。
淺野さんがブラジルへ向かったのは、その思いを確かめ、かたちにするためでもあった。

町本会で本について語る淺野さん。静かな語り口に、本への深い愛情を感じる。
「本のない世界」と「本のある世界」をつなぐ
ブラジルは、20世紀初頭に多くの日本人が移り住んだ「日本の外でもっとも日本人の多い国」。
彼らはいわば、日本の外にいる、もうひとつの「忘れられた日本人」たちだ。
言葉もろくに通じない異国の地で、人生を切り開いた彼らの生きざまが語られることは少ない。
淺野さんは、彼らに会いにブラジルへ行った。
そもそも彼らは、何を求めてブラジルへ旅立ったのか。
子孫たちは、なぜ父母や祖父母の故郷に戻ることなく、かの地に留まったのか。
それを確かめ記録に残すことが、淺野さんのブラジル留学のひとつの目的だった。
宮本常一を読んで育ち、レヴィ=ストロースに憧れた淺野さんは、
自分なりの「忘れられた日本人」を記すために、ブラジルへ向かったのだ。
淺野さんが熱心に話を聞いたのは、ブラジル奥地に住んだ日本人移民の古老たちだ。
そこには、日本人である彼らが解する日本語の本などあるはずもない。
「本のない世界」で、言葉も通じず身よりもない彼らの頼みの綱は、自らの生身の身体だけ。
彼らは、いわば身体という「野生の思考」を武器に人生を切り開いていった。
その生きざまは、淺野さんの心を魅了してやまなかった。
だが、彼らの歩みをアカデミズムの言葉に置き換えることに、
淺野さんはどうしても馴染めなかった。
ブラジルの奥地、「野生の思考」に従い逞しく生きた人たちが奏でる言葉を、
都会の研究室に持ち帰り、データに還元して専門用語で分析する。
そのことに空虚さを感じ、葛藤の末に大学院を辞めて日本に帰国する。2003年のことだ。
けれども、彼らが生きた証をかたちにしたいという思いは、消しがたく心に残る。
ブラジルで会った「忘れられた日本人」の言葉が脳裏にこだまする。
「『本のない世界』に息づく野生の知恵や物語を、
『本のある世界』につなげるような活動をはじめたい」
そういう思いがふつふつと沸き起こり、葉山(神奈川県)でサウダージ・ブックスを立ち上げ、
ブラジルや旅をテーマに本をつくり始める。
その後、2012年に京都を経由し、拠点を小豆島に移すことになる。
瀬戸内の島々に眠る物語を、本というかたちに残したいと思ってのことだった。
小豆島に着いたその晩、淺野さんと島田さん、淺野さんの友人の方々と一緒にご飯を食べる。
入った店は、ちょっとしたショッピングモールのようなところのすぐ近くにあった。
一画には、高松に本店を構え、全国に店舗を持つ宮脇書店もある。
意外に、と言うと怒られるかもしれないけれど、
小豆島は、「島」という言葉から想像していた以上に、ちょっとした町だった。
文藝の島に眠る物語
翌日、淺野さんが小豆島を案内してくれた。
クルマを運転しながら、「小豆島は牛のかたちをしているんですよ」と語る。
牛の頭に相当する部分をグルっと周る途中、西光寺という寺に立ち寄る。
そこには明治から大正時代を生きた自由律俳句の俳人、尾崎放哉(ほうさい)が眠る墓がある。
同時代を生きた種田山頭火とともに「漂白の俳人」と呼ばれる放哉は、
病に侵された身体で小豆島に辿り着き、最晩年をこの寺で過ごして41歳の生涯を閉じた。
寺の敷地内には、放哉が往時を過ごした庵を再建した「尾崎放哉記念館」もある。
展示を見ながら、放哉について何も知らない僕に、淺野さんが解説をしてくれた。
サウダージ・ブックスでは、去年(2013年)の秋、
放哉を主題にした『「一人」のうらに 尾崎放哉の島へ』(西川勝)を刊行している。
放哉は、酒に溺れる質の人だった。
金が手に入ると酒を呑み、金が尽きると誰彼構わず金の無心をする。
それを見かねた放哉の師匠にあたる荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)は、
自ら創刊した自由律俳句の機関誌で、放哉直筆の句の買い手を募り、援助の手を差し伸べる。
放哉は、ときの公務員の月給に相当する金額をいとも簡単に手にするも、
それがまた酒に消える。
それでも放哉の才能には多くの同人たちが惚れ込んでいて、
機関誌というメディアを通じて、少なくない資金が放哉のために融通されていた。
「それって今で言うところのクラウド・ファンディングですよね」
そうこぼすと、「そうですね、ソーシャルですね」と淺野さんは笑って応えてくれた。
驚いたのは、帰ってきて放哉のことを調べていたときのことだ。
井泉水が主宰する機関誌の名は『層雲』という。
まさにクラウド(雲)による資金集めではないか、と目を丸くしたのとあわせて、
「漂白の俳人」たる放哉が、雲によって生かされていたと思うと感慨深い。
流れ行く雲は、ひとつところに留まって生きることのできなかった放哉の人生を連想させる。

西光寺に建てられた放哉の句碑。刻まれている句は、「いれものがない 両手で受ける」。『「一人」のうらに 尾崎放哉の島へ』(西川勝)によれば、ひとり病に冒され、暮らしがままならなくなった放哉が、自らの孤独と不如意を笑う句だという。(筆者撮影)
淺野さんいわく、小豆島は文藝の島だ。
圧倒的に有名なのは壺井栄の『二十四の瞳』(角川文庫)だが、島には放哉がいて、
小林多喜二に並ぶプロレタリア文学の旗手として活躍した小説家の黒島伝治もいる。
黒島伝治の短編を集めた『瀬戸内海のスケッチ 黒島伝治作品集』も、
放哉の本と同じ時期にサウダージ・ブックスから刊行された。
淺野さんは、これからどんな物語を島から掘り起こしていくのだろう。
町本会のイベントまでには時間があり、島の図書館にも足を運ぶ。
そこは、僕がいま住んでいる町(神奈川県茅ヶ崎市)の図書館と
変わらないぐらいの広さがあるように感じた。
一画では、島の個人蔵書家が寄贈したという本が展示されている。
海外文学全集や萩原朔太郎全集がずらっと並ぶさなかに、
ビジネス書や時事問題を扱う本がひょっこり混じり込む。
一室では古本市も開かれ、
小学校の教室の半分ほどのその部屋は、掘り出しものの本を探す人たちで賑わっていた。
島の人たちも本を求めているのだと、
言葉にしてみれば当たり前のことを確認して、何だか少し嬉しくなった。
島の本屋にも立ち寄った。個人経営のさほど大きくない本屋だ。
聞けば、1階を店舗、2階を住居にしているという。
コミックがあって雜誌があって、旅行のガイドブックがあり、Hな本もある。
売れ筋の文庫や新書、単行本も取り扱う。どこでもよく見かける、ごく普通の本屋だ。
島でどんな本と出会えるのかと期待に胸を膨らませていた僕は、
その普通さに肩透かしをくらったような気分になった。
けれども、それは外からやってきた人間のひとりよがりでしかない。
島の本屋は、たまに外からやって来る人のためではなく、
島に住む人たちのためにあるはずなのだ。
地域を支える「苛烈な読書」
町本会は、西光寺からも程近い「Cafe de MeiPAM(メイパム)」で開かれた。
辺り一帯は、古くから「迷路のまち」と呼ばれるほど、通りが入り組んでいる。
島民たちが、中世の海賊行為や南北朝時代の戦乱から身を守るために、
あえて路地を入り組ませ、部外者に容易に侵入させないようにしたのだそうだ。
「MeiPAM」は、「迷路のまち」全体をミュージアムに見立ててアート活動を行い、
その拠点のひとつとして、カフェを運営している。
店内では、サウダージ・ブックスや夏葉社、ミシマ社など、
近年活動を始めた独立系出版社の本の販売も行う。
その名も「迷路のまちの本屋さん」。本記事冒頭の写真が、店の書棚だ。
カフェの2階では、サウダージ・ブックスが事務所を構える。
つまりここは、淺野さんが本をつくって届ける場でもある。
僕が目指す「本屋」も、こんなふうに始まっていくのだろうか――。

「Cafe de MeiPAM」でのイベント当日の様子。参加者からもさまざまな意見が寄せられた。
イベントの参加者は15人ほど。2時間の予定が3時間になるほど話は盛り上がり、
話題は多岐にわたったが、ここではポイントを絞って紹介したい。
淺野さんは、ブラジルで「辺境」と言われる地を訪ね、
自らの手で暮らしをつくる人たちと直に接し、話を聞いてきた。
「本のない世界」に生きる彼らは、自分自身の身体に豊かな物語と哲学を刻印し、
ひとたび聞き手をつかまえると、あたかも自身の肉体が書物であるかのごとく、
生身の肉体に宿る「身体の言葉」で淀みなく話し続ける。
そういう「辺境」の地にも、「書物の言葉」を持つ人たちがいる。
村の知識人と呼ぶべき彼らは、圧倒的な量の本を読み
本から得た知識と関連づけて地域の歴史を語り、地域の行く末を案じる。
彼らが本を読むのは、都市に住む読書家たちとは理由がまるで違う。
都市の読書家が本を読むのは、あくまで自分ひとりのためだ。
知識欲を満たし、仕事の糧にできればそれでいい。
だが、村の知識人たちは、村のため、地域のために本を読む。
勉学の道に進みたくても進めなかった人たちの思いを背負い、
地域を少しでもよくしたいと願って一心に本を読む。
淺野さんは、それを「苛烈な読書」と呼ぶ。
図書館に寄贈した個人蔵書家も、ここ小豆島で「苛烈な読書」をしていたのだろうか。
町の本屋の担い手たち
淺野さんの話を受け、島田さんが『本屋図鑑』(夏葉社)の取材時の体験を語る。
地方の町の本屋、それも個人店は、戦争から帰ってきた人たちが、
町の文化向上のために始めた店であることが多いという。
店主たちの肩には、戦場で命を落とした戦友たちの思いが見え隠れする。

対談の掛け合いで笑みをこぼす淺野さんと島田さん。島田さんは二度目の出家(前回参照)で、以前とは印象がずいぶん変わった。
ここからは僕の推測だが、そういういわば「苛烈な本屋」が、
戦後の出版文化の一翼を担ってきたのだろう。
だが、本にかける彼らの苛烈な思いも、寄る年波にはかなわない。
終戦時に20歳だった人は、もうじき90歳になる。
1990年代後半に22,000店以上あった本屋が、いまでは14,000店強にまで減った。
その理由はさまざまに語られはするけれど、
「苛烈な本屋」の担い手が店から退き、あるいは生涯を全うしつつあることも、
少なからず影響しているのではないだろうか。
いま、「苛烈な本屋」が築いたひとつの時代が終わりを迎えようとしているのだとすれば、
これから、町と本の関係はどうなっていくのだろう。
いまを生きる僕らが、新たに「苛烈な本屋」にならなければ、
町から本が消えてしまいかねない。
ネット書店が津々浦々に本を運んでくれるとしても、
町に住む人が、ふと本と出会う場が失われてしまう。
それは、本にとっても町に暮らす人にとっても、途轍もなく大きな損失なのではないか――。
規模は小さくとも、町に本のある場をつくることが、
いま求められていることなのだとあらためて噛みしめる。
僕が目指しているのは、きっと、僕なりの「苛烈な本屋」をつくることなのだ。
小豆島からの帰り道、高松行きのフェリーのなかで、そんなことを島田さんと話し込む。
「やろうと思った人間がやるしかない」。そう口走ったことをはっきりと覚えている。
思いだけでは生きていけない。それがわからない年齢ではないけれど、
思いがなくては始まらないと、青臭いことを思う。
高松では、宮脇書店の総本店に島田さんと足を運ぶ。
売り場面積およそ2000坪、日本有数の規模を誇る店舗に足を踏み入れると、
フェリーのなかで抱いた思いが、すべて吹き飛びそうになった。
こんな規模は、個人の力ではどうしたってできっこない。
初めて見る本が、山のようにある。まともに勝負したら、どう考えても勝ち目がない。
イベント参加者のひとりが、「島にも大きな本屋がほしい」と切実に語ったことを思い出す。
弱気の虫が思わず顔を出し、打ちのめされそうになりながら、店を後にする。
ふと、島で立ち寄った本屋のことが頭に浮かぶ。
地方に住む人たちは、どういう本屋を求めているのだろう――。
本屋はそれに、どう応えていけばいいのだろう――。
結局、本屋を始め、続けていくには、この素朴な問いに向かい続けるしかないのだろう。
島田さんと、高松で別れを告げる。次に会うのは一週間後、舞台は札幌だ。
北の大地に、放哉ではないけれど、
クラウド・ファンディングで経営危機を乗り越えようとしている本屋がある。
僕はそこで、本屋の厳しい現実を知り、いくつものヒントを手にすることになった。