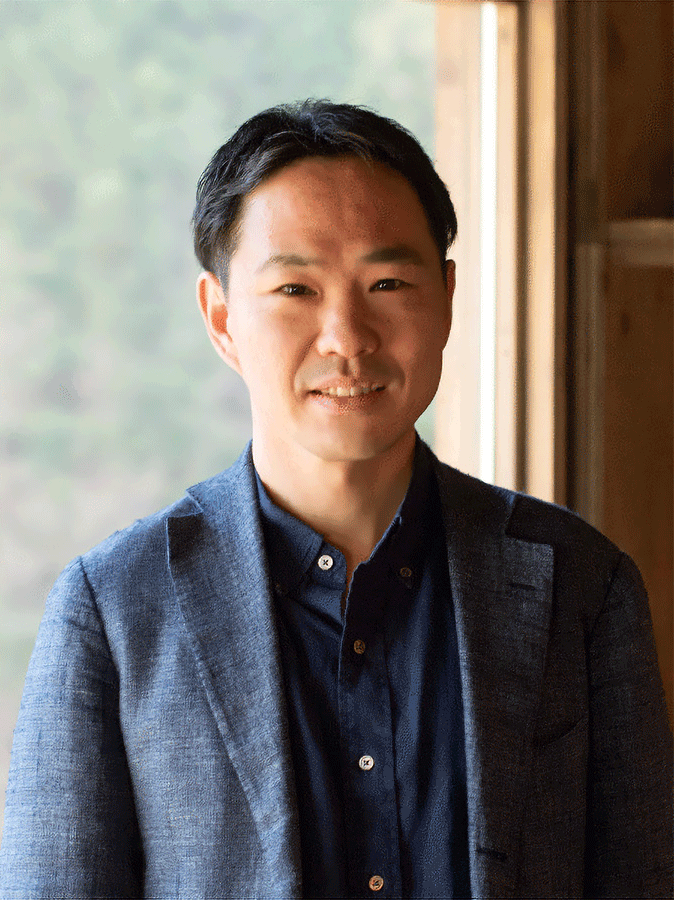瀬戸〈中外陶園〉 働き方改革と新しいデザインで 進化する招き猫

「せともの」のまち愛知県瀬戸市で、招き猫や干支置物など、
縁起置物や季節飾りを製造してきた〈中外陶園〉。
三菱UFJ銀行東支店の伊藤大知さん、堀紗緒理さん、
三菱UFJニコスの中村直幹さんが、その工房や〈招き猫ミュージアム〉、
体験型複合施設〈STUDIO 894〉を見学。
伝統を受け継ぎながら、新しいプロダクトやものづくりの環境に
さまざまな改革を起こしてきた、4代目社長の鈴木康浩さんにお話をうかがいました。
複雑な立体を生み出せる、瀬戸の土
中世から現代まで生産が続く焼きものの産地、六古窯(ろっこよう)。
愛知県瀬戸市を中心に生産される瀬戸焼は、その六古窯のひとつとして
約千年もの歴史を紡いできました。陶磁器全般を指す「せともの」という言葉が、
瀬戸の焼きものに由来していることも、瀬戸焼の歴史の古さや影響力を物語っています。
「焼きものには陶器と磁器がありますが、両方を焼ける産地は全国でも瀬戸くらいです」
と説明するのは、〈中外陶園〉の鈴木康浩社長。
ふたつの大きな違いは、原料。
陶器は「土もの」と呼ばれ、粘土が主な原料なのに対して、
「石もの」の磁器は長石や珪石、粘土を用い、それぞれ製法も異なります。
1952年に創業した中外陶園は、陶器と磁器の両方を製造していますが、
「せともの」としてよく知られる食器ではなく、
招き猫や干支の飾りのような置物に特化したものづくりを行っています。
江戸時代末期に江戸で誕生したといわれる招き猫は、日本ならではの縁起物。
瀬戸で量産されるようになり、いまなお中外陶園の主力アイテムです。
どこか懐かしく愛らしい佇まいの〈瀬戸まねき猫〉や、
〈BEAMS〉とコラボしたオレンジ色のまねき猫、
「シンプル」と「新しさ」を追求し、表情さえも削ぎ落とした〈SETOMANEKI〉など、
ユニークなラインナップを展開しています。

技法やスタイルを受け継ぎ新たにブランド化した〈瀬戸まねき猫〉。

現代的でスタイリッシュなデザインが特徴の〈SETOMANEKI〉。
これらに受け継がれているのが、明治以降にヨーロッパから入ってきた、
石膏型を用いる技法です。

石膏型は「型屋さん」と呼ばれる専門の業者が製造。

こちらの石膏型は、招き猫の手の部分。小さなパーツをくっつけていくことで、複雑な立体表現が可能に。
「たい焼きを想像していただけるとわかりやすいのですが、
たい焼きは小麦粉の生地を型に流すのに対して、
陶磁器の場合は排泥鋳込みといって、泥状にした瀬戸の陶土を石膏の型に流し込みます。
石膏は水を吸う性質があるので、石膏と接している面の土が徐々に固まってきます。
しばらくして内側の固まっていない土を流し出すと、
たい焼きのあんこが入っていない状態、つまり外側だけが残ります。
これをきれいに整え、絵付けを行っていくのです。
石膏型を使って鋳込みをする産地はほかにもありますが、
より複雑な立体を成形できるのが瀬戸の強みといえます」

工程を丁寧に説明してくれた〈中外陶園〉の鈴木康浩社長。
招き猫の腕のように細かいパーツは別途つくり、本体に後づけしていくのですが、
瀬戸の土の特性である粘りの強さがそれを可能に。
こうして瀬戸焼の置物は表現の幅を広げ、
戦後、海外輸出向けの「セトノベルティ」として発展します。
「中外陶園ももともとは貿易の会社で、“中でつくったものを外に出す”
ということで、この社名になった経緯があります。
戦後は、ヨーロッパやアメリカで流行っていた置物づくりの下請け時代が長く続き、
バイヤーに買い叩かれるなどして、当時の職人たちは悔しい思いもしたようです。
だけどそのときに石膏型で精緻なものをつくる技術を
一生懸命勉強させてもらったからこそ、いまに続いているのだと僕は思っています」

日本が豊かになるとともに、セトノベルティの流行は終焉。
ものづくりの対象は国内マーケットへと切り替わっていきますが、
その間、廃業していく製造元も多く、中外陶園のように企業として残っているところは、
5軒あるかないかだそう。
鈴木さんの説明を聞きながら、棚に並ぶ大小さまざまな石膏型を見て、
「ここには何パターンくらいの型があるのでしょう?」と伊藤さんが質問。
「うちではいま、1000アイテム以上つくっているので、本体だけで1000以上。
手などのパーツを含めると2000近い型があるかもしれません」

型から現れたクマに、「かわいい!」と歓声を上げる3人。左から、堀紗緒理さん、中村直幹さん、伊藤大知さん。

型から外して間もない状態。外すタイミングは石膏のサイズによって異なるだけでなく、気温や湿度にも左右されるので、職人の経験と勘がものをいう。
若い世代も飾りたくなる招き猫を
鈴木さんは、家業である中外陶園の4代目ですが、
大学卒業後は大企業で働いていました。
「いつか実家に戻るつもりではいましたが、
東日本大震災や、父が60歳になったのを機に、
自分の人生をあらためて考えるようになりました。
祖父が病気がちだったため、父は若くして代替わりをして苦労したそうで、
小さい頃からその話を聞いていました。それもあって父が元気なうちに、
仕事をしているところを近くで見ておきたいと思ったのです」

2025年の干支「巳(へび)」の置物。〈薬師窯〉というブランドで、招き猫や干支置物などを製造販売してきた。

中外陶園の商品のほか、猫雑貨などを展示販売する〈おもだか屋〉。
こうして2011年、中外陶園に入社し、一社員としてキャリアをスタート。
「商売自体は順調でしたし、父親がやってきたことは
ひとつの正解だろうと思っていました。
半面、自分がやりたいことはちょっと違うのかもしれない、と
さまざまな経験をしながら思うようになりました」
違和感の答えは、同社が運営している〈招き猫ミュージアム〉にありました。
郷土玩具や骨董など、日本中から集められた招き猫のコレクションに心惹かれる一方で、
いまつくっている商品は、あまりにも観光客向けの
お土産になってしまっているように感じたのです。

〈日本招猫倶楽部〉の世話役を務めるご夫婦の個人コレクションを展示する〈招き猫ミュージアム〉。歴史あるものや、地域性に富んだ珍品が勢ぞろい。
「当時の主力商品は、神社・仏閣の門前でお土産品として買うような招き猫でした。
でも自分たちの世代が家に飾るとしたら、
もっとシンプルでクラシカルなデザインのものを好むと思ったんです」
そして鈴木さんが指揮をとって立ち上げたのが、〈瀬戸まねき猫〉というブランド。
本物の猫のようにすらりとしたフォルムや、
猫背を特徴とする「古瀬戸(ふるせと)型招き猫」のスタイルと、
セトノベルティの伝統技法を受け継いでいます。

セトノベルティの伝統技法を用いた瀬戸まねき猫。クラシックだけど、どことなくモダンなところがポイント。
あるとき、展示会で伊勢丹のバイヤーと名刺交換にこぎつけ、
瀬戸まねき猫をアピールしたところ、年末年始の催事の話に。
納期的には到底無理と思えたものの「できます!」と即答し、
現場の協力を得てなんとか実現させたのでした。
「実を言うとこの業界において、
我々つくり手が直接小売と接触するのはご法度とされているんです。
なので僕が自ら伊勢丹の売り場に立つことは、本来はNGなんですけど、
ここは“業界のルールを知らない息子”の立場を利用してしまおうと思いました」
そして伊勢丹新宿店の催事で販売したところ、なんと完売。
さらに催事に立ち寄った、セレクトショップ〈BEAMS〉のバイヤーの目に留まります。
折しも、日本の魅力を発信するショップ
〈BEAMS JAPAN〉のオープンを控えたタイミングで、
この出会いがきっかけとなり、BEAMSカラーのオレンジ色の招き猫が誕生。
BEAMS JAPANではオープン初日に完売し、
以後、予約の時点で売り切れてしまうこともあるほどの人気商品となったのです。

〈BEAMS JAPAN〉の人気商品〈まねき猫〉(左)と、〈まねき犬〉(右)。
「鈴木社長は『とにかくすぐやる』を経営の信条にされていますが、
その姿勢は社長になる以前から一貫しているのですね」(伊藤さん)
「それだけ必死だったのでしょうね。
当時の社長、つまり父も『息子のことを手伝ってくれ』と、
ほかの社員を巻き込んでくれていましたけど、当初は周りも
『別にこんなことをやらなくても、いまの商売で食べていけるのに』
という思いがあったはずです。
けれど少しずつ成果が見えてきたのと同時に、僕の必死さが伝わって、
新商品の開発に一緒に取り組めるような若い世代が徐々に増えていったのです」

働き方改革で、社員のやりがいをものづくりに反映
鈴木さんが父から社長のバトンを渡されたのは2021年、コロナ禍のさなかでした。
生活様式や価値観の変化を感じ取った前社長は、
当時まだ30代だった鈴木さんにこれからの中外陶園を託したのです。
そして社長になった鈴木さんが
「次の30年のために、いまやらなければいけないこと」として着手したのが、
社内の働き方改革でした。
「前職では管理畑の総務人事にいたのですが、
当時はグループ会社も含めると3万人を超える大組織でした。
もちろんうちの規模とは比べものになりませんが、
女性の多い職場というのは共通していましたし、社員をひとつにまとめる考え方は、
そのときの経験がとても役に立っています」

パーツを接着して表面を整えたあと、乾燥させた素地(きじ)に下絵付けを施していく。下絵付けには主に呉須(ごす)という青い顔料を使用。

濃度の異なる呉須を塗り重ねていく筆さばきに見入る3人。
また、若い人が入って経験を積んでも、
結婚や出産のタイミングで辞めていくことが少なくないことを、
常々課題に感じていました。
新たにやりたいことができて会社を辞めるのは、それぞれの人生なのだから致し方ない。
しかしこの仕事にやりがいを感じて、できることなら続けたいけれども、
勤務条件がネックで辞めざるを得ない……。
そうやって後ろ髪を引かれる思いで辞めていく人を減らすことが、
社長の使命であると考えたのです。
「その点、前職の業界は、女性が働きやすい環境づくりでは
時代のトップを走っていたので、それを中小企業なりに噛み砕いて、
育児休業制度などを充実させていきました」

焼成後、赤や金など鮮やかな色を施していく、上絵付け。
また、いわゆる年齢給を廃止し、能力や仕事内容を重視した給与体系に変更。
社員ひとりひとりの声に耳を傾けることで、辞める人が徐々に減るだけでなく、
セカンドキャリアとして中外陶園を選択する人が増えてきたのです。
こうした人事制度改革を通して、開発部門でも製造部門でも
若い風を取り込むことができるように。
入社当初は新規事業の開拓に孤軍奮闘していた鈴木さんでしたが、
若い社員からの発言も増え、社員全員で新しいことにチャレンジできる場へと
変わってきました。
同社で働くために瀬戸へ移住する人も増えています。
兵庫県出身の基すやかさんもそのひとり。
2023年9月に誕生した体験型複合施設〈STUDIO 894(やくし)〉の
オープニングスタッフとして働いています。

2023年にオープンした〈STUDIO 894〉。その昔、中外陶園の敷地内に薬師如来の祠があり、それが薬師窯の名前の由来に。「先代が大切にしてきたこの名前を受け継ぎながら『894(やくし)』と数字に置き換えることで、これからの新しいものづくりと、父への感謝を込めています」(鈴木さん)
「カフェの仕事や絵付け体験のアテンドなど、幅広い仕事を任せてもらっていて、
『どんな仕事をしてるの?』と友だちに聞かれると、
いつも答えに詰まってしまうんです。ひと言では言い表せないところが、
ちょっと誇らしくもあり、やりがいを感じています」(基さん)

STUDIO 894で働くために移住した基すやかさん。「瀬戸のことはもちろん、磁器と陶器の違いもよくわからないところからのスタートでしたが、『いろいろな人と会話をしながら、吸収していけばいいよ』と先輩方に言っていただいて。地元の方や、観光の方、最近は海外から来られる方も多く、刺激のある毎日です」

“心地のよい違和感”を生み出し、新しい文化をつくり続ける
STUDIO 894の計画が持ち上がったのも、やはりコロナ禍。
先代の発案に、鈴木さんは当初「このご時世に新しい施設をつくるなんて」と猛反対。
しかし、社員がふと漏らした「生活必需品ではない置物をつくる仕事は、
この先も残っていくのだろうか」という言葉に、自分のやるべきことが見えたそう。
「バーチャルではなくリアルな場所へ行く意味、
見たり触ったりして実感できる職人の手仕事のすごみを
伝えていく必要性を感じたのです。
僕らがやってきたことを体験してもらえて、しかも瀬戸に住む人たちが
遊びに来た人を連れて行きたくなるような場所にしたいと思いました」


絵付け体験は、下絵の具で絵付けした素地を焼成する「磁器 絵付け体験」と、その日のうちに持ち帰ることのできる「陶器 ぬり絵体験」の2種類。職人から学べるより本格的なプログラムや、親子で楽しめるイベントも定期的に開催。
STUDIO 894は、カフェ、アートギャラリー、絵付け体験の機能を持つ、
スタイリッシュな空間。おいしいコーヒーを飲むだけでももちろんいいし、
同じスペースで絵付けを楽しんでいる人もいて、興味をそそられます。
ギャラリーでは、さまざまなジャンルのアーティストやプロジェクトの企画展が開催され、
中外陶園とコラボレーションした作品の展示販売も行われています。

STUDIO 894で開催されていた、人気画家ミロコマチコさんの展示。原画のほか、瀬戸焼のタイルに描いた作品も。

中外陶園とコラボした作品。通常はスケッチなど平面で作品のイメージを伝えるところを、ミロコさんは紙粘土で表現。「そのときつくってくださった原型の、ぼこぼことした手の跡がおもしろいと思い、石膏型で忠実に再現しています」(鈴木さん)
「新しい商品を生み出したり、いろいろな作家さんとコラボレーションされたりなど、
すばらしい行動力だと思います。その原動力といいますか、
新しいことをする際はどんなことを大事にしているのでしょう」(堀さん)
「BEAMSさんとのコラボがいい例ですが、
これまで僕らの商品と接点のなかったようなファッション好きの人が、
BEAMSさんを介して工芸に興味を持って、生活のなかに取り入れてくれる。
僕はそれを“心地のよい違和感”と呼んでいます。
本来、交わることがなかったものを僕たちのセンスでミックスして、
新しい文化にする努力を続けていきたいし、
それが中外陶園のこれからの生きる道だと、社員のみんなと共有しています。
コーヒースタンドやギャラリーだって、
普通に考えたら陶器屋がやることではないのでしょうが、
絵付けとどうミックスさせて、心地よいものにできるか。
その違和感を楽しめるような企業文化をつくっていきたいのです」

応援の意味を込め、カフェでは瀬戸の作家がつくったコーヒーカップを使用。コーヒーは東京・三軒茶屋のスペシャルティコーヒー〈OBSCURA COFFEE ROASTERS〉の豆。
ギャラリーで展示販売されるアーティストとのコラボレーション作品を生み出す過程は、
職人にとって刺激の連続。
工房長の鬼頭智さんも、「10年ほど窯を担当していますが、
いままで扱ったことのないような形だったりするので、毎回神経を使います」
と話します。

主に施釉と焼成を担当する、工房長の鬼頭智さん。「これだけ多くのアイテムを扱っていて、工夫されていることはありますか?」(伊藤さん)「過去に製造したアイテムは、注意点をノートに記録しているので、それをよく見返しています」(鬼頭さん)
「名だたる作家さんと一緒にものづくりをして、しかも作家さんに
『いい仕事をしてくれてありがとう』と言ってもらえることが、
現場の人たちには大きな自信になっているようです。職人魂に火がついたり、
喜んでいる様子を見ることができるだけでも、やってよかったと思っています」

釉薬をかけて焼成するガス窯。約1300℃で20時間ほどかけて本焼きを行う。
多彩な瀬戸焼のコラボレーション〈SETOMANEKI〉
鈴木さんは今年40歳。若くして社長を継いだからこそ、
「勢いでいろんなことにチャレンジできた」とも言います。
「大きな決断をすることに、不安ももちろんあると思うのですが、
どうやって乗り越えてきたのでしょう」(中村さん)
「2年前に会社が70周年を迎えたのですが、
次の人にバトンを渡せるのは僕しかいないので、不安よりも使命感が大きかったですね。
ほかの会社が廃業していくなか、中外陶園が残ってこられたのは、
やっぱり時代に合わせてアップデートしてきたからなのでしょう。
大切にしなければいけない技法や伝統は変えずに、表現をアップデートしていけば、
まだまだやれることはあるはずです」

本物の猫に近いフォルムが特徴的な、瀬戸型の招き猫。
その言葉を体現している、もうひとつのブランドが〈SETOMANEKI〉。
凹凸の少ないシンプルなフォルムですが、
耳や手の形から招き猫であることが一見してわかります。
「70年間、手を替え品を替え招き猫をつくってきた僕たちが、
どこまで削ぎ落とせるかに挑戦してみました。
シンプルが好まれる時代や風潮だからこそ、
アップデートを重ねてきた僕たちが挑戦することに意味があると思ったのです。
だから、“猫”という名前さえも削ぎ落としているんです」

デザイナーと何度も話し合いを重ね、「削ぎ落とす」ことにこだわったSETOMANEKI。コンセプトは「NEW MANEKINAKO」。
SETOMANEKIは新しい招き猫の形であると同時に、
「瀬戸に招く」という思いを込め、新しい瀬戸のかたちもイメージしているそう。
「中外陶園は形をつくるのは得意ですが、釉薬の種類はそれほど多く持っていません。
なのでSETOMANEKIでは、中外陶園が成形を担当して、
瀬戸のいろいろな工房さん、作家さんに得意とする釉薬をかけてもらい、
10種類のカラーバリエーションにしています。
瀬戸焼はこれほど多種多様なことを知ってもらい、
瀬戸を訪れるきっかけになってほしい、という願いを込めているんです」

鈴木さんがUターンした頃、あるいはコロナ禍と比べると、
瀬戸のまちにはSTUDIO 894に続くコーヒースタンドができたり、
若い人が新しい店を始めたりなど、活気が生まれてきているそう。
「僕らが挑戦し続けることで、業種は関係なく、
新たにチャレンジしやすい雰囲気が育まれていくと思うのです。
そうやって挑戦する人たちと一緒にお仕事をさせてもらうことで、
瀬戸でがんばりたいと思う人がもっと増えていけばいいですよね」

「女性の方、若い方が多く、みなさん真剣に生き生きと働いていらっしゃる姿が印象的で、
新しいことに積極的に取り組む会社の雰囲気や、
瀬戸の魅力が伝わってきました」(堀さん)
瀬戸の招き猫が、次はどんな“心地のよい違和感”を引き寄せてくれるのか、楽しみです。

information

中外陶園
web:中外陶園
information
STUDIO 894
住所:愛知県瀬戸市薬師町1番地
TEL:0561-84-0894
営業時間:10:00~17:00(絵付け体験最終受付15:30、コーヒースタンド16:30L.O.)
定休日:火曜(祝日の場合は営業)、年末年始
web:STUDIO 894
writer profile
photographer profile
https://hiromikurokawa.com