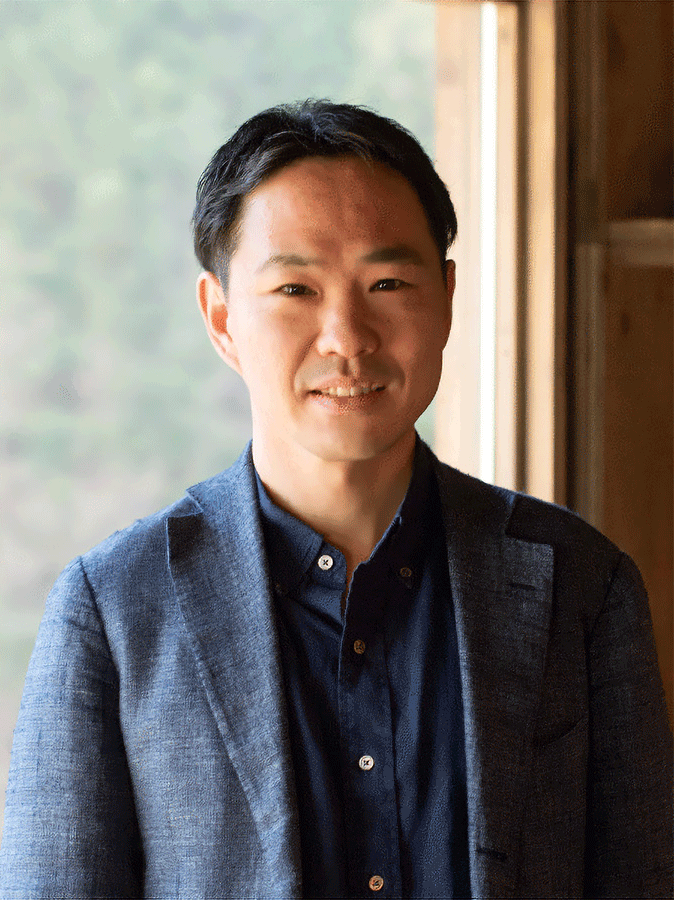和倉温泉「多田屋」6代目 多田健太郎さん

さまざまな経験を経て、自分の道へ。
豊かな自然と独自の文化が残り、北陸新幹線の開通で、
いまさらなる注目を集める能登半島。
その能登半島の中心部にある和倉温泉の、
七尾湾を一望する高台に建つ旅館が、多田屋だ。
それほど大きな宿ではないが、明治18年から続く歴史ある旅館で、
落ち着いたあたたかい雰囲気が漂う。
「長旅でお疲れではないですか」と気さくな笑顔で迎えてくれたのは、
多田屋6代目の若旦那、多田健太郎さん。
能登で生まれ育った多田さんは、
いずれ多田屋を継ぐということは漠然と頭にありながらも、
自分のやりたいことを見つけたいという思いもあり、東京の大学に進学。
卒業後はアメリカに留学し、短大でインテリアなどを学んだ。
帰国後もすぐには地元に戻らず、東京のIT会社に就職。
1年勤めたあと多田屋に入社するが、いきなり大阪に転勤。
旅館案内所で営業を担当するためだ。少し遠回りをしているようにも思えるが、
それもいろいろな経験ができてよかったと多田さんは笑う。
「アメリカでは最初、言葉が通じなくて挫折を味わったり、
東京の会社で働いていたときは毎日終電で帰るような生活で、落ち込んだりもしました。
自分の核となるものがわからないまま転がっていった感じでしたね」
それでもいつか能登に戻るということは心に決めていた。
そのタイミングだと思った29歳のとき――それは結婚のタイミングとも重なったそうだが、
能登に戻ったのだという。
「いつか僕が継ぐのであれば、旅館を僕流にしていかないといけない。
これ以上、父のやり方でいくと、軌道修正が大変だと思ったんです」

七尾湾に面した抜群のロケーション。このオーシャンビューが多田屋の自慢。
どんな業界でもそうだが、特に伝統ある家業の場合、世代交代は一筋縄ではない。
守っていくことや受け継いでいくことだけでなく、
時代の移り変わりやニーズを的確に読み取り、新しいことにもチャレンジしていく。
そうでなければ、廃れてしまうことにもなりかねない。
「もちろん息子として父のことは好きですし尊敬していますが、
一緒に仕事をできるかというとなかなか難しい。
父親だけど社長という関係も、その距離感をつかむまでが大変でした」
社長である父の世代の価値観と、自分の世代の価値観ではズレがある。
これから若い世代の人たちにも多く来てもらうためには、
多田さんは自分のやり方を少しずつとり入れていかなくてはいけないと感じたのだ。
能登に戻る少し前、新しく露天風呂つきの客室をつくる改装工事をすることになり、
そのときに、自分にもやらせてほしいと掛け合い、8室のうち、
半分の4室を社長が、あとの4室を多田さんが手がけることになった。
「一緒につくるのではなくて、ライバルみたいな感じですよね(笑)。
ひと部屋ひと部屋コンセプトを考えて、
こういう内装にしたいと業者の人たちに相談しましたが、
なかなかわかってもらえなくて大変でした」
ただゴージャスなのではなく、シンプルで洗練されたしつらえの部屋。
できあがってみると、多田さんが手がけた部屋は30~40代のお客さんに好評で、
結果として多田屋の客層を広げることにつながった。
「お客さんに喜んでもらえるものができたという、ちょっとした自信になりました。
父も、それで少し認めてくれたのではないかと思います」

多田さんが改装を手がけた客室。竹をモチーフにし、随所に意匠が凝らされている。

床材にも竹を使用。自然の素材に触れることで気持ちがやわらぐ。

部屋についている露天風呂から七尾湾が見渡せる。このほかにも和洋さまざまなテイストのお部屋が。
さらに、旅館を本格的に多田さんが牽引していくことになった
大きなきっかけのひとつが、料理長の交代。
旅館のおもてなしの大きな要素である料理は、多田さんが特に重要視していた点。
これからの時代を考えたときに、料理長の交代は必然だったという。
当然、父である社長は助けてくれない。
自分で新しい料理長を探してくると言ったものの、
まだ人脈がそれほどあるわけでもなかった多田さんは、
必死で自分の考えや感覚を共有できる料理人を探し回り、
ついに金沢の料亭で腕を振るっていた、自分と同い年の料理人を招聘することができた。
新料理長の就任後はみごとに売り上げが上がり、
その頃から社長も多田さんに仕事を任せてくれるようになっていったそうだ。
「父に反対されても、自分の考えはきちんと言うし、
ちゃんと結果を出して初めて認めてもらえる。
ある程度社長をたてながら、自分のやり方を実践していく。
いまは無事、世代交代は終わっています」
まず、能登のいいところを伝えたい。
多田さんの大きな功績のひとつに、インターネットでの発信がある。
社長は手のつけられなかった分野だが、IT企業勤務の経験もある多田さんは、
旅館のイメージを伝え、多くの人に興味を持ってもらうのに、
インターネットの重要性は充分すぎるほどわかっていた。
その多田さんが多田屋のホームページを制作するにあたって心がけたのは、
能登のよさをきちんと伝えるということ。
「東京や大阪、さらにアメリカと、各地を転々として帰ってきて感じたのは、
能登は本当にいいところだということ。
だから、能登ってこんなにいいところなんだよ、ということをまず伝えて、
その能登にある多田屋、ということをきちんと表現したいと思いました」
その多田さんの強い思いをウェブサイト上に表現したのが、
東京のデザインチーム「spfdesign」。
アートディレクターの鎌田貴史さんをはじめ、
カメラマン、ライター、イラストレーターのチームが
何度も能登を訪れてホームページを制作。
彼らもすっかり能登に魅了され、仕事というよりもプロジェクトとして
楽しんでつくってくれているのが伝わってきたという。
その後、1度リニューアルを経て現在のホームページとなっているが、
それも彼らの手によるもの。完成後も、個人的に能登に遊びに来てくれたりする
メンバーもいるのがうれしいと多田さん。
さらに、そのspfdesignのメンバーたちと制作したのが
「のとつづり」というウェブサイト。
能登の美しい風景や能登に暮らす人などを紹介し、
四季折々の能登の魅力を発信している。
多田さんがこんなところはどうかと提案し、
最終的には制作チームが取材する場所を決め、1年間かけて取材した。
「住んでいる人から見ていいなと思うところと、
お客さんとして来る人が訪れてみたいと思うポイントは違うと思っていたので、
押しつけずに紹介だけして、取材ポイントを選んでもらいました。
自分も一緒に取材に同行しましたが、新しい発見があったり、
人との対談はすごく刺激になったり、とても勉強になりました」

ガイドブックには載らないような視点で能登の“いま”を伝える「のとつづり」。多田さんも各地を取材。
たとえば、ブリの定置網漁の取材では、
漁師たちの仕事を初めて目の当たりにして感動したという。
「朝早く寒いなか、みんな無口なんですが呼吸を合わせて、
自分の持ち場についてテキパキと作業していく。その連携がすごい。
こういう思いをしてブリをとってくれているんだということがわかると、
旅館で料理して出すときに思いが違ってきます。
ただ話を聞くのと体験するのとでは全然違うと思いました。
同級生がその船に乗っていたんですが、友だちを見る目が変わりましたね(笑)。
こいつすごいやつだと、かっこいいと思いました」
自ら感じた能登の魅力を伝えていきたいと話す多田さん。
「能登発信基地、というのが旅館のひとつの役目だと思っています。
旅館で出すお料理は、こんなにおいしいものがあるよと
地域の食を発信することができる。将来的には、器やコーヒーカップなども、
地元の作家さんのものを使うことができないかと考えています。
いま能登には都市部から移住してこられたアーティストの方も増えていますが、
そういう人たちの発表の場ともなっていけたら」
これからも多田屋と多田さんの挑戦は続く。
「田舎の人たちは自分たちがいいものを持っているとなかなか言わない。
はたから“これはいいものだ”と言われて初めて、“そうか、いいものなんだ”と気づく。
そういうものを大切にしていきたいです。
大事なものがなくなってしまう前に、これはいいものだと伝えて広めていきたい。
そして、いいものがたくさんある能登で旅館をやっている多田屋です、
と言いたいですね」

多田屋をともに切り盛りする女将(奥様)とフロントにて。
profile

KENTARO TADA
多田健太郎
1976年石川県生まれ。多田屋6代目。立教大学経済学部経営学科卒業後、アメリカ留学、東京での就職を経て、2006年に能登に戻り、能登の魅力を伝える活動をしながら代々続く旅館「多田屋」を運営。趣味はカメラと自転車。
information
多田屋