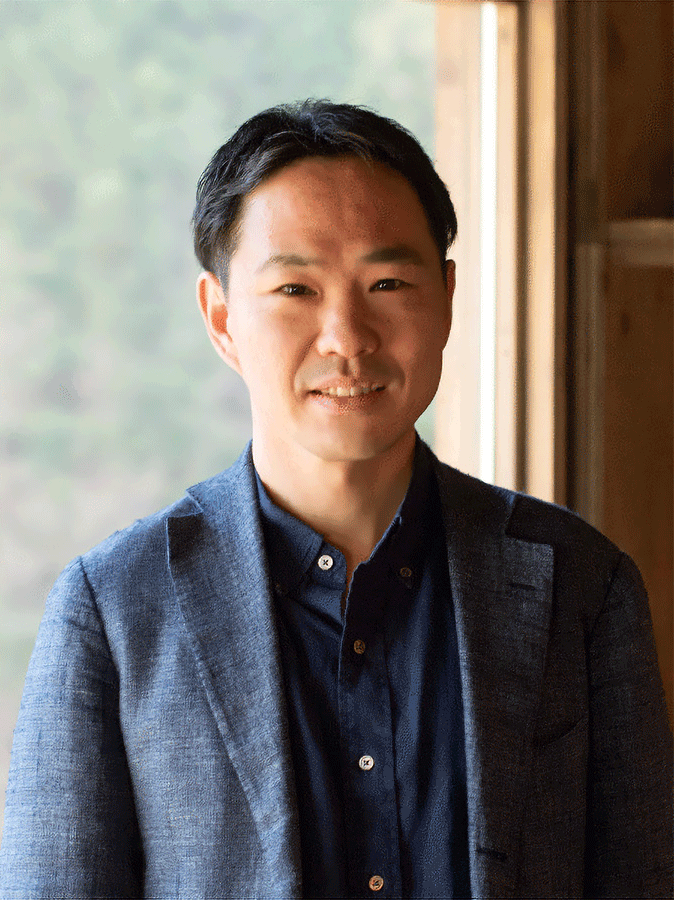太古の地形をお菓子でめぐる「ジオガシ旅行団」

海底火山で生まれた、伊豆半島。
濃い緑が広がり、山と海の香りが入り交じる、伊豆半島。
歴史的な名所である下田をはじめ、山や海を求めて毎年多くの観光客が訪れる。
ところが、この半島が太古の昔に海底火山として生まれ、
珍しい地形をいくつも擁する地層の宝庫であることは、あまり知られていない。
壮大な地形に出会い心を動かされたのが、「ジオガシ旅行団」のふたり。
この風景を他の人にも伝えたい。
そう考えて始めたのが、なんと、この地形そっくりのお菓子をつくることだった。
その精巧さには目を見張るものがある。

伊豆急下田駅から車で15分ほどの爪木崎の海岸で見られる。伊豆半島が海底火山だった時代に固まった溶岩。
「伊豆半島は、約2000万年前に、はるか南の深海で誕生した海底火山群だったんです。
少しずつ北上して、ついに本州に激突し、60万年前に今のかたちの半島となりました。
その後も火山活動が繰り返されて、現在の地形ができていますが、
今も年に4センチは北上し続けているんです」
そう教えてくれたのは、寺島春菜さん。
地形を前にしたら、静かにその地に刻まれた年月に思いを馳せるといい。
見えない時間を想像しようとする者に、大地はしっかりと応えてくれる。
今、日本には33のジオパークがあり、
伊豆半島も、2012年に日本ジオパークとして認定された。
浸食の少ない、比較的もとのかたちをそのまま残す海底火山として、地質学者の評価も高い。

下田市須崎の恵比寿島で見られる、海底に降り積もった火山灰が織りなす地層美。

伊豆市爪木崎。亀甲状にひび割れた溶岩は「柱状節理」と呼ばれる。
3年ほど前、知人に誘われて気軽にジオガイドの認定を受けた春菜さんは、
伊豆半島のもつ地形の魅力に、惹かれた。
春菜さんの友人である鈴木美智子さんも、初めて見た風景に、衝撃を受ける。
「これまで普通に暮らしていた土地なのに、
何千万年という、気の遠くなるような時間がこの地形に凝縮されていることを知って、
周りの風景が違って見えるようになりました。
しかもいろんな種類の地形があって、それぞれに成り立ちが違うんです」(美智子さん)
この面白さを広く伝えたい、とふたりは考えるようになる。
“ジオ”といえば、どうしても地質学の堅いイメージがつきまとう。
もっと身近に感じられて、多くの人に愛されるようなかたちで表現できないか。
そうして生まれたのが、地形をお菓子にした「ジオ菓子」だ。
カフェを運営していた春菜さんがお菓子づくりを担当し、
当時、東京から伊豆へ戻り、デザインの仕事を始めていた美智子さんが
パッケージデザインやPRなどプロデュースを行う。
ふたりでツアーを企画したり、ジオガイドもこなす。
「ジオガシ旅行団」の誕生だった。

左が鈴木美智子さん、右が寺島春菜さん。(Photo: Kosuke Harada)
地形にそっくり。でも、れっきとしたお菓子です。
まずふたりは、ジオ菓子を、実物の地形に似せることに徹底的にこだわった。
美智子さんいわく、目指すは「そこまでするか! と笑ってもらえるほどのリアリティ」
春菜さんのお父さんはプロの陶芸家。
彼女は受け継いだ才能を、余すことなくお菓子づくりに注ぎこんだ。
「ひとつのお菓子を開発する時は、
どうやったら実物に近くなるか、実験のような試行錯誤が続きます。
素材を泡立てたり、焼いたり、揚げてみたり。
見た目だけでなく、味もよくなければいけないので、
普通のお菓子づくりでは考えられないようなところに、
手をかけています」(春菜さん)

(左)伊豆市下白岩の有孔虫化石。有孔虫は、暖かい海にいる原生生物のことで、この化石は1100万年前のものといわれている。
(右)有孔虫化石ヌガー。有孔虫の形をしたレンズ豆や、地元のお米のパフを使用。

(左)伊豆市茅野の鉢窪山。1万7000年前に噴火してスコリアの丘となった。スコリアとは、マグマに含まれるガスが泡立つことでできた岩石。
(右)鉢窪山スコリア焼きチョコ。茅野産の黒米を使っているため泡立てることはできず、揚げてクッキー状に。

(左)南伊豆町弓ケ浜。長さ1200メートルにわたって美しい弧を描く白砂の浜は、海底火山灰層の砂粒でできたもの。(Photo: 伊豆半島ジオパーク推進協議会)
(右)さしクッキー。南伊豆のアロエを使っている。
さらにふたりが大切にしたのが、地形と同じ土地の産物を使うこと。
爪木崎のジオ「桂状節理」を模したココアクッキーには爪木崎産のヒジキ、
弓ケ浜の「さしクッキー」には南伊豆のアロエ、
三島の縄状溶岩クッキーは、三島で有名なメークインを使用。
なぜその地でその産物が育つようになったのか、もとを辿れば
地形の成り立ちと深い関係を持っていることもわかってくる。
「例えば、箱根からきた火山灰によってできた肥沃な土壌があるから
この土地は土がよくて根菜類がよく育つ、など地形を入り口にたどっていくと、
その土地の歴史、文化、産業、宗教観にまでつながります。
地形を楽しみながら保全することが大切だろうと改めて感じます」(美智子さん)

南伊豆町に構える工房にて。お菓子にしたいジオサイトを選び、素材を決める。ふたりで考えたお菓子を春菜さんがかたちにする。
ジオガシ旅行団と行く、“お菓子なツアー”
“旅行団”と称するだけあって、活動はお菓子づくりにとどまらない。
ジオ菓子のパッケージには、必ずモデルとした地形の位置を記した地図が入っていて、
その場所を訪れることができるようになっている。
さらには、ふたりともジオガイドの認定を取得し、
自分たちでガイドを務めるジオツアーも行う。
伊豆半島がかつては海底火山だったこと、
地底で固まった溶岩が美しい幾何学模様をつくっていること、
1100万年前の有孔虫の化石が見られること……などなど、
壮大なジオサイトを訪れ、地形の歴史を話す。

お菓子をもって各ジオサイトをめぐる「ジオガシ旅行団とめぐる南伊豆のお菓子な風景ツアー」には30人ほどが参加した。

バスのなかで、ジオサイトの説明をするふたり。

海底火山だった頃にできた地形に立ち、参加者は興味津々の様子。

下田須崎の恵比寿島。地形を見て面白さを直接感じてもらうのがツアーの目的。
バスで周るほか、自転車やカヤックでのツアーもある。
「海の上からしか見えない地形など、
これまでは、漁師さんしか見たことがない風景だったんですよね。
海沿いに暮らす人たちに聞いても、知らないという方が多い。
この価値にもっと地元の人たちが気付いたらいいなと思います」(美智子さん)

自転車でのツアーの様子。
お菓子をきっかけに。
ふたりのユニークな活動が話題をよび、
最近では月に製作するお菓子の数も、ひと月に1300〜1600個と増えた。
地元の道の駅や、土産物の店などで扱われるようになり、
東京では渋谷ヒカリエの「d47 design travel store」などでも販売されている。
「伊豆は昔から観光業が盛んな土地ですが、
人工的なもので人を呼ぶ従来の観光は、あまり好きになれなかったんです。
でも、ジオの存在が広まることで、
この土地本来の良さを自信をもってアピールできます」(春菜さん)
ふたりとも伊豆の生まれ育ちで、土地への思いは深い。
「伊豆のむせかえるような自然と、南伊豆のゆるやかな時間の流れが好きで。
東京で働いている間も、ずっといつかは伊豆に戻りたいと考えていました。
ここ、南伊豆でも過疎化は進んでいます。
お菓子は小さな糸口にすぎないけれど、
ジオ菓子をきっかけに伊豆に行ってみたいと思ってもらえたら嬉しい」(美智子さん)

ガイドを終えたふたり。伊豆最古の神社、白浜神社を背景に。
実際に東京でお菓子を買って興味をもち、
「ジオサイト全部まわりました!」と連絡をしてくれるお客さんもいるのだそう。
少しずつ広がりを見せている、ジオガシ旅行団のユニークな取り組み。
これからも、伊豆の新しい楽しみを教えてくれるだろう。