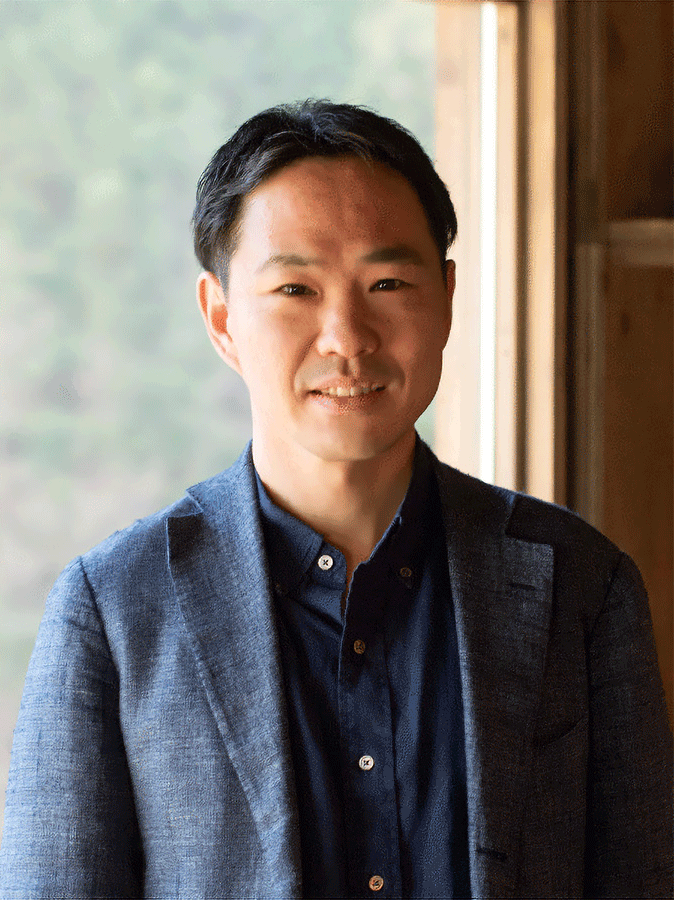木のノート〈Shiki Bun〉 に どんな言葉を綴りますか? 伊那の森と暮らしをつなぐ 〈やまとわ〉の活動

「変化することが美しい」
「経木」の実物を見たことのある人は、そう多くないかもしれない。
木を薄く平らに削ってつくる経木は、
その名の通り、かつてはお経を書き記す媒体だったという。
以降は特に食の場面で使われた。おにぎりを包んだり、落し蓋にしたり、
揚げ物の下に敷いたり、まな板代わりにして肉や魚を切ったり……。
「経木は、ビニール製品ができる50年くらい前までは、
食べ物を包んだりするメジャーな包装資材でした。ただ、現代は食生活が違う。
だから時代にあった使い方を提案しているんです」と語るのは、
長野県伊那市に事務所を構える〈株式会社やまとわ〉の代表取締役・中村博さん。
同社は伊那のアカマツを素材にした現代版の経木〈信州経木Shiki〉を製造販売している。

〈株式会社やまとわ〉の代表取締役・中村博さん。

〈信州経木Shiki〉の乾燥工程。生木を伐ってから3週間以内に削り、1日〜1日半かけて乾燥させる。

〈信州経木Shiki〉。右から2番目の Lサイズは長さ48センチと大きいが、これは素材となるアカマツの節から節の長さに応じてつくられた結果だ。
「例えば経木でパンを包むと、アカマツの調湿作用で焼き立てのパンの汗を吸収したり、
冷凍保存してもカピカピにならなかったり。
県内外のパン屋さんのユーザーが増えています」
そのほかにも納豆の包装、スーパーの調理用生魚のドリップの吸収シート、
さらに照明やビールのラベルの資材など、用途は多彩だ。
極めつけは〈信州経木Shiki〉をもとにつくられた木のノート〈Shiki Bun〉だろう。
同じ伊那市にある美篶堂が手製本で綴じ、
表紙と1ページ目には同県松本市の藤原印刷が印刷を施した。
添加物などを一切使用していないため日焼けや反りなど経年変化していくが、
「むしろ変化するのが美しい」という嗜好のユーザーに爆発的に受け、
制作中に予約で完売することも多いという。

〈信州経木Shiki〉でつくられた木のノート〈Shiki bun〉。美篶堂の手製本で綴じられている。

「親子の交換日記とか、大切な人に言葉を書いて贈る人が多い。使われ方が美しいんですよ」と中村さんは笑う。
「僕らも手作業で削るし、美篶堂さんも手製本だから、
大量生産して流通に乗せるような商品ではないかもしれない。
でもこれらの商品、特に〈信州経木Shiki〉は、僕らの考える、
もっとも本質的な意味をユーザーさんの食卓にまで届けてくれるんです」
必要なのは、適切に消費すること
「本質的な意味」とは何か。
中村さんは「地域の木を消費してほしい」のだと言う。
環境保全というと、消費よりも保護のイメージを抱くのが一般的だろうが、
中村さんはむしろ
「枯渇しない程度に資源を使うことで、荒廃した森の健全化につながる。
それが生態系のバランスを保つために必要なんです」と訴える。

「(気候変動で)生態系のバランスが崩れるスピードがすごく早くて、焦っちゃうこともあります。だけど、やれることをやるしかない」と中村さんは語る。
そう考えるに至ったきっかけは2002年、当初は木工職人を志した中村さんが、
地元で開かれたきこりの養成講座で森林について学んだことだった。
地球上の森林面積は全体の1割に過ぎず、かつ急速に減っていること。
しかもその理由の約75%を、森林火災や違法伐採、焼畑農業など、人的要因が占めること。
一方、日本は国土の約7割が森林だが、
戦後復興期に家を建てたり土留めをつくったりしたことで山の木を使い切り、
次世代のためにとたくさん植樹したものの、高度成長期になって木の需要が減り、
間伐や枝打ちなど木の保育がされない森ばかりになってしまった。

〈信州経木Shiki〉の制作工程。和歌山の職人が使っていた50年前の専用の機械で削る。削っても平らにすることは難しく、技術を習得するのに「1年半以上かかった」と中村さんは言う。
「僕はそれまで材木屋さんに
『海外産のブラックウォールナットをください』と注文していたんです。
だけどそれでは海外の森林減少や、日本の山の荒廃化に加担していることになると気づいて。
だけどふとまわりを見たら、伊那には木しかない(笑)。
だったら、すぐ近くにたくさんある地域の木を使おうと」
それ以来、地域の木材を使うワークショップなどの活動を個人で続けた。
だが社会を変えるには「このやり方では無理だ」と限界を感じ、
2016年に〈やまとわ〉を設立。
社名は「山・杜・環」にちなみ、
「山と森の資源を循環させる社会をつくる」というビジョンを表現した。

自社で木を伐る際も「『この木のあの部分は経木に』『根元の部分は違うプロダクトに使おう』と、選んで使っている」という。
いまでは100%、地元伊那産の木材だけを使用するに至った。
さらに、もともと自社で木を伐採していたが、
製品の生産量が上がったため賄いきれなくなり、地域の森林組合や市場など、
地域のネットワークを使って木材を購入しているという。
どうせ枯れてしまうなら……
長野県の樹種分布を見ると、北信(北部)はスギ、東信(東部)の上田市はカラマツ、
中信(中部)から南信(南部)の上伊那はアカマツ、
さらに南に行き下伊那はスギやヒノキ、木曽はヒノキやカラマツが豊富だ。
「『日本はスギしかない』ってよく言われますけど、
伊那はスギが1%しかなく、マツが65%を占めるめずらしい場所なんです」
松竹梅に象徴される「おめでたい木」のひとつであり、
調湿や抗菌作用も持つマツと、伊那の人々は古くから共存してきたのだ。

地元で伐採・製材してもらった木材を買い付けて家具をつくっている工程。
ところがいま、国内のマツが〈松枯れ病(マツ材線虫病)〉という病気で激減している。
特に2015年以降は、長野県で被害が拡大しているのだ。
松枯れ病は、海外からの輸入材に付着したセンチュウの一種によって上陸し、
マツノマダラカミキリに媒介して日本に広まったと考えられている。
「マツノマダラカミキリはあたたかい土地でしか暮らせないんですが、
地球温暖化によって標高の高い土地にも進出してきたんです。
それでいま、長野県が被害に遭っています。
特に松本はひどい被害地で、アカマツが大量に枯れています。
現在の最前線は標高850メートル。
伊那はちょうどその高さにあたります。すぐそこまで来ているんです」

家具の仕上げ工程。カンナで精巧に削っていく。
生活の恵みを与えてくれた森という豊かな自然資源から私たちの暮らしが遠ざかり、
病気にかかって枯れつつあるアカマツは
「税金を使って伐られて捨てられるだけ」。
中村さんが考えた最善策は、枯れる前に木を使って、新しい木を育て、
森全体を循環させることだった。これが中村さんの言う「消費」の意味だ。
「地球という生命の大きな営みとして見れば、
いま滅びる順番が来ているだけだと僕は思う。
人間だって年老いたら死んで、新しい命に変わっていくという循環がずっと続いてきた。
植物も同じです。
命が循環するのなら、収穫期の木を適切に使い、新しい木を育む必要がある」
木に寄り添って生きる技術
かつての暮らしと同じように日常生活のなかで木を使うために、
中村さんたちはさまざまなプロダクトをつくってきた。
家具、住宅、薪ストーブなどに加え、
冒頭の経木や木のノートが開発されたのもこの理由だ。

〈やまとわ〉の家具ラインのひとつ、〈DONGURI FURNITURE〉の製品。
すべての製品は木の種類やねじれなどの性質を考慮したうえで、
「木の特性に寄り添った」加工を追求している。
また加工に適さない木材は社屋の暖房ボイラーの燃料にしたり、炭にして畑に撒いたり、
経木の削りかすは地域の酪農家が引き取って牛舎の牛床や牛糞の堆肥化に使ったりと、
ムダを出さない。
さらに冬場に自分たちで森の木を切る=林業だけでなく、
夏は無農薬・無化学肥料の循環型農業を行い、食材の加工にも取り組む。
「森をつくる暮らしをつくる」とは〈やまとわ〉の理念だが、
まさに生活全般を視野に入れた多角経営は「生きていくために必要な要素」なのだと、
中村さんは言う。
「僕たちはエコシステムの一部として生きている。
山で木を切り、使ったり、ご飯を食べるために土を触ったり、植物を育てたり……
そういう、生きていくために必要な技術や技能のある人が
少なくなっていると思うんです。
だからそういう人を育てることはすごく大事なんです」

オフィス内壁の一部にもアカマツが使われている。
ただ、「だから自給自足の生活をすればいい」というわけではないのがポイントだ。
中村さんは、イタリアのファッションブランド〈ブルネロクチネリ〉が掲げる
「人間的資本主義」を引き合いに、
「単に『エコでいいよね』では意味がない」と力説する。
「人間らしく暮らしていくためには、やっぱりある一定程度の収入が必要です。
つまり、ちゃんと経済と結び付けること。
だからといって自然の恵みを侵害するようなことはしてはいけない。
きちんと稼ぐけど、稼いだ「上がり」はちゃんと世の中に還す、
という経営が求められると思います」
伊那は人間らしく暮らせる場所
2024年、創業から8年目を迎え、5人だった従業員は24人に増えた。
その半分以上は、〈やまとわ〉の理念や活動に賛同して
伊那市や周辺地域に移住してきた人たちだ。
さらに林業やまちづくりの方面にも活動や人的つながりは広がり、
「反応してくれる人が増えているという手応えは感じている」と中村さんは言う。
では今後、中村さんは伊那をどんな地域にしていきたいと考えているのか。

オフィスの雰囲気はカジュアル。若いスタッフが多く活気がある。
「僕は、『未来少年コナン』という宮崎駿監督作品に出てくる
ハイハーバーという島がすごく好きなんです(笑)。
山地でブタやヤギを飼ったり、海で魚を養殖したり、麦を育ててパンをつくったり、
鍛冶屋がいて、機織りして……小さい村ですっごく幸せそうに生きていて。
伊那もそうなれるって結構本気で思っているんです」
例えば伊那は、ふたつの大きなアルプスに囲まれているため台風のような災害にも強く、
また谷間にもかかわらず日照時間が長いため、扇状地で農業に従事する人も多い。
長野県の大動脈である中央自動車道からは適度な距離があり、
中村さん曰く「都会にならない」エアポケットのような場所だが、交通の便は悪くない。
もちろん、森が多く自然が豊かだ。

事務所に隣接したアカマツの森。すでに一部が枯れ始めているという。
「伊那なら、自然資源を生かし切る暮らしができる。
そういう場所や、僕たちみたいな企業が日本中にいくつかあれば、
森の健全化は達成できる。
そうしないと、僕らは多分、生命として存在できなくなると思うんです。
地球が僕らを不必要だと思ったら僕らは排除されるだろうとは思います。
だけど僕は人間だし、人間らしく暮らしていきたい。
だったら、僕たちらしく生きていく、ということを、この地で見せていきたいし、
ほかの場所にも仲間をつくっていきたいんです」
そう語る中村さんの表情に悲壮感はなかった。
問題意識と信念を持ちながら「遊ぶように仕事をして」、楽しく生きること。
未来は、いきなりは変えられない。
きっとそのような積み重ねから生まれていくのだろう。

オフィスから伊那のシンボル、南アルプスを望む。
profile

中村博
なかむら・ひろし●1969年、長野県伊那市生まれ。〈株式会社やまとわ〉代表取締役、家具・木工職人。郵便局員を経て木工の道へ進み、2002年から伊那谷産木材を用いた木工に取り組む。16年、同社創業。「森をつくる暮らしをつくる」を理念に掲げ、地域の木のプロダクト開発や森林のトータルプランニングなどを行う。