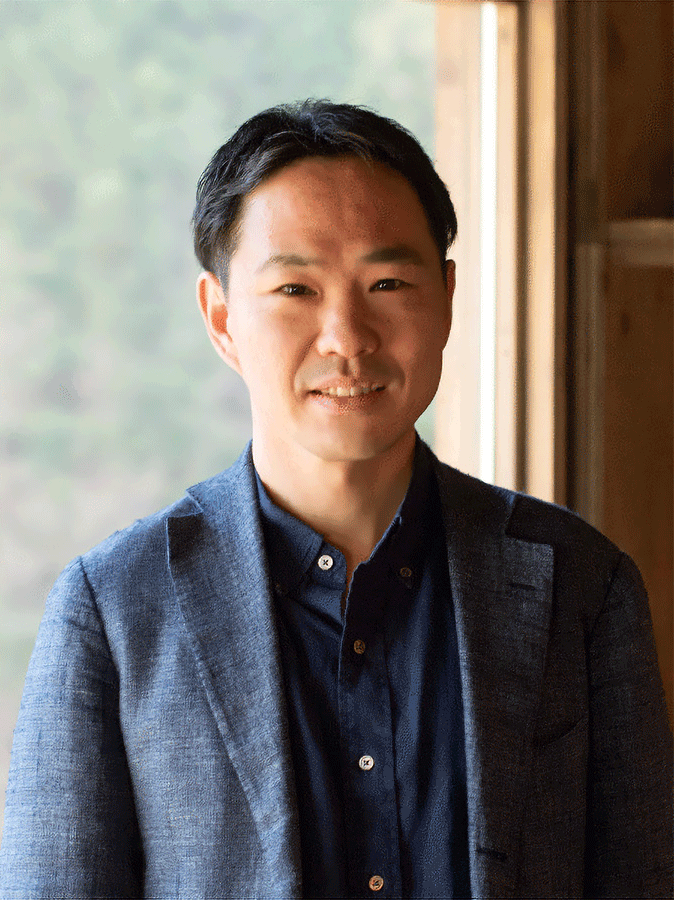【見逃し配信あり】 本と場所の関係を考える。 内沼晋太郎さん登壇 コロカルアカデミーVol.2

日本のローカルの魅力を発信する「コロカル」は、ウェビナー講義シリーズ「コロカルアカデミー」の第2回を開催しました。ゲストはブック・コーディネーターの内沼晋太郎さん。東京・下北沢にて新刊書店〈本屋B&B〉の運営や、「本のまち」を掲げる青森県八戸市の市営書店〈八戸ブックセンター〉のディレクターとしての活動など、本を通じた多様かつ個性的な取り組みで注目を集める内沼さんに、本をめぐる環境や、ローカルと本屋の関係について、深く語っていただきました。
見逃し配信を視聴したい方はこちらからお申し込みください。
▶︎視聴登録はこちら

内沼晋太郎(うちぬま・しんたろう)さん
ブック・コーディネーター
1980年生まれ。株式会社NUMABOOKS代表取締役、株式会社バリューブックス取締役。新刊書店「本屋B&B」共同経営者、「日記屋 月日」店主として、本にかかわる様々な仕事に従事。また、東京・下北沢のまちづくり会社、株式会社散歩社の代表取締役もつとめる。著書に『これからの本屋読本』(NHK出版)『本の逆襲』(朝日出版社)などがある。現在、東京・下北沢と長野・御代田の二拠点生活を営む。
本は、本単体では存在しない

内沼さんが自己紹介の中でお話して下さった中で印象的だったのは、「本は本だけで存在しているわけではない」とのこと。本は誰かに手に取られ、読まれ、その行動に影響を与え得るものであるということ。本屋は、本を売るだけの商売が難しくても、地域にとって必要な拠点として人々から必要とされ得ること。
本を考えることは、場所について考えることなのかもしれない。そんな発見がありました。
出版業界の現状と、都市/ローカルそれぞれから見た書店の現在地

ではそんな本をめぐる状況は今、どうなっているのか。内沼さんによれば、出版数は今、ピーク時の半分以下に減少しているそうです。ただ、2014年以降は電子書籍のようなデジタル(とくに漫画)の増加によって、カバーされているような状況。同時にいわゆる書店の数も減少しているようですが、今回のメインテーマでもある独立(系)書店と呼ばれる小さな書店は増えていっているとのことでした。
SNSやシェア型書店、文学フリマなどといった活動も含め、本をめぐる状況は、確かな変化が起きているようです。都市とローカル、それぞれの側から見た書店の現在地とその後の在り方の展望についてもお話いただきました。
そもそも、書店や本屋の価値とは──

そもそも本が並んで売られている書店や本屋という場所にはどんな価値があるのでしょうか。その問いに対して、内沼さんは「大きな本棚」ということばを使って、説明します。
「一度にたくさんの本を実際に目の前にすることで、世界の圧倒的な大きさを知る。そのことで、自分が世界について知っていることの少なさに気づくことができる。知識を増やさない限り、検索やAIも使いこなせないし、知っていることを増やすことで、自身の潜在的な関心にも気づき、もっと考えたいという知的好奇心を育むことができる=考える人を増やすことができる」とのことでした。
スマートフォンを開けば膨大な情報があるようにも感じますが、その情報はあくまで数インチの電子媒体の中に詰まっています。そう思うと、たしかに「大きな本棚」を目の前にし、それを一堂に目に入れ、物理的な本の重みや手触りを五感で味わいながら、身体を使って知ることには大きな価値があるはず。
同時にまた、内沼さんは、「大きな本棚」について、物理的な大きさも大事だけれど、何より「世界の広さ」が大事だと語っていました。哲学の棚が消えてしまえば、その世界から哲学がなくなってしまうというお話は、まさに「大きな本棚」という概念の持つ奥行きと、本を並べるという行為の価値に紐づいていると感じました。
「書店」と「本屋」の違い、そしてローカルな本屋とは

一般的には同義語とされる「書店」と「本屋」という言葉について、内沼さんはニュアンスの違いを語ります。書店は立地であり、サービス。売れ筋が揃う便利な場所であり、拡大を目指していくビジネス。一方本屋は、人であり、コミュニケーション。維持を目指すスモールビジネスとして、あるいはライフワークとして存在するもの。
小さく、便利ではないかもしれない本屋ですが、ここにこそ、ローカルな、それぞれの価値を生み出せる可能性があるのではないか、とのことでした。講義の中ではさらに踏み込んで、ローカルに根差した本屋の具体的なスタイルや、独立系の書店はむしろ地方の方が成り立ちやすいといった興味深い視点も紹介されていました。
コミュニティの可能性としての本屋──

内沼さんが書店や本屋というビジネスを薔薇色の儲かる商売として語ることはありません。ですが、同時に内沼さんが一貫して強調していたのは、「本というものを通じて世界の広さを知り、考えられるようになる豊かさ」と、そして何より「コミュニティのハブとしての本屋の可能性」です。
地域(ローカル)の人たちが集まり、語り合う場所として、公民館を使うことはできるかもしれない。でも、普段あまり入ったことのない、壁が真っ白な会議室で話すよりも、普段から道行く場所にあり、古今東西さまざまなことばの詰まった書物の並ぶ本屋という場所で話す方が人も集まりやすいし、語りやすいし、話すこともより濃密なものになっていくのではないか。本屋の店主の多くも、本を媒介として、お客さんといきなり深い話ができた経験を持っているそうです。
本は、私たちを結びつけながら、より遠くに、より深く連れていってくれる「場所」そのものかもしれない。そんな本の無限の可能性を知り、それを生かしていくきっかけを感じる講義でした。
講座本編終了後のQ&Aセッションでは、ローカルな本屋を支援するための海外事例との比較や、ローカルな専門店形式の書店についてのこと、ローカルで本屋をやるにあたって土地による地域差に着目するべきなのかなど、より具体的な話題も盛りだくさんでした。
本が好きな人、本屋が好きな人、地域に根ざしたお店・場所を作りたいと考えている人などに、とくにおすすめです。
見逃し配信を視聴したい方はぜひ、こちらからお申し込みください。
▶︎視聴登録はこちら