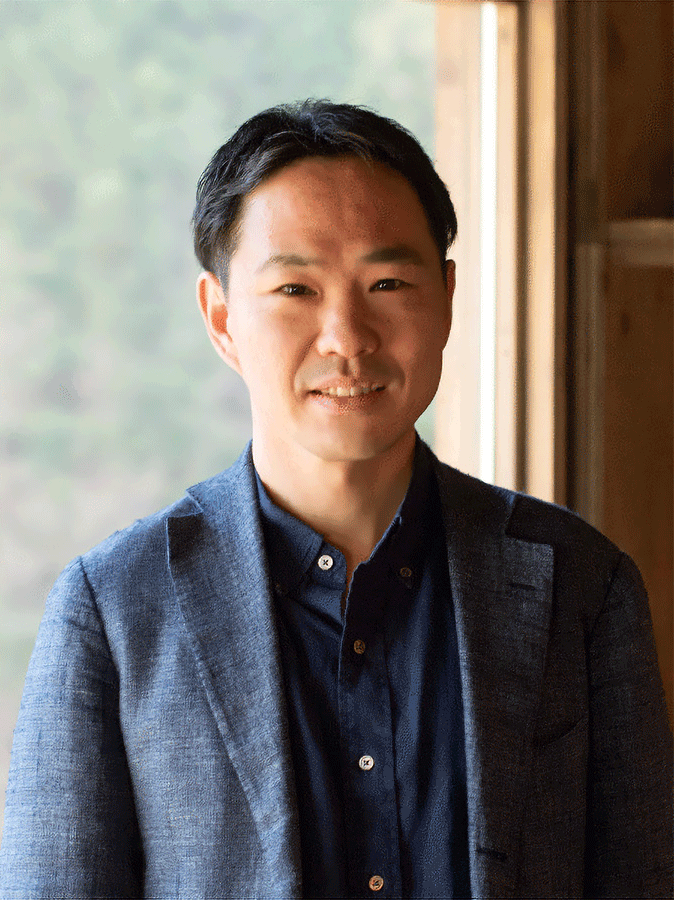アートディレクター・ 佐藤亜沙美の旅コラム 「北へ“人と本”に会いに行く」

さまざまなクリエイターによる旅のリレーコラム連載。
第37回は、アートディレクター・デザイナーの佐藤亜沙美さん。
子どもを産む前と産んだ後では、
旅に求めるものが変わってきたという。
そんな出産後に再訪することになった八戸市。
子どもと一緒に訪れたことで、感じたこととは?
子どもが生まれて変わった旅への意識
出産以前と以後で一番変わったのは旅の目的かもしれない。
歳とともに衰えていくものと思っていた好奇心はどんどん強くなるばかりで
産前には見たことがない場所、食べたことがないもの、
触れたことのない文化に足が向かった。
あるときは地図にも載っていないようなイタリアの山奥に、
あるときは沖縄の離島に、タイの屋台に、台南の朝のお粥文化に。
それは外に外に向かっていた。
移動距離の長さや現地で体験する予期せぬできごとの多様さによって
旅の満足感は高まった。
子どもが産まれたことで行ける場所も行ける距離もぐっと小さくなった。
子どもは縦横無尽に動き回るため、常に気を張って見ていなければならないし、
旅の直前に体調を崩す可能性も頭に置いておかなければならず、
計画をするだけでも精神的に負荷がかかる。
かつてのわたしはそれらの不自由をさぞ負担に思うだろうと思っていた。
わたしが人生の中心に据えていたのは常に「自由であること」だったからだ。
自分のわがままをいかに貫いていくかに生きるエネルギーのすべてを割いていた。
産後、体調が落ち着くとすぐに内なる好奇心が発動した。
旅での移動を、車で1時間、2時間とどんどん時間と距離をのばしていった。
そして先日、ハードルの高い新幹線移動を乗り越え、
ようやく自分がこれまで行った最北地点である八戸を再訪した。
はじめに八戸を訪れたのは2017年12月、
全国でも希な市営の本屋である〈八戸ブックセンター〉の企画に
デザイナーとして参加したときだった。

八戸市西東部にある種差海岸(たねさしかいがん)。
縁もゆかりもないその地に足を踏み入れたそのときは、
人生における一、二を争うほど過労の時期で
常時、背中に8枚、肩こりを緩和する湿布を貼った状態だった。
移動中の新幹線でもみっちり3時間半仕事をし、
歓迎をうけるはずの宴会に遅刻気味で着いたときには
盛大に盛りつけられた刺身の盛り合わせに向き合うエネルギーは
すでに枯渇していて焦った。
半ば気力を振り絞って笑っていた宴会で、
八戸を本のまちにしたいという当時の八戸市長の熱量と
東京の書店で働いていたところを応募して移り住み、
八戸ブックセンターのスタッフとなった森花子さん、佳正さん夫妻と話しているうちに
不思議とどんどん解放されていく感覚になった。
それはわたしが東北生まれで、みなさんの方言を懐かしく思ったからかもしれないし、
シャイだけどあたたかい人柄に親しみがわいたからかもしれないし、
東京からの距離が気持ちを大きくしたのかもしれない。

八戸市公営書店、〈八戸ブックセンター〉。
八戸は食文化が豊かな土地で、
それまで東京で世界中のものが食べられると思っていたわたしは
市内の居酒屋で見たこともないお酒の銘柄や食べ物のメニューを見て驚いていた。
「今日はこのお酒がある! 佐藤さん、ついてますよ!」などと言われて、
それまでの自分の視野の狭さを痛感し、八戸という土地の奥行きを感じた。
何度か八戸を訪れるうち、
小説家の夫を連れだって行った先でさらに人の縁がつながり、
気がつくと市街の〈みろく横丁〉で酒を呑みハシゴしては気持ちよく酔い、
気がついたら書店スタッフの森夫妻と肩を組んで歌っていたりした。

八戸名物の「ほや」と「おやじ」をかけ合わせた横丁のゆるキャラ〈よっぱらいほやじ〉。
その後、世界中がコロナ禍に包まれ、わたしたちの足も八戸からも遠ざかった。
もし次に行くならどの土地かと想像したときに一番先に浮かんだのが八戸だった。
産後、わたしの好奇心のあり方は変化していた。
いつのまにか旅の目的は「未知のもの」ではなく「会いたい人」に移っていて、
会いたい人がいる土地を思い浮かべるとモチベーションが高まった。
ちょうど森家にも我が家と1年違いで子どもが産まれていて、
ときどき子どもの写真を送ってもらっては夫と目を細めていた。
会いたい! 勢いで八戸行きを決心した。
幼児連れで訪れた八戸は、子の視点とともに大人の目線も変わり、
見渡してみるとこれまでと違うまちの姿があった。
子どもが思いっきり走り回れる公園があり、
誰もが等しく使える施設が充実していて、大人たちの子どもへのまなざしがやさしい。
自分と森夫妻の子どもらが公園で戯れている姿をみたとき、
なんだかもうこれで充分だ、という満ち足りた気持ちになった。
同時に、都内では子連れでいるだけで申し訳なさそうにしていた自分が
解放された瞬間でもあった。
なによりどの施設もデザインが洗練されていて、
子ども用の施設にありがちな「ほっこり感」に気後れしてしまうわたしは、
視覚的にも楽しかった。

「八戸公園こどもの国」。

地域観光交流施設〈はっち〉にあるキッズスペース。
40代になり「もしいつか死ぬ瞬間が訪れるとして」と考えることが多くなった。
同時にデザイナーよろしく
老いて死ぬときの走馬灯をどうデザインするかを考え始めた。
旅の目的が人に会いに行くことになったのも、
もしかしたら走馬灯デザインの一環なのかもしれない。
未知の領域を広げるよりも
「あの人とあの人が楽しげに笑っていた」という記憶を残すことの優先順位が
日に日に高くなっている。
次はあの人の住んでいるまちを旅してみたい。
北に南に次々行きたい場所が浮かんでくる。
今回の旅はマイ走馬灯の大きなポイントになるなと思いながら満足げに帰宅した。
行ける範囲は狭くなったけれど、
思い出したい時間をたくさん持ち帰ることができた。
帰宅する頃には娘を抱えた腕がしびれて、クタクタだったけれど。

種差海岸には日本では珍しい天然芝が広がる。
profile

Asami Sato
佐藤亜沙美
アートディレクター・デザイナー。1982年福島県生まれ。2014年独立。『文藝』アートディレクター。大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、日本テレビドラマ『だが、情熱はある』のタイトルロゴも手がける。
Instagram:@satosankai
text