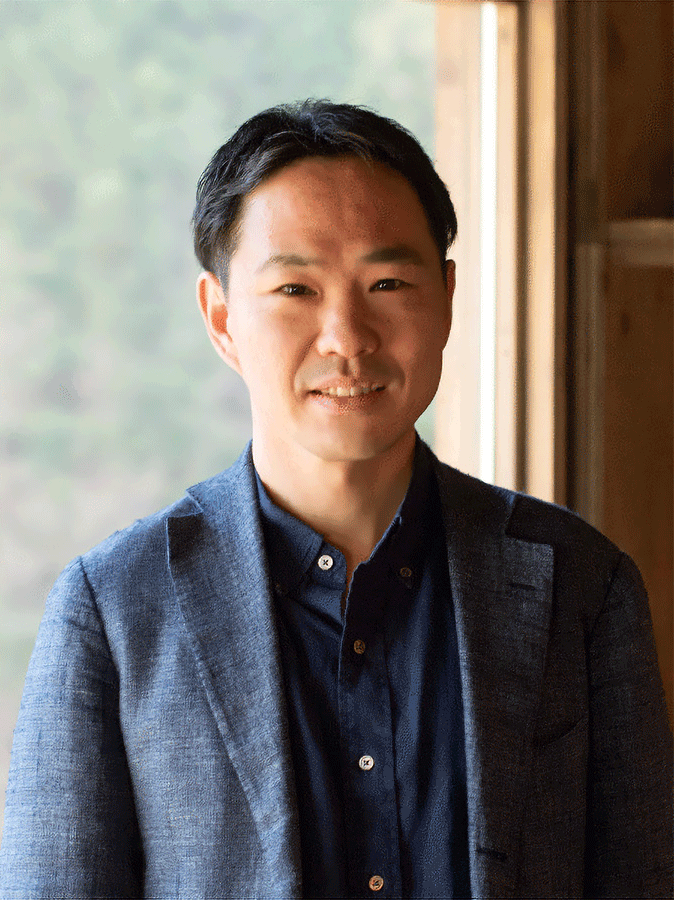映画『もち』小松真弓監督インタビュー
岩手県一関市が舞台、
「もち」でつないだ地域文化を残す

information

映画『もち』
日本の里山のイメージそのままの景観が残る、岩手県一関市の本寺地区。
古くから根づいている、もちの文化を織り交ぜながら、
実際にここに暮らす14歳の少女の1年を追う、みずみずしい映画『もち』が完成した。
神事、冠婚葬祭、人生の節目、そして日常など、ことあるごとに登場するもち。
監督・脚本を手がけた小松真弓さんは、一関のもち文化をどう捉えたのか。
制作エピソードとともに語ってもらった。

“やさしい暗号”が気づかぬうちにすべて消えていく
正月のお雑煮を見てもわかるように、もちの食べ方や供し方は地域によって多種多様。
それだけ古くから根づいてきた食べものといえるが、
全国でも群を抜いて多彩なもち文化のある地域が、岩手県一関市。
伝統的な儀礼や風習をまとめた一関の「もち暦」によると、
もちを食べる機会は年間60回以上。
極端な話、人が集まるところにはもちがあるような地域なのだ。

そんな一関を舞台に、『もち』というストレートなタイトルの映画が誕生した。
主人公は、800年前の景観とほぼ同じ姿で守られてきた本寺地区に暮らす、
14歳の少女ユナ。
映画は雪がしんしんと降り積もるなかで行われる、祖母の葬式のシーンから始まる。


機械ではなく、臼と杵を使ってもちをつきたいと言い出す祖父と、
最初はやや億劫そうにそれを手伝うユナ。
一方、彼女が通う全校生徒14人の中学校の閉校が決まり、
親友は隣町へ引っ越すことになり、
淡い恋心を抱いていた親友の兄は進学で東京へ行くことに。
彼女とその周辺が刻々と変化していく1年を、
儀式の場や日々の食卓にあるもちの風景を映し出しながら綴っていく。
出演しているのは役者ではなくすべて一関の人たちで、
フィクションとノンフィクションの間をたゆたうような作品に仕上がっている。


監督を務めた映像ディレクターの小松真弓さんは、これまで多くの映像作品を手がけ、
劇映画としては2011年に蒼井優主演の『たまたま』を監督している。
仕事やプライベートで世界の多くの国を見てきた小松さんは、
日本という国のいい面も悪い面もあらためて強く感じていた。
「島国だからこそ“自然と人”、“人と人”とのつながりをより深めることが必要で、
そのために先人たちの知恵や教えが暗号のように散りばめられている。
それは舞となって踊られ、物語として語り継がれ、行事として日々の生活に入り込み、
地域に根づく伝統工芸や衣装、文様、方言、
さまざまなものにかたちを変えて受け継がれてきました。
この“やさしい暗号”があったから、
日本人には奥深い思いやりの心が染みついているのだろうと感じています。
そしてその暗号を見つけて意味を知ることができると、
大切に次につないでいかないといけないと思えます」
一関を訪れてその土地で生きることで生まれた話を、学校で、飲み屋で、
ときにはすれ違いざまに話しかけ、
さまざまな角度から聞いていくことを通して、あることを発見する。
「現地の人が当たり前すぎて気にもとめないけど、
都心部に住んでいる私から見たらかけがえのない“やさしい暗号”がたくさん見えました。
そして、それらは風前の灯であるとも感じました。
時が過ぎ生活の形態も変わり便利な世の中になることは正直うれしい。
ただその裏で、面倒くさいことがなくなっていく。
伝統文化はもちろんのこと、人づき合いもライトなものになってきている。
それが悲しくてしかたない」
しかし一方で、人の記憶は忘れるようにできていることも、自らの経験から知っていた。
「まったく別の話のようですが、自分の記憶の話でいうと、
おじいいちゃんやおばあちゃんが生前教えてくれた言葉を覚えているかと問われると、
孫である私に伝えようとした言葉なので
大切なことを語ってくれていたのだと思うのですが、私はすべてを覚えていません。
卒業式という、人生のなかでも強く記憶に残る日に担任が話してくれた言葉、
ずっと覚えていようと思った言葉も、時が経つと薄れていきました。
人の脳は忘れていくように組み立てられていて、忘れていかないと次に進めない。
それでも忘れたくないこと、失いたくないもの、
つなげていかないといけないことはどうしたら残せるだろう、
という疑問が常に自分のなかにありました」
神楽を舞う主人公との印象的な出会い
キャストを探しているなか、
山あいの本寺地区で主人公のユナを演じた佐藤由奈さんと出会う。
彼女が通う中学校では『鶏舞』という神楽を復活させていた。
「歴代の生徒の親御さんたちが手づくりし、修繕してきた鶏舞の衣装を着て、
校庭で神楽をひとりで踊ってくれました。
その姿が野生動物のようであまりにも美しく惹かれました。
土地に生きている感じがすごく強かった」


その後、小松さんは橋が途中で真っ二つに折れ、
渓谷に向かって崩落している異様な光景を見た。
「祭畤(まつるべ)大橋」と呼ばれるその橋は、
2008年に起こった岩手・宮城内陸地震の災害遺構だった。

「その橋はあえて残しているのだと聞いて、自分のなかですべてがつながりました」
一関の生き字引のような蓬田 稔さん(ユナの祖父役として出演)に出会い、
さまざまな話を聞いたこと。
中学校の閉校が決まっているなかで、復活させた神楽を踊り続けること。
地震で崩落した橋をそのままのかたちでとどめていること。
すべてに共通しているのは「努力して残すこと」なのだと。
「さまざまな“やさしい暗号”が、気づかぬうちにここからすべて消えてしまう。
そう思ったとき、『誰かが気づいて残せばいいのに』と、
まるで他人ごとのように口走っていました。
自分は、映像を撮って残す技術を持っていますが、そんなことをするのはおそれ多いし、
そもそも東京で仕事を抱えているのだからやれるわけがない。
映像で残すことは何より想像を絶するくらい大変だと思いました。
でも、気づいてしまったのに知らんぷりをすることもできず、
撮影できる勇気も自信もまったくありませんでしたが、
脚本を書いて文章で残そうと考えたのです」
結局、東京での仕事を1年半もの間断って、
ほぼ自主制作のような態勢でつくることになった。
小松さんにそれだけの覚悟をさせたのは、
「自分が死んだあとの世界でも、この“やさしい暗号”が
今まで受け継がれてきたことの裏に大切な意味があることに気づいて
少しでも残っていてほしい」という切実な思いだった。
「“自然と人”、“人と人”のつながりを残そうとした人々の
“やさしい暗号”の記録を撮っておけば、
仮にその文化が消滅したとしても映像には残っている。
そして真の意味をわかっていれば誰かの気持ちに引っかかって、
ユナちゃんたちの学校が神楽を復活させたように思い出せるのでは、
という気持ちが強かったのです。
始めたら絶対に逃げないでやり遂げるという強い約束を自分にしていたから、
何が起こっても負けずに制作を進められました」

気持ちを分け合うために、もちがある
『もち』というタイトルがついているものの、もちの歴史にまつわる物語ではない、
と小松さんは強調する。
描きたかったのは「人ともちの裏にあることの意味」。
一関のもちの歴史や文化を知るほどに、その部分に魅せられていったのだ。
「まず原料になるもち米は、ひとりではつくれない。
農作業はみんなでやるものですよね。茅葺屋根もひとりで葺き替えることはできなくて、
地域のみんなの手を借りて作業します。
ひとりでなんでもできるような生活環境じゃないから、
人と人のつながりが自然と強くなるんですけど、それをつなぐ道具がもちなんですよね。
ひとつの臼と杵でついたもちを、みんなに配るのもそう。喜ばしいときも悲しいときも、
みんなで集まってもちをついて配ることで、気持ちをわけ合っているんです」
人の絆を強めるために存在する、単なる食べもの以上の意味を持つ、もち。
そのことを教えてくれた一関に住む人たちが出演しているので、
ドキュメンタリーのように自然に会話を交わしているのが印象的だ。
小松さんは、いろんな人から聞いた大切な話をパズルのように組み合わせて脚本を書き、
演出として手を加えることは極力避け、
撮影中も人の話の行方によって全体の流れを変更することもあった。
「脚本はあってもないようなものでした。
たとえばユナとおじいちゃんが河原で話すシーンがあるんですけど、
おじいちゃんには
『前に私に話してくれた、もちつきの話をユナにしてください』って伝えるんです。
ユナには『おじいちゃんの結婚式の話を聞いてほしいんだよね』とだけ言っておく。
そうするとお互いに要点は伝えているから、
多少話がそれたとしても脚本に書いてあることを自然に話せるんですよね。
もし話が変わっていったら、
逆に脚本のほうをその都度変えて最終的に軌道修正できるようなことを毎回考え抜く。
だからスタッフも次にどうなっていくのかわからない、当日知るみたいな感じでした」


みんなが努力をしたから残っている
知らない土地の、知らない物語なのに、懐かしさに似た感情がこみ上げてくるのは、
もちとそれを取り巻く文化や習慣が日本人のDNAに刻み込まれているからなのだろうか。
そう思わせるくらい、本作には日本の普遍的な事象が詰まっている。
「臼と杵を見なくなっても、
もちをつくということの意味がきちんと残っていくといいなと思います。
祭畤大橋や神楽もそうだけど、
残すためにみんなが努力をしているから残っているんですよね」
劇中、「努力しないと忘れてしまうものなんて、なんだか本物じゃないみたい」という
ユナの印象的な言葉がある。
たしかに本当に忘れがたいことは、努力などしなくても覚えているのかもしれない。
だけど、すべてを鮮明に記憶しておくことは難しく、
時間とともに風化するのは自然の摂理ともいえる。
小松さんが『もち』をつくったのは、祭畤大橋や神楽を残す感覚に近いという。
「予測があまりできない撮影だったけれど、
流れに任せながら映像としてまとめていく経験と技術はあるので、それを提供して、
私の感じたこの土地の匂いを記録していきました。
なので、この『もち』を自分の作品といったらそれこそおこがましいことです」

地域の魅力を外に向けて発信したり、自分たちの暮らす土地の豊かさを見つめ直し、
郷土愛を育むような映画。
そんなローカルムービーとして、『もち』はその布石を打つ映画にもなり得るだろう。
「その土地に行かなくても見ることができるという意味ではいいのかもしれないけど、
きれいなヴィジュアルのカタログみたいになっていたり、
映像技術を見せびらかせたりするようなものには、私はそんなに興味がない。
その点、『もち』はむしろ古いくらいの印象を受けるかもしれないけれども、
私のなかでは全然古くないんです。なぜなら人を撮っているから。
もちから入ったけれども、やっぱり興味深かったのは人なんですよね」
もちのある風景から見えてくる、人と人のつながり。
800年前から変わらない稀有な土地を舞台にしながらも、
誰もが持っている遠い記憶に光を当てるような、
かけがえのない瞬間が映し出されている。

profile

KOMATSU MAYUMI
小松真弓
広島県福山生まれ、神奈川県茅ケ崎育ち。武蔵野美術大学卒業後、1996年、東北新社企画演出部に入社。2011年より、フリーランスの映像ディレクターとして活躍。生き生きとした表情を引き出す独特の演出や細部にこだわった映像美に定評があり、これまでに多くの映像作品を手がけている。CMの企画・演出を中心に、ミュージックビデオ、ショートムービー、映画、脚本、イラスト、雑誌ディレクションなど、フィールドを広げている。
information

映画『もち』
一関シネプラザ(6月26日〜)・渋谷ユーロスペース(7月4日〜)ほか全国にて公開
脚本・監督:小松真弓
エグゼクティブプロデューサー:及川卓也
プロデューサー:谷田督夫
撮影:広川泰士
照明:タナカヨシヒロ
整音:丸井庸男
編集:遠藤文仁
VFX:白石守
音楽:Akeboshi
音楽プロデューサー:山田勝也
(C)TABITOFILMS・マガジンハウス
Web:映画『もち』公式サイト 公開劇場情報