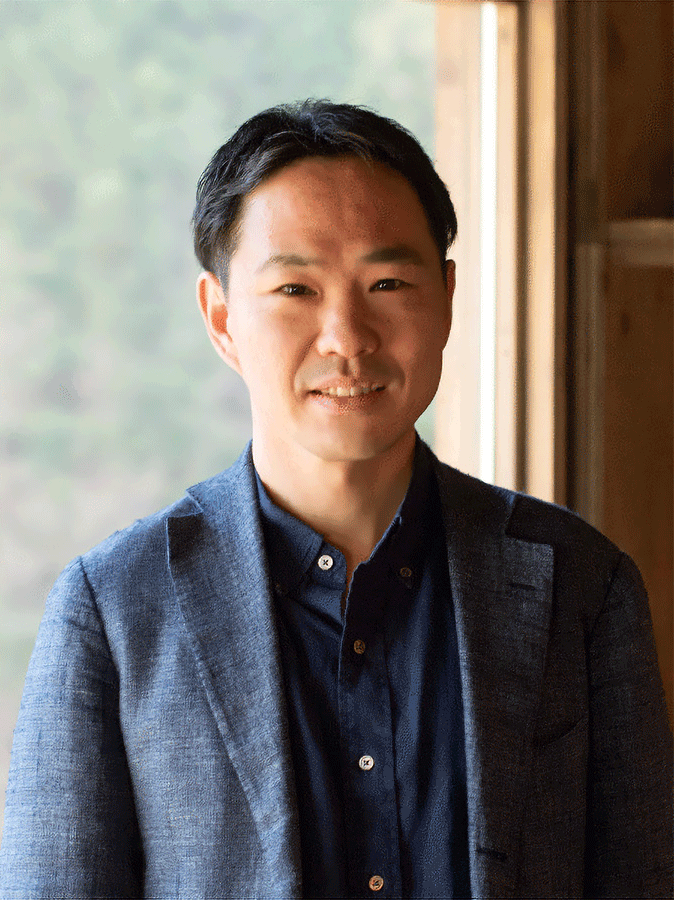多可の和紙、丹波篠山の陶器、 三田の青磁。 兵庫県中部の伝統工芸の産地を巡る 〈ひょうごフィールドパビリオン〉 Vol.1

歴史も風土も多様な五国は、まるで日本の縮図のよう。
兵庫県では県そのものを大きなパビリオンに見立て、
地域の人々が主体となって地元の魅力を発信する〈ひょうごフィールドパビリオン〉を展開。
県内各地でユニークなプログラムが用意されている。
和紙、陶器、そして青磁器。
自然に囲まれた兵庫県中部ならではの環境と生活風習から生まれた工芸品たち。
受け継がれる伝統の背景はもちろん、
現代のライフスタイルや未来につなぐ試みにも目を向けてみたい。
多可、丹波篠山、三田を巡り、
現地でしか体験できない兵庫の手仕事の魅力に触れてみてはいかがだろう。
「1000年残る紙をつくるために」
兵庫県の中央、山間部に位置する多可町の道の駅〈杉原紙の里〉。
思わず深呼吸したくなる山間にあるこちらは、
1300年の歴史を持つ播磨紙を継ぐ和紙、杉原紙の産地として知られている。

自然に囲まれた多可町〈杉原紙の里〉。目の前を流れる杉原川で紙の原料となる楮(こうぞ)をさらす。近くには青玉神社も。
杉原紙は美しく、高級和紙として鎌倉時代には公家や武士に愛され、
その後は広く一般に流通。
浮世絵や版画などにも使用されていたことでも知られている。
紫式部の『源氏物語』もこの紙に書かれた、という説もある。
現在は兵庫県の重要無形文化財に指定されている伝統工芸品だ。
〈杉原紙の里〉にある〈杉原紙研究所〉では現在も、
昔ながらの製法を大切に受け継ぎながら和紙が生み出されている。

杉原紙は地元の小学校の卒業証書や感謝状などにも使用されている。
杉原紙の特徴は色の白さ。地域で採れるクワ科の植物、
楮(こうぞ)とトロロアオイを原料とした、
いわば多可の自然環境と人々の知恵が生み出した賜物である。
手すきの際の水も、天然の澄んだ井戸水を使用しているそうだ。
「水道水でもそこまで問題はないんですが、
これまでこの紙が1000年残ってきたように、
これから1000年残る紙をつくるために昔ながらの手づくりの製法を守り続けています」
そう話すのは〈杉原紙研究所〉所長で紙すき職人の藤田尚志さんだ。

〈杉原紙研究所〉所長で紙すき職人の藤田尚志さん。入口では書道や手紙展などを展示。
藤田さんに聞けば、冬は楮の収穫期。伝統の製法はまず、
皮の表面を剥いだ楮を杉原川にさらし、繊維を白くする。
そして、その楮を蒸して繊維をほぐすことで和紙の原料となる。
川さらしの光景は遠方からも見物客が訪れる冬の風物詩となっているという。
かつて杉原紙は農家が農閑期につくっていたもの。
手すきのタンクに混ぜ合わせる粘剤のトロロアオイの粘度を保つためにも、
冬の冷たい水が適しているのだそう。
「ここでつくる紙は生き物のようなものだと考えています。
例えば、新鮮な魚をすぐに料理すれば美味しいのと同じで、
収穫期に採った楮(こうぞ)を冷たい水にさらし、日光を当てる。
そうすると白く美しい紙になるんです」

楮は乾燥させ、川の中にさらすことでさらに白い紙に。冬期、約8トンを収穫。〈杉原紙研究所〉には資料館も併設。
杉原紙の紙すき体験で、世界で一枚のはがきをつくる
〈杉原紙研究所〉では手すきの和紙つくり体験ができる。
はがきサイズ、半紙サイズ、A3サイズのなかから、
まずは紙のサイズを選び、それに合った掬桁(すきげた)で水をすくっていく。
この作業を繰り返し、紙に厚さを出していく。
職人さんいわく、すくう作業は掬桁をまっすぐ水面に入れるのがコツなのだそうだが、
個人差が出やすく、厚さの違いやシワができてしまう。
その個性がおもしろいポイントではあるけれど、
均等の厚さと紙面ですくい続ける手すき職人の集中力や高い技術を想像できるかもしれない。
すくった紙に、楮に染料を加えた5種類ほどのカラーをつけることや、
紅葉や銀杏の葉を紙に付けることもできる。
すいた紙は乾燥させ、トータル1時間半ほどで完成。
掬桁の網の目が紙に薄くつくことも手づくりならではの味わいだ。
杉原紙づくりの体験を通じて、自然に寄り添いながら、
カルチャーを生み出してきた多可町ならではの歴史の一端を感じてみてはいかがだろう。
information
杉原紙研究所
住所:兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽768-46
TEL:0795-36-0080
休館日:水曜、年末年始
所要時間:30分
料金:450円~900円
決済手段:現金のみ(杉原紙研究所の紙すき体験、売店についてはPayPayのみ可)
受入可能人数:5~6名程度(最大20名)
予約:要
予約方法:予約フォーム または電話
Web:杉原紙研究所
Web:多可の語り継がれる伝統産業・芸能
51の窯元の作品が並ぶ横丁で、丹波焼作品を選ぶ楽しみ
瀬戸、常滑、信楽、備前、越前と並び、日本六古窯のひとつである丹波焼。
丹波篠山の〈丹波伝統工芸公園 立杭 陶の郷〉は
伝統工芸品である丹波立杭焼を広く紹介する拠点であり、窯元の中心となる複合施設だ。

〈丹波伝統工芸公園 立杭 陶の郷〉からの眺め。館内にはレストランやギャラリー、資料室も。
850年の歴史がある丹波焼。
丹波焼、といえば茶褐色で素朴なイメージがあるかもしれないが、
昔から変わらぬ特徴は陶器の原料である土にある。
周囲の山の原土のみならず、田んぼの粘土層である奥土を混ぜ込むことが特徴。
原土は山の層によって質が異なるため、それをまとめるのが奥土の役割なのだそう。
「お肉でもあるように原料となる土は霜降りなんです。
山の赤い土と白い粘土層が混じる霜降り。
丹波焼の命は土ですね。いくらいい窯があったとしても土次第。
ここの土がないと焼くことはできません」
そう話すのは丹波立杭陶磁器協同組合の理事長、市野達也さん。

丹波立杭陶磁器協同組合の理事長の市野達也さん。自身も植木鉢専門の窯元〈市野伝市窯〉を運営。
現在も職人による配合で混ぜられた土を基本原料としている。
そこに、各窯元が制作する器の種類によっては荒い土を加えるなど工夫し、
焼き方も窯元により異なる。つまり素朴で茶褐色だけでない、
多様な丹波焼が生まれている。
〈丹波伝統工芸公園 立杭 陶の郷〉内にある、その名も〈窯元横丁〉では、
51の窯元が制作した陶器を紹介、販売している。
いうなれば各窯元のアンテナショップだ。
1店あたり2畳半ほどの小さなスペースだが、
ハシゴしてそれぞれの窯元のユニークな持ち味をうかがえるのが楽しい。

人気の小皿や小鉢。日用陶器として時代のさまざまなニーズに応える。

〈丹波伝統工芸公園 立杭 陶の郷〉の窯元横丁。組合員の51の窯元による陶器を販売。
市野さんいわく、日用陶器として丹波焼は時代のライフスタイルとともに変化する。
そんな丹波焼の現在形の魅力が伝わってくるようだ。
「丹波焼は茶色くて重たい。そんなイメージがあるかもしれませんが、
世代や生活様式によって、色や形、つくるものが変化しています。
例えば、昔は家族用で揃いの器やカップのセットが主流だったけれど、
今は家族でもそれぞれが好きなものを選ぶ時代。
もちろん、土や製法など昔ながらの伝統を重んじていますが、
時代に合ったものを表現することが丹波焼の特徴でもあります」
もし窯元横丁で気に入った窯元があれば、直接出向き、
陶工さんにオーダーすることもできるそう。
すべての窯元は施設を中心に2キロ範囲内に存在しているのも、この産地ならではである。
現存する最古の登り窯へ
もうひとつ、この産地で忘れてはならないのは、
丹波焼最古の登り窯が現存していること。
築窯は明治28年、〈丹波伝統工芸公園 立杭 陶の郷〉から徒歩10分ほどの場所にあり、
全長は約47メートル。兵庫県の有形民俗文化財に指定されている。

全長約47メートルの丹波焼で現存する最古の登り窯。最上部が蜂の巣と呼ばれる煙突。

登り窯の内部の高さは約90センチ。その低さが特徴でもある。薪を入れる体験も。
登り窯の焼成室は9つ。天井の低さが特徴で、釉薬をかけず、
1300℃の白い炎で焼き締める。炎と陶器が同色になると焼き上がりとなる。
完成するまで3日3晩、交代で火を見守るのだそう。
5月には登り窯での焼成も予定されている。
〈丹波伝統工芸公園 立杭 陶の郷〉では陶芸体験ができるのはもちろん、
日曜の午前中に開催されている陶器のガラメンアクセサリーづくりも人気。
並べられた陶器の破片=ガラメンをいくつか選び、
金継ぎしピアスやブローチなどのアクセサリーをつくることができる。
これは商品として使えなくなった焼き物の活用方法でもあり、
丹波焼の新展開だといえるかもしれない。

ワークショップでは好きな形や色の丹波焼のガラメンを金継ぎし指輪や髪留めなどをつくることができる。

湯呑みから芸術作品まで、手回しろくろを使った自由な陶芸体験も。所用時間は約90分ほど。
そして、4月から各窯元でさまざまなワークショップのプログラムが予定されている。
例えば〈直作窯〉での風鈴づくり体験、
〈夢工房〉でのスマートフォンのスピーカーをつくる体験、
それに手びねりはもちろん、3Dプリンターを使った企画まで、
時代とともに進化する丹波焼を体感できるプログラムが数多く用意されている。
ぜひとも足を運んでほしいところだ。
作品に囲まれて眠る。陶泊で丹波焼の歴史や背景を知る
昨年からは陶芸家の工房に宿泊できる体験も。
プロジェクト名は「陶泊」。泊まれる窯元、〈昇陽窯〉の3代目である大上裕樹さんは、
まずは丹波焼の産地の風景をゆっくりと楽しんでほしいそうだ。
寝室の窓からは現在は使用されていない42メートルの登り窯が間近に見え、
「窯ビュー」を堪能できるのも、ここならでは。

陶芸家の工房に宿泊できる体験、陶泊。〈昇陽窯〉の宿泊スペースでは地元の食材でディナーも。

〈昇陽窯〉2階からの眺め。「風景から土地の歴史や背景を味わってほしい」と〈昇陽窯〉の大上裕樹さん。
「景色を楽しんでもらって、
そこから丹波焼の歴史や背景を感じてもらえたらうれしいですね。
より深い体験をすることで丹波焼の本質を少しでも味わっていただければ」
現在、宿泊は1か月に1組の限定だが、今後は広く展開していきたいそう。
宿泊プランには窯元のツアーや、地の食材を使った料理と
地酒のディナーなどが用意されている。
丹波焼の里に泊まる選択肢もありかもしれない。
information
丹波伝統工芸公園 陶の郷
住所:兵庫県丹波篠山市今田町上立杭3
TEL:079-597-2034
体験場所:各窯元(窯元によるワークショップ in 工房)
陶芸教室(丹波焼金継ぎアクセサリーワークショップ)詳細
実施日:日曜
所要時間:1~2時間未満
料金:3300円(税込み)
決済手段:現金・クレジット・PayPayなど
受入可能人数:6名まで
予約:完全予約制
予約方法:じゃらん
Web:「日本六古窯」丹波焼の里を訪ねる
世界三大青磁のひとつ、三田青磁の変わらない強さと美しさ
透明感のあるエメラルドグリーンの美しさが魅力の磁器、青磁。
中国浙江省の龍泉青磁、朝鮮半島の高麗青磁、
そして三田市の三田青磁は世界三大青磁のひとつに数えられている。
三田青磁の特徴は型押し。図柄が細かく彫り込まれた型を使い、
平皿や小鉢などに模様を付けることによって、
光り方の違いや細かいバリエーションが楽しめる。

型押しが特徴的な三田青磁。磁器といえば青緑色だがその濃淡もさまざま。
その歴史は古く、江戸時代後期からこの地で生産されている。
きっかけは三田で青磁の原料となる陶石が採れたことだ。
明治~大正期には全国に広まったが、戦時下の高級品製造の規制などで窯が閉鎖。
以降、下火となってしまったが、名品、優品も数多く残されている。
あらためて今、三田から生まれる青磁に 注目してはいかがだろう。
JR相野駅から徒歩15分ほどのロケーションにある〈三田陶芸の森。〉は
陶芸体験の教室やギャラリースペースなどを備えた施設だ。

三田青磁を知るならこちら。教室、展示室、ショップが入る総合施設〈三田陶芸の森。〉。
お話をうかがったのは館長の伊藤瑞寶さん。
作家で現在、三田青磁の唯一の継承者である。
この地で35年、青磁を制作し三田青磁の魅力を紹介し続けている。
「この地域で採掘した江戸時代の青磁器のカケラを見てもそうですが、
割らない限りは長い年月を経ても変わらない強さがある。
それに変わらない色の美しさがあるのが特徴です」

〈三田陶芸の森。〉2階では出土した江戸期の青磁や伊藤瑞寶さんの作品が展示されている。岡本太郎の石版画3部作も。
青緑色に見えているのは表面のガラスで本来は透明だが、
光に当たることで見え方が変わる。
そして朝と夕方の光量によって色が変化するのも青磁ならではの趣きと言えそうだ。
ちなみに、障子越しの自然光で眺めるのが最も良いとされているそう。
「三田青磁といえば、薄い青ではなく深い緑が代表的ですが、
その色合いや濃淡は製法によってさまざま。それぞれの美しさがあるのが魅力です」
鉄分を含んだ釉薬の量や木灰の種類、
そして窯の中の酸素量を制限する還元焼成を行うことで表面に濃淡をつける。
それらの微妙な調整やテクニックによって、美しい磁器が仕上がるのだそう。
そして、表面にヒビ(貫入)がなく、ゴミが溜まらないため陶器より強いのも特徴だ。

三田青磁のショップ。工芸品としてだけでなく日用磁器として生活に取り入れて欲しいと伊藤館長。
〈三田陶芸の森。〉ではスクールのほかに、青磁つくりを体験することもできる。
マグカップなどに絵を描く絵付け体験、型押し体験、
そして手びねり体験やろくろ体験、と素焼きまでの行程を気軽に体験することができる。
乾燥から本焼まで、1~2か月ほどで作品が完成するそうだ。

広い教室では絵付けや手びねりの体験ができる。体験は事前予約制。
それらのワークショップを通じて、国内だけでなく三田青磁を世界に、
そして未来に伝えていきたいと奮起し続ける伊藤さん。
三田の風土が生み出した青磁の魅力を今、体験してみるのはいかがだろう。
information
三田陶芸の森。
住所:兵庫県三田市四ツ辻720-2
TEL:079-568-4340
実施日:三田陶芸の森。の開館日(※月曜休館)は通年で実施可。詳細はHPで確認
所要時間:2~3時間
料金:絵付け:2200円(税別)、型押し:3000円(税別)、手びねり:4000円(税別)、ろくろ:6000円(税別)
決済手段:現金のみ
受入可能人数:60人程度まで
予約:要
予約方法:電話もしくは「三田陶芸の森。」HP、OTA(じゃらんnet)から要予約
Web:三田陶芸の森。
Web:三田青磁の歴史と魅力を識る
information

ひょうごフィールドパビリオンとは
兵庫県内のさまざまな「活動の現場(フィールド)」を、地域の方々が主体となって発信し、多くの人が来て、見て、学び、体験する取り組みです。
Web:ひょうごフィールドパビリオン
Instagram:@hyogo_field_pavilion
*価格はすべて税込です。